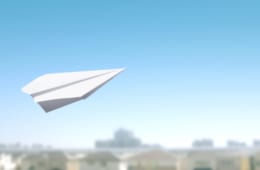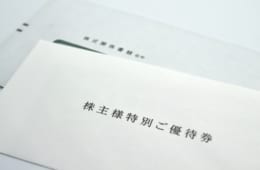文/印南敦史

1923(大正12)年11月5日に大阪で生まれた佐藤愛子さんは、2023(令和5)年に100歳を迎えた。『老いはヤケクソ』(佐藤愛子 著、リベラル社)は、そんな佐藤さんへのインタビューを主軸に、家族や師、相棒たちのエッセイなどを収録した一冊である。
記念すべき“100歳インタビュー”を行った新聞記者の山田泰生氏は、その当日のことを次のように綴っている。
一〇〇歳の人と話をする機会なんてそうそう滅多にやってこない。まして、佐藤さんは舌鋒鋭く社会を批評してきた直木賞作家である。(中略)
柔和な笑顔を浮かべて居間に現れた佐藤さんの姿はかくしゃくというよりも、愛くるしかった。孫娘の桃子さんが通訳よろしく同席し、「おばあちゃん、忘れているんです」と言いながら記憶の糸をたぐりよせてくれた。(本書「一〇〇歳インタビューについて」より)
かくして穏やかに始まったインタビューは2時間余りに及んだという。しかし受け答えはしっかりしており、とても100歳の人を相手にしているとは思えなかったそうだ。
10余年前に書き下ろされたエッセイ『九十歳。何がめでたい』(小学館)がベストセラーになったこともあってか、佐藤さんは「老い」について書かれたエッセイが多いといわれる。
しかし、ただ注文が来るから書いているだけで、書きたいテーマだというわけではないようだ。
私が「老い」の評論家の第一人者? 老いの何を論評するんですか。ヤケクソみたいなことをいうしかないんですよ。みんなヤケクソで、老いていっているんですよね。真面目に老いていたらやりきれないですよ、情けなくて。(本書40ページより)
ヤケクソということばが意味するのは、文字どおり「焼けた糞」。つまり、「なるようになれ」という意味合いなのだという。
その根底にあるのは戦争体験である。「なにも悪いことをしていないのに、頭から焼夷弾が落ちてきて逃げ惑った」体験があるからこそ、ヤケクソ以外に対処する方法がないと考えるわけだ。
何かあるとすぐ「頑張れ」っていう時期がありましたけど、ヤケクソは「頑張る」っていうのではないんですよね。頑張るっていうのは、言い換えると「耐える」っていうことなんです。戦争の時代はそうですよ。(本書42ページより)
戦争、離婚、借金の返済など、現在に至る佐藤さんの道のりは苦労の連続であったように映るかもしれない。しかし、どんなことをも笑い飛ばし、明るく楽観的に生きてきた。
しかしそれも、“それだけのこと”だと考えていらっしゃるようだ。
私の文章を読んでね、それが役に立つなんてことはないんですよ。読者が役に立った気がするだけで。うーん、なるほどね、そういう意見もあるわねっていって、それで知識が増えていけばいいんでしょうね。その通りにならなくたって別にね。だいたい私ね、知識っていうのはあんまりね、自分に知識がないもんだからね、こだわらないんですよ。(本書64ページより)
勤勉な他の作家を見るにつけ、「やっぱり勤勉でなきゃ人間は一流にはなれないんだな」と思うのだそうだ。一方、ご自身は子どものころから勉強嫌いだったので、怠け癖は死ぬまで治らないと考えておられるという。
私たちとしては「とんでもない」と感じたくもなってしまうが、ご本人にとってそれは偽らざる本心なのだろう。本気でそうお考えであるからこそ、数々の実績を打ち立ててこられたのだろうとも考えられる(ご本人は「とんでもない」とおっしゃるだろうが)。
それに歳をとると、いろいろなことがどうでもよくなるのだという。甘えても許されるという境地なのだそうだ。
ありのままを人に見せることができるのは楽ですよ。相手もありのままに話してくだされば、私のありのままで対すればいい。昔の自分と比べたところで、これがいまの私だからしょうがない、許してくださいと。年寄りっていうのは、だいたいそういうふうに、許してもらうよりしょうがないわと、どこかで思っていますよ。(本書65〜66ページより)
そのため、どう思われてもかまわないと感じていらっしゃるようだ。「自然体で生きるっていうのは楽ですよ」ともおっしゃるが、つまりそれは実体験からくる思いなのだろう。
だがこれは、100歳を越えた佐藤さんだけにあてはまることではないはずだ。
佐藤さんからみれば、私たちはまだまだ「ひよっこ」の部類なのかもしれない。しかしそれでも、私たちもまた自分なりに自然体でいるべきだからである。いわばそれは、生きていくうえであるべき本質なのだろう。

佐藤愛子 著
1540円
リベラル社
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。