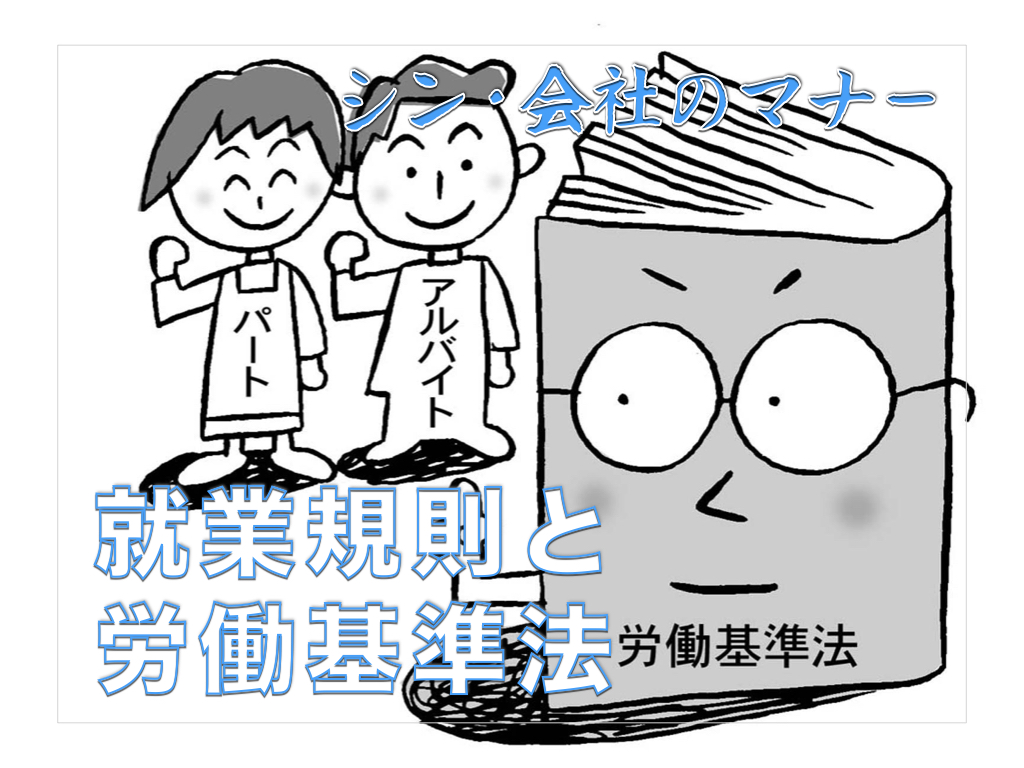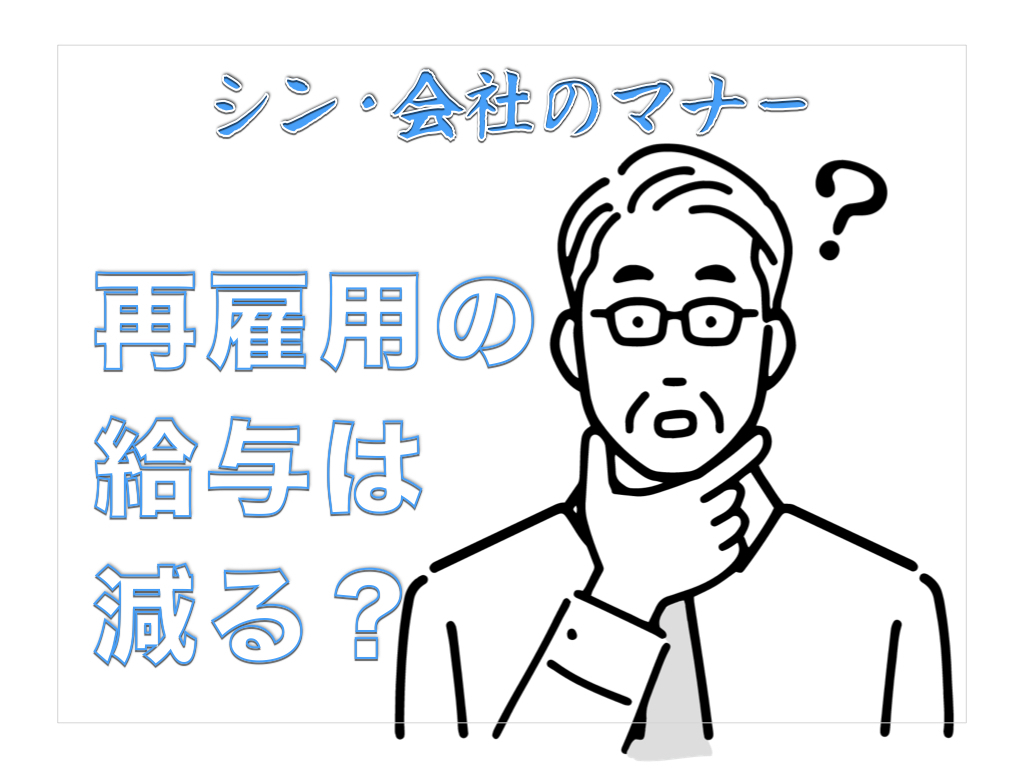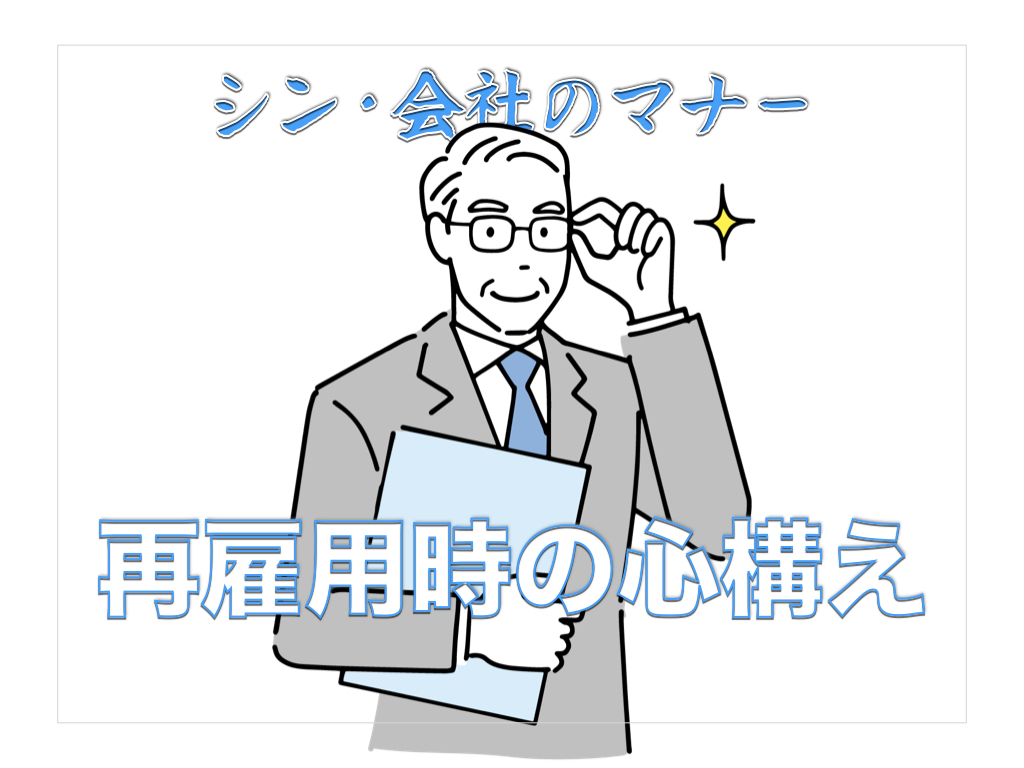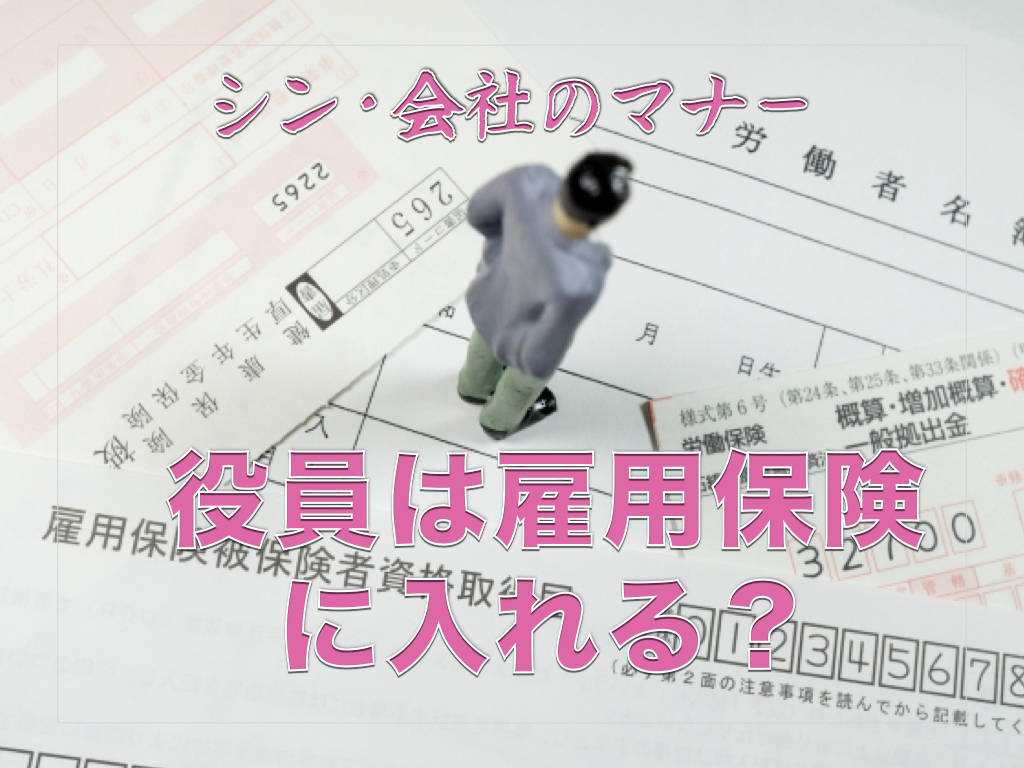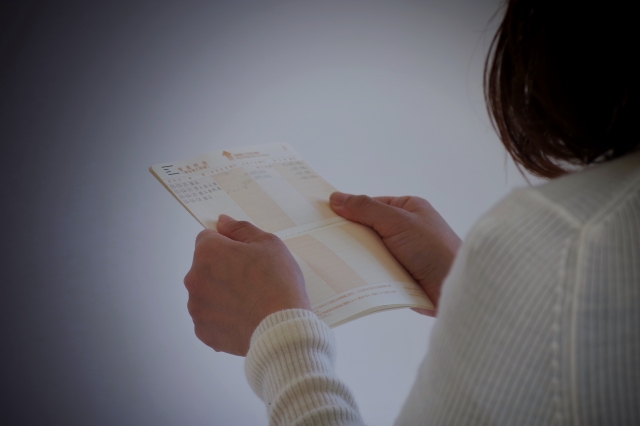労働に関する法令の中でも、「労働基準法」は大変有名な法律です。
内容は十分に知らないという人も、名前は聞いたことがあるのではないでしょうか? 今回は会社の就業規則と労働基準法の関係について、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
就業規則と労働基準法はどちらが優先? 基本ルールをわかりやすく解説
労働時間・休憩時間のルールを正しく理解しよう
就業規則違反とは? 違反時の対応と法的効力をチェック
まとめ
就業規則と労働基準法はどちらが優先? 基本ルールをわかりやすく解説
会社の就業規則が労働基準法に違反しているということはないのでしょうか? 就業規則の法的な位置づけについて見ていきましょう。
就業規則と労働基準法の違いとは?
労働基準法は様々な労働法規の核となる法律であり、すべての労働者に適用される労働条件の最低基準が示されています。
一方、就業規則は個々の会社が、職場における労働条件や服務規律を定めたものです。就業規則に必ず記載すべき項目は、労働基準法によって決められています。常時10人以上の労働者が働く事業場は、就業規則を労働基準監督署に届け出なければなりません。
会社によって労働条件などは違いますから、就業規則の内容は会社ごとに異なっています。 ただし、基本的に就業規則で定める労働条件は、労働基準法で示されている最低基準を下回ることはできません。
就業規則と法律が異なる場合、どちらが優先される?
就業規則と法律が異なる場合は、法律のほうが優先されます。
労働規範の優先順位は、
1.法令
2.労働組合との間で取り決めた労働協約
3.就業規則
4.労働契約
という順位になります。法令や労働協約に反する就業規則を定めることはできません。労働基準監督署長は、法令および労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。
また、個々の労働者と使用者の間で結ばれる労働契約は、就業規則よりもさらに優先順位は下。就業規則に定めた労働条件に達しない労働契約は、その部分について無効となります。
無効となった部分は、就業規則の基準が適用されることになります。
有給休暇や退職における優先順位を具体例で紹介
具体的な例を挙げて、労働規範の優先順位を確認してみましょう。
例えば、年次有給休暇のルールです。労働基準法では年次有給休暇の付与日数が定められており、入社後6か月勤務して8割以上出勤した人の有給休暇は10日となっています。
これを就業規則で15日と定めたとしても問題はありません。けれども8日と定めたら労働基準法の基準を下回ることになり、変更する必要が生じます。
もう一つの例は退職のルールです。就業規則の中で、「退職は1か月前に申し出る」と定められていたとします。
けれども、民法では、退職の意思を伝えてから、2週間経過すると労働契約が終了すると規定されています。 就業規則より法律のほうが優先されますので、2週間前に退職を申し出られても、会社は拒否することはできません。
労働時間・休憩時間のルールを正しく理解しよう
労働条件のうち、労働時間・休憩時間のルールは働く人にとって身近な問題です。 法令ではどのように決められているのか確認してみましょう。
労働基準法に基づく労働時間の基本ルール
労働基準法では、「休憩時間を除き、1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせてはならない」と定められています。
例外的に週44時間の労働が認められている業種もありますが、それは小売業や映画、演劇や映画の興行、医療機関や接客娯楽業など、一部の事業に限定されています。
一定の手続きのもとに、フレックス制や変形労働時間制などを採用している会社もありますが、労働時間の原則は変わりません。「自分はもっと働いている」という人もいることでしょう。
法で定めた労働時間を超えて働くことは時間外勤務とされ、割増賃金が支払われます。
使用者は「36協定」という労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、労働者に時間外労働や休日労働をさせることができます。 もちろん、無制限に働かせることができるわけではなく、月45時間以内、年360時間以内などのルールが決められています。
休憩時間の規定|6時間・8時間勤務時の休憩時間はどうなる?
労働基準法では、使用者は労働時間の長さに応じて、休憩時間を労働者に与えなければならないと定められています。
労働時間が6時間以下だと休憩時間は不要ですが、6時間を超えると最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を付与する必要があります。では、10時間以上の長時間にわたる労働の場合はどうなるでしょうか?
この場合でも、1時間の休憩時間を付与すれば法的な問題はありません。 ただし、休憩は労働時間の途中に与えなければならず、前後に与えることは認められません。

就業規則への労働時間・休憩時間の記載例を紹介
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休憩は就業規則の「絶対的記載事項」です。就業規則には、必ずこの項目が記載されていなければなりません。
例えば、このような書き方です。
第〇条 1日の勤務時間は、休憩時間を除き1日8時間とし、1週の勤務時間は40時間以内とする。
第〇条 原則となる始業、終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合により全部または一部の従業員に対し、始業もしくは終業の時刻を変更することがある。この場合、前日までに従業員に通知する。
始業 午前9時
終業 午後6時
休憩 正午より午後1時まで
なお、休憩時間は自由に利用させることが原則です。 持ち場を離れられないなど、業務に拘束されている場合は、休憩時間とはみなされないこともあるので使用者は注意が必要です。
就業規則違反とは? 違反時の対応と法的効力をチェック
就業規則違反は、従業員側の違反と会社の側の違反、2通りあります。 それぞれについて例を挙げて解説していきます。
1.従業員側の就業規則違反とは?
従業員が就業規則に定められたルールを破った場合、これが窃盗や傷害など、刑法上の犯罪にあたる行為であった場合は法的措置をとるのが普通です。
けれども、例えば、遅刻や欠勤、副業の禁止、服装や髪形などのルールに違反した場合はどうでしょうか? これらは、犯罪として裁かれる性質のものではないので、就業規則で懲戒規定を定めておく必要があります。
懲戒の定めがないと、会社は安易な処分はできません。また、懲戒処分についても、労働基準法で一定の制限が設けられているので、会社側は注意する必要があります。
2.会社側の就業規則違反にどう対応する?
会社が就業規則の届出義務を怠っている、従業員に周知していないというのは、労働基準法違反となります。必要事項の記載がない、法令に反したルールを定めているというケースも少なくありません。
また、就業規則は法令通りに作っていても、実際は残業代が払われない、休日を取得させてもらえない、という会社もあります。会社が違反行為を行なっている場合、従業員は労働基準監督署に直接申告することができます。
立ち入り調査により労働基準法違反が認められた場合、労基署は会社に是正勧告を行ないます。
ただし、是正勧告には法的な強制力はありませんので、深刻な違反行為の場合、訴訟などに発展する場合もあることを、会社側、労働者側双方が認識していなければなりません。
まとめ
就業規則の作成・届出は、会社にとっても従業員にとっても大切なことです。従業員が職場のルールを守ることによって、会社は一定の秩序を保つことができます。 また、働く側からしても、会社が法律に反する行為をしないための抑止効果があるといえます。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com