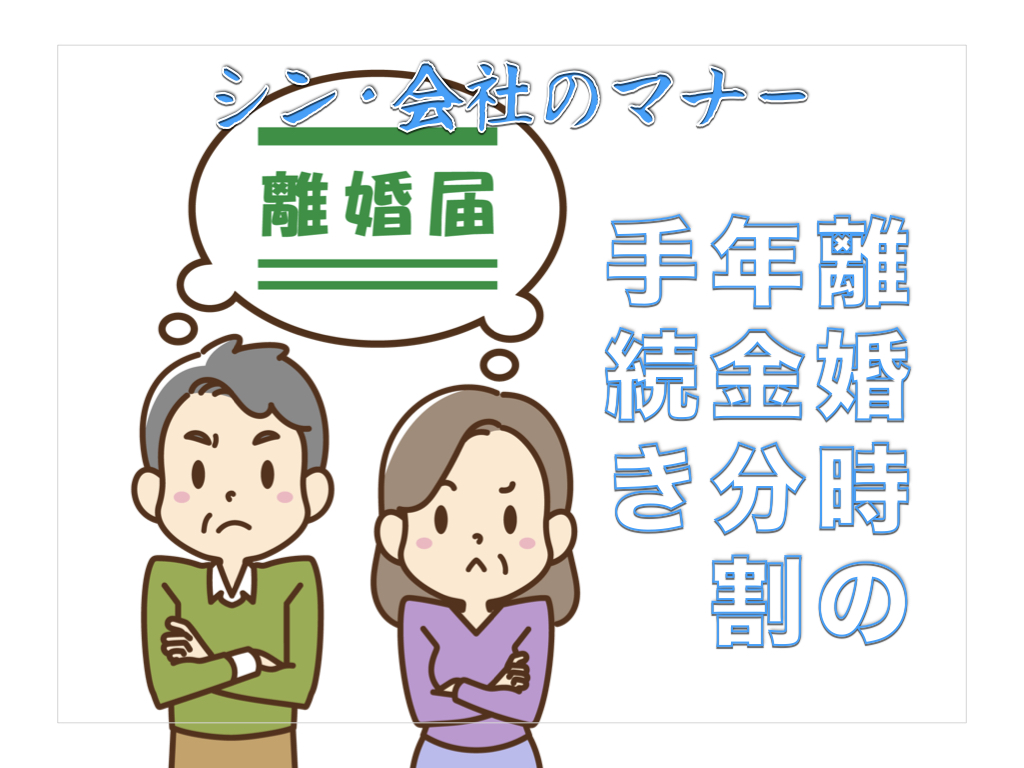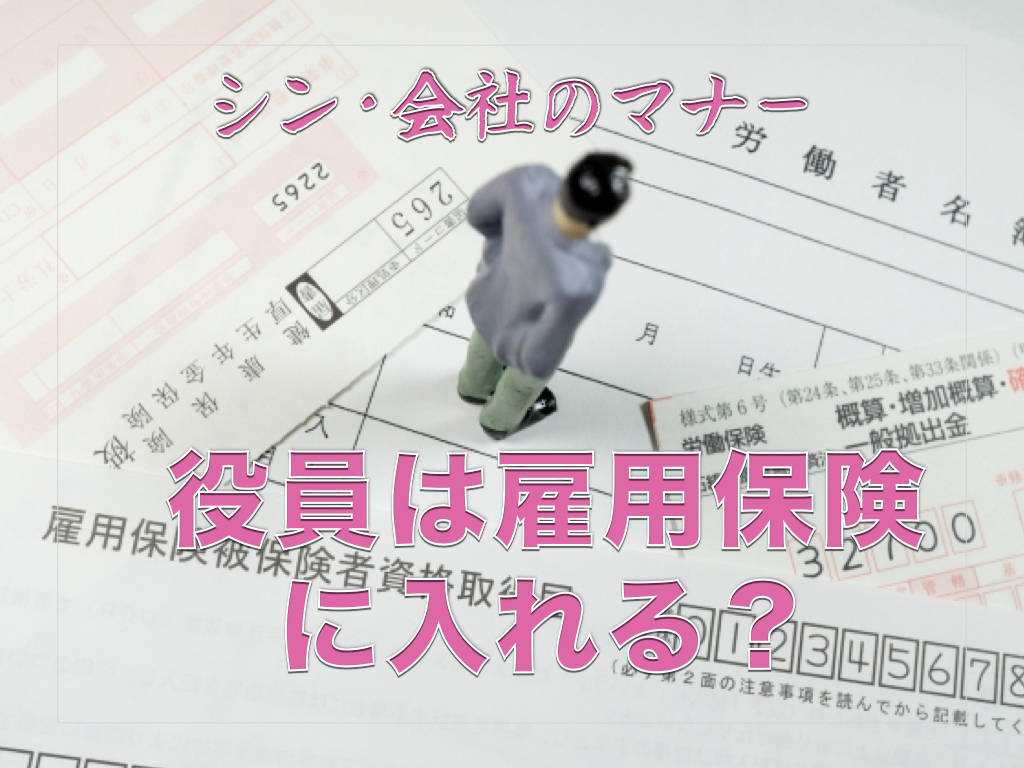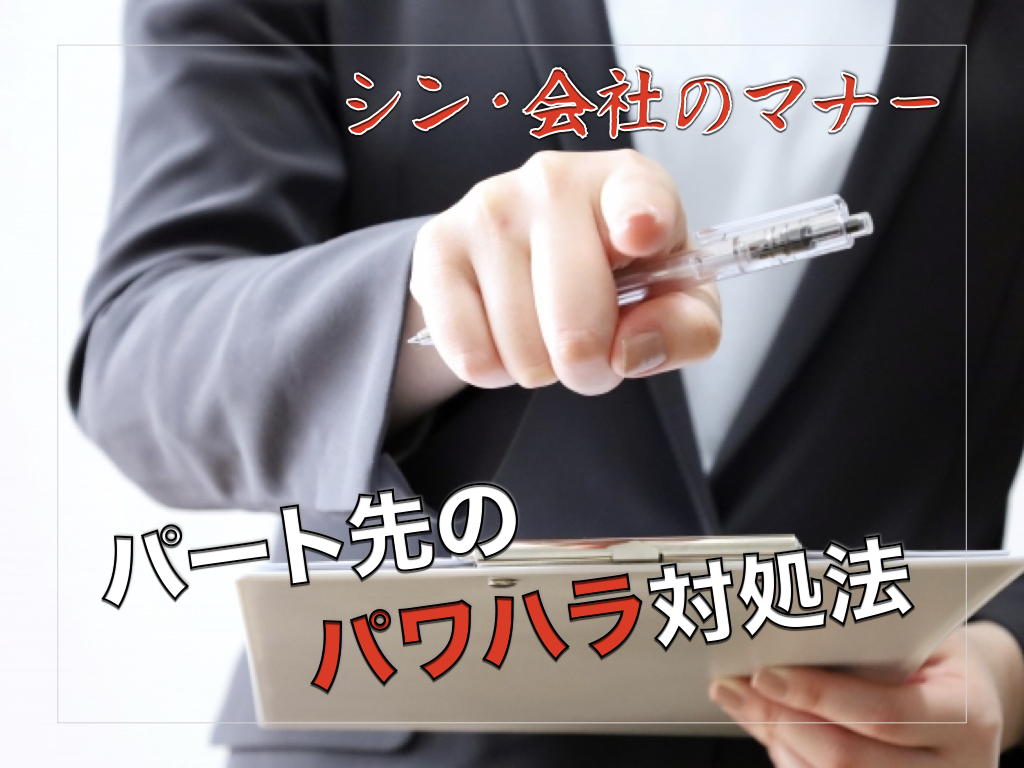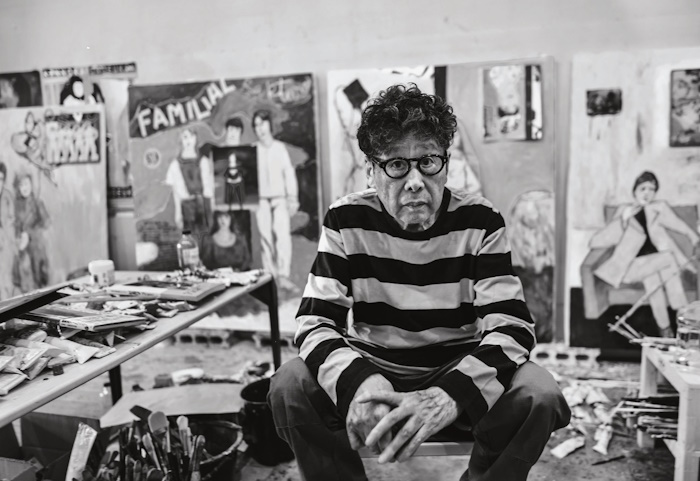多くの人が働く職場では、従業員の働き方や待遇等を定めた就業規則が存在していると思います。
けれども、その内容をしっかり確認している従業員は意外と少ないのではないでしょうか? 今回は就業規則の基本について人事・労務コンサルタントとして、「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
就業規則とは? 労働基準法との関係をわかりやすく解説
就業規則は誰でも見られる? 閲覧権と確認方法を解説
就業規則がない会社は違法? 10人未満の事業所の対応を解説
まとめ
就業規則とは? 労働基準法との関係をわかりやすく解説
就業規則は、法令ではどのように定められているのでしょうか? 就業規則の目的と法的な位置づけについて見ていきましょう。
就業規則とは何か? 知っておきたい基本ポイント
就業規則とは、労働者の労働条件や遵守する規律などを定めた職場における規則集です。
就業規則の内容は、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、職場で定めをした場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。法で定められている絶対的必要記載事項は次のようなものです。
(1) 始業および終業の時刻、休憩時間、休暇、交代制勤務の場合は就業時転換に関する事項
(2) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これに対して相対的必要事項は、退職手当、賞与、表彰、制裁、安全に関する事項や職業訓練に関する事項などが該当します。就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、行政官庁への届出が義務付けられています。原則として職場で働く人すべての人に適用するルールとして作成しなければなりません。
労働基準法との違いと優先順位とは?
就業規則は、労働基準法などの法令に反してはならないとされています。また、労働組合との間で取り決めた労働協約に反することもできません。

遵守すべき優先順位は、(1)法令、(2)労働協約、(3)就業規則、(4)労働契約の順になります。
注意すべきことは、就業規則は労働契約よりも優先順位が上だということです。労働契約とは、個々の労働者と使用者との間で労働条件などについて取り決めたものです。就業規則で定めた基準に達しない労働契約については、その部分は無効になります。 無効になった部分は就業規則の定めを適用することになります。
厚生労働省が示す就業規則の役割とは
従業員の労働条件や職場内で守るべきことは会社によって異なります。就業規則は、会社と従業員との「約束」を明文化したものと言えます。
就業規則を定めることで、従業員は法に反した不当な労働を強いられることがなくなり、会社もまた訴訟などのリスクを軽減できます。
労使間のトラブルを防止し、良好な労働環境を維持することは就業規則の重要な役割です。厚生労働省は、届出義務の有無を問わず就業規則の作成を奨励しており、作成支援のためのモデル就業規則などをホームページで公開しています。
就業規則は誰でも見られる? 閲覧権と確認方法を解説
会社で働いているが就業規則を見たことがない、という人もいると思います。ここでは、就業規則の閲覧について解説します。
就業規則を閲覧する権利はある? 労働者として知っておくべきポイント
従業員には、就業規則を閲覧する権利が当然あります。
労働基準法では、「就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって周知しなければならない」と定められています。
閲覧したい場合は堂々と要求しましょう。また、会社によっては、パソコンなどで就業規則が常時閲覧できるようになっている場合もあります。
自分の職場では、どのような形で内容を見ることができるのか確認しておきましょう。
入社前や家族も閲覧できる? 閲覧の範囲と注意点
就職内定者が入社前に就業規則を見たいということもあると思います。内定者は会社と労働契約が成立しているとみなされますので、就業規則も適用されることが原則です。就業規則の服務規律や労働条件などは内定者にも見せる必要があります。ただ、内定段階では就業義務はありませんので、会社がすべてを開示しなくても違法ではありません。
また、内定者の家族に閲覧を求められる場合があるかもしれませんが、基本的には内定者本人のみの閲覧という形にしたほうがいいでしょう。
「就業規則を見せてもらえない」ときの対応策
従業員が就業規則の閲覧を要求しても会社が見せてくれないという場合は、労働基準法違反の疑いがあります。従業員に就業規則を周知することは法令で定められており、周知していない就業規則は無効と判断されるおそれがあります。
会社が就業規則を見せることを固く拒む場合は、同僚とともに複数で閲覧を求めるといいでしょう。会社としても、従業員が労働基準監督署などに申告すれば、行政指導を受けることになりますので、きちんと対応する必要があります。
内定者に対しても、就業規則の閲覧を拒むと、「規則に不備がある」という疑念を持たれかねません。作成義務のある会社は、職場でいつでも見ることができるように就業規則を整備しておくことが重要です。
就業規則がない会社は違法? 10人未満の事業所の対応を解説
就業規則はすべての会社に作成義務があるわけではありません。従業員が少人数である会社の対応についても確認してみましょう。
就業規則の作成義務はある? 10人以上と未満の違い
労働基準法において、就業規則の作成義務が定められているのは、常時10人以上の労働者を使用している事業場とされています。10人の中には正社員だけでなく、パート・アルバイトなども含まれます。
この条件に該当する会社は、就業規則を作成し、労働者の過半数代表者からの意見書を添付して所轄労働基準監督署に届け出る義務があります。
なお、規則に反対する意見書であっても、就業規則の効力には影響しません。必要事項に変更があった場合も届出が必要になります。 従業員が10人未満である場合は、作成・届出の義務はありません。
就業規則がないときのリスクと対策
少人数の会社は作成が義務付けられていないので、就業規則がない会社も多数あります。けれども、就業規則がないことによるリスクは軽視できません。
まず働く側のリスクです。会社と労働者との労働契約は、個々の労働者に対する民事的ルールであるため、労働基準法のような罰則はありません。就業規則があれば、従業員は法に守られているという安心感を持って働くことができます。
会社にとっても、就業規則がないことによるリスクはあります。社員が大きな問題を起こしても、服務規律や懲戒・解雇などの定めがないと安易な処分はできません。
労務トラブルや訴訟などを避けるためにも、就業規則の役割は重要です。
まとめ
就業規則の作成・届出義務があるのは、常時使用している労働者が10人以上の事業場です。けれども、届出義務のない会社であっても、就業規則の重要性を考えると、作成した方が望ましいでしょう。就業規則は会社と従業員双方にメリットがあるものです。適切なルールのもとで安心して働ける会社をめざしましょう。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com