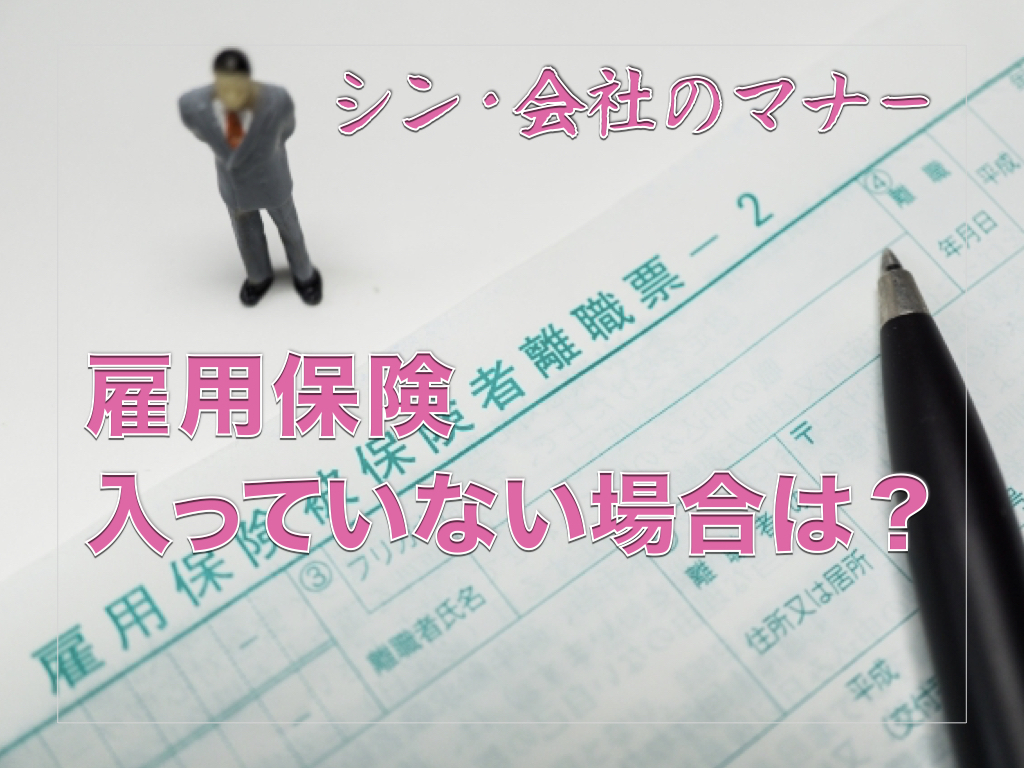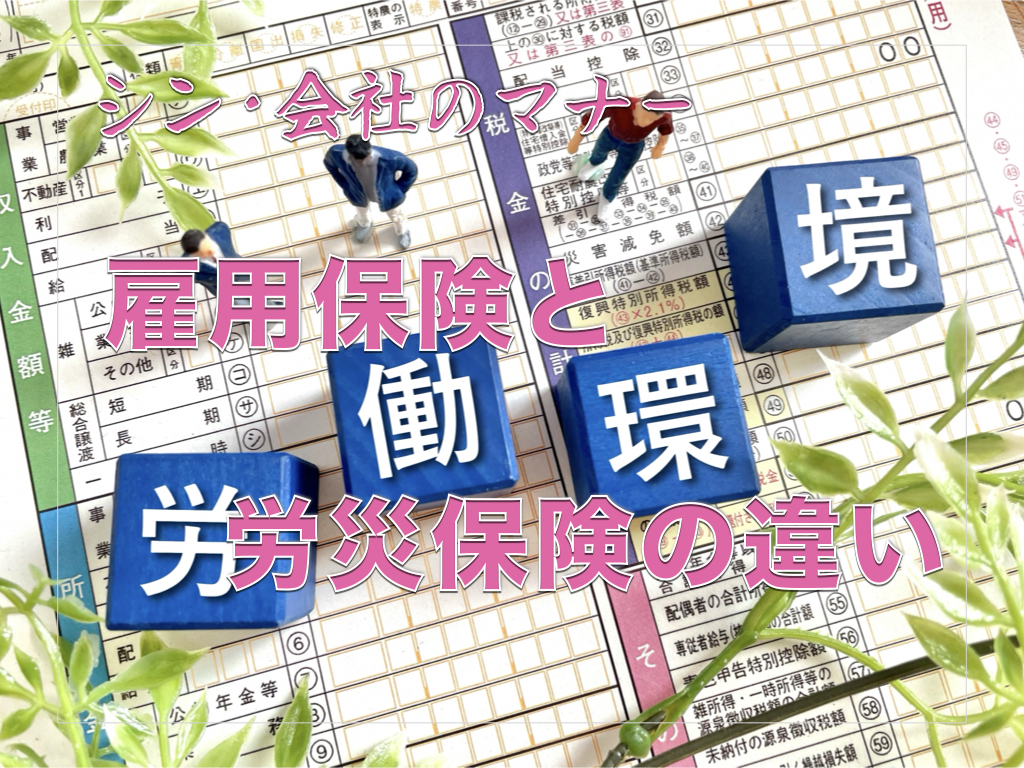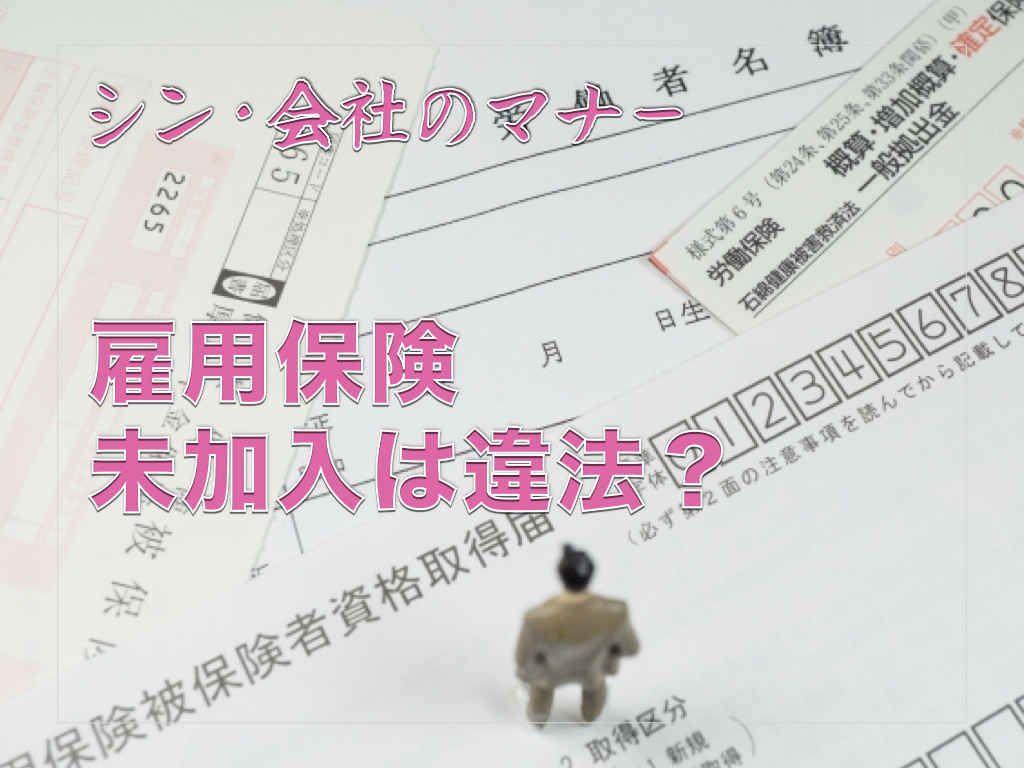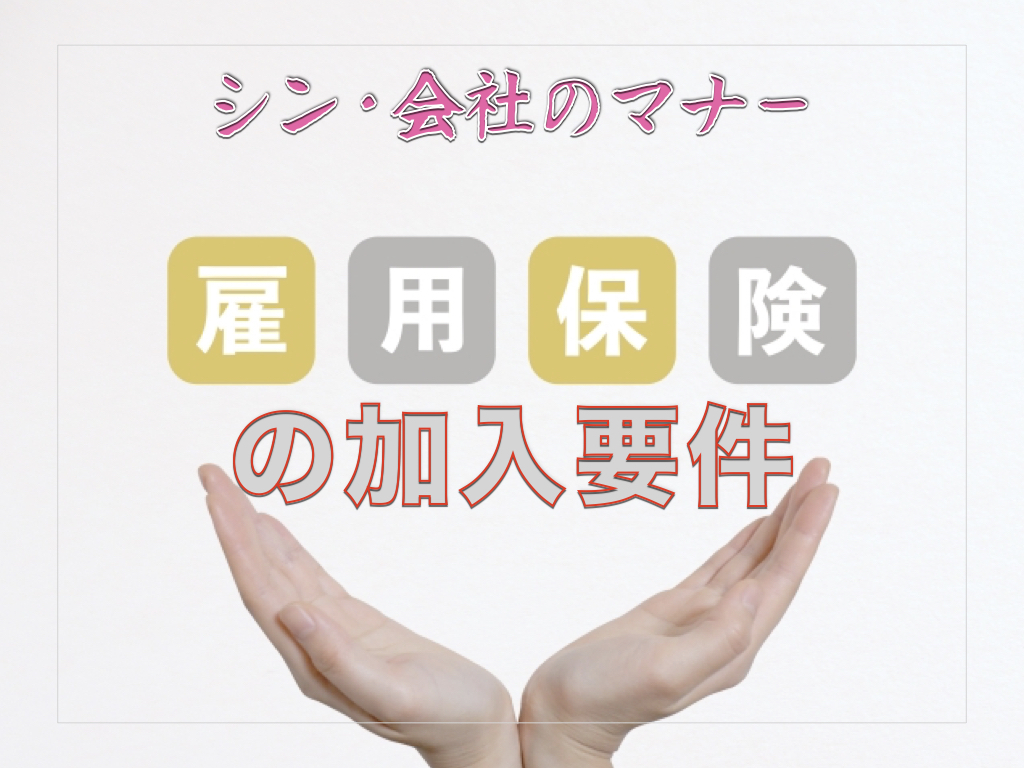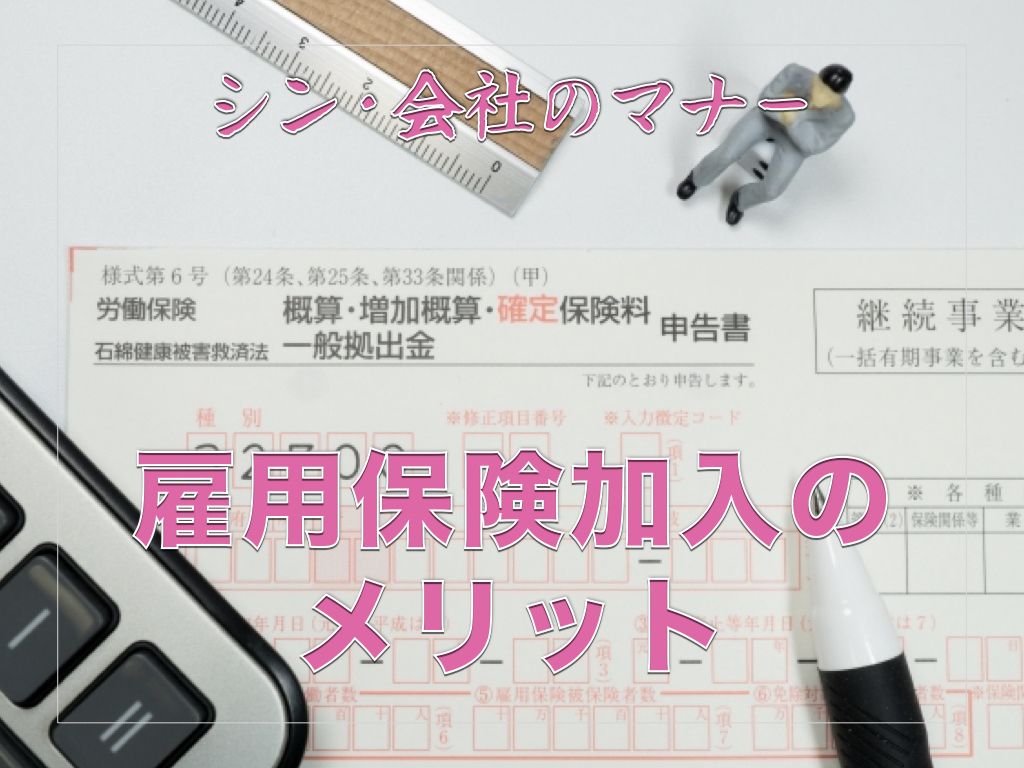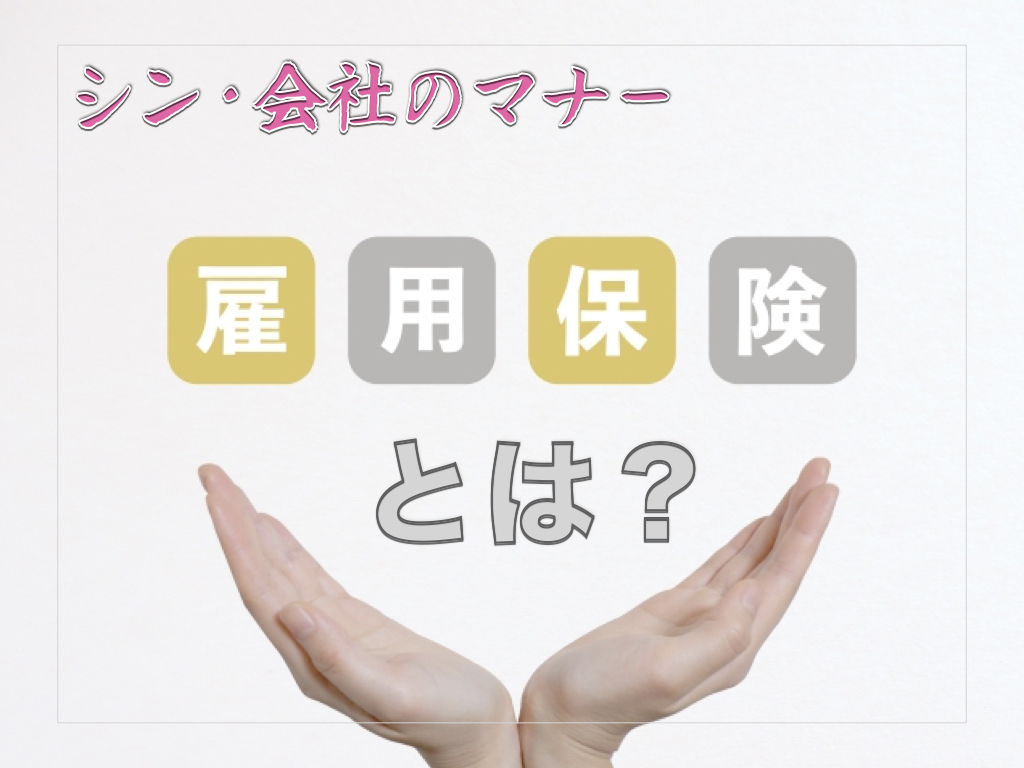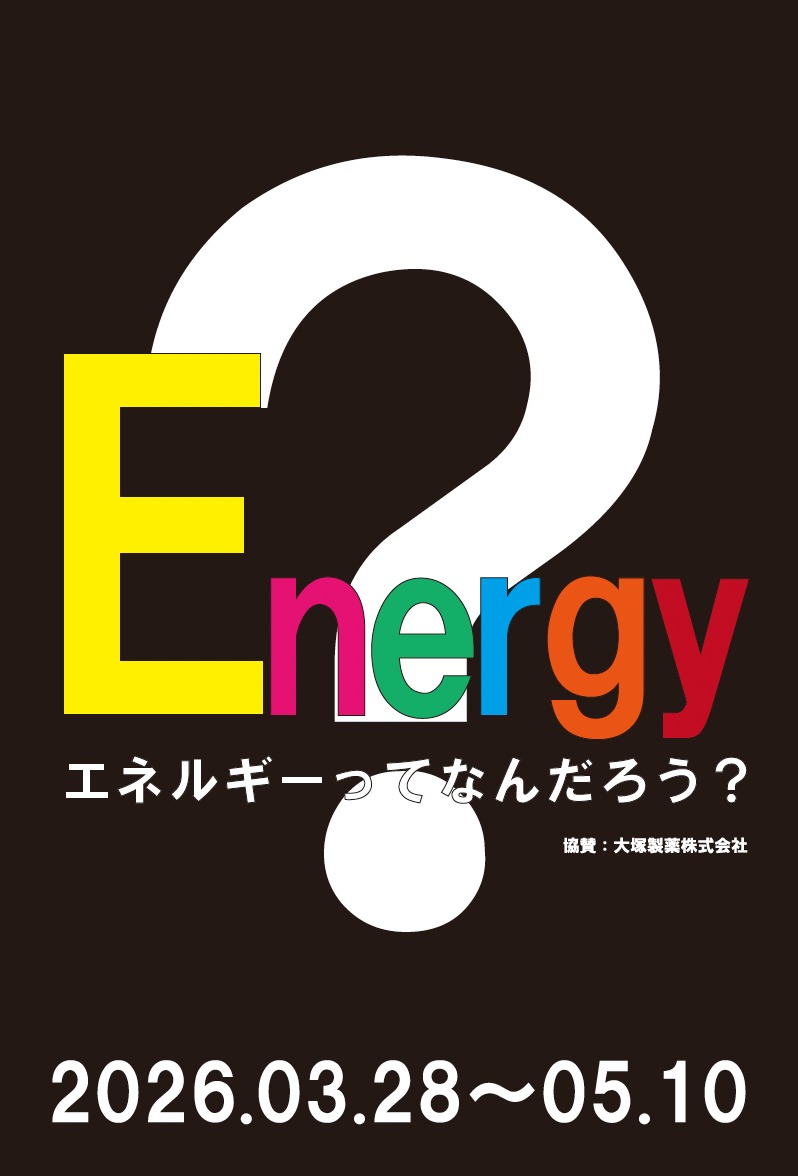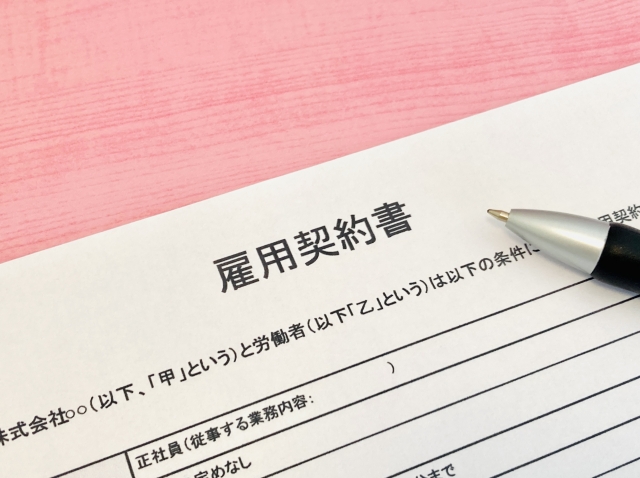
雇用保険制度は文字通り、事業所に雇用されて働く人のための制度です。雇用保険は、労働者が失業したり、育児・介護・高齢などで雇用の継続が困難になった時に、経済的にサポートするという重要な役割を担っています。それゆえ、労働者を一人でも雇用している事業は原則として強制的に適用事業所となります。適用が任意なのは個人経営の農林水産業など、ごく一部だけです。
そうなると、労働者がいればほとんどの事業があてはまりそうですが、実際はそうではありません。適用事業所ではない会社、事業所は数多く存在します。これはどのような理由によるものでしょうか? 今回は、雇用保険の適用事業所について、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
雇用保険の適用事業所とは?
適用事業所の条件
条件に該当しない場合、どうなる?
まとめ
雇用保険の適用事業所とは?
雇用保険は、企業単位ではなく、本店、支店、工場などの個々の事業所を単位に適用されます。冒頭に書いた通り、労働者を一人でも雇用している事業は原則として強制適用事業所になります。強制適用に該当する事業所は、当然に雇用保険が適用されますが、保険料の徴収や給付の手続きをする上で届出は必要です。
事業所を設置した時は、その設置の日から起算して10日以内に、適用事業所設置届を所轄のハローワークに提出しなければなりません。例えば、一つの会社でも、独立性のある支店、工場などがいくつかあるとすると、会社は事業所ごとに届出を提出する必要があります。
一方で、雇用保険への加入が任意となる事業もあります。それは、個人経営であって、常時雇用する労働者が5人未満の農林水産業です。これらは、行政がすべてを把握するのは困難であるという理由もあり、暫定任意適用事業とされています。ただし、水産業の中でも、船員を一人でも雇用している場合は、強制適用となります。
このように加入が任意である事業は限られており、法人の場合は、雇用している人が5人未満であっても、任意適用とはなりません。それにもかかわらず、適用を受けていない会社とはどのような会社を指すのでしょうか? もちろん労働者を雇わずに、一人で事業を行なっているのでしたら、雇用保険は適用されません。けれども、人を雇って賃金を支払っていても、適用事業所にならないケースも存在します。
これは、労働者の定義にポイントがあるのです。次にこの労働者の定義について、具体例を挙げて説明していきます。
適用事業所の条件
繰り返しますが、労働者を一人でも雇っている事業は強制的に適用事業となります。ただし、被保険者となる人がいない場合や、雇用しているすべての労働者が適用除外者である場合は適用事業所にはなりません。ここで適用除外者という言葉が出てきました。雇用保険は被保険者となる要件があります。それは「所定労働時間が週20時間以上であること」と「31日以上雇用される見込みがあること」です。この要件を満たさないと被保険者になることはできません。
また、こうした要件にかかわらず、雇用保険の対象とならない人もいます。事業主はもちろん、事業主と同居している親族、取締役、役員は原則として被保険者になれません。家事使用人、昼間の学生、4か月以内の期間を定めて、週30時間未満の労働時間で、季節的に雇用される人なども適用除外となります。ただし、会社の役員や学生であっても被保険者となるケースもありますので、判断が難しい時はハローワークでの確認が必要です。
被保険者にならない人のみを雇用している場合は、適用事業所になりません。つまり、適用事業所というのは、被保険者となるべき労働者を、一人以上雇用している事業所ということになります。また、一般被保険者の要件とは異なる要件の被保険者もいます。
季節的に雇用される労働者であって、4か月を超える期間で週30時間以上の労働時間で雇用される短期雇用特例被保険者、日々雇用される日雇労働保険者という区分があります。これらの人を雇う事業所は、被保険者がいるので適用事業所になります。

条件に該当しない場合、どうなる?
では、適用事業所でない事業所で働く人は雇用保険に加入することはできないのでしょうか。適用除外の理由が労働時間だけである場合、週20時間以上働くことになれば、被保険者の要件を満たすことになります。そうなると会社は、雇用保険の適用事業所の届出と、被保険者の資格取得届を提出しなければなりません。
しかしながら、小規模な事業所などは労働契約が曖昧なところも多く、担当者も雇用保険の知識が乏しいことがよくあります。そうなると実際は雇用保険の被保険者となるべき人がいるのに、適用事業所となっていないケースも少なくありません。本来、労働条件の提示は雇用する側の義務なので、労働時間や雇用保険の加入の有無などについてはしっかり確認しましょう。
届出を出すべき時からかなり日数がたっていても、2年間はさかのぼって加入することができます。さらに、暫定任意適用とされている事業所の場合でも、雇用保険に加入することは可能です。個人経営の農林水産業で労働者が5人未満の場合は任意適用となるので、適用事業所にならなくても違法ではありません。けれども、事業主の加入意思と働く人の2分の1以上の同意があれば、雇用保険に任意加入することができます。
では、事業主に加入する意思がなかったらどうなるでしょうか? その場合でも、2分の1以上の労働者が希望する場合は、事業主に加入義務が生じます。つまり4人雇用されている事業所だと、2人が希望すれば良いということです。任意加入する場合は、任意加入申請書と労働者の同意書をハローワークに提出し、厚生労働大臣の認可を受けることになります。
まとめ
雇用保険は、働く人の雇用・経済の安定のためには重要な制度です。被保険者となる要件を満たして働いていても、会社が適用事業所でなかったら、必要な給付を受けられなくなってしまいます。そのためには、雇用保険加入の有無を含め、労働条件についてしっかりと会社に確認する必要があります。もしも、会社がなかなか手続きをしてくれなかったり、被保険者になれるかどうかわからないという場合、ハローワークに相談しましょう。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com