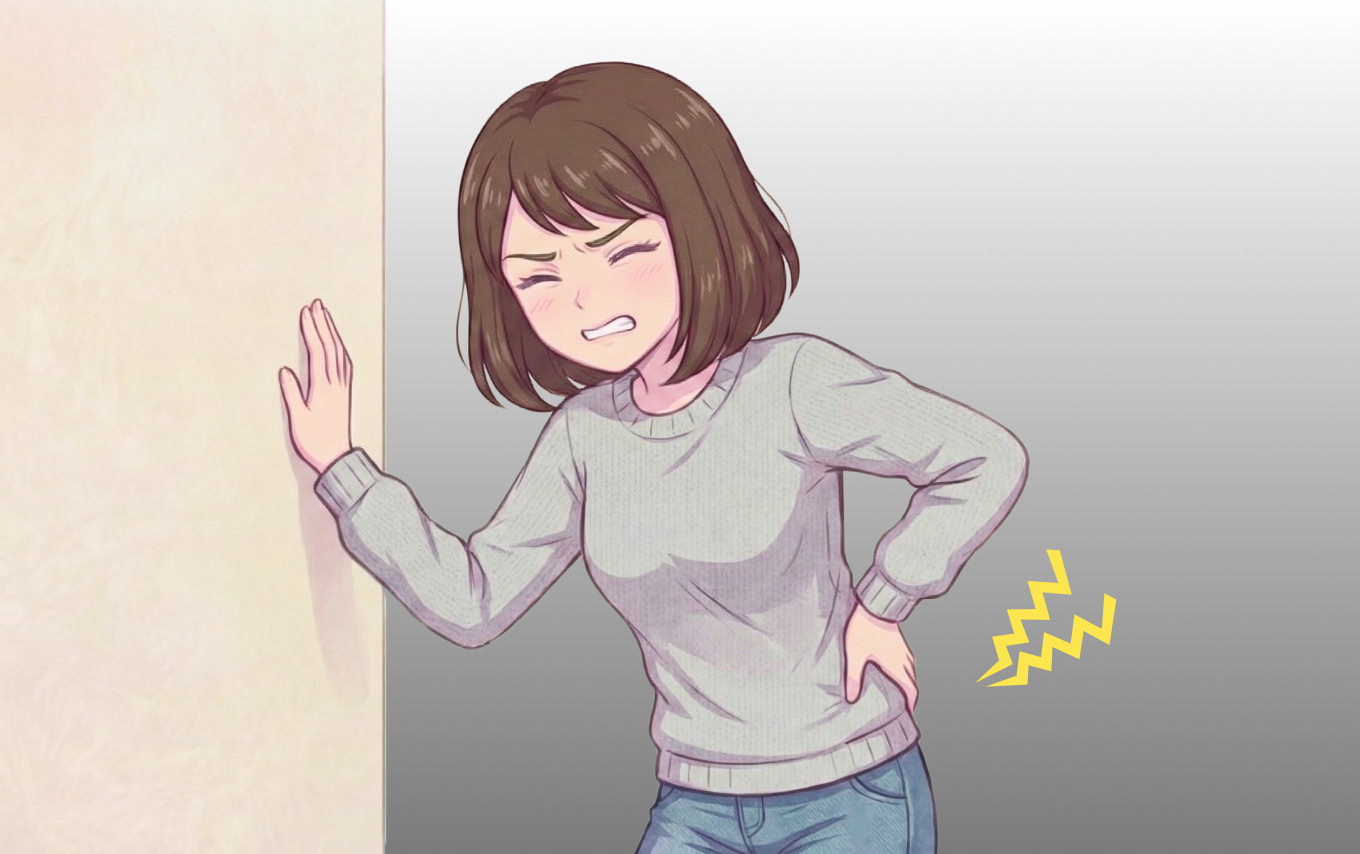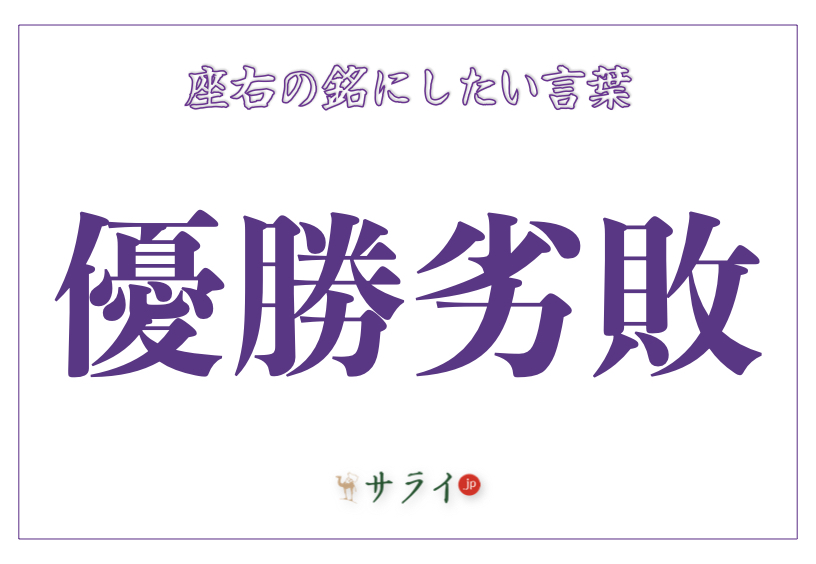高卒にも関わらず、多くの仕事を任された
芳雄さんの会社は、高卒採用者は製造ラインに回されるのが常だという。
「ただ、僕は物理や数学ができたからか、経理部に回されたんですよ。今、そこは子会社になっていますけど、僕のときは本社の一部門でした。毎日、毎日、伝票と帳簿と格闘し、絶対に間違えてはいけないから確認作業の連続。コンピューターが導入されていましたが、扱いが難しく、できることは限られていたので、ペーペーの僕は触れない。決算の時期は泊まり込みになることもあり、親父が“何もしなくても給料がもらえるわけじゃないんだな”と言っていたことを覚えています。仕事は大変でしたけれど、上司や同僚に可愛がっていただいていました」
転機は勤続3年目のとき。開発部門に異動したことだ。
「当時の企業は本人の適正に関わらず、強制的に異動させるようなところがありました。僕は気が弱いから人当たりがいい。さらに当時は“紅顔の美少年”だったので(笑)、開発部門の人が“渉外担当者として使える”と思ってくれたのでしょう。顧客の設備を提案し、維持管理する部署に抜擢され、43歳まで働きました。高卒なのに、多くの仕事を任され、場数を踏めたのはありがたかったですね」
2003年に芳雄さんがこの会社を辞めたのは、2001年に発足した小泉内閣が掲げた「聖域なき構造改革」からのリストラがあったからだ。
「大企業もすごかったですよ。子供がいない人から“肩叩き”を食らい、拒否すると僻地の工場や閑職に回された。大卒で格別優秀な人以外は、対象になったんじゃないかな。リストラを担当した人が、心を病んで退職したなどの噂も流れました」
当時43歳の芳雄さんは妻と結婚してから13年目で子供はいなかった。
「妻は看護師で働いている。家も買っていなかったので、辞めさせられるくらいなら、自分から辞めちまえと腹を括った。加えて、両親もとっくに亡くなっており、実家の事業も他人に譲渡されていました。リストラされる前に、自主退職する道を選んだことを取引先で話したら、“ウチに来ませんか?”と言われ、渡りに船で話に乗ったんです」
取引先に就職するときに、芳雄さんが気をつけたのは、上下関係を間違えないこと。
「大手企業の社員だったプライドというのは確かにある。中小企業は仕事量も多い。でもそれに不満を言ったり、周囲の人を見下すような態度をとると、たちまち疎外される。だから、常に上下関係を意識し、拾ってくれた会社に染まるように、日々を過ごしました」
ある資材のリサイクル工場を運営するその会社で、芳雄さんは大手勤務の知見を活かし、ラインを整え業務拡大に貢献した。
ただ、高卒なので給料は安く、同族企業なので役員にはなれない。「今後、どうしようか」と考えているときに、15年前に辞めた会社から「アルムナイ制度が導入されました。再び働いていただけませんか」という連絡があった。
【社員としての賞味期限のようなものはある……その2に続きます】
取材・文/沢木文
1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』 『不倫女子のリアル』(ともに小学館新書)、『沼にはまる人々』(ポプラ社)がある。連載に、 教育雑誌『みんなの教育技術』(小学館)、Webサイト『現代ビジネス』(講談社)、『Domani.jp』(小学館)などがある。『女性セブン』(小学館)などにも寄稿している。