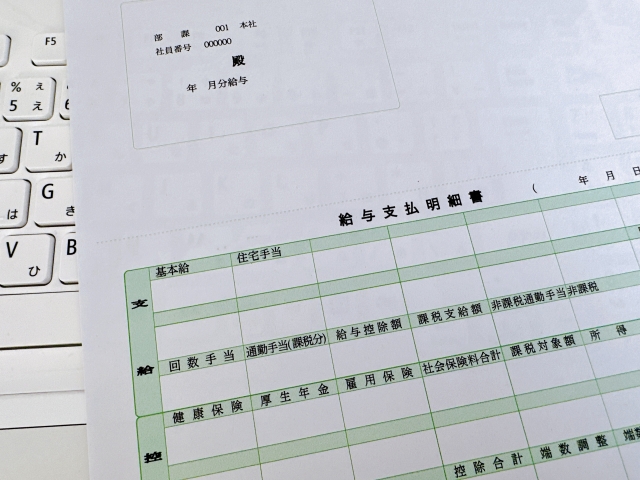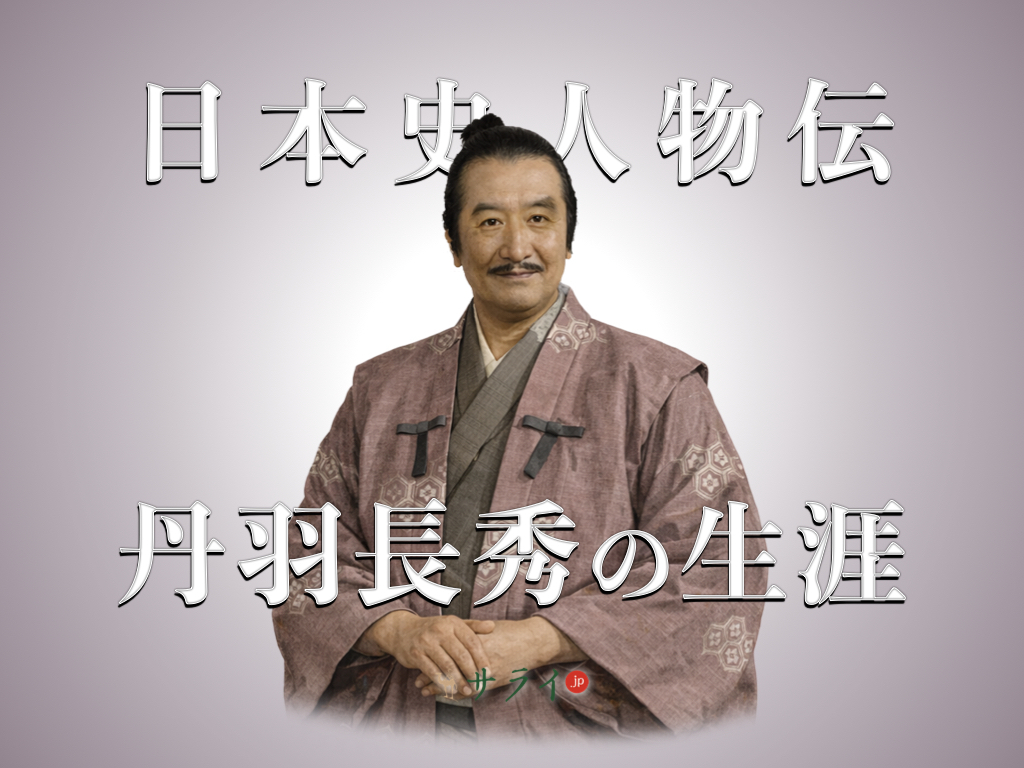マネジメントに必要なものは素養でしょうか? それとも、素質なのでしょうか?。マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)では、一つの答えを提示します。
* * *
「マネジメントは素養」
「マネジメントは素質」
どちらが正解でしょうか。
さまざまなご意見があるでしょうが、今回は再現性、継続性の観点、かつマネジメント従事者や候補者の皆さんに明るい未来を期待させたいという観点で、一つの答えをお示ししたいと思います。
誰もがマネジメントの一流からスタートするわけではない
言葉の意味から解説していきましょう。
素養は、「日々の学習や訓練によって得た知識や能力」であり、素質は「生まれつき持っている性質や能力」を指します。
誰もがマネジメントのスキルを持って生まれてきたわけではないはずです。
例えば、代々、経営者やリーダーの家系であれば、幼少期から「あなたは将来、経営者になるのよ」とか、「リーダーたる立ち居振る舞いをしなさい」など、その教育や環境によって、自ずと「マネジメントのいろは」を刻み続ける生活に染まっていくことになるのかもしれません。ただ、たとえその血に素質があったとしても、そのような絶対自動マネジメント力向上環境が一切ない環境やコミュニティで過ごせば、マネジメントにおけるスペシャリストのレールから脱線することもあるでしょう。
逆に、親も親戚も代々全て平社員。素質はまるでなし。幼少期も通信簿は普通ばかり。このようなケースでも、マネジメントのスペシャリストになり得るものです。
つまり、誰もがマネジメント力を向上させることができる、そのカギとは、ズバリ、素養です。
では、その「素養」のメカニズムを解説していきます。
ソヨウのヨウソ
では、素養には何が必要なのでしょうか。
素質をもっていると考えている持ち主にとっては、そんな根も葉もない「ソヨウのヨウソなんてヨソウヨ」などという声が聞こえてきそうですが、識学では「成長」というキーワードで説明しています。
すべての人は「成長」する――識学にはこの考え方が根底にあります。その方程式は以下の通りです。
成長とは……「できなかったことが → できるようになること」
【識学の成長の定義】
できないことは練習や学習によって身に付き、できるようになることで、その能力が成長するということです。
マネジメント力もしかり。これを否定するとなると、世の中の部長や従業員たちは「会社というBOX」に対して「上司ガチャ」というもので、運を天に任せることとなるのではないでしょうか。
上記をまとめると、このように言えます。
「素養」という名の「成長サイクルづくり」が、すべての部下だけでなく、すべての上司のマネジメント力さえも向上させることができる。
では、その成長サイクルの条件をご案内しましょう。
成長サイクルの条件
成長するためには絶対条件として、経験(量)が欠かせません。
仕事以外のものを例に取れば、野球でも勉強でも成長の要件としては、打席数や勉強時間などといったものがその量として表現できます。
ただし、経験という名の量をただひたすら繰り返すだけでは、成長の条件としては不十分であり、同時に質(集中)が不可欠です。集中せずに、ただバットを振り回す回数を増やしても、打率や打点が上がるわけではないでしょう。
マネジメントにおいては、部下が業務に集中して、目指すべき最後のゴールへ突き進むためには、上司はそのゴール(結果)を明確に設定することが必要となります。
このゴール設定はマネジメントの一丁目一番地。ここから始まります。
そして、ゴールを迎えて未達成となった場合は、その未達成(不足の内容や数量)を明確にして、不足を埋めるための行動変化を部下に考えさせ、次の結果を約束させることが重要です。次のサイクルの結果設定を上司が明確化し、部下はその結果に向けて質という名の集中力を持ち、走り続けることとなります。
ここで重要なポイントとなるのは、ゴールを切ってから次のスタートをするまでの上司と部下のグリップであり、スタートとゴールの間の経過ではないということです。
この前のゴールと次のスタートの間における上司部下のコミュニケーションや約束を識学では「結果の完了」と呼び、この作業を淡々とサイクル化して実行することで、部下の不足が明確化され、その不足を埋め続ける部下は必然的にできないことができるようになっていきます。
これこそが、結果の完了という名の成長サイクルづくりの仕組みです。この再現性や継続性は、特定のスペシャリストしかできないものでしょうか。そんなことはありません。識学の面白いところは、ロジック通りにやってみると誰もができるというその再現性や継続性といった点です。
結果の完了の4要素
ただし、この結果の完了は部下任せでは成立しないものです。
結果の完了では、次の4つの要素が不可欠となります。
・結果を明確に設定すること(結果の明確化)
・期限時の過不足を明確にすること(不足の明確化)
・不足を埋めるための行動変化や改善策を考えさせ実行させる(行動変化の明確化)
・不足を埋めることを約束させる(次の結果の明確化)
成長のためには、「できないこと=自身の不足を認識させること」が不可欠となります。
その一連の流れや行動は、部下に任せていてもなかなかできるものではないので、上司がその結果の完了サイクルにより、部下の迷いも同時に排除します。完了の管理をし続けることは、自ずと成長の管理をすることとなるわけです。
このとき、行動変化や具体的な解決策までを示唆したりアドバイスしたりしないようにしましょう。結果が出なかった際に、部下が「上司の指示通りにやったのに、結果が出なかった」「指示を出した上司が悪い。自分には未達となった責任はない」と考えたり、言い訳したりするかもしれません。
識学ではこれらを「免責」と呼びます。免責が発生する組織では、結果や自身の責任に対して、無責で言い訳癖の強い、他責思考で無責任な部下が量産されることとなります。
マネジメントは素養!
マネジメントの正解は見つかりましたでしょうか。
「マネジメントは素養!」
識学はこの素養、成長のテーマを基に「識学を広めることで人々の持つ可能性を最大化する」を掲げ活動しています。部下だけでなく、自身でさえも、成長のためには結果の完了をサイクル化し、そのサイクルを早めることで、成長も加速化すると定義しています。
マネジメントに課題をお持ちの経営者や管理職の皆さん、ぜひとも識学の門を叩いてみてはいかがでしょうか。忌憚なきご意見、ご要望、ご相談をいつでもお待ちしています。
【この記事を書いた人】
シニアコンサルタント営業2部係長 田中晃/――なぜ識学に興味を持ち、入社することになったのか教えてください。 理由はいたって簡単で、わたしが抱いていたマネジメントの課題を解決できるのは識学だけだったから。これに尽きます。わたしだけでなく、クライアントも同じような悩みを抱えていました。このような悩みを解決することで、人の役に立ちたいと思い入社を決めました。
引用:識学総研 https://souken.shikigaku.jp/
コンサルタント紹介はこちらから https://corp.shikigaku.jp/introduction/consultant