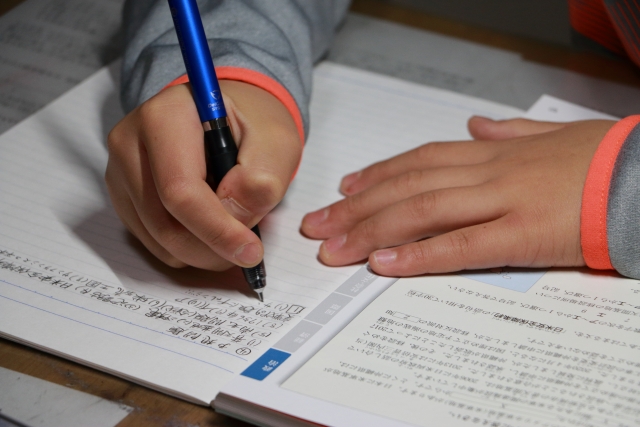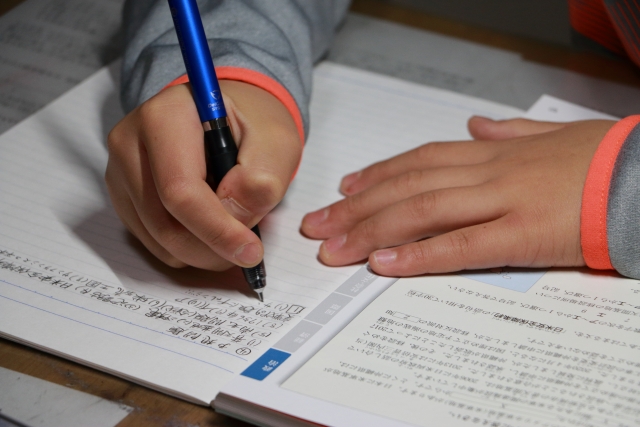
取材・文/沢木文
親は「普通に育てたつもりなのに」と考えていても、子どもは「親のせいで不幸になった」ととらえる親子が増えている。本連載では、ロストジェネレーション世代(1970代~80年代前半生まれ)のロスジェネの子どもがいる親、もしくは当事者に話を伺い、 “8050問題” へつながる家族の貧困と親子問題の根幹を探っていく。
* * *
「金はあっても、文化はない」という劣等感
聡志さん(仮名・70歳)は、都内郊外の広い家に息子(41歳)と2人暮らしをしている。大手企業に定年まで勤務し、親の遺産を基に資産も形成していたが、コロナ禍を機に息子が転がり込んできて、悪夢のような現実を突きつけられた。
聡志さんは東海地方の資産家の家に生まれ、県立トップの高校から、都内の有名私立大学に入った。そこは、政財官界の名家の子弟が集まる学校で、小学校からその学校に入学しているグループと、大学から入学しているグループでは、文化が大きく異なったという。
「大学に入って、“日本は階級社会だ”と思いました。僕はベビーブーム世代で、戦後の爪痕がまだ残る時代に生まれ育ち、みんなが貧しいと思っていた。そんな中、実家は裕福で、“食べるのに困る”という経験をしたことがなく、“お金がないから諦める”ということを考えたこともなかった」
聡志さんの実家は地元の名家で、広い庭に池があり、政治家が金を借りに来ている風景を何度も見たという。
「大学に入るまでは、“ウチが日本で一番豊か”だと内心は思っていた。しかし、大学の“上流クラスの人々”とは天と地ほどの差があった。大学の同級生には、日本史の教科書に登場している人の子孫がゴロゴロいて、昭和40年代なのに海外で生活をした経験がある人も多かった。留学経験がある人もおり、もう段違いだった」
最も異なるのは“文化”だったという。
「ウチも金はあったけれど、子供に海外留学させるという発想はないし、コネもない。当時、そういうことを“普通”のように語っていることに驚きました。なぜか私はそのグループに気に入られて、卒業する頃には仲間の一人になっていた。今でも交流は続いており、自宅も仲間の紹介で手に入れたんです」
聡志さんの話を聞くと、恵まれた人の中で情報や金が回っているのだと感じる。
「なんだろう、動くものと人が大きく、彼らはケチケチと私腹を肥やそうとはせずに、“天下の周りもの”と鷹揚に構えているところがある。なにもかもが違うから、劣等感はあっても、うらやましいとは思えなかったよね」
【息子の小学校受験は不合格だった。次のページに続きます】