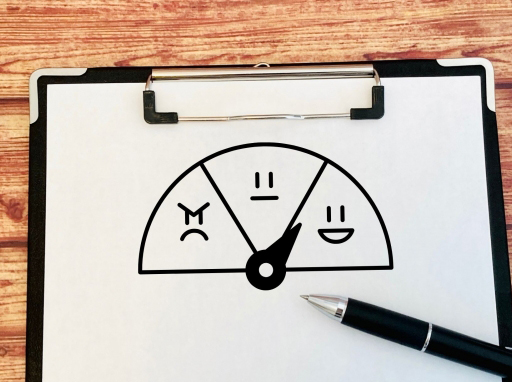学力につながる試練に挑むことが受験にもつながる
―――自分を律し、自分で能力を磨いていく子供を育てるにはどうすればいいのでしょうか。
やはりほめることだと思いますよ。あとは、目標を設定することも大切です。やはり、目標がないとモチベーションが上がりませんから。
そこで私は「算数検定・数学検定」(実用数学技能検定)を受けさせたのです。根拠が明確な基準なので、合格すれば子供もうれしいものです。
幼稚園のときに、1年生相当を、1年生の時に2年生と3年生相当をと、先取りで受験していたのです。そして、合格したら協会からいただく表彰状のほかに、私が子供向けにメダルを手作りして、表彰していました。この積み重ねの先に、長男が小学生で獲得した算数オリンピックの金メダルがあると思います。
定期的に試験を受けることは、本番に強くなるメリットもあります。与えられた時間で、どの時間配分で問題を解くか。その集中力の練習にもなるんですね。
――そんな子供を見守っていると、大人自身が気付くことは多々あります。
子供目線になると、大人も楽しいですよ。特に、乳幼児期から学童期にかけて、子供と一緒に楽しく遊ぶことが気付きの連続でした。子供の好奇心を想像して、先をくみ取りながら、問いかけを繰り返していく。子供と接していると、お互いが学び合いであり、「ちょっと何かを楽しもう」という発想があります。
――祖父母の立場から、どのように子供の能力を育てればいいのでしょうか。
影ながら応援するという立場でいいと思います。私自身、両親に子供を預けることがありましたが、「特に何もしなくていいから。いっしょに遊んでくれたらいいよ」と言っていました。
すると私の両親や夫の両親は、日常の畑作業につれていったり、自分たちの興味がある場所に連れて行ってくれるんです。
私たち親はどうしても買い物や総合施設・テーマパークなどに連れて行ってしまいますが、両親は孫たちに神社や姫路城などの史跡を見せてくれました。田畑や菜園を持っていたので、大豆を乾かしたり、梅干しを干したり……ありのままの生活が、子供にとっては学びの連続だったようです。
子供たちは絵日記帳を持って行くのですが、そこには、子供ならではの気付きが描かれていたのです。家に帰って、事典であらためて調べ直しをしていました。
子供はさまざまな能力があり、それが学力に結びついていくのです。それに気づき、ほめて伸ばすことが大切です。
* * *
子供の学力を伸ばす親というと、いわゆる「教育ママ」を連想するがそうではない。おおらかに子供を見守り、個々の才能を伸ばす。正解がない時代に生き抜く力は、自ら研鑽する力なのではないだろうか。
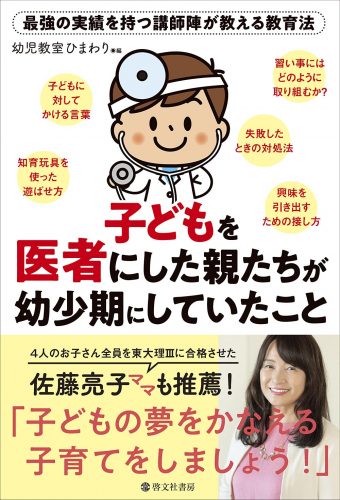
幼児教室ひまわり著 啓文社書房 1650円
難関校に合格するのはもちろん、子供の能力を最大限に引き出すことに定評がある「幼児教室ひまわり」の教育方法を紹介。柴田さんは、ここで講師を務めている。東大に首席合格、算数オリンピックで金メダルなど、最強の子育て実績を持つ講師陣が教える秘策を解説している。