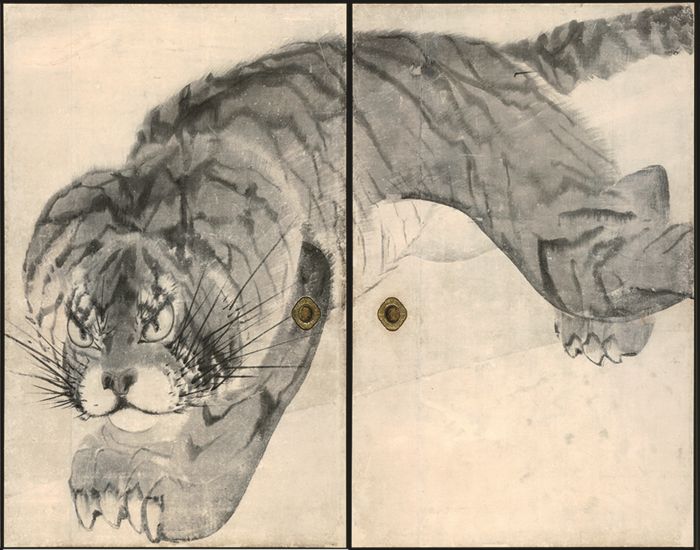取材・文/坂口鈴香

篠文代さん(仮名・54)は、介護歴15年のベテラン介護職員だ。同居していた篠さんの実父(90)は脳梗塞で2度倒れた。1回目の後は自宅で介護していたが、2回目には担当医から「もう自宅介護は無理」と言われてしまった。
【1】はこちら
父は生きようとしている
その後、父親は1回目のときにも入院したリハビリ病院に転院した。
「リハビリ病院では、『家に戻しませんか?』と言われました。『施設を探します』と答えたところ、びっくりするくらい対応が冷淡になりました。1回目の入院で家に戻ると言ったときは、ものすごく熱心にリハビリをやってくれたので、あまりの対応の違いに驚いたほどです。あとで考えると、患者が家に戻ると保険点数が高かったんだろうと思います」
リハビリ病院から、もうひとつ提案されたことがある。「胃ろうをつくらないか」ということだった。胃ろうとは、お腹に小さな穴を開けて、胃に直接栄養を送ることができるようにしたものだ。
「ずっと経鼻のチューブをつけているのは本人にとってもつらいので、胃ろうにしてはどうかということでした」
篠さんには特養で働いていた経験があり、胃ろうの高齢者の介護もたくさん行っていたという。
「だから、胃ろうをつくると“人間らしい状態ではなくなる”ということが、肌身に沁みてわかっていたんです。だから、胃ろうには反対でした。それに、以前父が元気だったころ、胃ろうの話になって『もしそんな状態になったらどうする?』と父に聞いたら、父は『したくない』と即答しました」
それでも篠さんは、胃ろうをしてはどうかという提案を受けるか、迷った。
「そのとき父は頭もしっかりしていましたし、リハビリもがんばっていました。父は生きようとしているというのがよくわかったんです」
父親は生きようとしている――だから、篠さんは胃ろうを選んだ。
そして、いや、しかしと言うべきなのか、篠さんは最終的な判断を父親に仰いだ。
「でも、私は父に『うん』としか言えないような聞き方をしたんです。『鼻のチューブが気持ち悪いよね。胃ろうをつくれば楽になるから、がんばって生きようね』と……」
できるだけ父に会いに行くことが父の幸せ
リハビリ病院に入院して40日後、父親は篠さんが以前勤めていた特養に入所がかなった。
本当のことを言えば、自分が以前勤めていた特養に父親を入れることにはためらいもあった。
「この特養は自宅から近いので、知っている人もいるし、以前の同僚もいます。父がこうなる前までは、自分が勤めていたところに父を入れるのは恥ずかしいと思っていました。でも、今の私にできることは、できるだけ父に会いにいくこと。外に連れ出すこと。それが父の幸せだと思いました。だから、家から近いところにお願いしようと決めたんです」
胃ろうなので、職員の目が届きやすいように4人部屋に入った。費用は月に約10万円。4人部屋ということもあり、かなり安価だ。
「父は自営業だったので、年金だけではまかなえませんが、蓄えたお金があるので、100歳まであと10年生きても足りるでしょう。家族にはできない十分なケアをやってもらってこの値段は、ありえないくらい安いと思います」
そして篠さんも父親の入所と同時に、その特養で再び働きはじめた。父親の相談をしたときに、上司から「もう一度うちで働かないか」と誘われたのだ。
この決断は、コロナ禍では幸運なことだった。
「家族の面会が禁止になり、先日からはようやく月に1回、アクリル板をはさんで15分だけ面会できるようになりました。そんななか、私はこの特養で働いているので、父の顔を見ることができています。といっても担当の階が違いますし、家族と面会できていない入所者さんのことを考えると、私が父とゆっくり話すのは申し訳ないので、本当に顔を見る程度なのですが」
そんな幸運に感謝する一方で、篠さんはずっと苦しい思いを持ち続けている。胃ろうという選択をしたことに対してだ。
【3】に続きます
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。