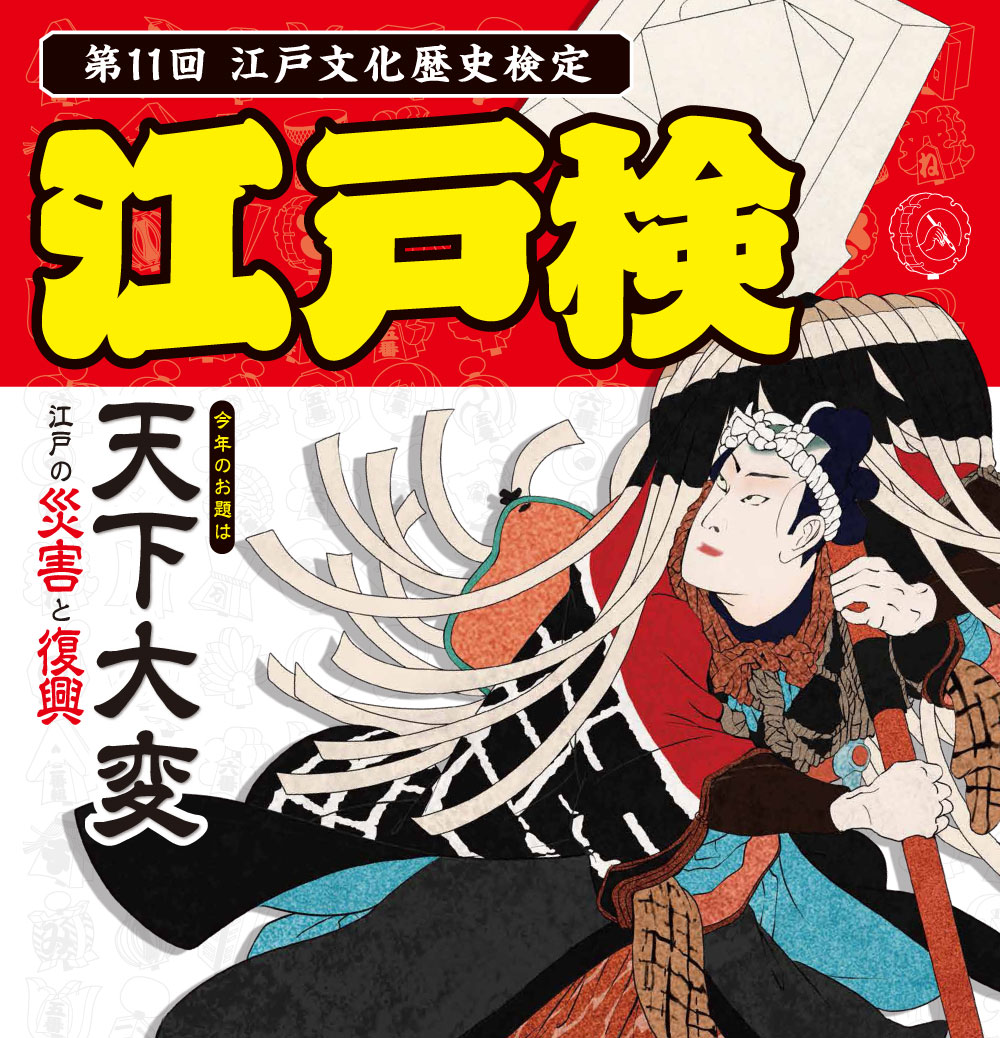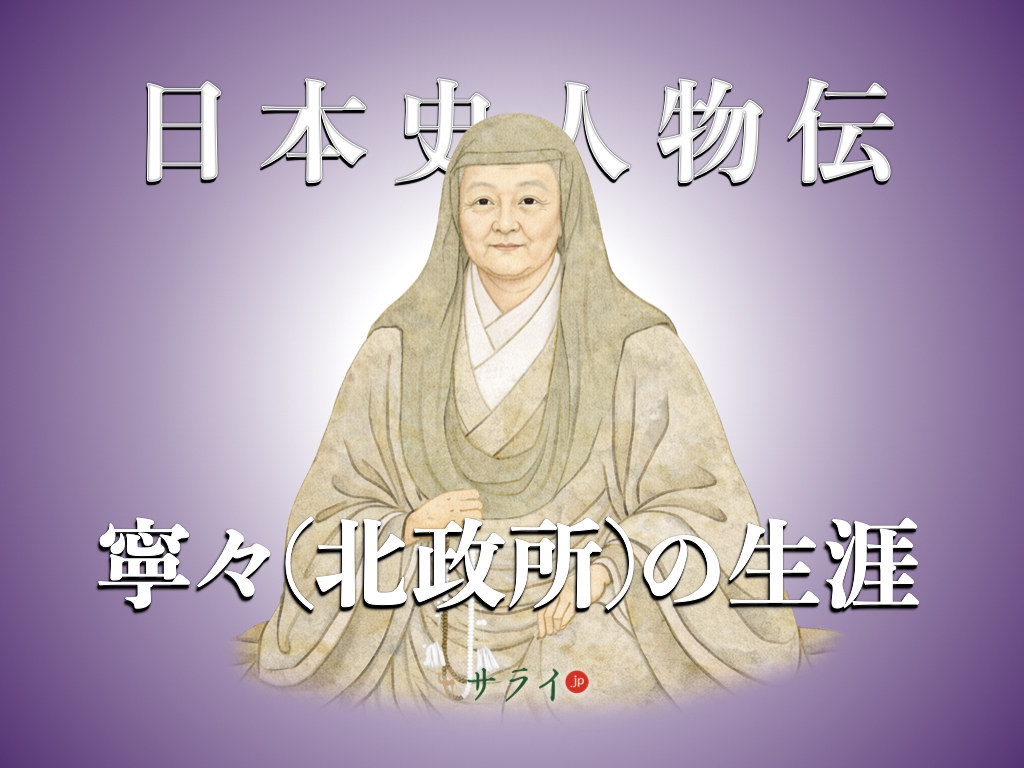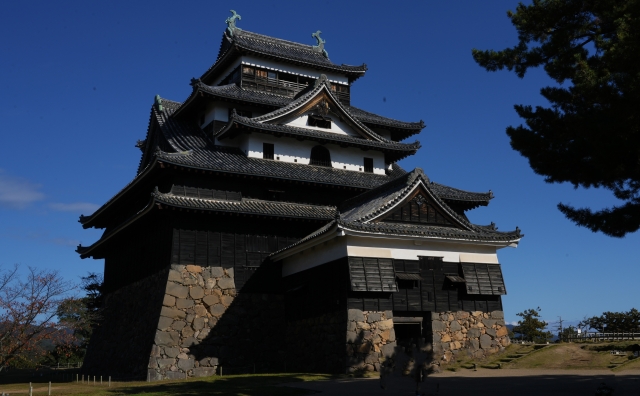いきなりですが、クイズです。
【1】天和2年(1682)12月の火事で避難先の寺小姓と恋仲になり、再度その寺小姓に会いたい一心で放火し、処刑されたという女性は誰でしょう?
(い)魚やお六
(ろ)八百屋お七
(は)薬屋お八
(に)居酒屋お千
【2】安政2年(1855)に江戸で大地震が起きた際、ある生き物が描かれた摺り物が多く発行されました。これは、鹿島神宮の要石が、地震の原因とされた地中のこの生き物を押さえているという俗信によるものです。さて、その生き物は何でしょう?
(い)ウナギ
(ろ)ナマズ
(は)モグラ
(に)カメ
……さて、いかがでしょう。難しいですか? それとも簡単すぎました?(答えは記事の最後に!)
上の2問は、『江戸文化歴史検定』(通称「江戸検」“えどけん”)の3級の例題です。すんなり答えられた方は、日本史や江戸時代について関心の高い御仁とお見受けします。
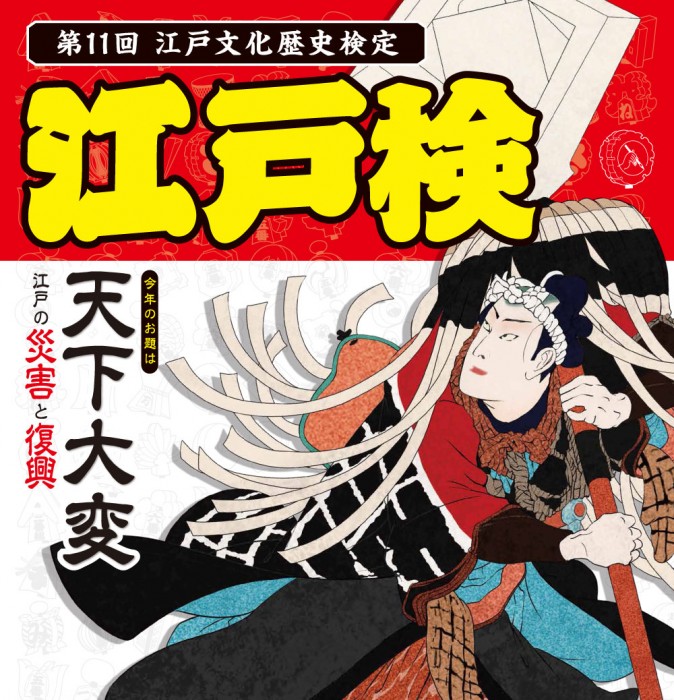
これまでに延べ4万人を超える「江戸ファン」が受検したこの江戸検。ただ今、2016年11月に行われる第11回検定の受検申し込みが受付中となっています。
今年のお題は「天下大変~江戸の災害と復興~」。戦乱こそなかった江戸時代の日本ですが、地震・津波はもとより、大火や、疫病の流行、火山の噴火と飢饉など、幾度となく天災にみまわれ、多くの人命が失われました。現代に暮らす私たちにとっても、今まさに抱えている喫緊の問題である「災害」とそこからの「復興」。その江戸時代に関する問題が、全体の2割ほど出題されることになっています。
江戸時代を学ぶことは、日本を学ぶことであり、ひいては日本人について学ぶことでもあります。私たちの国を知り、私たち自身を知ることにもつながります。検定受検をきっかけに、きっと深い学びの機会を得ることができるでしょう。
試験日は11月3日(木)の「文化の日」。時代劇や時代小説が好きな方も、歴史好きな方も、知の腕試し、してみませんか?
※受検申し込みの詳細については、下記のサイトをご覧ください。
http://www.edoken.jp/
※冒頭のクイズの答え
【1】ろ 【2】ろ でした!