【サライ・インタビュー】
古谷三敏さん
(ふるや・みつとし、漫画家)
――漫画家デビュー63年――
「作品には自負があります。誰もやっていないテーマを、先んじて手がけてきました」

仕事場で机に向かい漫画原稿を執筆。目の前にうずたかく積まれたのは、長年かけて集めたスポーツや映画などのビデオ映像。
※この記事は『サライ』本誌2019年2月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地 工)
──82歳にして現役の漫画家です。
「僕は夜型で、今日も朝の8時まで仕事をしていました。現在2本の連載をもっています。毎日新聞日曜版の『ぐうたらママ』と、『漫画アクション』( 双葉社)の『BARレモン・ハート』。『レモン・ハート』は昭和60年からの連載で、単行本は33巻になりました」
──漫画家を目指したきっかけは。
「僕は満州(現・中国東北部)で生まれ、秦皇島という軍港の近くで育ちました。終戦後、日本に引き揚げて両親の実家がある茨城県に落ち着きました。その3年後、小学5年生のとき、手塚治虫先生の『新宝島』に出会ったのです。ものすごい衝撃でした。それまでの漫画と違い、アメリカのコミックのようなバタくさい絵の中を流線型の車が走っている。なんともカッコよかった。“俺もこういうのを描ける漫画家になりたい“と思いました」
──絵は得意だったのですか。
「小さいときから好きで、描いていました。茨城県の衛生ポスターで、小学生部門の2位に入賞したこともあります。皆が一生懸命、大きな絵をみっちり描き込んだ応募作の中で、僕のは色紙くらいの大きさで背景も真っ白。そこにお母さんが蒲団を干している絵をさらさらっと描いて〈ふとんをほしましょう〉と。そうすると、100枚くらいある絵の中で、逆にものすごく目立つ。500円の賞金をもらったけど、いつのまにかオヤジの酒代に消えてしまったようでして。思わぬオヤジ孝行をしました」(笑)
──どんな父親でしたか。
「寿司職人です。ギャンブル好きで、満州の自分の店に『一点張り』という名をつけたくらいです(笑)。父親にすれば“息子も寿司職人に”という思いもあったようですが、僕は魚をおろすのが苦手で。オヤジが鰻をさばいてるのを見て、気持ち悪くなっちゃった。今では自分で料理をしてお惣菜もつくりますが、魚はおろせない。それで、中学校を出ると、大阪で既製服の仕立てをしている洋服屋さんに就職したんです」
──漫画家への夢はあきらめたんですか。
「3年ほどその店で働きましたが、やっぱり、漫画が描きたくて仕方ない。タダ同然で朝から晩まで働かされて仕事もきついし、辞めさせてもらいたかったのですが、なかなか手放してもらえない。何せ金の卵ですからね。一計を案じ、お袋に“病気だから帰ってこい”というウソの手紙を書いてもらった(笑)。それで、ようやく辞めることができました」
──漫画家デビューは19歳でした。
「いわゆる持ち込みです。1年半かけてストーリーを考え、『みかんの花咲く丘』という128ページの漫画を完成させると、東京の出版社へ持っていきました。そしたら“なかなか面白い”と単行本にしてくれたんです。それがデビュー作です。漫画家志望の青年は多くても、それだけのページ数の、まとまったものを描ける人はそういなかった」
──どんな内容だったのですか。
「静岡のミカン畑を母とふたりで守る少女の物語です。物語の中で少女がミカンの缶詰工場を訪ね、〈なんでこんなにきれいに実が入っているんですか?〉と聞くと、工場の社長が〈塩酸の溶液に漬けて剥くんだよ〉と答える場面があります。この場面を描くため、僕は静岡の缶詰工場を見にゆきました。僕自身、どうやって房から実を取り出すのか不思議に思い、知りたかったんです。それで、薄い塩酸溶液で房を溶かし、さらに中和剤を使って人体に影響のないようにしているということを知り、それを描きました。後年、僕の蘊蓄漫画につながる原点だったかもしれません。
原稿料は3万円でした。サラリーマンの月給が3000円くらいの時代ですから、破格の原稿料です。妹と弟に、鞄や洋服を買ってやったのを覚えています」
──その後は、どうしましたか。
「単行本を数冊出し、セミプロのようになって、東京のおばさんのところに下宿しながら漫画を描き続けていました。そしたら、手塚先生がアシスタントを探しているので、面接を受けてみないかという話が舞い込んだのです。僕は小躍りして、次の日の朝早く、初台(渋谷区)にある手塚先生の事務所へ行きました。玄関のチャイムを鳴らすと、中から眠たい顔の人が出てきて、徹夜で仕事をしてまだみんな寝てるからここで待ってろ、と応接間へ通してくれました。待たされている間にテレビを見ていると、皇太子(現在の天皇陛下)のご成婚パレードを中継していました」
「月曜から金曜まで赤塚さんと仕事場で枕を並べて寝ていました」

赤塚不二夫の仕事場で飯を掻き込む。のちに『釣りバカ日誌』を描く北見けんいちが撮影。「仕事の合間に、飲みに行ったり、銀玉鉄砲を撃ち合って遊んだりした。青春でした」
──昭和34年4月10日だったわけですね。
「まったくの偶然です。そのあと面接してもらい、無事に採用されました。週刊漫画誌が創刊されたばかりで、手塚先生はあちこちの月刊誌に『鉄腕アトム』や『リボンの騎士』などを連載していました。
このときアシスタントを募集することになったのには、ちょっとしたエピソードがありまして。アシスタントのひとりがミカンを買ってきてみんなに配り、最後に手塚先生へミカンを渡したら、これが腐っていた。手塚先生は、“会社だったら俺は社長だよ。社長に腐ったミカンを渡すとはどういうことだ”と怒った。怒られた人はそれを苦にしたのか、次の日に辞めてしまったそうです。それで急遽、欠員の募集となり、僕が運よくすべり込めたというわけです」
── 憧れの先生のそばで働くことができた。
「それは、嬉しかったですよ。同じ部屋で仕事をしながら、胸をドキドキさせて先生を仰ぎ見ていました。先生と町を歩くことがあると、“俺は手塚先生と歩いているんだぞ。みんな、気がつかないのか”といった調子で、胸をそらしていましたから(笑)。手塚先生のところには3年半くらいいましたかね。手塚先生は、だいたい3年くらい経つとアシスタントをすべて交代させる方針だったのです」
──そのあとはどうされましたか。
「手塚先生の担当だった編集者が、赤塚不二夫さんの担当になり、その人が赤塚さんのアシスタントをやらないか、と声をかけてきたんです。僕は最初、“アシスタントは大変だからもうやりたくない”って断ったんです。細々でもいいから、自分でやろうと。ある雑誌で、連載も決まっていましたし。
ところが、第1回の原稿を入れたところで、印刷されないうちにその雑誌が廃刊になってしまったんです。そんなタイミングもあり、“ともかく一度会ってみたら”というので、赤塚さんと会いました。初対面で、僕が第一声で言ったのは、“僕、ギャグ嫌いだから”でした」(笑)
──それでも、一緒に働くことになった。
「赤塚さんは会ってみると優しそうな人だし、働きやすそうな仕事場だった。短期間でよければ、と引き受けることにしました。赤塚さんはね、人の使い方がうまいんですよ。手塚先生のところに3年もいた人だから、と下にも置かず持ち上げてくれました」
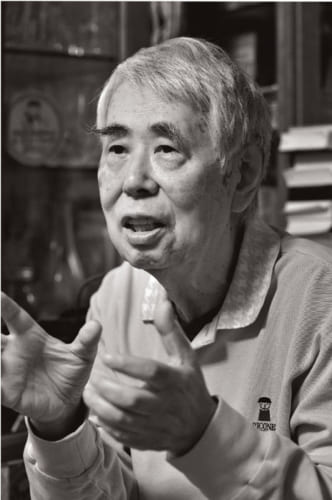
赤塚不二夫の『天才バカボン』のアイディアのほとんどを捻り出した。「バカボンは古谷がいないとできない、と言われてました」
──どのくらいの期間いたのですか。
「居心地がよく、10年以上いることになりました。ともかく忙しくて、月曜から金曜日まで仕事場に泊まり込み、赤塚さんと枕を並べて寝ていました。ふたりとも結婚して子供もいましたから、“俺たち結婚して家族もいるんだよな”なんてボヤキながら。それで、土曜日の午後3時か4時頃に家へ帰ろうとすると、赤塚さんは“これから新宿で餃子パーティだ”なんて言い出す。僕が“冗談じゃない。今日帰らないと離婚されちゃうよ”って帰ろうとすると、赤塚さんが罵声を浴びせるんです。“このマイホーム主義者!”って。結局、赤塚さんは離婚しましたけどね」(笑)
──その頃、『ダメおやじ』の連載が始まる。
「昭和45年です。赤塚さんがタレントみたいになって、やたらテレビに出だしたりした頃でね。あるとき、僕は“漫画をおろそかにしてどうする。漫画を描いての赤塚不二夫じゃないか”って怒ったんです。そんなことから、ちょっと居づらくなりまして。
そこへ『週刊少年サンデー』(小学館)から“ちょっと大人っぽい作品を描いてみないか”という誘いがあったんです。大阪万博から日本列島改造ブームへと続いていく時代で、誰も彼もが中流で幸せみたいな空気が流れていた。そんな社会の風潮に、会社でも家でもバカにされているダメな主人公を描き、一石を投じたかった。悪書と呼ばれてもいいと覚悟し、最初は何か月かのつなぎという話だったんですが、好評で11年半も続きました」
──『寄席芸人伝』はそのあとですね。
「『ビッグコミック』(小学館)に昭和53年から連載しました。僕は昔から落語が好きで、古今亭志生や三遊亭圓生、三遊亭金馬が特に好きでよく聴いていました。名人といわれた噺家たちの芸と人生を、描いてみたかったんです。実際に芸人さんたちを取材して“そんなに綺麗な世界じゃありませんよ”と言われもしたけど、僕はこの作品を暗く悲惨な匂いのするものにしたくなかった。ある種のファンタジーのような絵物語でいい。そう思い、僕の頭の中にある芸人の世界を描きました」
──週刊誌で『減点パパ』も連載されました。
「『週刊ポスト』(小学館)に連載し、蘊蓄漫画といわれました。それまで料理やお酒の蘊蓄をテーマにした漫画ってなかったんです。そのときの担当編集者がその道に詳しい人で、自宅にワインセラーまであった。そういう人たちの協力も得ながら構築していきました。
それまで、お酒にそれほど興味はなかったんです。赤塚さんのアシスタント仲間と、仕事終わりに新宿あたりのバーで飲んでいた頃は、ウイスキーの『サントリー・オールド』一辺倒でした。それが『グレンリベット』を飲み、スコッチ・モルト・ウイスキーの旨さに開眼したのがこの頃です。それからはいろいろなモルト・ウイスキーを愉しむようになり、コレクションするようになりました」
──それで『レモン・ハート』が誕生した。
「バーを舞台にした物語です。もともと凝り性で、自分でも突きつめたいから、忙しい仕事の合間を縫ってバーテンダー・スクールやソムリエ・スクールにも通いました。本場の蒸溜所を訪ねてイギリスにも旅をしました。
バーテンダーでもよく知らないお酒を登場させて、びっくりさせてやろうといつも思っています。漫画を読んだバーテンダーが、その酒を探し求めるような現象も起きました。あまり珍しいお酒は出さないで、と問い合わせが殺到した酒販店から頼まれましたが」(笑)

さまざまな悩みを抱え、バーを訪れた人の心が、マスターの出す酒と会話でほぐされてゆく(『BARレモン・ハート』第33巻より)。
──今ではバーも経営されています。
「飲み仲間でビルのオーナーが、地下のフロアが空いたから店をやらないかと言ってきたんです。カラオケ・バーだった店をバーに改装し、娘に“やってみるか”と聞いたら“やってみたい”という。それで、きちんと勉強させて、任せることにしました。今では孫が受け継いでカウンターの中に入っています」

自らが経営する練馬区大泉学園のバー『レモン・ハート』で(※東京都練馬区東大泉4-2-15原田屋ビル地下1階 電話:03・3867・1682 定休日:日曜、月曜、水曜)。バーテンダーである孫の陸さん(28歳)に薦められ、思い出の「グレンリベット」を飲む。
──健康のために何か心がけていることは。
「不心得者で、まったくといっていいほど身体に気遣いをしていません。運動はしないし、小太りで、酒は飲み、煙草も喫う。何度か入院し、手術もしました。まあ、唯一、心がけているとすればカラ酒はしないということでしょうか。酒を飲むときは、必ずつまみを食べるようにしています。“このつまみなら何を飲もう”“この酒だったらどんなつまみを合わせようか”といつも考えている(笑)。それが元気の秘訣といえば、そう言えるのかもしれません」
──人生の終幕は意識していますか。
「以前、心臓の手術をしたときに、“もしかすると、このまま麻酔がさめないで死を迎えるかもしれない”、そう思うことがありました。でも、本人はそのまま眠り続けるようなもんだし、それはそれでいいんじゃないでしょうか。心残りがあるとすれば、長年かけて集めたスポーツや映画、ドキュメンタリーのビデオ映像ですね。時間がなくて、まだ半分くらいしか見ていない。
やってきた仕事には、それなりの自負をもっています。『ダメおやじ』にしろ『寄席芸人伝』にしろ『レモン・ハート』にしても、それまで誰もやっていなかったテーマを最初に手がけてきたつもりです。じつはひとつやってみたいテーマがあってね。それは仏像なんです。中身の詳しい話は、まだ内緒にしておきましょう」

“男の料理”が珍しかった時代から日常的に台所に立つ。冷蔵庫の残り物でつくる名もない創作料理が得意。今夜のおかずは、おでん。大根によく味がしみている。
●古谷三敏(ふるや・みつとし)昭和11年、満州(現・中国東北部)生まれ。19歳で漫画家デビュー。その後、手塚治虫、赤塚不二夫のアシスタントを経て、『ダメおやじ』『寄席芸人伝』で売れっ子漫画家に。『減点パパ』は料理や酒の蘊う ん蓄ちく漫画として注目された。『BARレモン・ハート』は昭和60年より連載が続く。漫画以外にも『男のウンチク学』『落語うんちく高座』『酒大事典』などの著作がある。
※この記事は『サライ』本誌2019年2月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地 工)




































