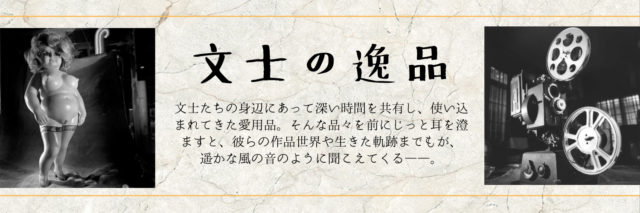
◎No.09:壺井栄の姫鏡台

壺井栄の姫鏡台(撮影/高橋昌嗣)
文/矢島裕紀彦
高さ70.5センチ。薄茶色の小さな姫鏡台。それが、小豆島・内海(うちのみ)町の壺井栄文学館内、奥にしつらえられた畳の間に、遠来の客を待つかのようにちょこなんと座っていた。
この島に生まれ育ち、やがて作品を通して郷里の名を全国津々浦々にまで知らしめる壺井栄。その栄が娘時代から使い、後年、東京の住まいにまで持ち込んだ鏡台である。
栄は淡泊かつ清楚。きらびやかな絹より木綿を好んだ。貧しい家計を支えていた郵便局員時代は、決まって母の手織りの着物と紺の袴姿。だが同時に、独得の髪型を考案して村娘の流行をリードするお洒落な一面もあった。新しい髪型を試す時、栄はきっとこの鏡台の前に座ったに違いない。
ある時、喉を傷めた栄が思案の末に白い包帯を頸に巻いた。それを見た娘たちは、最新のファッションと勘違いして真似をしたという。まるで中国・漢代の「折角」の故事に似た挿話だ。『二十四の瞳』の作中、颯爽と潮風切って自転車で岬の分教場に通う大石先生のモデルは、鏡の中に映った栄自身でもあったろうか。そう思うと、この鏡台に無性に海を見せたくなった。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。『サライ.jp』で「日めくり漱石」「漱石と明治人のことば」を連載した。
写真/高橋昌嗣
1967年桑沢デザイン研究所 グラフィックデザイン科卒業後、フリーカメラマンとなる。雑誌のグラビア、書籍の表紙などエディトリアルを中心に従事する。
※この記事は、雑誌『文藝春秋』の1997年7月号から2001年9月号に連載され、2001年9月に単行本化された『文士の逸品』を基に、出版元の文藝春秋の了解・協力を得て再掲載したものです。




































