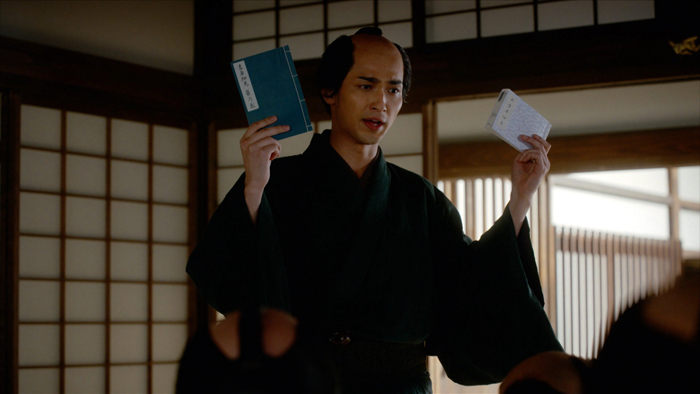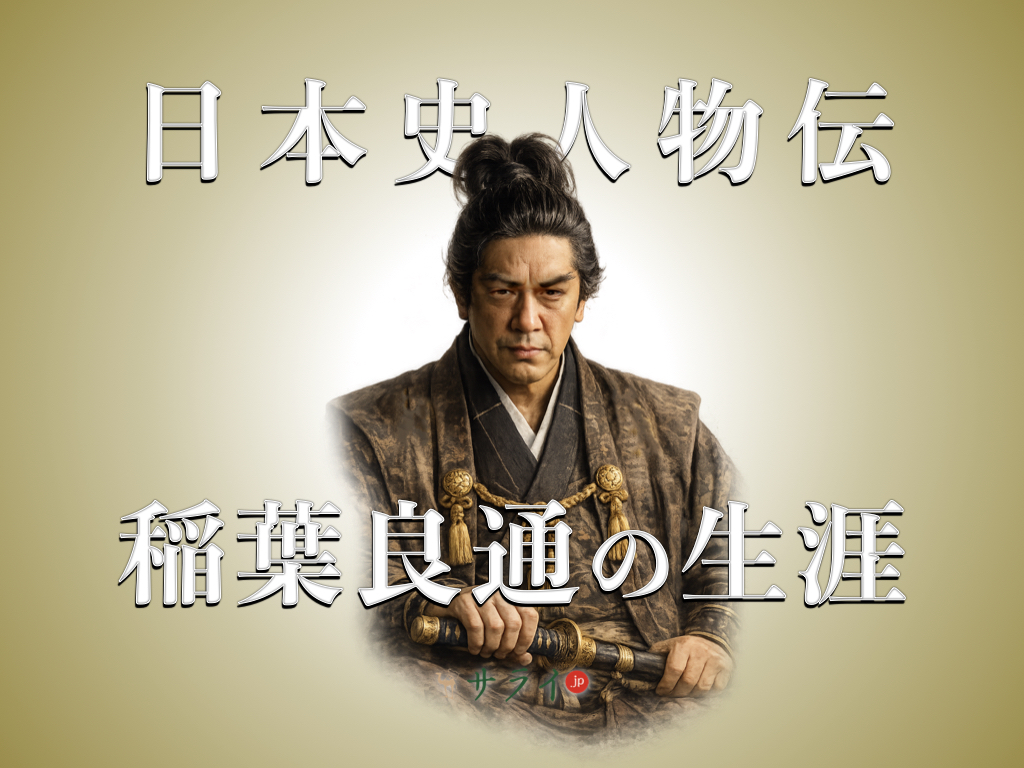ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第17回のトピックスは、意次(演・渡辺謙)の相良入りではないでしょうか。
編集者A(以下A):意次の相良入りについて説明する前に、意次の「出世街道」に触れたいと思います。意次は第9代将軍家重の小姓としてスタートしますが、父意行が亡くなって田沼家を継いだときの石高は600石です。
I:600石から始まって大名にまで上り詰めたんですね。
A:第5代将軍綱吉の側用人を務めた柳沢吉保もおよそ500石から最終的に15万石へと出世階段を上り詰めます。第6代家宣、第7代家継の2代の将軍のもとで側用人、老中格として活躍した間部詮房は猿楽師から5万石の大名に出世しました。意次は最終的に5万7000石まで石高を増やしますが、柳沢吉保、間部詮房と違って、正式に筆頭老中になっているのです。そして、相良城の築城にあたっては、将軍家治(演・眞島秀和)の許しを得て、天守閣を造営します。
I:第17回で描かれたのは、前年に「竣工」した相良城に初めて訪れる場面。安永9年(1780)のことでした。この意次の相良入りは、江戸を4月7日に出立して相良には13日に到着する行程だったようですね。
A:大名は1年おきに江戸と国元を行き来する「参勤交代」を行なうのが常ですが、側用人、老中として常に政権枢要に位置した意次は参勤交代の機会がなかったということです。意次が築城した相良城は、江戸中期になっての新規築城にもかかわらず、将軍家治に天守閣造営を許可されています。現在城跡には、牧之原市相良庁舎、牧之原市史料館、小学校などが林立しています。牧之原市史料館では『べらぼう』関連の企画展「田沼意次の新時代展」が催されています。こんな機会でもなければなかなか行けない場所でもありますので、ぜひ「意次の領地」を体感してほしいですね。
I:Aさんは昨秋に実際に訪れているんですよね。
A:はい。静岡駅から路線バスで1時間ほどの地にあります。劇中で意次が「良港」ということをいっていました。地図で確認していただけるとわかるのですが、相良は駿河湾に面しています。海運が物流の中心だった当時の一等地です。さて、現在、牧之原市史料館の場所に意次の銅像が立っています。これが作られたのは令和になってから。その理由がなぜかわかりますか? 城跡に当時の建造物が一切残っていない理由も含めて「江戸の闇」を感じる話になります。
I:どういうことでしょう。
A:『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」歴史おもしろBOOK』の受け売りになりますが、相良城は、意次が亡くなったあとに「そんなことありえるの?」というくらい徹底的に破却されたそうです。改易こそ免れたものの、5万7000石が1万石に減じられ、転封させられます(その後相良に復帰する)。
【権力闘争に敗れた意次。次ページに続きます】