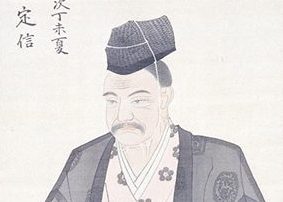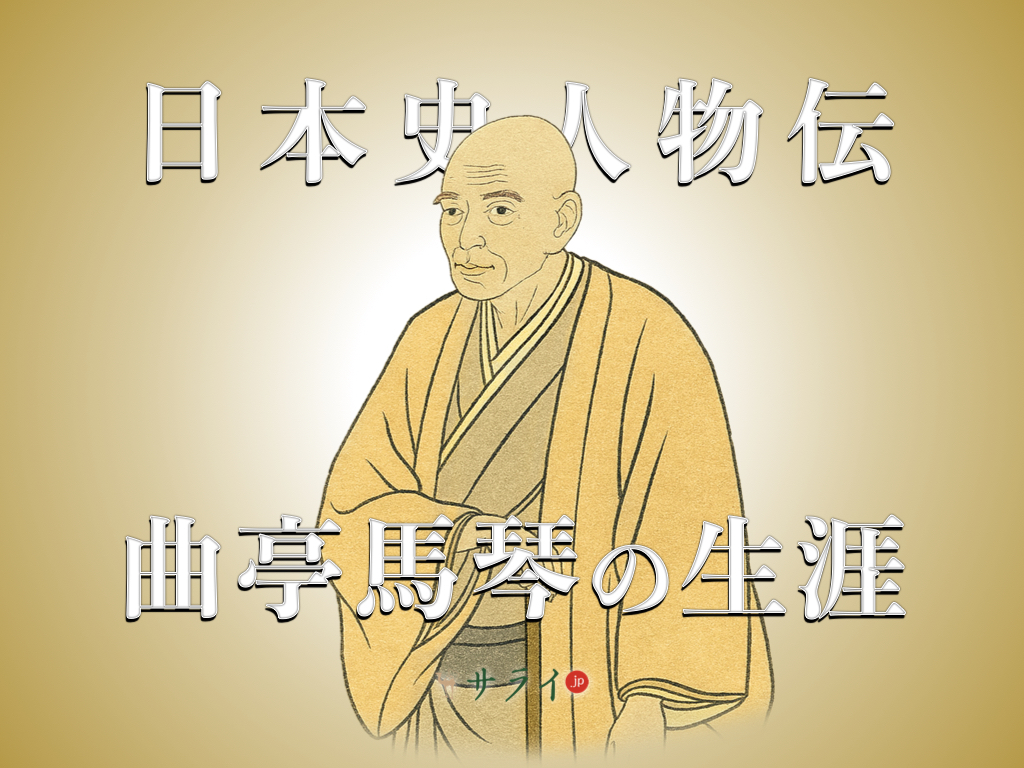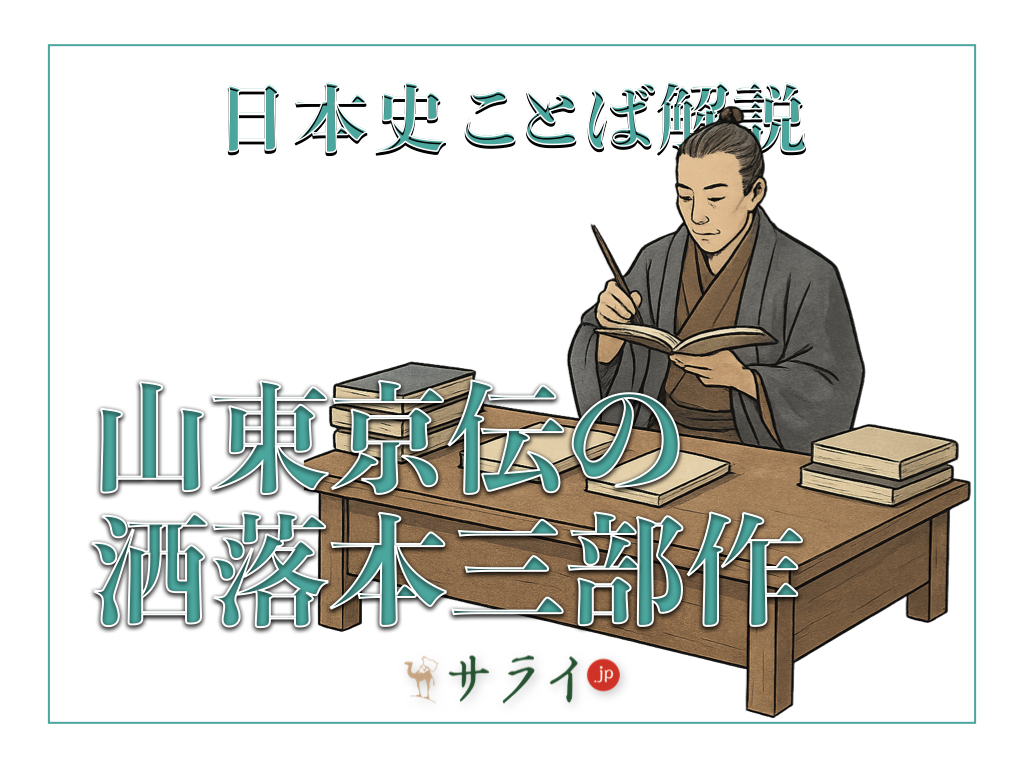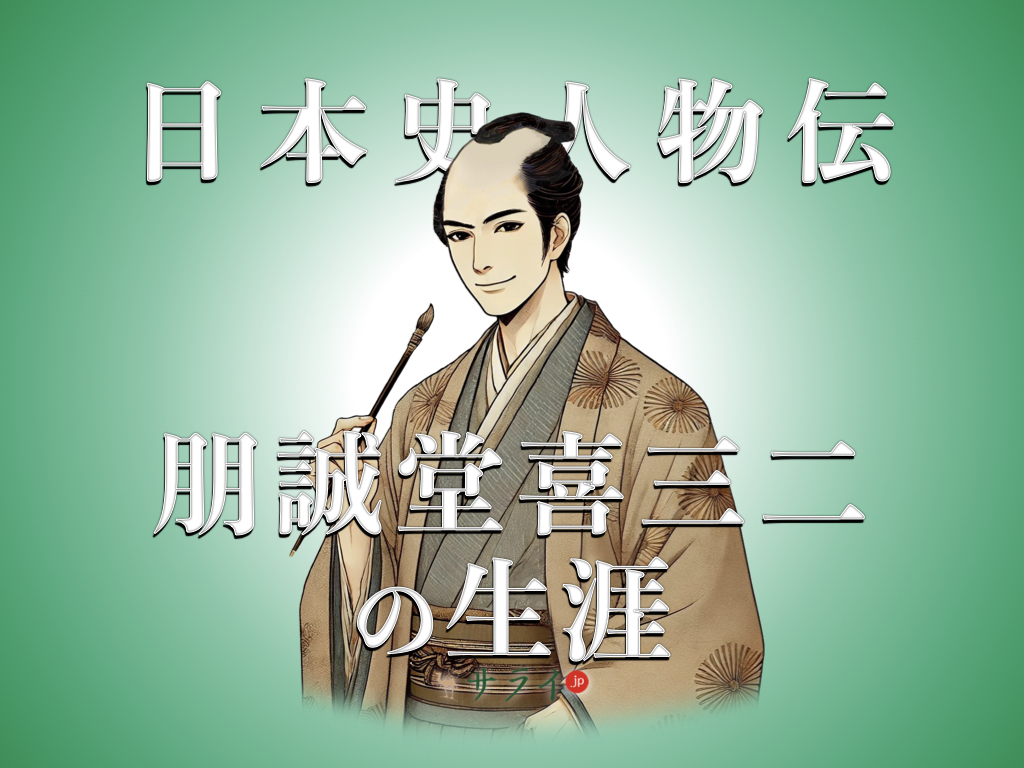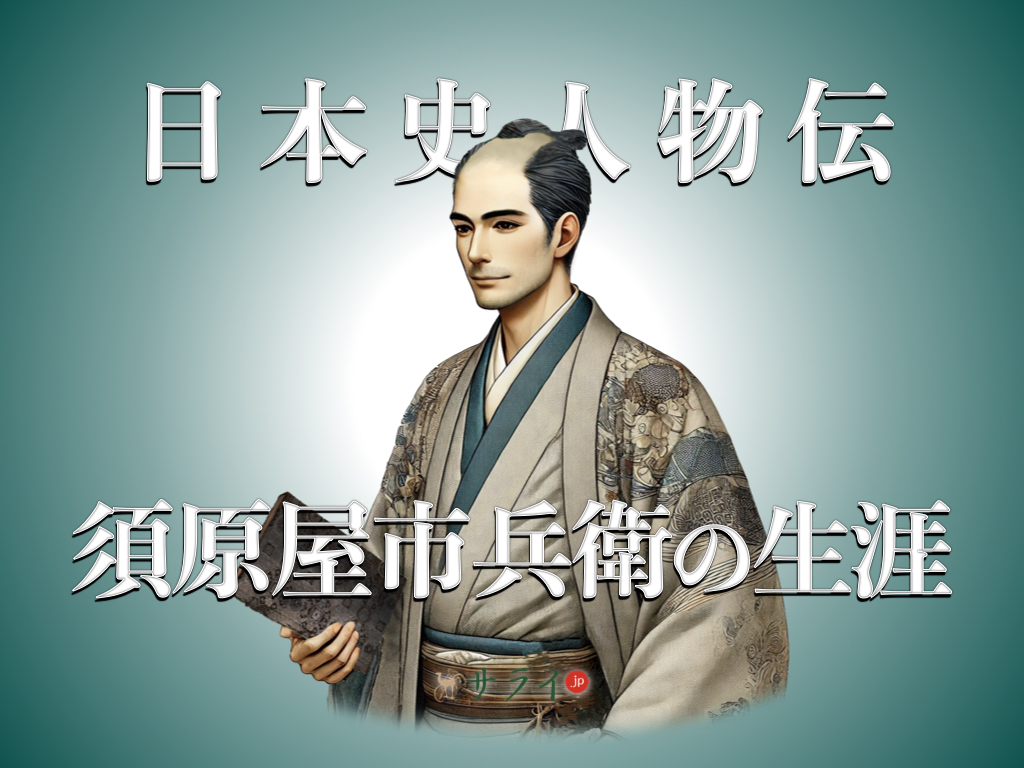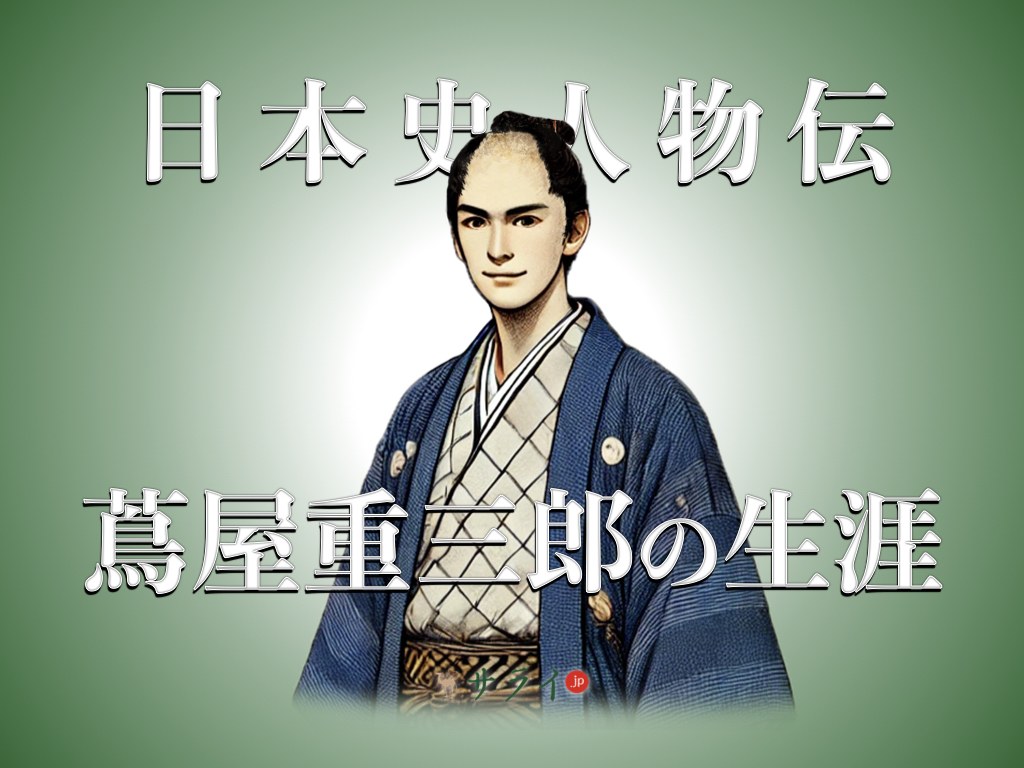大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、江戸の浮世絵師たちが描き出した華やかな町人文化が生き生きと描かれています。中でもひときわ目を引くのが、人物の顔を大きく描いた「大首絵」(おおくびえ)です。
一枚の画面に感情や存在感を凝縮させたこの表現は、当時の人々にとってまさに「推し」を讃える芸術でした。今回は、浮世絵文化の象徴ともいえる「大首絵」の魅力と意義に迫ります。
この記事では、「大首絵」についてご紹介します。
「大首絵」とは?
「大首絵」とは、人物の顔や上半身を大きくクローズアップして描いた浮世絵の形式で、主に役者や美人を描く際に用いられました。従来の全身像や群像構図とは異なり、表情や視線、髪型、衣装の柄といった細部まで緻密に描写することで、人物の魅力や個性がより強く印象づけられるのが特徴です。
その起源は、団扇絵(うちわえ)にあると考えられており、享保年間(1716〜1736)頃から徐々に大首の構図が登場し始めます。本格的に様式として定着し、盛んに制作されるようになったのは、安永年間(1772〜1781)以降のことです。
以後、大首絵は浮世絵の中でもひときわ人気を集めるジャンルとなり、江戸後期から明治時代にかけて数多くの絵師によって描かれ続けました。一枚の画面に感情や物語性を凝縮したこの様式は、江戸の町人文化を象徴する浮世絵の中でも、とりわけ人々の心を捉えた表現といえるでしょう。

昇雲 [画]『いますがた』[24],松木平吉,明治40.
国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/2591683
「大首絵」の特徴と魅力
「大首絵」の最大の特徴は、人物の顔の表情を際立たせる構図にあります。特に役者絵においては、目線、歯の見え方、眉の上げ下げといった微細な表現が、演じている役の感情や性格までも伝える手段となっていました。
また、美人画においては、髪の結い方やかんざし、衣装の柄などが繊細に描き込まれ、鑑賞者は描かれた女性の気品や色気を間近に感じ取ることができたといわれます。
これは現代の「アップ写真」や「ポートレート」に通じる感覚であり、当時の人々の「推し活」の原点ともいえるかもしれません。
写楽・歌麿らによる代表作
「大首絵」の様式を語る上で欠かせないのが、喜多川歌麿(きたがわ・うたまろ)と東洲斎写楽(とうしゅうさい・しゃらく)の存在です。両者は、それぞれ美人画と役者絵の分野で、独自の感性と技術を発揮し、大首絵の黄金期を築きました。
美人画の革命児・喜多川歌麿
美人画の名手として知られる歌麿は、大首絵の連作『歌撰恋之部(かせんこいのぶ)』『婦人相学十躰(ふじんそうがくじったい)』などを手がけ、遊女や町娘たちの心理的な深みまでを描き出す独特の顔貌表現で人気を博しました。
寛政年間には『高名美人六家撰(こうめいびじんろっかせん)』『当時全盛美人揃(とうじぜんせいびじんぞろえ)』などで、実在の遊女や茶屋娘をモデルに、それぞれの個性を繊細に描き分けるなど、単なる美人画家にとどまらぬ肖像画家としての才を発揮します。
その大首絵の成功を後押ししたのが、版元・蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう、通称:蔦重)です。挿絵や狂歌絵本で頭角を現していた歌麿を見出し、美人画の浮世絵版画に起用。
とりわけ、背景に雲母(きら)や貝殻粉を使って光沢を加える雲母摺(きらずり)の技法により、画面全体に高級感が生まれ、従来の全身画とは一線を画すインパクトを放ちました。
異端の天才・東洲斎写楽
歌麿に続いて蔦重が世に送り出したのが、謎多き絵師・東洲斎写楽です。彼のデビューは寛政6(1794)年5月、いきなり28点もの役者大首絵を発表するという異例のものでした。
写楽の大首絵は、写実的な描写と大胆な構図で、従来の「美化された役者絵」とは一線を画するものでした。中でも、黒雲母摺(くろきらずり)と呼ばれる、黒光りする背景が役者の表情を際立たせ、画面全体に強烈な存在感を与えました。
しかし、そのリアルさが仇となり、役者本人やファンからの評判は芳しくなく、結果的に購買層の反発を招くことになります。写楽の活動期間はわずか10か月。その間に145点以上の作品を残し、忽然と姿を消しました。

国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/2533724
蔦屋重三郎という仕掛け人
歌麿や写楽といった才能を見出し、大首絵というジャンルの革新を主導したのが、出版人・蔦屋重三郎でした。絵師の個性と時代の気分を巧みに読み取り、表現の枠を押し広げながら新たな浮世絵文化を生み出した彼の手腕なくして、大首絵の隆盛は語れません。
まとめ
「大首絵」は、ただの美人画や役者絵ではありません。そこには、江戸の人々の「好きなものをもっと近くで見たい」「この瞬間を永遠に残したい」という思いが込められていました。
喜怒哀楽の表情を、極限まで大きく、丁寧に描き出した浮世絵の名品たちは、現代のポートレートやアイドル文化にも通じる感性を映し出しているかのようです。
『べらぼう』をきっかけに、写楽や歌麿たちが残した大首絵に触れてみれば、江戸の人々がどれほど「顔」を愛したのか、その理由がきっと見えてくるはずです。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)