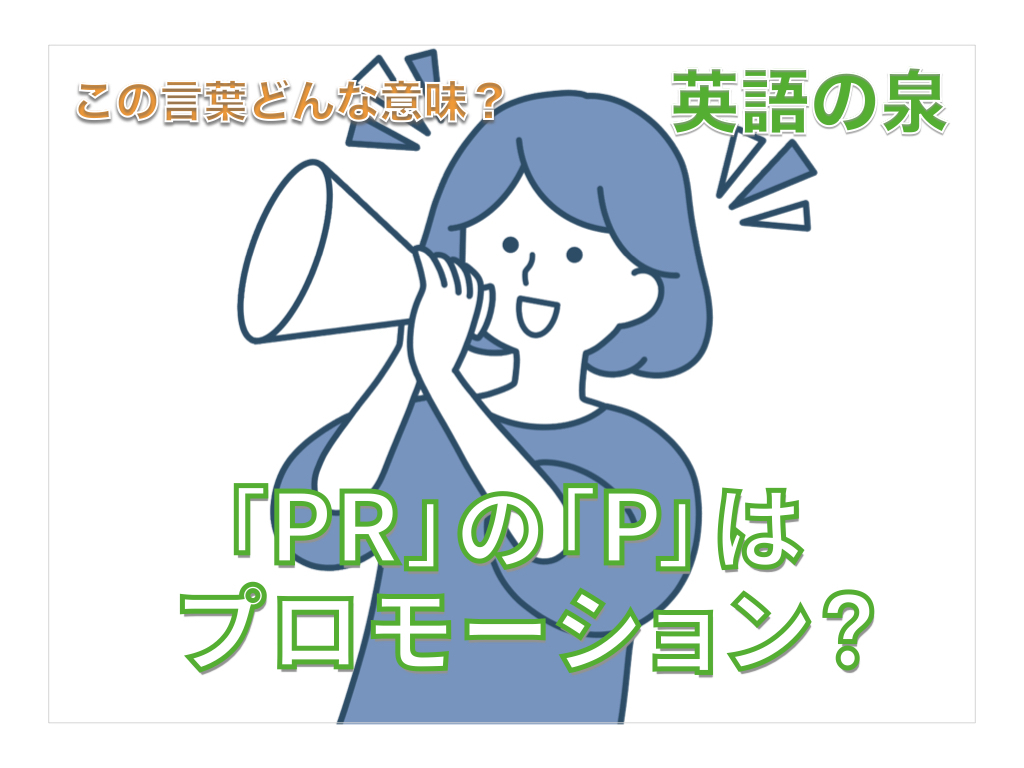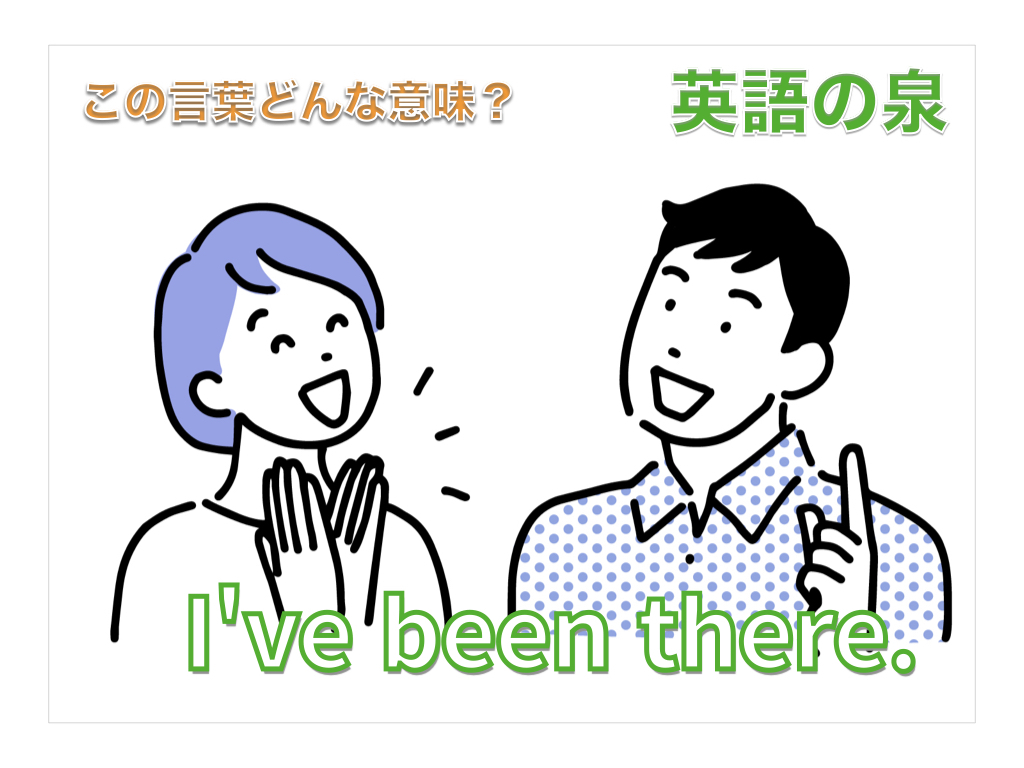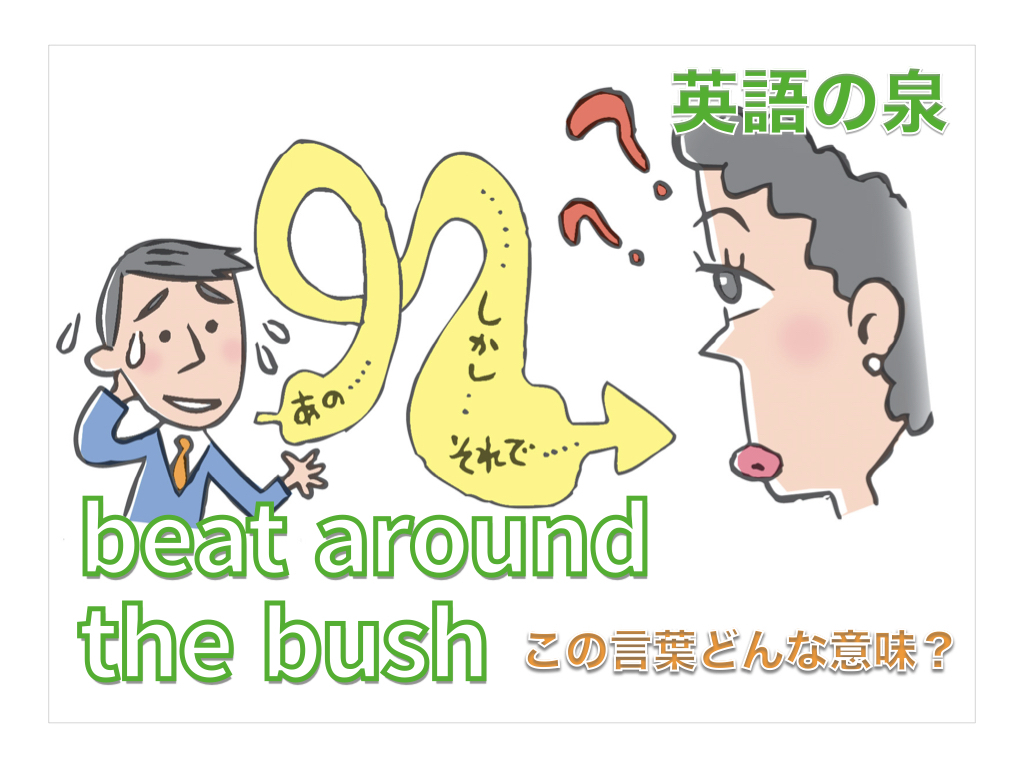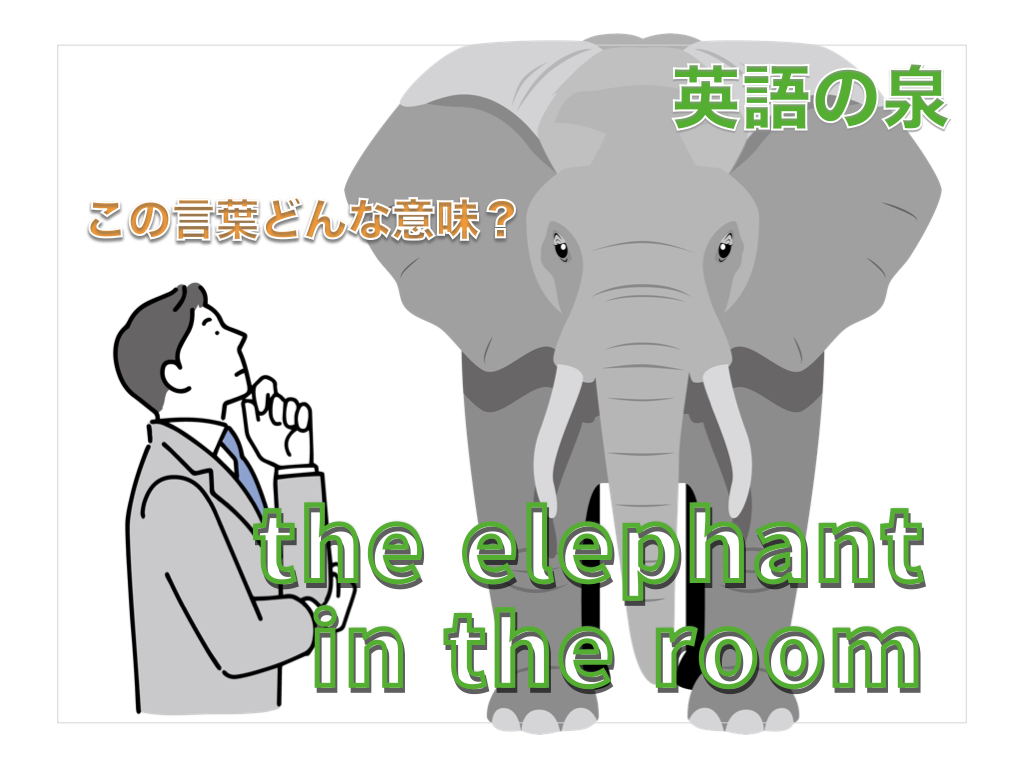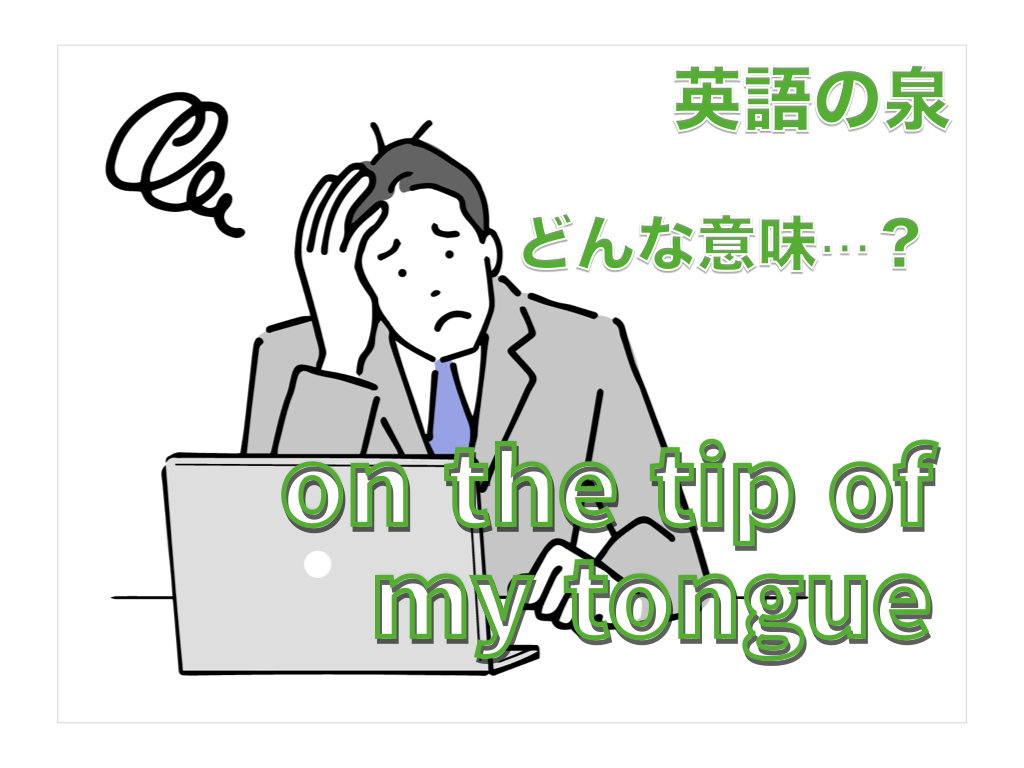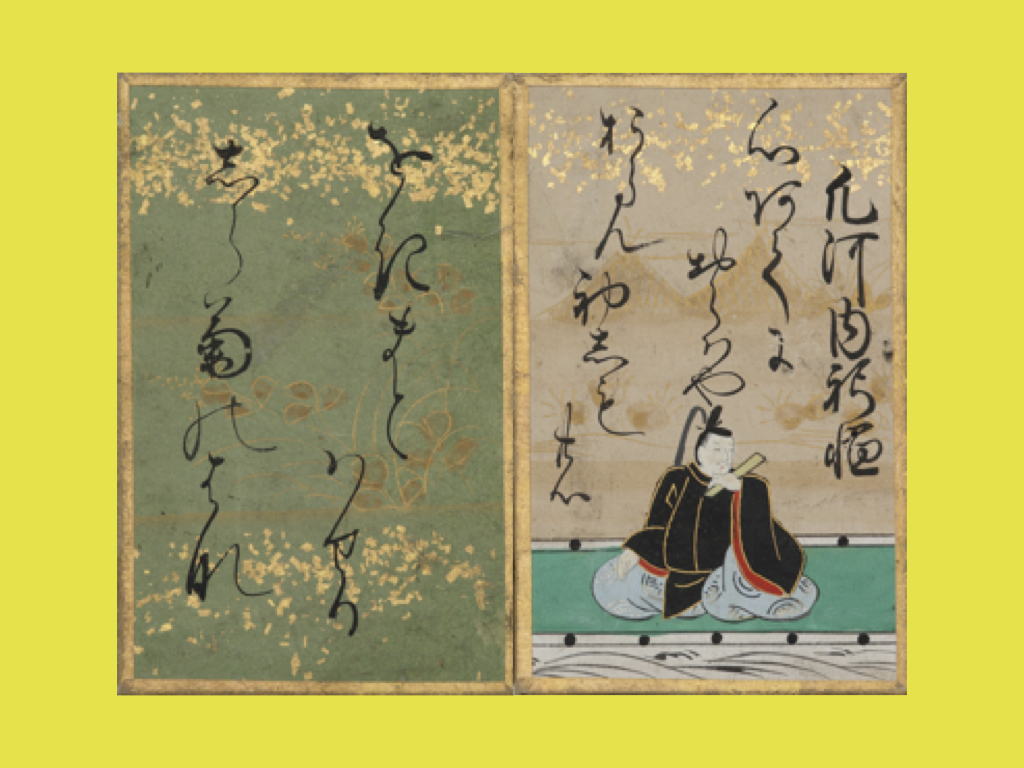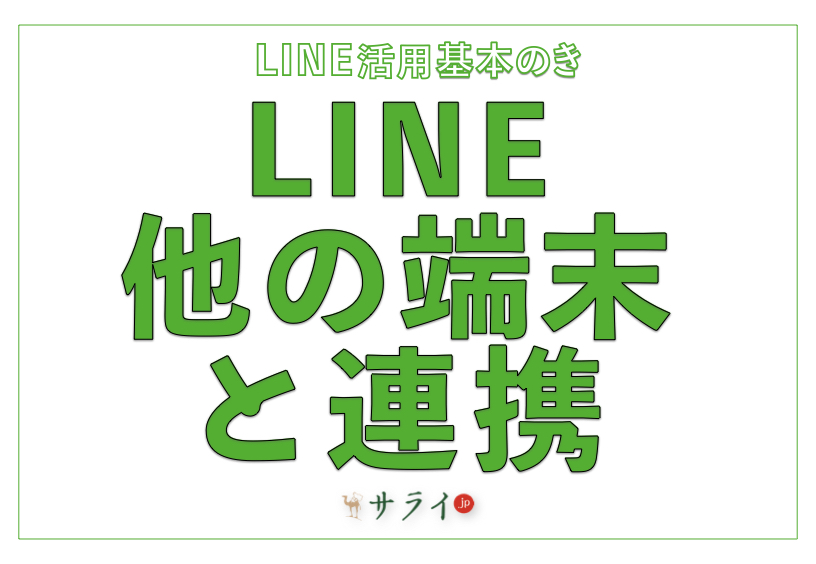私たちが日々何気なく使っている言葉には、英語本来の意味とは少し違ったニュアンスを持つことがあります。今回取り上げる“PR”も、そのひとつ。日本語にすっかり定着したこの言葉ですが、英語の本来の意味と、日本語の使い方には意外な違いがあります。今回は、その微妙なニュアンスについてご紹介します。

目次
“PR”の意味は?
PRのはじまりとその歩み
「透明性」と「信頼性」の英語
最後に
“PR”の意味は?
“PR” は英語の Public Relations(パブリック・リレーションズ=広報活動)の略です。
これは、企業や団体が世間(public)といい関係を築くための取り組みを指しています。宣伝だけでなく、ブランドのイメージ管理やメディア対応、危機管理など、幅広い活動が含まれているようです。
例えば、
“Our PR team is handling the press release.”
自社の広報チームがプレスリリースを担当しています。
“We hired a PR firm to improve our company’s public image.”
会社のイメージを改善するためにPR会社にお願いしました。
などと使われます。
『ランダムハウス英和辞典』(小学館)には、「=public relations. ((単数扱い)) パブリックリレーションズ,ピーアール(PR),広報(活動);渉外(事務):会社・政府などの広報活動」と書かれています。
一方、日本語で「PR」というと、商品や「自己PR」と言うように、その人自身を魅力的に伝える時に使われる印象がありますね。本来の意味からすると、やや異なった意味として使われています。
PRのはじまりとその歩み
「PR」という言葉の元になっている Public Relations(パブリック・リレーションズ) が歴史の中に初めて登場したのは、1807年のアメリカ。第3代大統領トーマス・ジェファーソンが、政府と国民との関係について語った演説の中でこの表現を用いたとされています。
その後、20世紀初頭に入ると、「PR」はしだいに“戦略的な広報活動”としての性格を強めていきます。なかでも重要な存在が、「現代PRの父」と呼ばれるエドワード・バーネイズです。彼は、精神分析の祖ジークムント・フロイトの甥であり、心理学をPRに応用したことで知られています。彼は人の無意識や価値観に働きかけ、自然と行動が変わるような広報をつくり出しました。
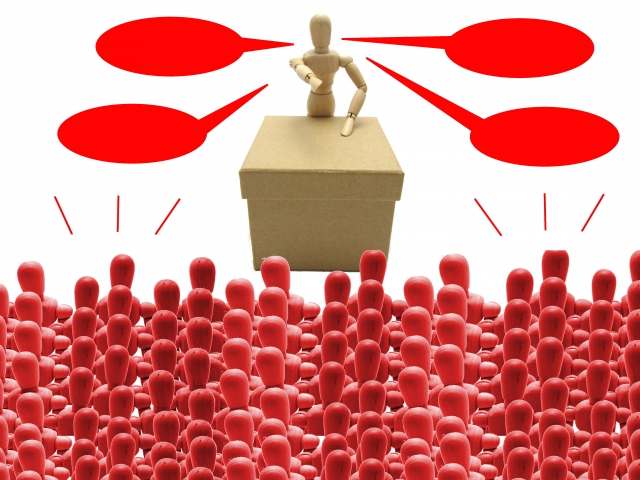
バーネイズが広報の分野に関わるようになったのは、第一次世界大戦中に設立された「クリール委員会(公報委員会)」での活動がきっかけでした。アメリカ政府はこの委員会を通じて、戦争への支持を集めるための大規模な情報操作、「プロパガンダ」を展開しました。
バーネイズもこの活動に参加していましたが、戦後、「プロパガンダ」という言葉がマイナスのイメージを持つようになったことを受け、より中立的で好意的な響きを持つ「Public Relations(広報)」という言葉を広めるようになったのです。
アメリカの朝食文化にまつわる彼の代表的なエピソードがあります。バーネイズは、あるベーコン会社から「ベーコンをもっと食卓に広めたい」という依頼を受けました。そこで多くの医師が推奨しているとして、「健康的な朝食にはしっかりとした食事がいい」ことを新聞で紹介しました。その結果、ベーコン&エッグは健康的な朝食というイメージが広まり、アメリカの食文化に深く根づいていきました。
このように、バーネイズのPRは、「〜すべき」と直接的に訴えるのではなく、「そうしたくなる」ように人々の心をそっと刺激するものでした。事実だけを伝えるのではなく、そこに感情やイメージ、信憑性を添えて、世論を導いていく。こうした手法はときに「情報操作」と紙一重でもあり、倫理的な問いを投げかけるものでもあります。
インターネットやSNSが発達し、情報が瞬時に拡散されるようになった今、PRにはかつて以上に「透明性」や「信頼性」が求められています。誰もが発信者となれる時代だからこそ、広報の在り方も、より誠実で開かれたものになるべきなのかもしれません。

「透明性」と「信頼性」の英語
英語には「透明性」や「信頼性」を表す言葉が多くあり、それぞれに微妙なニュアンスの違いがあります。
たとえば、
「透明性」は transparency、 visibility
「信頼性」は reliability、credibility、trustworthiness
などがよく使われます。
最後に
アメリカの現代詩人トーマス・スミスの、「Trust (信頼)」という詩の最後の部分をご紹介します。
Trust
…
And sometimes you sense how faithfully your life
is delivered, even though you can’t read the address.
ときには、自分の人生がどれほど忠実に届けられているかを感じる。たとえその宛先が読めなくても。
…
~ Waking Before Dawn ~ Thomas R. Smith著 Red Dragonfly Press 2006年刊
この詩は、見知らぬ係員に荷物を託したり、夜間金庫に小切手を入れたりするような日常のありふれたシーンを通して、見えないところで物事が静かに、確かに運ばれる「信頼」を描いています。風は木々を抜け、凍った川はしかるべき場所にたどり着く、と。
不確実な世界にあっても、信じるという選択があり、人生は何かに確かに導かれている。私たちは思っている以上に、多くの信頼と信用に支えられた豊かな世界に生きているのかもしれません。
次回もお楽しみに。
●執筆/池上カノ
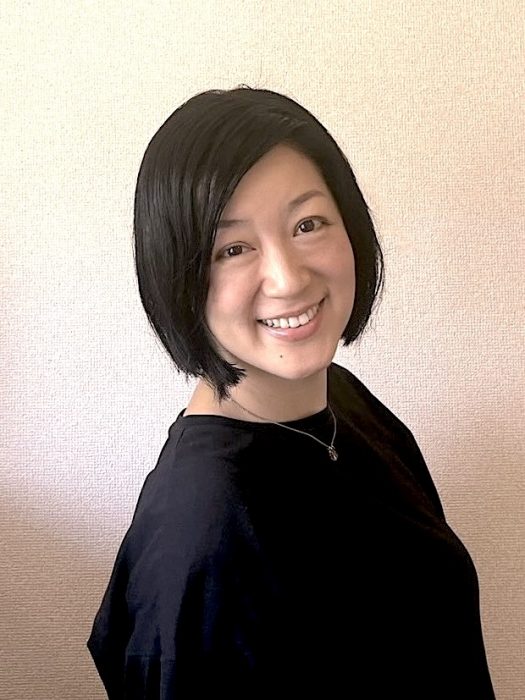
日々の暮らしやアートなどをトピックとして取り上げ、 対話やコンテンツに重点をおく英語学習を提案。『英語教室』主宰。 その他、他言語を通して、それぞれが自分と出会っていく楽しさや喜びを体感できるワークショップやイベントを多数企画。
インスタグラム
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com