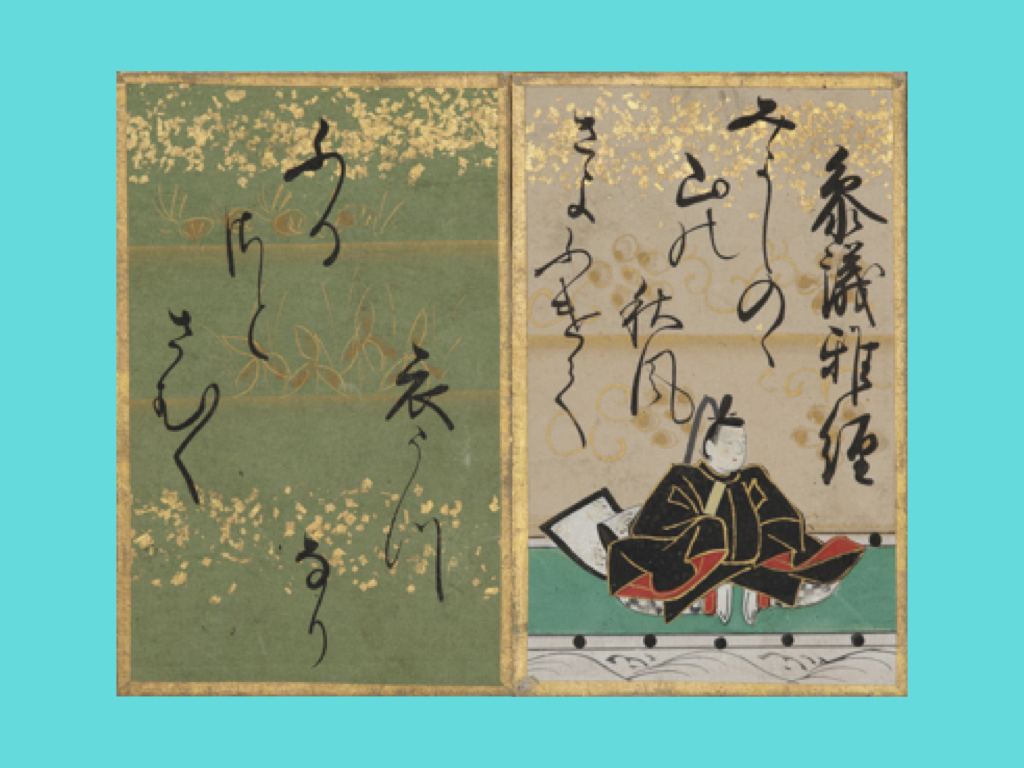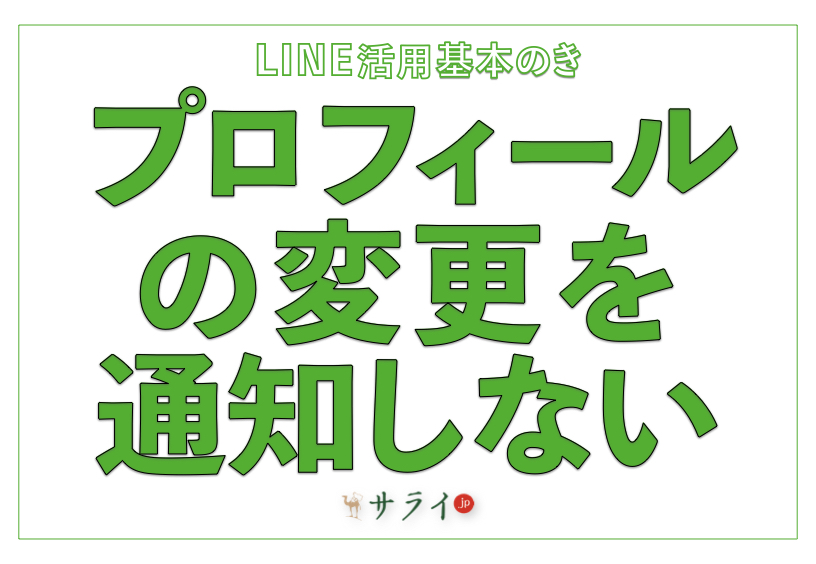歯ぐきの腫れ、出血、じんじんする痛み、それは「歯肉炎」のサインかもしれません。
歯科医院での治療といえば、ブラッシング指導や抗菌薬が一般的ですが、最近では漢方薬によるアプローチも注目されています。
中でも「立効散(りっこうさん)」という漢方薬は、急性の歯ぐきの炎症や痛みにすばやく作用するとして、一部の歯科医院でも処方されているほど。
今回は、そんな立効散の効果や使い方、併せて行いたいセルフケアなどをあんしん漢方の薬剤師で、漢方薬製剤の研究にも携わる碇 純子さんにお話を伺います。
立効散はどんな方におすすめ?

立効散は、その名の通り「効き目が早い」という意味合いの漢方薬です。
主に、歯痛に効果があるとされ、急性の歯肉炎や歯槽膿漏による痛み・腫れに対して用いられることがあります。
1.歯ぐきが赤く腫れて、ズキズキと痛む

「何もしていなくても歯ぐきが痛い」「頬が腫れてきた」など、炎症が強く出ている状態におすすめです。
立効散には、炎症を抑える「黄連(おうれん)」や「黄芩(おうごん)」といった生薬が含まれ、体の内側から熱を冷まし、痛みを鎮めてくれます。
2.歯磨きや食事のときに歯ぐきから血が出る
歯肉炎が進行すると、少しの刺激で出血することもあります。
立効散には止血作用のある生薬も配合されており、炎症を落ち着かせることで出血もしだいに軽減していきます。
3.疲れると歯ぐきが痛くなる、口内環境が不安定
「疲れがたまると歯ぐきが腫れる」「口の中が熱っぽい」そんな体質的に炎症が出やすい方にも立効散は適しています。
体の熱を冷まし、気の巡りを整えることで、慢性的な口内トラブルにもアプローチできます。
立効散と併せて行いたいセルフケア

立効散だけでなく、毎日のセルフケアも歯肉炎対策には欠かせません。
炎症を抑え、再発を防ぐために次のポイントを意識してみましょう。
1.正しい歯磨きで清潔を保つ
歯肉炎はプラーク(歯垢)が原因です。
やさしく丁寧にブラッシングすることで、炎症の元をしっかり除去。
歯科衛生士による定期的なクリーニングも効果的です。
2.口の中の乾燥を防ぐ
唾液は口内の自浄作用を助ける大切な存在。
水分をこまめに摂り、口呼吸を避けるなどして、唾液の分泌を促す工夫をしましょう。
3.ストレスや疲労をため込まない
免疫力が下がると、炎症が出やすくなります。
質の良い睡眠やリラックスできる時間を意識的に作ることで、体のバランスを整えることができます。
立効散に副作用はある? 安心して服用するために

立効散は比較的安全な漢方薬ですが、体質や体調によっては合わない場合もあります。
【主な副作用】
・胃のムカつきや食欲不振
・軟便や下痢
・のどの渇き、体の冷え
これらの症状が気になる場合は、すぐに服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
漢方は、症状だけでなく体質に合っているかがとても重要です。
自己判断で使うのではなく、できれば歯科医師や薬剤師など、専門家に相談のうえ服用するのが安心です。
漢方薬は「誰にでも同じように効く」ものではありません。
ご自身の体質や現在の症状に合った処方を選ぶことが、効果的で安全な使用のポイントです。
▼【専門家による体質チェックもできるあんしん漢方はこちら】
●あんしん漢方:https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=221432a9sera0260&utm_source=sarai&utm_medium=referral&utm_campaign=250621
歯ぐきの炎症や痛みは、生活の質に大きな影響が

「立効散」は西洋医学とは違う角度から体に働きかけ、速やかに痛みを和らげてくれる頼れる存在です。
歯肉炎に悩んでいる方は、ぜひ歯科医院での相談時に「漢方」という選択肢も視野に入れてみてください。
内側からのケアで、健やかな口元を目指しましょう。
<この記事の監修者>

碇 純子(いかり すみこ)
薬剤師・元漢方薬生薬認定薬剤師 / 修士(薬学) / 博士(理学)
神戸薬科大学大学院薬学研究科、大阪大学大学院生命機能研究科を修了し、漢方薬の作用機序を科学的に解明するため、大阪大学で博士研究員として従事。現在は細胞生物学と漢方薬の知識と経験を活かして、漢方薬製剤の研究開発を行う。
世界中の人々に漢方薬で健康になってもらいたいという想いからオンラインAI漢方「あんしん漢方」で情報発信を行っている。
●あんしん漢方(オンラインAI漢方):https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=221432a9sera0260&utm_source=sarai&utm_medium=referral&utm_campaign=250621
イラスト:にゃたり