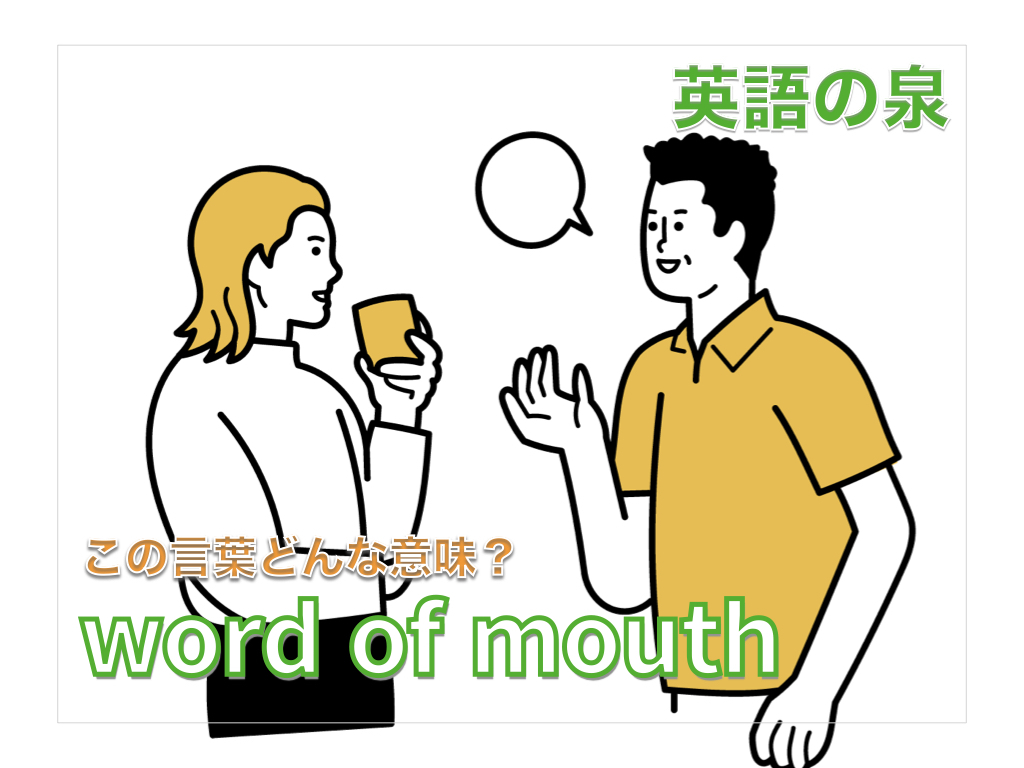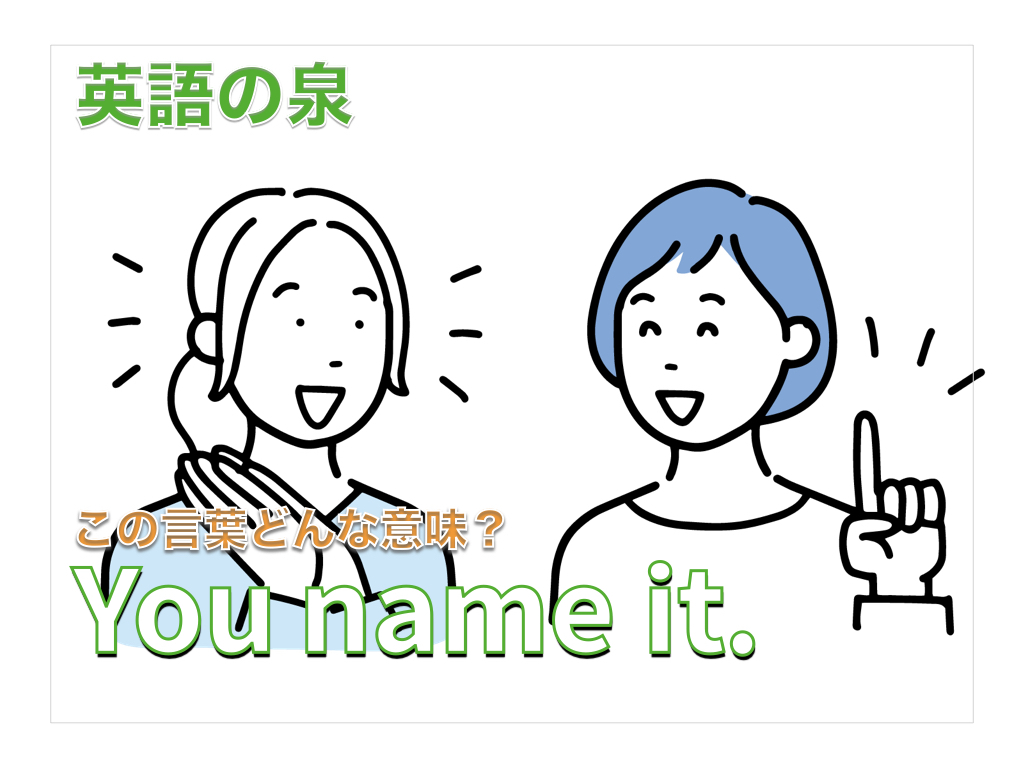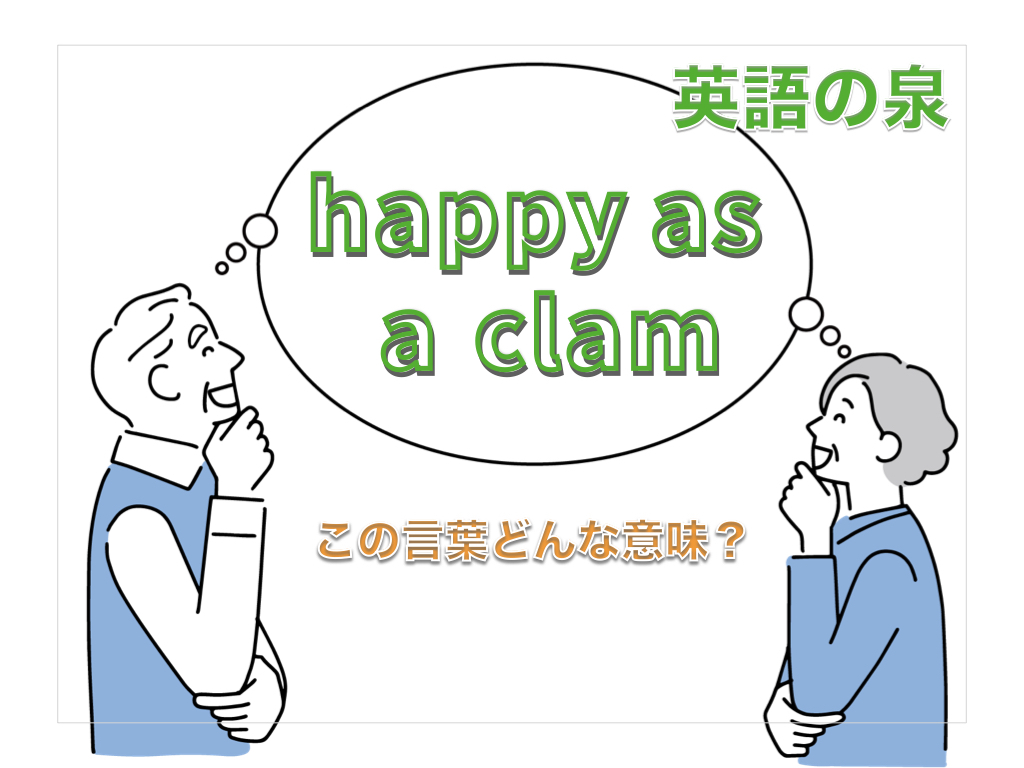サライ世代の多くの人にとって、英語で自然に会話することは容易でないかもしれません。発音や文法、言い回しが日本語とは大きく異なり戸惑うこともありますね。けれど、完璧に英語を話すことを目標にせず、母語や自分自身の個性を活かして話してみるのはいかがでしょう? 自分らしさを大切にコミュニケーションを取ることができれば、英語を学ぶことがより一層楽しくなるように思います。
さて、今回ご紹介するのは “word of mouth”です。
目次
“word of mouth”の意味は?
“word of mouth”の語源は?
“word of mouth” (口コミ)とは何?
最後に
“word of mouth”の意味は?
“word of mouth” を直訳すると、“word” は(ことば)、“mouth” は(口)で「口のことば」ですが……、そこから転じて
正解は……
「口コミ、口づて」という意味になります。
『ランダムハウス英和辞典』(小学館)には、「口頭による伝達、口づて、口コミ」と書かれています。

たとえば、
“I found out about the cafe by word of mouth.”
(そのカフェのことは口コミで知りました。)
“The news of their divorce was spread by word of mouth.”
(彼らの離婚はウワサで広まったよ。)
などのように使います。
また、“word-of-mouth” のようにハイフンでつなぐと「口コミの、口伝えの」と形容詞的に使うことができます。
“word-of-mouth advertising” (口コミ広告)
“word-of-mouth approach” (口コミ作戦)
“word-of-mouth effect” (口コミ効果)
など。
“word of mouth”の語源は?
「口コミ」という日本語は、社会評論家でありジャーナリストでもあった大宅壮一が生み出した造語です。彼は「恐妻」や「太陽族」、「一億総白痴化」といった数々の言葉を生み出しました。
若い頃、生計を立てるために英語を教えたり、翻訳本の出版にも精力的に関わったようです。英語版『アラビアンナイト』の全翻訳に携わるなど、英語と深い関わりを持つ一面がありました(『千夜一夜』集英社刊より)。
英語の「口コミ」を意味する “word of mouth” という表現は、1500年代から広まりました。中世ラテン語の “viva voce”(生きた声で)というフレーズに由来するといわれています。

近年では、SNSやオンライン上で「口コミ」という言葉を頻繁に目にするようになりました。この新たに登場した、「口コミ」に関連する表現を2つご紹介します。
1.“blow up”( 炎上する)
SNSなどで火が勢いよく燃えるかのように、好意的でないコメントが集中して投稿されること表現する際に使われます。
“X blew up.”
(X が炎上した。)
“She blew X up with the photo.”
(彼女はその写真でX を炎上させた。)
2.“go viral” (拡散される、バズる)
インターネットや口コミを通じて情報が急速に拡散されることを指します。
“The video went viral on social media.”
(その動画はソーシャルメディアで拡散された。)
SNSやデジタル時代の「口コミ」は、言葉の世界に新しい風を吹き込んでいるようです。
“word of mouth” (口コミ)とは何?
口コミは、もともと人々が直接言葉を交わして伝えることから始まりました。“word of mouth”は、個人の経験や意見が他者に伝わるという意味です。一方で、ここに “pass down”を加えると、文化や伝統が口伝えで受け継がれるという意味になります。
たとえば、
“We pass down our traditions through word of mouth.”
(私たちは伝統を口伝えで後世に伝えています。)
“The history of our village has been passed down by word of mouth for generations.”
(私たちの村の歴史は何世代にもわたり口伝で伝えられてきました。)
特に昔話のような「口承」は、文字による記録とは異なり、語り手によって物語の内容や表現が変わります。その即興性や語り手の工夫が物語に新たな魅力を加え、味わいを生みました。語り手の情熱や聞き手の空気感が混じり合い、一期一会で伝えられる物語は、SNSの手軽さとは、別の体験となったのではないでしょうか。
最後に
幼い頃、母方の実家の長野県で参加した法事で、忘れられない体験がありました。ある親戚のおじいさんは昔話の名人で、親戚の子どもたちはその語りにいつも夢中でした。ある日、そのおじいさんが幽霊と死者の話を始めました。話が進むにつれ、私たちはどんどん引き込まれ、そして心底怖くなりました。
話が一段落した後、お寺での法事が始まり、その後、みんなでお墓参りをしました。お墓は、墓石の下が大人が2人入れるほどの小さな部屋のようになっています。記憶はあいまいですが、私たち子どもも促され、恐る恐る中に入りました。
そして出ようとした時、先ほどのおじいさんがゆっくりと私の目前で扉を閉めたのです。中は真っ暗になりました。その瞬間、先ほどの幽霊話が思い出され、恐怖で足がすくみ、声も出ません。後ろにいた幼いいとこも息を呑んで固まっています。数秒後におじいさんは笑いながら扉を開けてくれました。子どもをからかった、ただの冗談だったのですが、幽霊話の効果は絶大で、私にとってその体験は、どんなホラー映画よりも鮮明で恐ろしい記憶として残っています。
“word of mouth” (口コミ)の語源とされる“viva voce”(生きた声で)。相手の声を通じて得る情報には、大きな影響力があります。情報収集としての口コミは大変便利ですが、人の声が持つ熱量や情報量の豊かさには、特別な力があるのだと実感した体験でした。
次回もお楽しみに。
●執筆/池上カノ
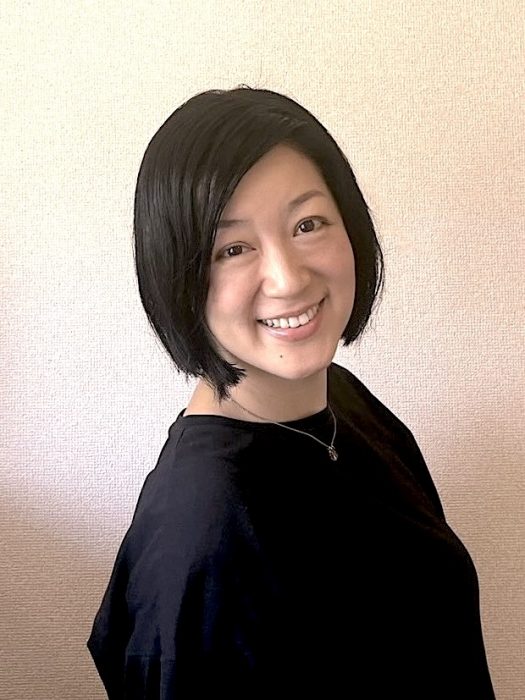
日々の暮らしやアートなどをトピックとして取り上げ、 対話やコンテンツに重点をおく英語学習を提案。『英語教室』主宰。 その他、他言語を通して、それぞれが自分と出会っていく楽しさや喜びを体感できるワークショップやイベントを多数企画。
インスタグラム
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com