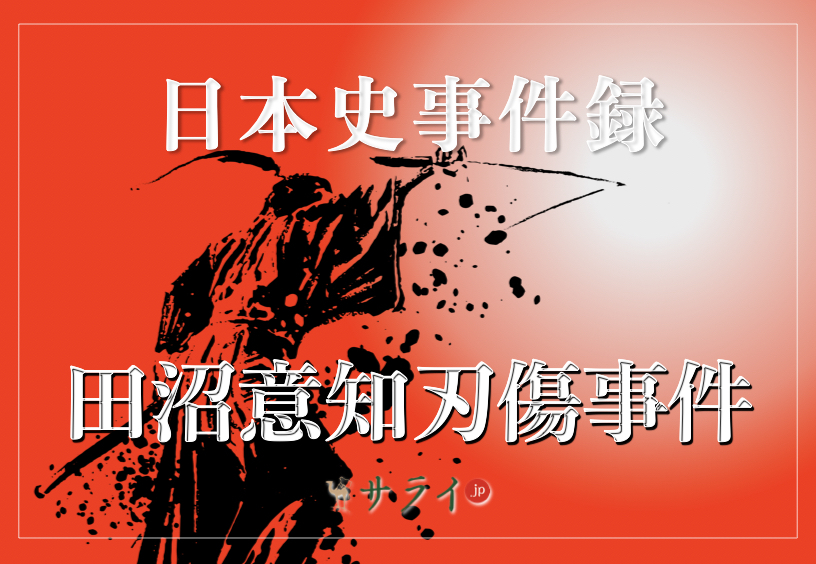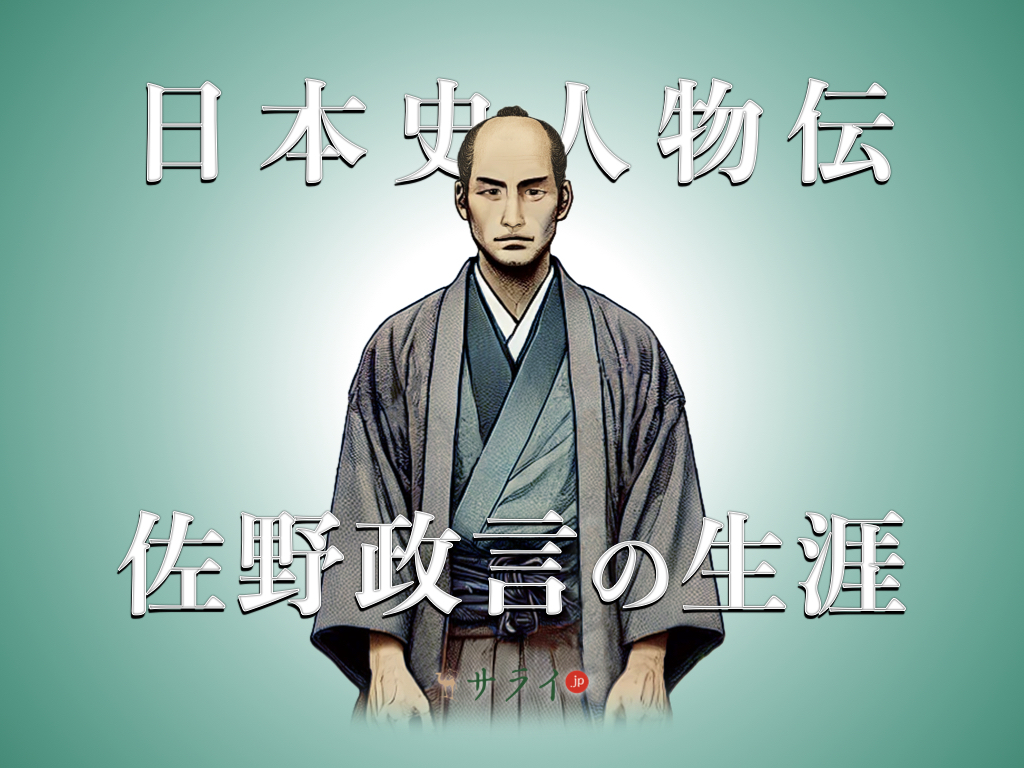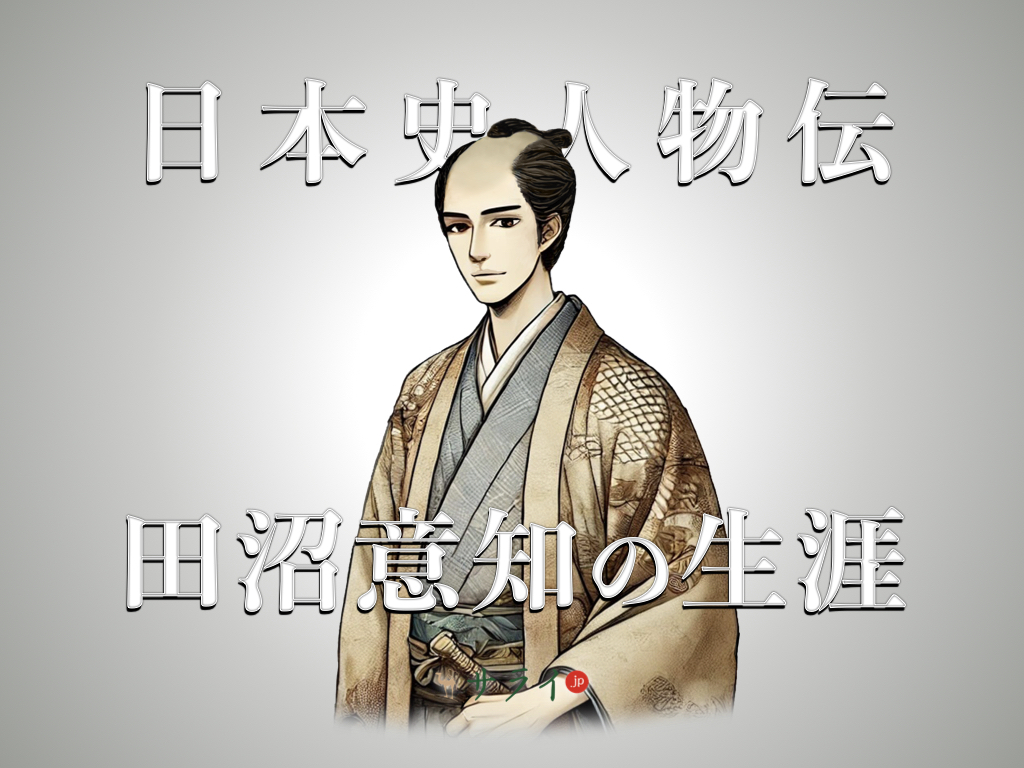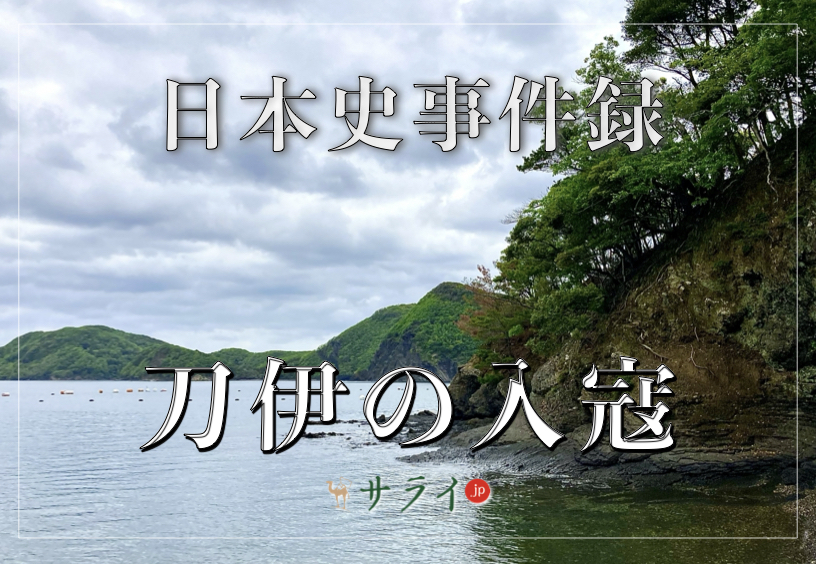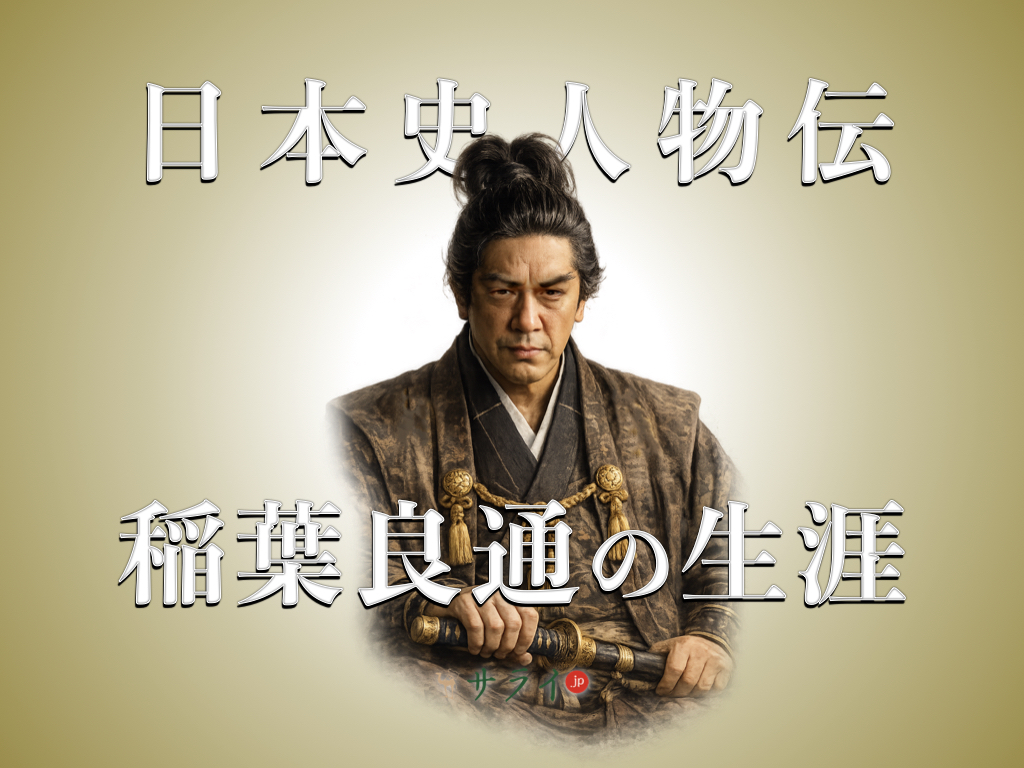はじめに-田沼意知刃傷事件とはどのような事件だったのか
江戸時代後期の政局を大きく揺るがせた「田沼意知刃傷(にんじょう)事件」。天明4年(1784)3月24日、江戸城中にて若年寄・田沼意知(たぬま・おきとも)が、旗本の佐野政言(さの・まさこと)によって突如斬りつけられました。
意知は重傷を負い、約1週間後に死亡。この事件は、単なる私怨によるものとされつつも、民衆の間では「世直し大明神」の伝説が生まれるほどの影響力を持ち、幕政に大きな転機をもたらしました。
この記事では、そんな「田沼意知刃傷事件」についてご紹介します。

目次
はじめに-田沼意知刃傷事件とはどのような事件だったのか
「田沼意知刃傷事件」はなぜ起こったのか
この事件の内容と結果
「田沼意知刃傷事件」その後
まとめ
「田沼意知刃傷事件」はなぜ起こったのか
この事件の背景について、丁寧に見ていきましょう。
個人的な怨恨が積み重なり…
事件を起こした旗本・佐野政言は、鎌倉時代から続く名門・佐野家の出身で、源左衛門常世の末裔とされます。もともと田沼意次・意知父子は、佐野家の家来筋にあたる立場にありました。
政言はこの縁を頼み、昇進を願って意知に賄賂を贈ったといわれます。しかし、その願いは聞き入れられず、さらに佐野家に代々伝わる七曜旗や系図まで奪われたとされます。
加えて、天明3年(1783)12月、将軍・徳川家治(とくがわ・いえはる)の鷹狩に同行した際、政言が射落とした雁について「本人が射ていない」などの理由で、他の者には褒美が与えられた一方で、政言には与えられなかったという屈辱的な出来事もありました。
こうした積年の不満と家名への侮辱が、刃傷に至る背景にあったと見られています。

広がる政治不信と民衆の反発
この事件には、当時の幕政に対する広範な不満も影を落としています。田沼意次・意知父子は、商人との結びつきを背景に財政改革を進めましたが、それが腐敗や賄賂の横行を生み、特に中下級武士や町人層からの反発を強めていました。
政言の行動は、こうした時代背景の中で「個人の怨恨」を超えた象徴的な事件として受け止められたのです。
【田沼意知刃傷事件の内容と結果。次ページに続きます】