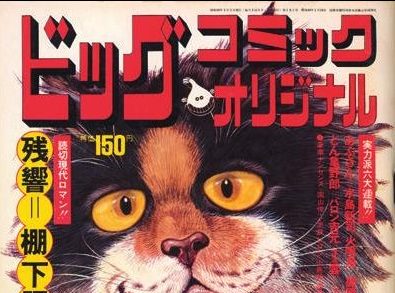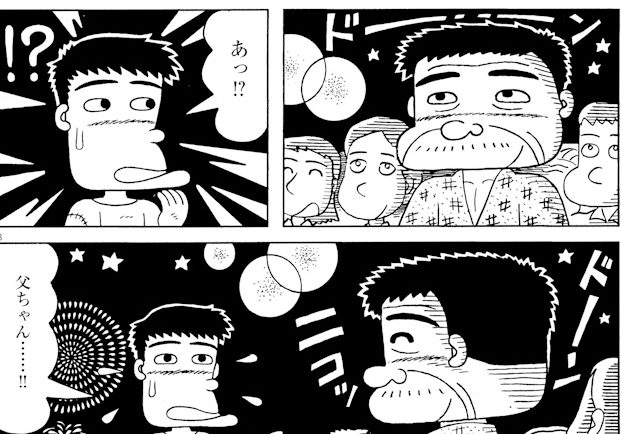古来、日本人は雲にさまざまな名前を付け、句にも詠んできた。天気の変化と気象現象を知り、雲の名がもつ意味を知れば、空を見上げることがより楽しくなる。
「昔も今も、雲は人々が思いを託せる身近な存在です」

解説:この秋はどうして急に年をとった感じがするのだろうか、雲に鳥が突っ込んでいく──。
芭蕉の最晩年の句です。身体が衰えてしまったことへの嘆きと、雲に鳥がぶつかっていく情景を重ねています。雲の痛み、鳥の痛みの両方を芭蕉は感じ取っているのでしょう。写真/plain picture/アフロ

江戸前期の俳人。寛永21年(1644)、伊賀(三重)で生まれる。「さび」や「軽み」を尊ぶ蕉風を確立。紀行文に『野ざらし紀行』『おくのほそ道』など。元禄7年(1694)、旅先の大坂で病死。51歳。写真/アフロ
「俳聖」と呼ばれた松尾芭蕉が亡くなったのは、元禄7年(1694)の旧暦10月12日のことだが、その少し前、9月26日に次のように「雲」の俳句を詠んでいる。
此の秋は何で年よる雲に鳥
俳人の小澤實さんは、この句を「芭蕉の代表句のひとつ」と評価する。
「“雲”という存在を、自分の内面の象徴のようなものとして描いています。この句が詠まれた背景には、芭蕉自身の老いや衰弱があります。何で年よる──なんと年老いてしまったことか、と嘆いています。その痛みや嘆きが、鳥に突っ込まれた雲の痛みと重なっている。個人の痛みが、雲によって存在感を放っているのです」
小澤さんによれば、俳人たちはこれまでも「雲」を句に多く詠んできたという。
「俳句という文芸は、五七五というわずか十七音からなっています。自分の思いを語るには短すぎます。だからこそ、俳人は、ものに思いを託しました。その代表的な句材が、“雲”です」
例えば与謝蕪村(江戸中期の俳人)の句。
廿日路(は つかぢ)の背中にたつや雲の峰
(廿日路= 中山道行く自分の背中に入道雲が湧き出ている)
あるいは小林一茶(江戸後期の俳人)。
しづかさや湖水の底の雲のみね
(湖水の上の入道雲が、湖の底に影を映している)
俳句だけではない。
平安時代に清少納言は、『枕草子』で「春」の趣あるものとして、「紫だちたる雲のほそくたなびきたる」様子を挙げた。
「昔も今も、雲は人々が思いを託せる身近な存在です。言い方を変えれば、詠み手が雲に何を託したのか。そのことに思いを馳せることが、雲の俳句の楽しみ方といえるでしょう」
夏雲は岩の如く
俳誌『ホトトギス』の創刊に関わったことでも知られる明治の俳人・正岡子規は、随筆にこんな言葉を残している。
春雲は絮(わた)の如く、夏雲は岩の如く、秋雲は砂の如く、冬雲は鉛の如く、晨(あさ)雲は流るるが如く、午(ひる)雲は湧くが如く、暮雲は焼くが如し(『寸紅集』)
「正岡子規は、科学的な目でものを捉える『写生』に開眼した俳人です。春の綿のような雲にはじまり、夏の入道雲は岩、秋の鱗雲は砂、どんよりとした冬の雲は鉛に喩えています。春の雲の明るさ、夏の雲の陰影の濃さ、秋の雲のかげり、冬の雲の重たさ、こうした特徴をよく捉えています」
だが、これは写実的であるだけではないと、小澤さんは言う。
「これらの切り取り方は、写実的であると同時に、それぞれの季節に特有の心の模様も表現しています。春の心は綿雲のようだと言われたら、皆さん、頷きますよね? 雲は観察の対象というだけでなく、子規にとっても、やはり心そのものなのです」
増えた雲の季語
小澤さんは、石橋辰之助の〈短夜の扉(と)は雲海に開かれぬ〉に別の面白さを見出す。
「俳句に詳しいと、この句には『短夜』『雲海』と夏の季語がふたつ使われていますので、少し疑問に思うかもしれません」
江戸時代まで、山は信仰の対象だった。明治以降、ヨーロッパから登山という文化がもたらされ、人々は気軽に山へ登るようになる。
石橋辰之助もそのひとりだ。登山に親しみ、句材としての「雲海」を発見した。
「石橋辰之助は、『短夜』という夏の季語とあわせて使うことで、『雲海』を季語としてならしていったのでしょう」
小澤さんによれば、「季語」を生み出すことも、俳人の醍醐味だ。
「芭蕉は、“俳句の原型を作った人”といっていいと思いますが、季語についてこう言っています。“季節(季語)の一ツもさがし出したらんは後世によき賜也”(『去来抄』)と。石橋辰之助も同じ思いだったのではないでしょうか」
俳人の目を通すと、雲はさらなる魅力を持ち始める。
解説:小澤實さん(俳人・67歳)

取材・文/角山祥道
※この記事は『サライ』本誌2024年7月号より転載しました。