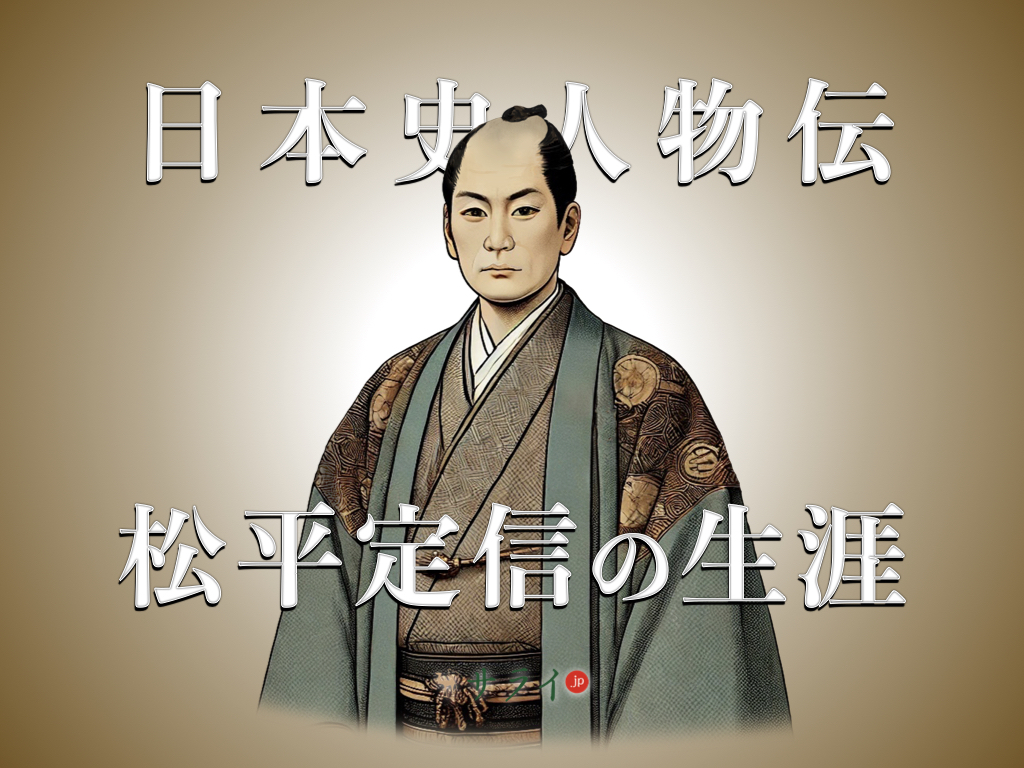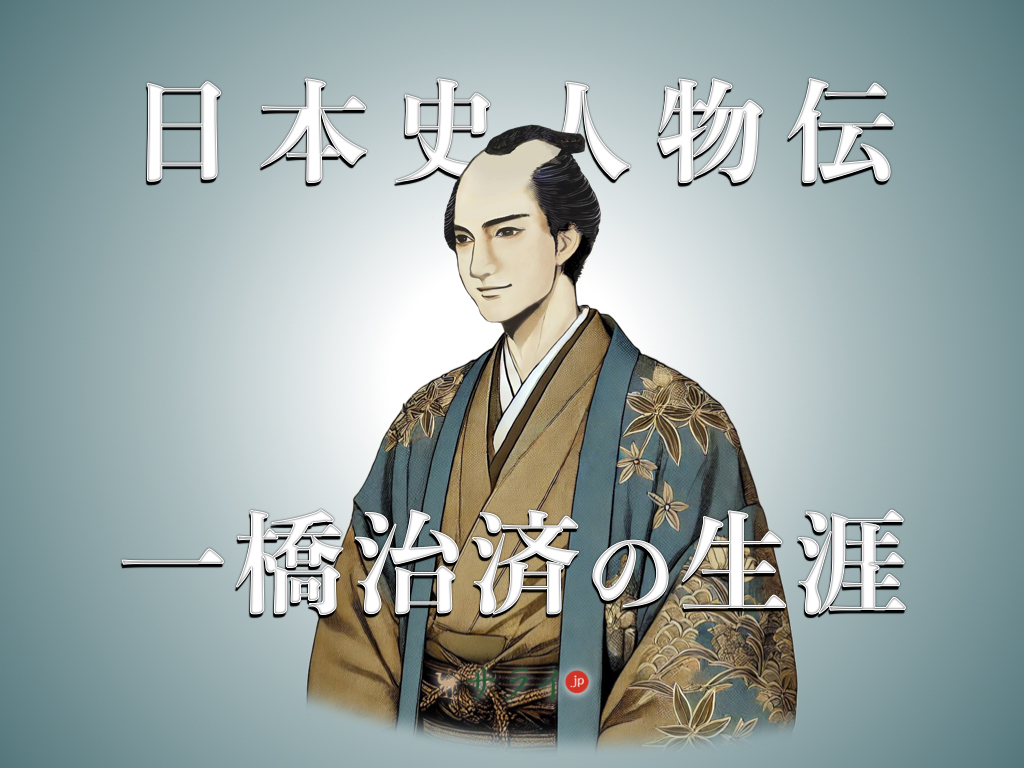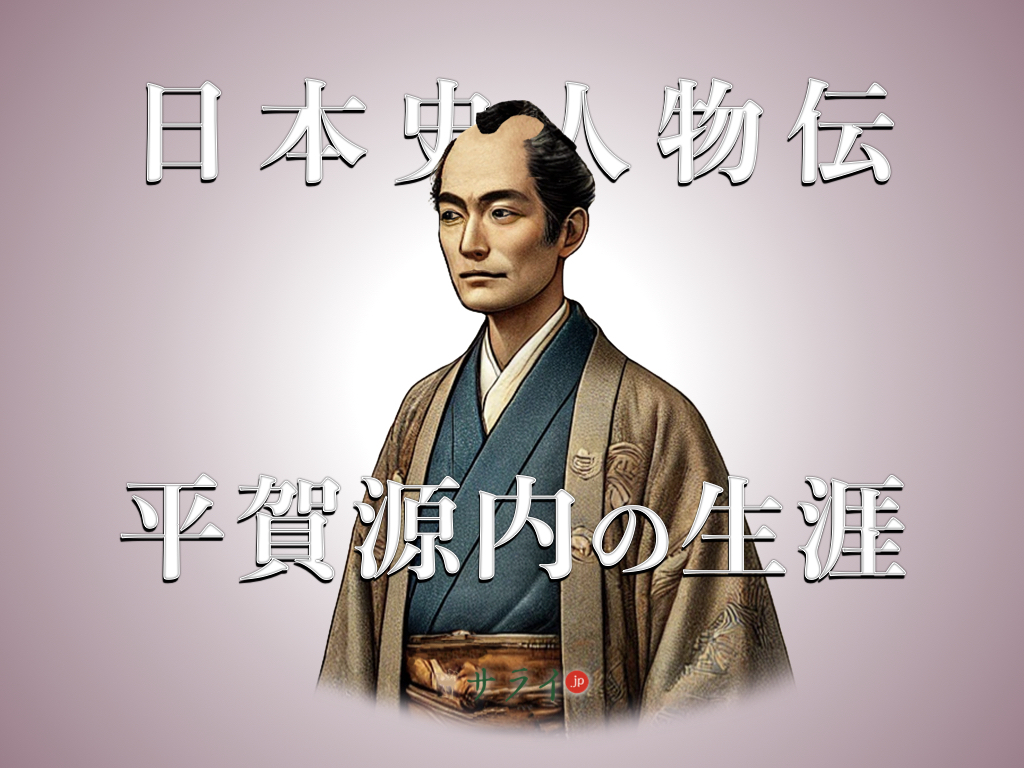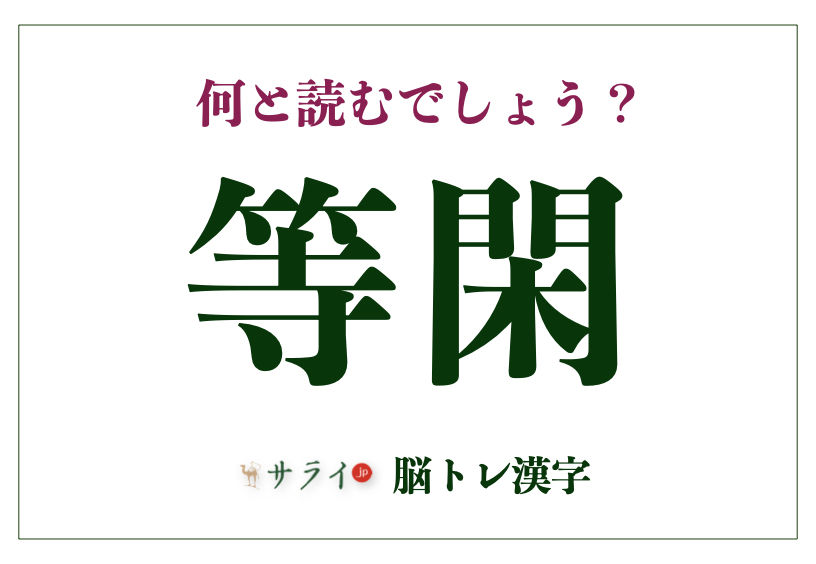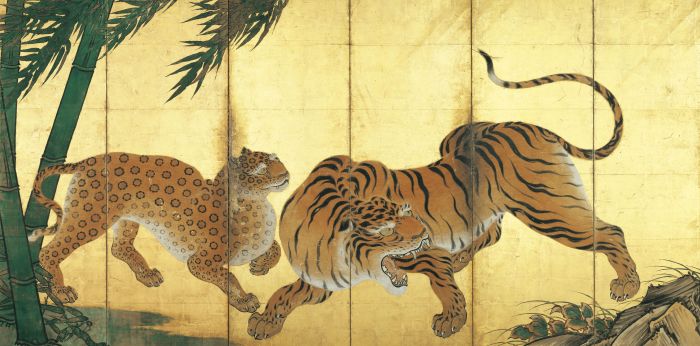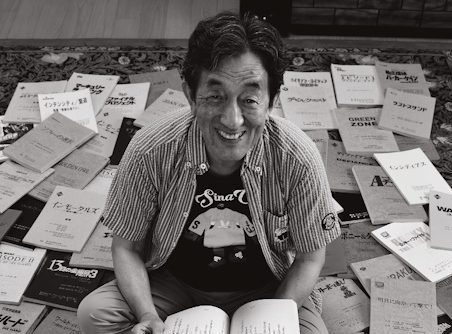老中首座に就任
「天明の大飢饉」含む数々の災害に苦しめられた人々は、当時の老中・田沼意次への不満を募らせます。一方、藩政立て直しと領民救済を成功させた定信は、たちまちに注目の的となりました。そして、天明7年(1787)6月、御三家と将軍・家斉(いえなり)の父・一橋治済(ひとつばし・はるさだ)の推挙を受け、田沼の代替わりするかのように、定信は老中首座に抜擢されたのです。

「寛政の改革」を行う
定信が行った政策は、そのほとんどが田沼時代に推進された重商主義への反動であるといえます。商業の発展を重視した意次の政治により、華やかな江戸文化が花開きましたが、一方で賄賂や縁故による人事も横行していました。
定信は、田沼時代に行われた政策を一掃し、緊縮財政と風紀の取り締まりによって、幕政を安定させようとしたのです。定信が6年の間に行った「寛政の改革」では、主に以下のような政策が実施されました。
財政再建
倹約令を発し、幕府支出を抑制。御家人や旗本の借金を棄却する札差棄捐令(きえんれい)を発布。大奥の抑制も行いました。
農村復興
荒地の開墾を促進し、農業人口の回復を図る旧里帰農奨励令(きゅうりきのうしょうれいれい)を実施。
出版・思想の統制
朱子学を振興し、異学を禁じる「寛政異学の禁」を発布。出版統制令も出しました。
社会秩序の維持
石川島人足寄場(にんそくよせば)を設置し、江戸の治安維持を図りました。

写真は、石川島灯台。
幕政と人々の暮らしの安定化を第一に考えた結果でしたが、前老中・意次とは真逆の理由で、人々は不満を募らせていくこととなります。
厳しい政治に高まる不満
定信は、意次の政治がうまくいかなかったのは、町人文化の繁栄による風紀の乱れが原因であると考えていました。風紀を正すために、洒落本(江戸で流行した小説の一種)や黄表紙(田沼時代に流行した小説の一種)などを発禁処分にします。また、武芸と学問を奨励し、朱子学を正学とする「寛政異学の禁」を出して、蘭学者を公職追放することに。
さらに、大奥や朝廷にかかる経費の節約を図り、華やかな田沼時代を謳歌した江戸市中の人々に対しても、贅沢を厳しく取り締まったそうです。当時流行した狂歌の中に、「白河の清きに魚も棲みかねて もとの濁りの田沼恋しき」「世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶ(文武)というて夜も寝られず」というものがあります。
定信の政策はある程度功を奏しましたが、娯楽や自由を奪われた人々の不満はかなり高まっていたことが分かります。
老中辞任と晩年
定信のあまりにも厳しすぎる政策に、人々の不満が高まっていた頃、日本の周りに外国船が度々出没するようになっていました。経世論家の林子平(はやし・しへい)は、著書『海国兵談』にて海防の必要性を説きましたが、幕政に口出しするものとして、発禁処分にされてしまいます。
発禁処分にしたものの、定信自身も海防を強化する必要があると痛感していました。そして、江戸湾付近を自ら視察し、防備に着手したのです。鎖国体制を続けつつも、外国の脅威から国を守るために奮闘した定信。しかし、寛政5年(1793)、政策の途中で老中を罷免されてしまいます。
その背景には、民衆の不満が高まっていたことのほかに、将軍・家斉が実父・一橋治済を大御所として江戸城に迎え入れようとしているのを定信が反対したことなどが関係しているのではないかといわれています。

その後は白河藩主として藩政や文化活動に専念し、藩校立教館の充実や『集古十種(しゅうこじっしゅ)』の編纂などに取り組みました。
晩年は江戸・築地の浴恩園(よくおんえん、定信が築いた庭園)で風雅な生活を送り、文政12年(1829)、72年の生涯に静かに幕を閉じました。
辞世は、〈今更に何かうらみむうきことも楽しきことも見はてつる身は〉です。

隠居後、自身のことを「楽翁」と号した。
2023年NHKドラマ10『大奥 Season2』で描かれた、松平定信
2023年NHKドラマ10『大奥 Season2』で描かれた松平定信は、物語の緊張感を高める重要なキャラクターです。このドラマは、よしながふみの人気漫画『大奥』を原作に、「男女逆転」という独自の設定をもとにした歴史改変ドラマ。江戸時代を舞台にしながらも、現実とは異なる世界観が描かれています。
この特異な世界観の中で登場する松平定信(演:安達祐実)は、8代将軍・吉宗の孫にあたり、次期将軍の座を狙う野心家として描かれています。母・宗武から「将軍になる」という野望を託された彼女は、将軍後継の座をめぐって田沼意次と激しく対立。
その対抗心はただの政権争いにとどまらず、個人としての誇りや宿命を背負ったものでした。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で描かれる、松平定信
『べらぼう』で描かれる松平定信(演:寺田心)は、聡明かつ生真面目な性格ですが、「武士はこうあるべき」という信念があるため、ときに感情的な人物として描かれるようです。
『大奥』と『べらぼう』、どちらの脚本も手掛けるのは森下佳子さん。繊細で奥行きのある物語作りに定評のある森下さんが、松平定信を『べらぼう』の中でどのように描き出すのか、期待が高まります。
まとめ
松平定信は、寛政の改革を通じて幕府権威の回復や社会の安定を目指しましたが、短期間で辞任に追い込まれるなど、その評価は賛否が分かれます。一方で、文化人としての活動や生涯200部以上の著作を残し、江戸時代の学問や文化に大きな影響を与えました。
幕政を立て直すため、様々な政策を行った松平定信。老中を辞職した後も、国の行く末を案じていたそうです。田沼意次とは真逆の厳しい政策で人々から非難された定信ですが、国と民衆のことを誰よりも考えていた人物だったといえるのではないでしょうか?
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
肖像画/もぱ(京都メディアライン)
HP: http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『朝日日本歴史人物事典』(朝日新聞出版)
『日本人名大辞典』(講談社)
『世界大百科事典』(平凡社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)