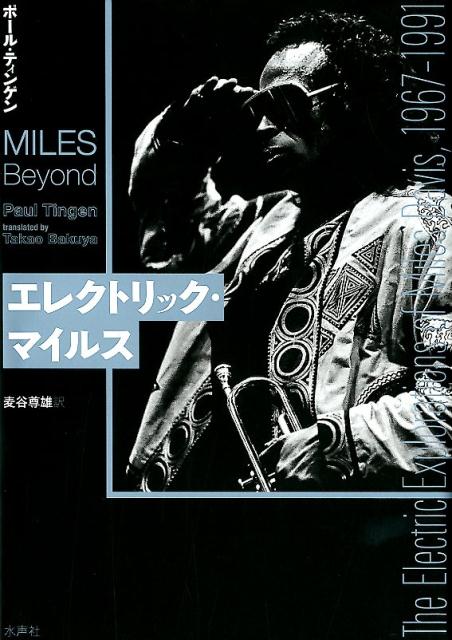文/池上信次

「外から見たジャズ(https://serai.jp/hobby/1127076)」の続きです。今回はスティングとマイルス・デイヴィスのエピソードを紹介します。
ロック界のスーパースター、スティング(ヴォーカル、ベース)は2003年に自伝『Broken Music: A Memoir by Sting』を著しました。日本語版は『スティング』(スティング著、東本貢司訳、PHP研究所)のタイトルで2005年に出版されましたが、そこには多くの「ジャズ」についての記述があります。スティングの音楽を聴けば、そのベースにはジャズがあることが容易に想像できますが、これを読むと、スティングにとってジャズは特別なものであったことがはっきりとわかります。
カレッジでバンドに誘われたスティングは、そのメンバーとディスカッションのあと、マイルス・デイヴィスの『ビッチェズ・ブリュー』のレコードを聴かされます。「彼は私の反応を注意深く見守った」とあるので、これがそのバンドの方向を示唆するものなのでしょう。スティングは「マイルズの前作はよく聴いていた(中略)が、この新作にはまだ馴染みがなかった。偉大なるトランペッターが、のちにフュージョンミュージックと呼ばれる斬新な路線を打ち出したこのアルバムは瞬く間に私の心を深くとらえ、それからの約1時間、私はその麻薬的な作用に酔いしれた」とあります。この後スティングはプロを目指して邁進していくので、『ビッチェズ・ブリュー』はそのための大きな刺激になったと思われます。
駆け出しの頃については、このほかにも、所属するバンドがチック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴァーの前座をし、その演奏に打ちのめされたことが書かれています。リターン・トゥ・フォーエヴァーのメンバー個々(チック:キーボード、ビル・コナーズ:ギター、スタンリー・クラーク:ベース、レニー・ホワイト:ドラムス)の演奏にまで言及していますので、強い印象だったことを感じさせます。ジャズはスティングのキャリア形成に大きな影響を与えているのです。
マイルス・デイヴィス『ユア・アンダー・アレスト』(コロンビア)
演奏:マイルス・デイヴィス(トランペット)、ジョン・スコフィールド(ギター)、ロバート・アーヴィング三世(キーボード)、ダリル・ジョーンズ(ベース)、アル・フォスター(ドラムス)、ヴィンセント・ウィルバーン・ジュニア(ドラムス)、スティーヴ・ソーントン(パーカッション)、スティング(ヴォイス)、ほか
録音:1984〜85年
冒頭収録の「ワン・フォーン・コール/ストリート・シーンズ」にはスティングがヴォイスで参加していますが、知らなければスティングの声とはわからないでしょう。
そして、そのずっと後、ザ・ポリス活動停止後の1984年、スティングはマイルスのアルバム・レコーディングに参加します。
私は初めてマイルズ・デイヴィスに会った。ニューヨークにある彼のスタジオに招待されたときのことだ。それに先立って私は彼の子飼いの優秀なミュージシャンを自分のプロジェクトに参加させていた。当時、ブルー・タートルズ・バンドのメンバーだったダリル・ジョーンズだ。彼が私たちを引き合わせた。
スティングはスタジオに行くとマイルスの冴えないジョークで歓迎され、困惑していると「フランス語はできるか?」と問われ、「ええ」と答えると、「オーケイ、これを訳してくれ」と紙を渡されたとあります。そこに書かれていたのは「ミランダ権利」と呼ばれる、アメリカで逮捕の際に告知される被疑者の権利を表した文章でした。マイルスがスティングに与えた時間は、どういうつもりかわずか5分。
渡されたものをみて絶句した。私のフランス語力はほんの初心者レベルで(中略)しかし同時に、仕事をくれた偉大なマイルズ・デイヴィスをなんとかして喜ばせたいとも思った。
スティングはロンドンに住むフランス語が堪能な妻のトゥルーディーを、外出先まで追いかけて電話をかけてつかまえ(携帯電話がない時代のニューヨークとロンドンです)、訳を頼んでなんとか準備完了。そしてすぐに録音が開始されました。
子供の頃のヒーローのひとり、マイルズ・デイヴィスとスタジオに立ち、ファンキーなトランペットが流れるなかで、私はフランス語でミランダ権利を叫ぶのだ。(中略)数分後、私はスタジオを出て街を歩いていた。詐欺にでも遭ったような気分だったが、恐ろしく幸せで誇らしかった。マイルズ・デイヴィスのアルバムに参加したのだ。
当時ザ・ポリスでロック界の頂点を極めたスティングでも、マイルスとの共演はとても誇らしいものだったのです。
一方、『マイルス・デイヴィス自伝』(マイルス・デイヴィス、クインシー・トゥループ著、中山康樹訳、シンコーミュージック・エンタテイメント刊)では、このアルバムのスティングの参加については、大きくは紹介されていません。これぐらいです。
1984年の後半から1985年の初めにかけては、『ユア・アンダー・アレスト』をレコーディングした。(中略)スティングも入っているが、ダリル・ジョーンズが彼とレコーディングしていて、連れていってもいいかと聞いたから、かまわないと言ったんだ。スティングはフランスの警官の声の役をやって、セリフだけで入っている。この時は、なかなか良い奴だと思った。ダリルを自分のバンドに雇おうとしているなんて知りもしなかったけどな。
マイルスからするとスタジオに「招いた」わけではないようです。のちにダリル・ジョーンズがスティングのバンドに引き抜かれたということについては、多くスペースを割いているので、その件のほうがマイルスにとっては重要だったようです。
しかし、このアルバムへのスティングの参加は、「アルバムのなかの1曲のいち要素」にとどまらず、じつはマイルスのキャリアに大きな影響を及ぼしているのです。どちらの自伝にも書かれていませんが、『マイルス・デイヴィス大事典』(小川隆夫著、シンコーミュージック・エンタテイメント刊、2022年)の『ユア・アンダー・アレスト』の解説によれば、飛び入りとはいえこの録音についてスティング(側)は当然ながらギャラ(高額)を請求。しかしマイルスのレコード会社は予定外として支払いを拒否し、なんとマイルスは自腹で対応。レコード会社に失望したマイルスは、この作品を最後にコロンビアからワーナーへ移籍するということになったのでした。
移籍後マイルスは『TUTU』など、さらなるヒット作、新しい代表作を作りましたが、もし、あのときスティングがフランス語は話せないと返事をしていたら、ロンドンのトゥルーディーがつかまらなかったら、その後のマイルスの状況はけっこう違うことになっていたかもしれませんね。
文/池上信次
フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中。(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(シンコーミュージック・エンタテイメント)、『後藤雅洋監修/ゼロから分かる!ジャズ入門』(世界文化社)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。