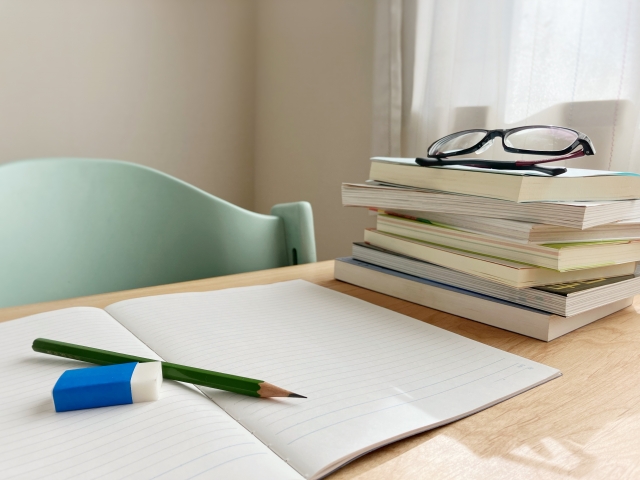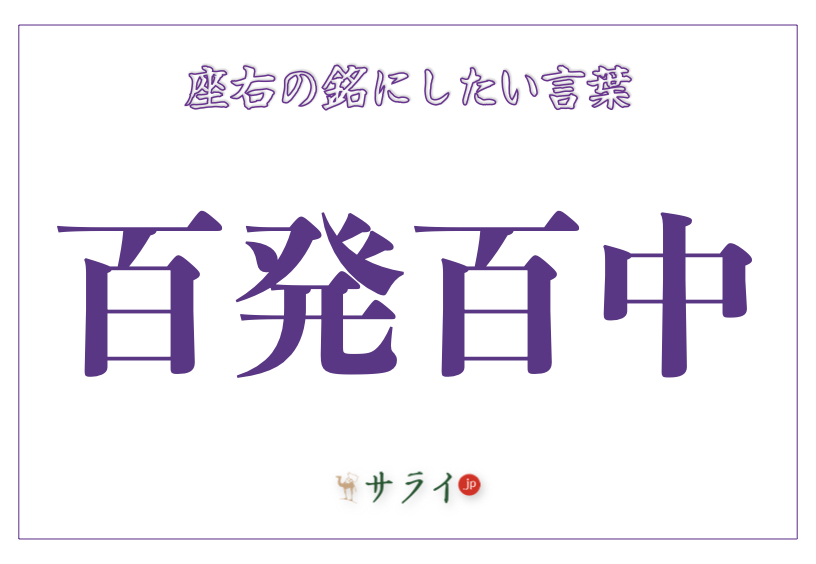文/印南敦史
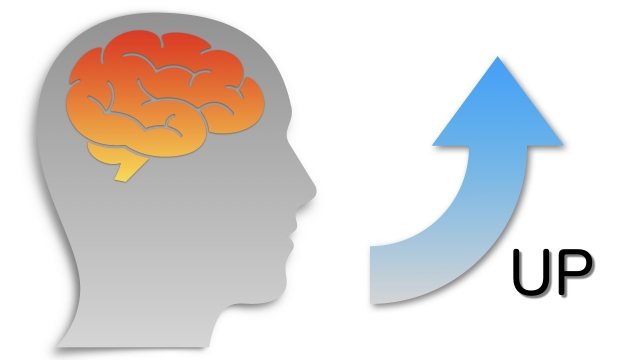
想像してみよう。もしも自分が80歳だったとしたら、「私は、もう80歳だ」と実感するのだろうか?
それは当たり前の発想なのかもしれないが、とはいえ「もう」という感じ方には多少なりともネガティブな印象がある。
では、これをポジティブな文章にするとしたら?
『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』(西剛志 著、アスコム)の著者によれば、その答えは「私は、まだ80歳だ」なのだという。
なるほど「もう」を「まだ」に置き換えただけで、ずいぶんポジティブな印象になる。それは「使うことばを変えただけで、“脳がよい方向にシフトチェンジした”ということを意味するようだ。
考え方ひとつで、見ている世界を変えられるということ。そして、ちょっとしたコツがあれば、いつまでも元気な脳でいられるということでもあるのだろう。
「脳が変わるとか、本当に?」という声が聞こえてきそうですが、決して、机上の空論ではありません。80歳をこれから迎えようという人や、もうすでに80歳は超えているけども、タイトルが気になって手にとってくださった人に対しても、私は自信を持ってこの本をおすすめできます。(本書4ページより)
そんな本書は、2022年にベストセラーとなった同名書籍の“増量版”。2024年12月時点での最新データも追加しつつ、「運動」「生活習慣」「人間関係」などのテーマごとに“脳を元気な状態に保つためのヒント”を網羅しているのである。
興味深いのは、「老人脳にならないためのマインドのつくり方」という章において著者が「主観年齢で生きていく」ことを勧めている点だ。
たとえば、85歳でも自分では50歳と思えば、主観年齢は50歳です。すると面白いことに、50歳のような行動をとるようになってくるのですね。もちろん本気で思わないとそうならないのですが。(本書251ページより)
主観年齢を若くすることは、脳の老化も防いでくれるようだ。そのことに関連し、韓国の研究で明らかになったという興味深いエビデンスも明らかにされている。
59〜84歳の被験者68人の主観年齢と脳の状態を分析した結果、主観年齢を実年齢より「若い」と答えた被験者は、灰白質の密度が高く、記憶力もよく、うつの傾向も低いことがわかったというのだ。
また、「若く見えるようにしただけで、血圧まで下がった」という嘘のような実験結果もあるらしい。
「ヘアサロン実験」というものなのですが、27歳から83歳の女性47名に対して、髪のカラーリングを行い、実年齢よりも若く見えるようにしました。するとこちらも驚くような結果が出ました。
髪を染めて若く見えるようになった人たちの血圧が、若い頃の血圧に戻っていたのです。(本書255ページより)
世の中には、若づくりをしている年配の人に対して「年齢不相応で恥ずかしい」などと陰口を叩く人もいる。ところが、それは勘違い。若づくりは、体にとっても脳にとってもよい方向に左右するというのである。
若づくりが脳内のイメージを変化させ、それにともなって生理的反応(体内で起こる化学課程)にまで影響を及ぼすということ。その結果、健康状態がよりよくなっていくわけである。
そればかりか、見た目年齢は血管年齢にも関係しているといわれてもいるという。「実年齢より見た目が若い人」と「実年齢より見た目が老けている人」の血管年齢を調査したところ、次のような結果が出たそうなのだ。
見た目が若い人 → 実年齢より血管年齢が若い 79%
見た目が老けている人 → 実年齢より血管年齢が若い 19%
(本書256ページより)
見た目が実年齢よりも老けている場合、81%の人が血管年齢まで高くなるということだ。
こうしたことからもわかるとおり、「自分は若い」という意識を持ち続けることには効果があるようだ。逆にいえば、「老けた」「歳をとった」「もう若くない」など“脳にとってのNGワード”は避けるべきだということにもなる。
歳をとっているというイメージは、死亡リスクまで高めます。自分の年齢に対して実年齢よりも8〜13歳高く感じている人は、死亡リスクや病気リスクが通常より18〜35%高かったというのです。(本書258ページより)
もちろん、加齢に従って運動機能が低くなるというようなことはあるに違いない。しかしそれでも、ポジティブな考えを持つことには大きな意味があるのだ。
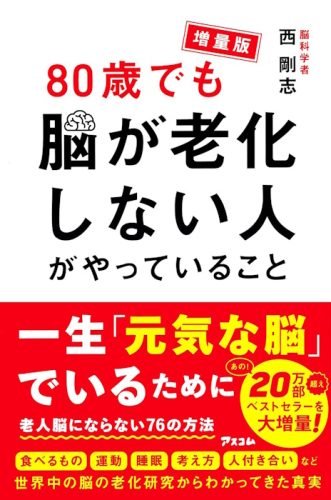
西剛志 著
1540円
アスコム
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。