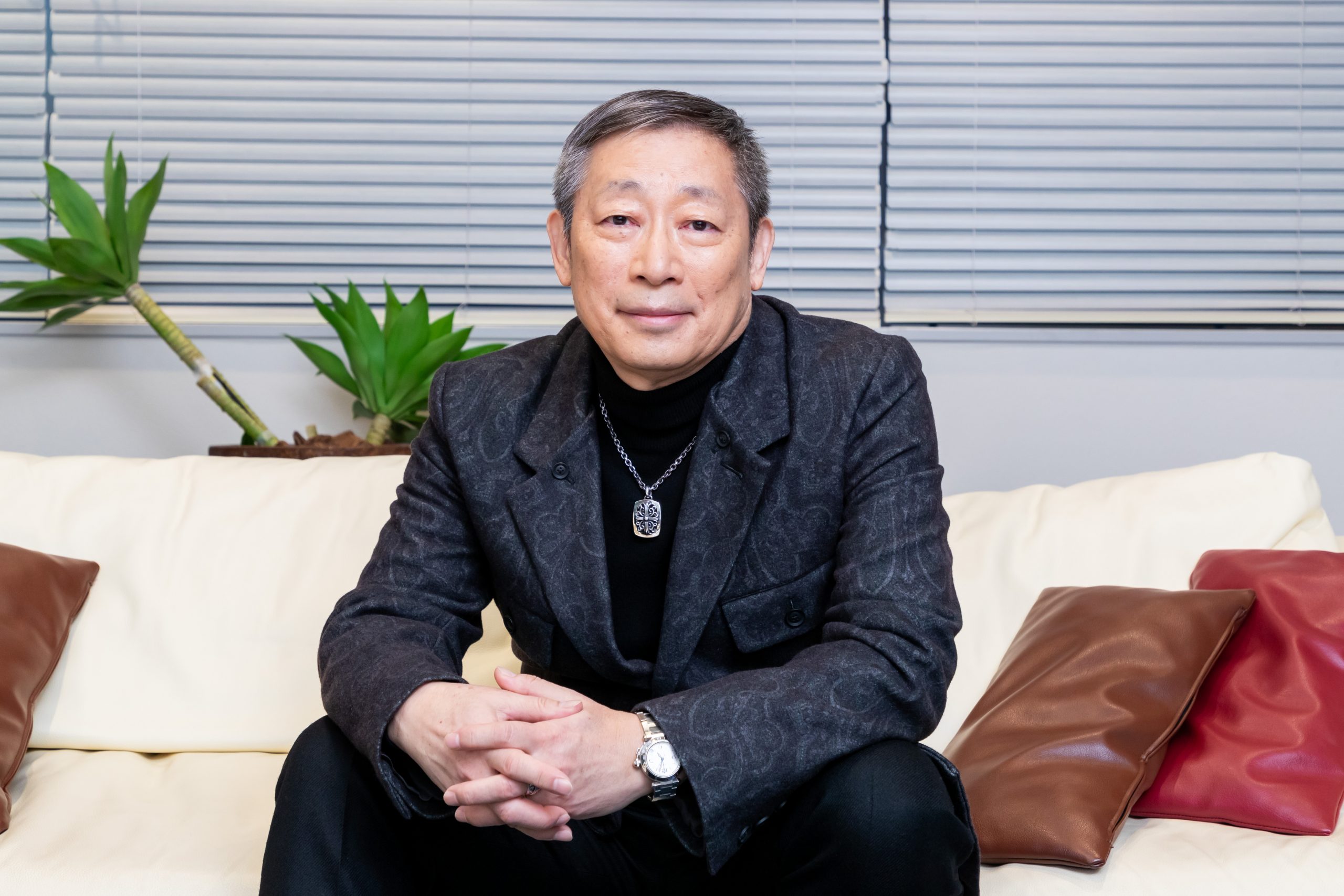日本語をロックのビートに乗せたいという強い思い
――森さんは、高校時代からバンド活動を始め、大学に入ってからは四人囃子(1971年結成)という伝説のプログレッシブ・ロックのバンドにゲスト・ヴォーカルで参加。表現の幅を広げていく。
シンガー&ソングライターとしてのデビューを夢見て、トリオ・レコードのShow Boatというレーベルに、曲を作っては日参していました。
あるとき「詩を書いてみない?」とディレクターから言われ、渡辺音楽出版を紹介されたのです。そのとき、ザ・ドリフターズに作詞作曲した『ドリフの英語塾』が松竹映画『正義だ!味方だ!全員集合!!』の劇中で使われました。
作詞家としてのデビューは22歳のとき。1976年、ザ・ドリフターズの『ドリフのバイのバイのバイ』という作品です。ちょうど志村けんさんが加入したころの作品です。渡辺プロダクションの創業者である渡辺晋社長の御自宅で、ドリフのメンバーに会う機会をいただきました。
当時の僕といえば、長髪で、ヒールが10センチくらいあるロンドンブーツを履いていている、ロックバカですよ。そんな若者が、お手伝いさんが3 人ぐらいいるような大邸宅に行き、そこにいたメンバーの皆さんはプロとして厳しい顔をしているのですから、緊張したんでしょうね。辞去するときに、僕は貧血を起こして失神してしまったんです。
そのとき、渡辺社長から「雪之丞は倒れるまで詞を書く男だ」と覚えていただき(笑)、キャンディーズ、あいざき進也さんなどの楽曲の作詞につながっていきました。
――なにが幸いするか、人生はわからない。そもそも、森さんはミュージシャンを目指していたが、戦後日本のエンタメ界を築いた渡辺晋さんに認められ、作詞家として世に出る。1977年に森さん作詞の『アル・パシーノ+アラン・ドロンより<あなた』の歌手・榊原郁恵さんがレコード大賞新人賞を受賞。作詞家・森雪之丞の名が、広く知られるようになっていく。
1980年代に入ってからは、シブがき隊ほかアイドルへの作品提供をするようになりました。彼らのデビューシングル『NAINAI 16』や1982年にレコード大賞新人賞を獲得した『100%…SOかもね』は、アイドル用語辞典に“載っていない”言葉をあえて使いました。「ジタバタするなよ」とか「世紀末が来るぜ」などは、当時は斬新だったんだと思います。
書いていても楽しかったし、攻めてもいいんだとも気付きました。音符に言葉を当てるときに、「ぞっこん」や「べっぴん」などの言葉を入れると英語に近づくなど、自分の中でも研究したのも、この頃です。
――森さんの歌詞は軽妙で洒脱だ。英語のように聞こえる日本語の歌詞や、インパクトがある言葉で、多くの人の心を魅了する。
僕はロックが大好きで曲をロックっぽく仕上げたいんですが、「日本語はロックに乗らない」と言われてきたんです。
それならやってみようじゃないかと、日本語を歯切れよくビートに乗せるために、いろんな試みをしてきました。例えば、“~でしょう”を英語の“SHOW”に置き換えたり、韻の踏み方でスピード感を出したり、そのほか、いろんなことをやっていましたね。
その大革命を起こしたのは、サザンオールスターズの桑田佳祐さん。1978年のデビューシングル『勝手にシンドバッド』は、日本語がロックのビートに乗っており、しかも強く響いてくる。彼は、日本語がロックになると証明した最初のアーティストです。あれ以降、日本の歌詞は大きく変わっていきました。
――森さんは80年代後半から、アニメソングを手がけるようになる。
アイドル曲と並行し、『キン肉マン』『Gu-Guガンモ』『キテレツ大百科』『悪魔くん』などのオープニング曲やエンディング曲の作詞をしました。アニメは毎週流れますから、多くの子どもたちが僕の詩を歌ってくれた。仕事で会う方から「子供の頃に聞いていました」と聞くと、やはりうれしいものです。
今回、詩集を出したのも、アーティストはもちろん、メロディーやビートもない中で、僕の言葉がどのくらい広がっていくかを試したかったこともあります。詩というのは、なかなかとっつきにくいジャンルで、かつては書店の詩集コーナーに行き、本のページを開かなければ接することはできませんでした。でも今はSNSを通じて詩に触れることができ、拡散もしていきます。
『感情の配線』も、僕自身によるトークとリーディングイベントを行いました。アーティストに言葉を託さずに、自分の言葉をどのように表現していくか……これは、未だに正解はなく、模索し続けるのかもしれませんね。
森さんは、作詞家としてだけでなく、自らミュージシャンとして、ミュージカル作家、訳詞家としても活躍している。次回では、「作詞家以外の顔」について、紹介していく。
●森雪之丞さんの最新詩集

『感情の配線』2750円 開発社/諧謔とエロティックさ、光と闇が共存する自選詩集。図形詩、戯曲詩なども収録。メロディー、ビート、そしてアーティストがない状態での詩の世界を堪能できる。
構成/前川亜紀 撮影/乾 晋也