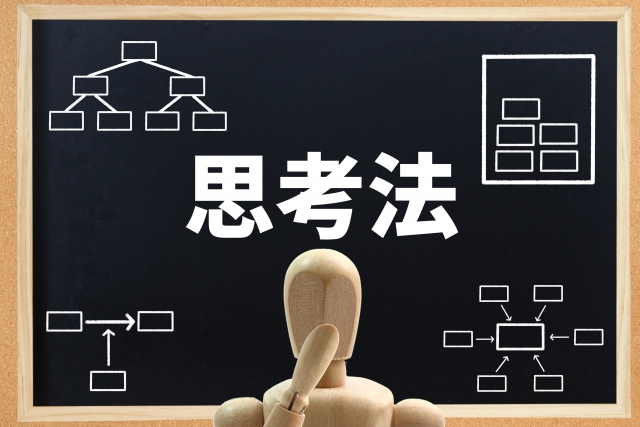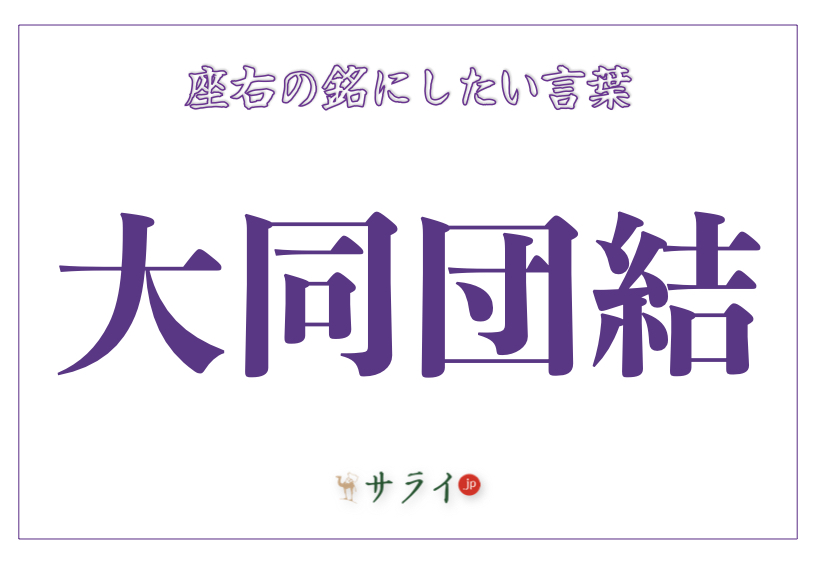マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回はチームマネジメントについての考察です。
はじめに
チームを運営していくうえで「仲の良いチーム」を理想に掲げて進んでいった結果、仲は良いがチームは勝てない、チームの目標を達成できていない、一人一人が成長できていないなど、成果が出ないのに人間関係は良好という状態を「仲良しごっこ」と表現したとすると、この「仲良しごっこ」から抜け出せずに悩んでいるリーダーの方もいるのではないでしょうか?
経営者や管理職の方から「チームの皆の仲が良ければ、協力して助け合いながらチームとしても個人としても上手くいくと考えていたのに成果が上がらない、どうすればいいのか?」と相談をお受けすることが増えてきました。
今回は、なぜあなたのチームは「仲良しごっこ」から抜け出せないのか? その打開策についてお伝えします。
チームの目的
チームの運営目的が、仲が良く楽しく過ごしていくことであれば、「仲良しごっこ」でも問題ありませんが、チームが会社組織となった場合、会社はお客様にサービスを提供し、対価を頂いて、従業員に給与を支払う事を継続していかなければいけません。会社組織の目的は、どうやって社会に貢献して有益性を発揮するか、そして有益性の対価として売上・利益をどうやって向上させるかが重要になってきます。
お客様のニーズに応え、競合他社に選ばれる会社になっていくためには、会社組織もそこで働く従業員の方も成長をしていかなければいけません。お客様からのクレームをいただくことがあれば、それを改善し同じことが起きないような再発防止にも取り組まなければいけません。そのためには、必要なルールを整備してルールを守れるように維持管理していく必要があるのです。
チームの存在意義
人は多かれ少なかれ存在意義を欲する習性があります。仲が悪いよりは仲の良い方が良いし、人からも好かれたい、そう思って当然です。ただし、リーダーという立場になった時に存在意義の獲得先が市場やお客様ではなく、従業員に向いてしまった時、会社はどうなるでしょうか? この仕事を受けると社員が嫌がるから受けるのは止めよう、と従業員の顔色を伺いながら、嫌われたくない、自分と従業員の仲が悪くなるかもしれない、と考えると会社は目的を見失い、市場へ有益性を発揮できなくなります。
ルールを逸脱するようなお客様からの依頼や従業員の労働時間や労働環境における健康被害が出るような状況では依頼を受けない等の基準は必要ですが、従業員に嫌われるかもしれない、仲良い状態が崩れてしまうかもしれないという前提で組織運営をしていては成果が出ないのは当然です。リーダーは市場から存在意義を獲得するために組織運営をしなければいけません。従業員から存在意義を獲得しようとする方向性は間違っています。会社が市場から評価されていることを従業員全体が実感し、会社に貢献した従業員に適正な報酬をきちんと支払う、そして当たり前ですがきちんと法律を順守した運営をしていれば、結果的に従業員からの存在意義は獲得できるものです。方向性を間違えないようにしましょう。
仲が良くないと組織は上手くいかないのか?
仲が良くないと組織が上手くいかないのではないか? 成果がでないのではないか? と心配するリーダーの方もいらっしゃいます。もちろん、仲が悪いよりは良い方がいいですが、仲が良いから成果が出るわけでもありません。
組織が存続する条件とは以下2つになります。
・外部に有益性を発揮している
・同じ目的を共有している
外部に有益性を発揮している状態とは前述したように、会社が有益性を発揮した対価として、必要な売上利益が得られている状態です。これがなければ組織は存続していきません。また、同じ目的を共有しているとは、ただ単に会社の理念や目標を従業員が覚えているという事ではありません。会社の理念を実現するために必要なルールがあり、そのルールを従業員が守り、理念を実現するために必要な各個人の役割を認識して行動している状態です。
仲の良い組織を目指していこうとリーダーが進めていくと、自分の役割を果たせないのは仲が良くない状態だからと言い訳を作ってしまう危険性があります。人間なので、相性の良し悪し、そして時には仲の良かった人と仲が悪くなることもあります。あの人とは仲が悪いから仕事で必要なコミュニケーションを取らない、といった考えで従業員に仕事をさせるのではなく、仲の良い悪いではなく、会社の目的達成や自分の役割を果たすために、仲が良い悪い関係なく必要なコミュニケーションをとってくださいと言わなければいけません。そのためには、ルールを設定し、役割・責任を明確にして管理する必要があります。
管理する側が管理される側と仲良くなりすぎると、ルールを違反しても注意できず、目標達成できなくても努力をせずに許されるような環境となってしまうため、「仲良しごっこ」の組織ではいけないのです。リーダーは部下と友達のように接して仲良くなるのではなく、一定の距離を保ってチームと部下の成長の為に管理をしなければいけません。
ただし、仲を良くする目的ではありませんが、チームの生産性を維持するために、従業員間で悪口を言い合っているのであればルールを設定して注意する、誰かに負荷が偏ってバランスが悪ければ仕事の役割を再設定するなどの対応は必要になります。
つまり、リーダーはチームの仲の良さを気にするのではなく、以下の点が出来ているかをチェックしていかなければいけません。
・チームの目的を部下に正しく認識させられているか
・一定の距離感を保っているか
・目標を設定して管理・評価できているか
・仲良くするためではなく、仕事を円滑に進めるためのルールを設定して守れるように指摘をしているか
そして仲が良い時も悪い時もリーダーとしてやるべきマネジメントに徹していれば外部に有益性を発揮できます。そうなった時、従業員同士で本当の信頼関係や絆が生まれます。社員同士の話のなかで、「プライベートでは仲良くなるタイプではなかったけど、今はお互いが役割を果たすことで自然と信頼関係が生まれてお互いを尊重し合っているんです」という言葉が出てくるようにマネジメントをしていきましょう。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/