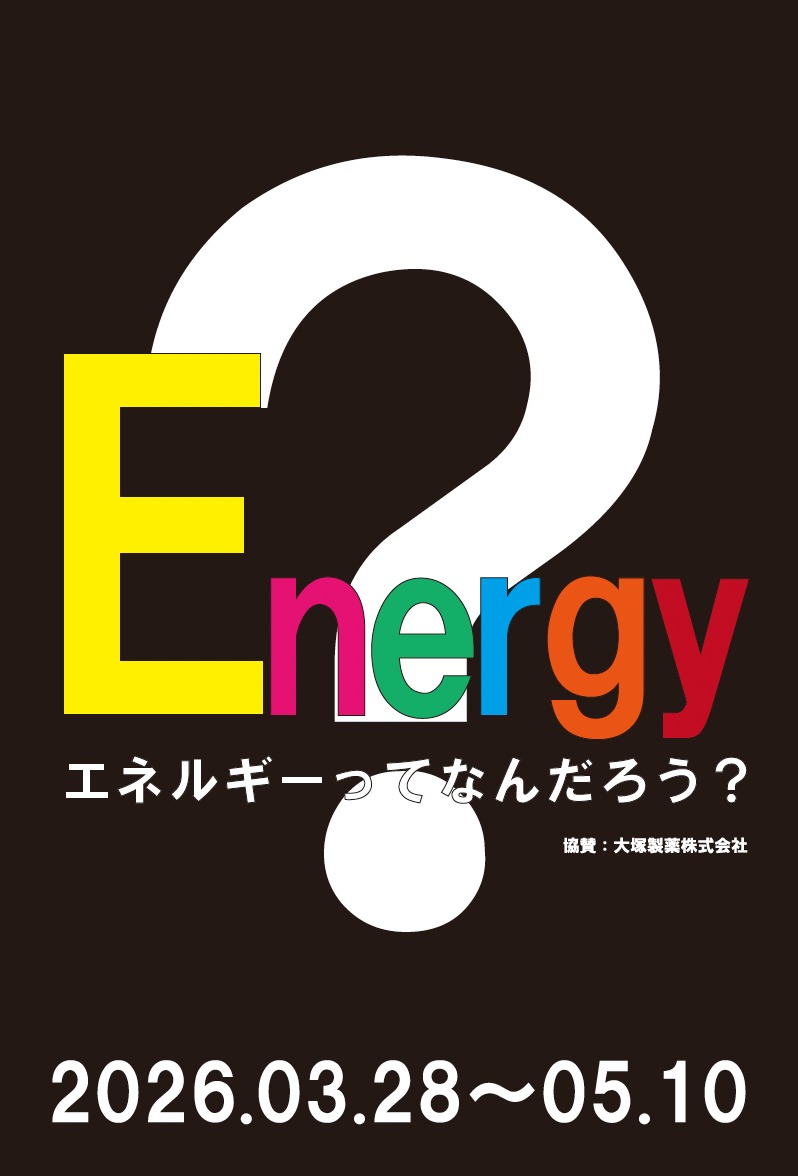マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、社員のポテンシャルを最大限に引き出し、社員を急成長させるためのマネジメントについて考察します。
はじめに
企業が成長していくうえで、最も重要なのは「人材」です。その中でも「急成長する社員」が一人でも多く現れることは、組織全体の成果に直結します。
しかし、なぜ同じ環境にいても、急成長する人と、なかなか伸びない人が生まれるのでしょうか? その差は、才能の違いではなく、マネジメントの仕組みにあることが少なくありません。
この記事では、社員のポテンシャルを最大限に引き出し、短期間で大きく成長させるマネジメントの本質について解説します。
「あいまいさ」が成長を止める
成長できない社員に共通して見られるのが、「自分が何を求められているのかが分かっていない」という状態です。「頑張ってはいるけれど、正解が分からない」「成果を出しているつもりなのに評価されない」――そんな不透明さがモチベーションを下げ、行動力を奪ってしまいます。
この原因は、上司と部下の間に生まれる「認識のズレ」にあります。上司は「自分が部下の頃にはこれぐらいは出来ていたので、部下も自分で考えることができる」と思っていても、部下は「何をすればいいか分からない、指示されないと動けない」と受け取ってしまうことがあります。このズレを放置すると、どれだけポテンシャルがある人材でも成長は鈍化します。
まず必要なのは、「役割と結果」の明確化です。どこまでが自分の責任で、どこからが他人の領域なのか。何を達成すれば評価されるのか。そのルール(評価制度)がクリアであればあるほど、人は主体的に行動できるようになります。
「評価の基準」があるかどうかで行動が変わる
人は評価される方向に行動します。しかし、評価の基準が不明確だったり、上司の主観や気分によってブレていたりすると、社員は「上司に気に入られること」に集中してしまい、本質的な成長を目指さなくなります。
逆に、「どんな行動や結果が評価に直結するのか」が明確であれば、社員はその基準に向かって自ら行動するようになります。「訪問件数が月◯件以上でA評価」「プロジェクト完了までのリードタイムが◯日以内で高評価」といった具合に、具体的な数値や行動基準が設けられていれば、行動の質もスピードも劇的に変わります。
成長する人材は、基準を理解し、自らの行動を調整できる人です。そのための「見える評価軸」を用意することが、マネジメント側の重要な役割です。
指導のしすぎが成長を妨げる
多くの上司が「部下が困っていそうだから」「間違わないように」と先回りして指示を出したり、細かく教えすぎてしまいがちです。しかし、それが成長を妨げているケースは非常に多いです。
このような上司の場合、部下側の思考としては「上司の言った通り行動したのに結果が出なかった」「何か困ったことがあっても考えなくても上司が教えに来てくれる」のように、自分事化せずに他者の責任範囲と考えてしまいます。
本来、部下は自分で考え、失敗し、改善していく中で成長します。上司の役割は「指示」や「命令」ではなく、「責任範囲を明確にすること」や「達成基準を示すこと」です。例えば、「このプロジェクトの最終目標はここ。どう進めるかは任せる」と伝え、部下の自律性を育むことが重要です。
そうすることで、部下は「どうすればこの目標を達成できるか」と思考を始め、実行し、失敗から学ぶようになります。「考えることを奪わない」。それが、自律的に動ける人材を育てるための第一歩です。
「感情」より「構造」で動かす
マネジメントにおいては、つい感情が入りがちです。「可愛がっていた部下だから高評価にしたい」「あの子は頑張っているから多めに見たい」――そんな感情的な判断が、組織全体の成長を妨げてしまいます。
重要なのは、一貫した構造とルールによって組織を運営することです。どんなに頑張っていても、ルールを守らなければ指摘する。成果が出ていれば、たとえ性格に難があっても正当に評価する。そういった「感情に左右されない姿勢」が、部下からの信頼を生み出します。
上司がブレずに判断し続けることで、部下も「この組織では平等に見てもらえる」と感じ、自らの行動に責任を持つようになるのです。
成長する人材は「責任」を引き受けている
急成長する社員は、例外なく「自分の仕事に責任を持っている」人です。そして、その責任を自分で認識できている人は、他人に指示されなくても、主体的に動きます。
逆に、「何をすればいいか分からない」「やっても評価されるか分からない」という状態では、責任を持とうにも持てません。
だからこそ、マネジメント側が果たすべき役割は、「責任の所在をはっきりさせること」です。「あなたの成果はここまでが範囲です」「この結果に対して、あなたが責任を持ちます」と明確に伝えることで、人はようやく主体的になれるものなのです。
まとめ:人は「明確さ」によって成長する
人材育成で最も重要なのは、「何をすれば成長できるのか」を明確にすることです。ルールがあり、基準があり、責任範囲が明確である組織には、自然と自律型の人材が育ち、結果的に急成長する社員が次々と生まれます。
優しさや熱意だけでは人は育ちません。むしろ、平等で明確なルールと責任の上にこそ、人は伸びるのです。感情に頼らず、構造で人を動かすマネジメント。それこそが、これからの組織に求められる新しい人材育成のあり方だと言えます。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/