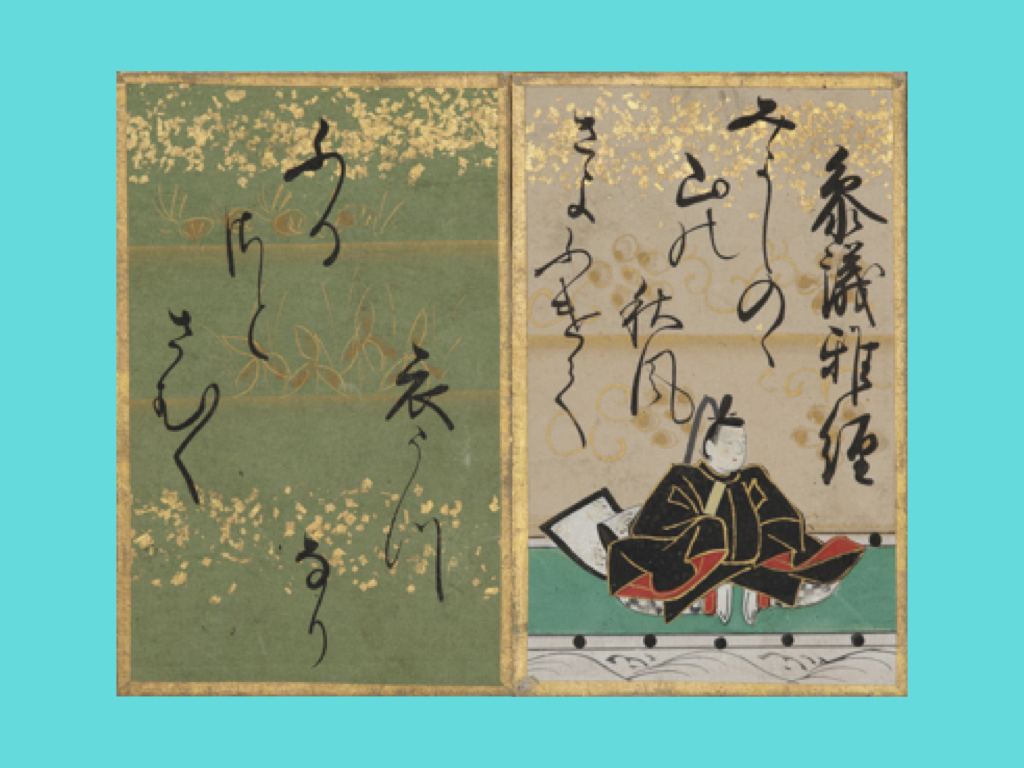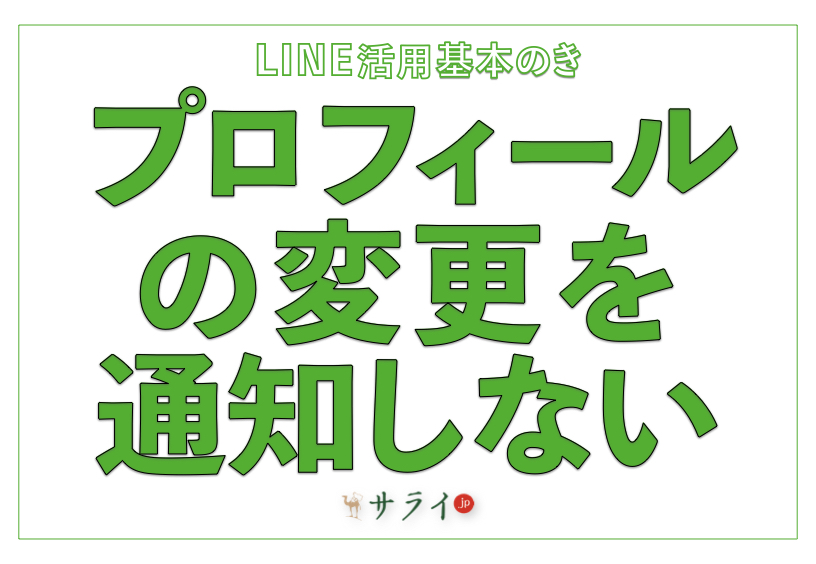マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
会社組織において、評価される人とはどんな特徴を持っているのでしょうか。今回は子どものおつかいを例に考察していきます。
はじめに
「晩御飯のためにトマトを買ってきて」と親から頼まれた子供が、自分はトマトではなくお肉が食べたいと思ってお肉を買って帰った場合、親はどのように感じるでしょうか。おそらく「なぜ言われた通りにしなかったのか」と叱られることでしょう。
この例は一見、微笑ましい日常の一場面に見えますが、実はビジネスの現場でも同じような構図が日々繰り返されています。つまり、上司が部下に対して「トマト(=成果物や対応)」を求めているのに対して、部下は「お肉(=自分が良かれと思うもの)」を持ち帰ってしまう――このような“ズレ”が評価に直結する大きな問題となっているのです。
評価とは「ズレがないこと」の証明
ビジネスにおいて「評価される人」とは、一言でいえば「求められた成果を正確に出せる人」です。決して「頑張っている人」や「良い人」ではありません。識学(意識構造学)では、評価を「結果に対する事実としての判断」と捉えます。つまり、「どれだけ過程で努力したか」ではなく、「最終的な結果が指示と一致しているか」が評価の全てです。
先ほどの子供の例でいえば、「お肉の方が豪華で、家族も喜ぶだろう」と思っていても、親が求めていたのは「トマト」だったわけです。本人の主観や善意よりも、「依頼された通りに動けるかどうか」が問われているのです。
これは、会社組織でも同様です。上司が「今期はAの目標を達成してほしい」と言っているにもかかわらず、部下が「それよりBの方が会社のためになる」と勝手に判断し、Bに注力してAが未達成になれば、どれだけBで成果を上げたとしても評価は下がります。
「ズレ」が起こる理由とその弊害
では、なぜこのようなズレが生まれるのでしょうか。その主な原因は次の3点に集約されます。
1.目的と手段の混同
部下が手段(やり方)を優先し、目的(上司が求めている結果)を正確に把握していない。
2.コミュニケーションの不足
上司の指示が曖昧であったり、部下が確認を怠ったりして、認識のすり合わせができていない。
3.自己評価と他者評価の乖離
「自分はうまくやっている」という思い込みがあり、他者の評価基準を見誤っている。
これらのズレが重なることで、部下は「頑張っているのに評価されない」という不満を抱き、上司は「指示通りに動かない」と不信感を持つという悪循環が生まれます。
評価される人は“上司の視点”を持っている
では、評価される人はどのように考え、行動しているのでしょうか。識学の観点から言えば、その最大の特徴は「上司の視点を持つ」ことにあります。
つまり、上司の立場になって「何が求められているか」を正確に理解し、それに応えることに徹するという姿勢です。そのためには、次の3点が重要です。
1. 指示は“解釈”せずに“確認”する
評価される人は、指示を勝手に解釈することなく、曖昧な点があれば必ず確認します。「トマトを買ってきて」と言われたときに、「どの種類のトマトですか? いくつ必要ですか?」と聞ける人です。これにより、成果物のズレが最小限になります。
2.成果の定義を言語化して握る
「良い結果を出します」と曖昧に言うのではなく、「何を、いつまでに、どの程度達成すれば成果と見なされるか」を上司とすり合わせます。これができていないと、仮に本人が120点のつもりで提出したとしても、上司の期待値が150点だった場合にはマイナス評価となります。
3.「今やっていることはトマトか?」を常に意識する
業務の中で自分が取り組んでいることが、果たして「上司が求めているトマト」なのか、それとも「自分が選んだお肉」なのかを日々自問自答できるかどうかが、継続的に評価されるかどうかの分岐点になります。
評価されない人の特徴は「自分軸」
一方で、評価されにくい人の多くは、自分の価値観や美意識で物事を判断しがちです。「自分はこうした方が良いと思った」「このやり方の方が効率的だと思った」――その判断が、指示者である上司の意図とずれていれば、どれだけ成果を出したつもりでも評価にはつながりません。
これは、「結果を出していない人」が問題なのではなく、「結果の定義を上司と揃えられない人」が評価されない、という構図です。つまり、個人の主観ではなく、組織の目的と評価軸にどれだけ正確に合わせられるかが、すべてなのです。
組織で信頼される人とは
組織における信頼とは、「この人に頼めば、期待した結果が返ってくる」という再現性の信頼です。評価される人とは、再現性が高く、ブレなく、指示された通りの結果を出し続ける人です。
裏を返せば、評価される人になるために必要なのは「能力」や「経験」ではなく、「ズレのない行動が取れるかどうか」に尽きます。識学が強調するように、ビジネスの評価とは感情や人柄によって決まるものではなく、“構造”と“事実”によって決まるのです。
まとめ
「子供のおつかい」というシンプルな事例にこそ、組織で評価されるための本質が詰まっています。「自分がやりたいこと」ではなく、「相手が求めていること」に全力で応える――これこそが、ズレのない行動を生み、結果として高い評価へとつながるのです。
あなたがもし「もっと評価されたい」「信頼される存在になりたい」と考えるのであれば、今日からでも「これはトマトか?」と自問自答する習慣を始めてみてはいかがでしょうか。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/