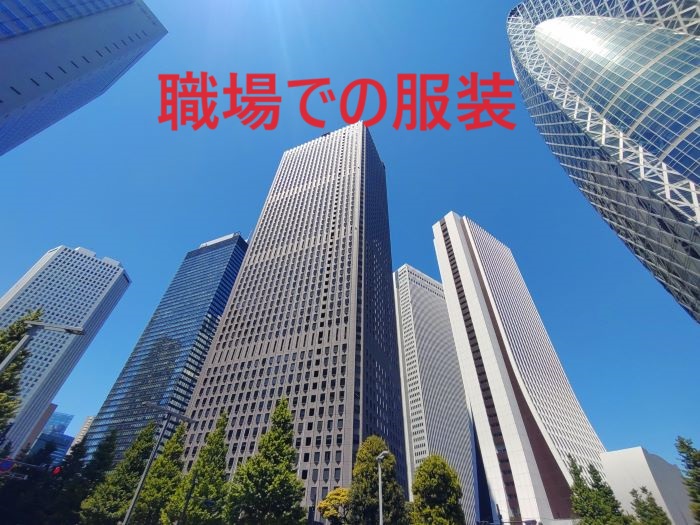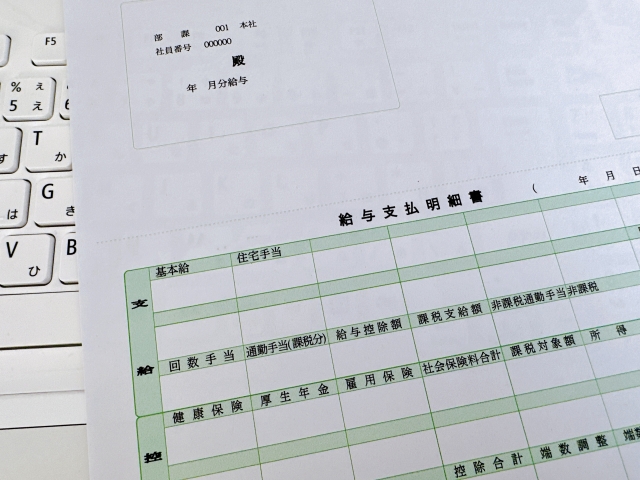マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
シルバー人材とは、一般的に定年退職後も就業意欲のある高齢者を指します。 豊富な経験や知識を活かして、社会参加や地域貢献に意欲的な高齢者が多く、企業や地域社会にとって貴重な人材資源となっており、日本では、60歳以上の高齢者をシルバー人材と呼ぶことが一般的です。
高齢者の就業率は年々上昇しており、企業は高齢者の雇用に対してより積極的に対応していく必要性が高まってきている中で、シルバー人材の活用におけるマネジメントのコツについてまとめます。
シルバー人材の活用の重要性と注意点
内閣府の「令和6年版 高齢社会白書」によると、令和5年には、労働力人口の13.4%を65歳以上の方が占めており、65歳以上の就業者数は20年連続で増加しています。60歳後半でも男性の6割以上、女性の4割以上が就業している現状があります。
※内閣府「令和6年版高齢者白書」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/index.html
労働力不足の解消と高齢者の就業意欲の高さが要因と考えられますが、企業側には、シルバー人材の活用における課題も存在します。例えば、高齢者の体力的な衰えへの配慮、ITスキル不足への対応、賃金体系の見直しなどが挙げられます。これらの課題を解決し、シルバー人材が能力を最大限に発揮できる環境を整備することが、企業にとって重要となっています。
さらには、シルバー人材の活用において、組織マネジメントの観点からの注意点については、以下の2点が挙げられます。
・評価制度の明確化
・評価者のマネジメント力向上
今回はこの2点について詳しく説明します。
注意点1:評価制度の明確化
評価制度における重要なポイントは以下の2点です。
1.目標設定が明確であること
2.公平な設定になっていること
1点目の「目標設定が明確であること」については、評価者と被評価者で認識のズレがない目標を設定していくことが重要です。定量化出来る目標は分かりやすいですが、定量化が難しい目標についても、完了状態が誰が見ても明らかになるような目標を設定していくようにしてください。
特にシルバー人材の活用においては、評価者と被評価者で経験量に大きな差がある場合があります。経験の差によって価値観が異なることは仕方がないことであり、それによってお互いの「当たり前」が異なる可能性があることを踏まえて、いかに認識のズレがない目標にしていくかが重要です。
2点目の「公平な設定になっていること」については、目標設定の難易度は同じ給与水準(等級)の方は、異なる業務を行っていたとしても、同等の難易度である必要がある点に注意が必要です。
シルバー人材の雇用においては、定年後の再雇用における非正規雇用者、定年を引き上げた上での正社員雇用の継続など、様々な雇用形態でシルバー人材を活用していくことが考えられます。
一方で、シルバー人材の中でも経験豊富な方に業務が偏ってしまうことでの公平感の低下などにも注意すべきです。それぞれの給与水準にあった目標設定がなされているか、会社内で評価者の目標設定の難易度チェックを行うことも必要です。
注意点2:評価者のマネジメント力向上
会社全体で評価者の目標設定の難易度チェックを行うことに言及しましたが、シルバー人材の活用において、評価者に求められる役割の重要性は評価目標の設定だけではありません。
シルバー人材の活用においては、評価者にとっては年上の部下を評価するという環境が当たり前となります。「年功序列」という言葉があまり使われなくなって久しく、年上の部下がいる、年下の上司の下で働いている、ということは珍しくなくなりました。しかしながら、年上の部下へのマネジメントに悩まれる方は未だに多くいらっしゃるのではないでしょうか?
つまり、シルバー人材の活用において、マネジメントの難易度が高いことを認識し、正しいマネジメントの型でマネジメントしていくことが重要です。
今回はポイントを2点にまとめます。
1.上司部下の立ち位置を明確にする
2.任せきりにしない
上司部下の立ち位置を明確にする
年上の部下を持つ上司の悩みの根幹は、上司部下の関係性を構築出来ていないことに尽きます。会社組織内にかかわらず、人はだれしも普段のコミュニケーションの中で無意識に、上下の位置関係が出来上がっています。
例えば、ある場所に旅行に行きたいと思っている方が、その場所に何度も訪れたことがある人にいろいろなことを教わっていると、教える立場と教わる立場という位置関係が無意識下に出来上がっているはずです。
年上年下という関係においても、大抵の場合、年上の方の方が多くの経験を積んでいることから、年上の方が教える立場、年下の方が聞く立場となりやすいです。そういった意味で、これまでの多くのコミュニケーション時の経験から、人は意識的に年齢によって上下を決めてしまうことがあります。
会社組織には組織図に応じた役割によって上下の位置関係が決まっているはずですが、このような意識のもと、「年上の部下に指示しにくい」「年上の部下を評価しにくい」といった意識が生まれてきています。
シルバー人材の活用という点においては、さらに年齢差がある場合も多く、自分が新入社員の時の最初の上司としてお世話になった方を部下に迎える、などということも起きているのではないでしょうか。
年長者を敬わなくてもよい、というわけではなく、あくまで組織で決められた役割の中で正しい、上司部下の関係性を構築していくことが重要と考えています。
任せきりにしない
上記のように、経験豊富な部下をもつ上司の立場で起こる誤解として、「この方には特にマネジメントは不要」と判断し、“任せきり”されることがあります。
もちろん、マネジメントにおいて、目標設定さえすれば、勝手に目標達成に向かって取り組めて、さらにプラスαの成果まで出せる人もいるはずです。だからといって、管理をしなくて良いとしてしまったら、どうなるでしょうか?
求めている成果以上の成果を出し続けてくれる場合もあるかもしれません。しかしながら、こちらが求めている成果と別の方向に進んでしまっていた場合には修正しなければなりません。
“任せきり”が続いていると、これまでは何も言われてこなかったにも関わらず、なぜ今回だけは口出しされなければならないのか、といった認識のズレが起きることで、修正に時間を要するなどの要因になりかねません。
シルバー人材の活用に限った話ではないですが、経験豊富で能力が高い部下であるときでも、管理は必要と考えることが重要です。
また、能力可否に関わらず、シルバー人材の活用方法がイメージ出来ずに“任せきり“ということも起こり得るので、評価目標の設定に留まらず、目標管理のための定期的な面談が正しく行われているかも会社全体でチェックしていく仕組みも必要になってきます。
まとめ
シルバー人材の活用は、企業にとって労働力不足の解消だけでなく、多様な経験や知識を持つ人材の活用という点でもメリットをもたらします。
高齢者が活躍できる社会の実現に向けて、企業の積極的な取り組みが不可欠であるからこそ、今回お伝えしたようなポイントをシルバー人材の活用のためのマネジメントのコツとして活用いただけますと幸いです。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/