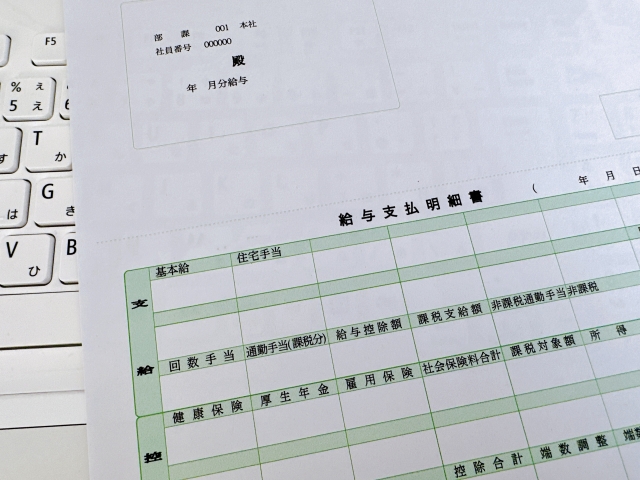マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
昨今の会社組織において退職理由のトップは人間関係です。リーダーとして、部下との人間関係を円滑にして、退職のない組織にしたいと思うのは当然のことです。ただし、会社という組織は目的を持って集まっている人間の集合体であり、ただ表面的に仲が良い「仲良しグループ」では、目的に対して機能しません。
この記事では、「本当に優しい上司」という切り口で、正しい上司像について掘り下げていきます。「総論賛成、各論受入れがたし」とならないように、具体的な注意点や組織という観点でも解説いたします。
「本当に優しい上司」とは?
「本当に優しい上司」とは? まずはここから認識を合わせましょう。
「本当に」がついていますので、「表面的に」とは正反対を意図します。そもそも、リーダーは部下より責任が大きいという役割上、より高い視座を持つ必要があります。視座が高くなると変わるのは「時間軸」です。目先の結果だけでなく、より未来に対し責任を持つということになります。
つまり、「部下の未来の成功(成長)にコミットしている」のが上司という存在です。未来の成功(成長)から逆算すると、未来の目標が高いほど「今が大変」になるのは言うまでもありません。業務の基準値が上がるためです。
よって、部下の未来の成功を獲得するために、部下が辛いと感じたとしても意図して高い基準を求め続けるのが「本当に優しい上司」と言えます。決して、表層の言動の優しさ、厳しさを論じているのではありません。
部下から、冷たく見える(厳しい)言動と受け取られたとしても、部下の未来の成功(成長)にコミットし、実現のために部下の現在のステージを見極め、高い基準値を求め続けるマネジメントを行っていくのが、「本当に優しい上司」ということになります。
忘れてはならない前提とは?
「前述のような識学的な切り口は本で読んだことがある」―そう感じる方もいらっしゃるかもしれませんので、具体の話をしていきます。まず忘れてはならない「前提」を明確にします。
部下の未来の成功(成長)のためには、当然ですが部下に応じた課題設定が重要です。見極めです。部下が知識をインプットする段階なのか、実践しトレーニングする段階なのか等、現在のステージを見極めてから最適な注力課題を設定します。
加えて、関わり方の粒度をどのくらい細かくするかという部下の尺度(知識と経験)を見極めた匙加減も力量が問われます。自分で進めていけるメンバーにマイクロマネジメントをしても、未熟なメンバーに全てを任せても、相互のひずみは発生し続けるでしょう。
また、仕事の目標は最終的に上司側に決める役割がありますが、部下のキャリア(今後どのようになっていきたいか?)は、部下が自らの責任で決めていくものです。
ですので、上司が一方的に「これは部下のためだ!」と思っていても、部下側と合致するかはわかりません。上司側の独りよがりは認識のズレを生む可能性があり、当然ながら部下との擦り合わせが必要になります。つまり、部下側の立場で「将来像」を合意出来ていないと、空回りする危険性があります。
部下のことを何も理解していない状態で、都合の良い時だけ「君の未来を考えている」というオーラを出しても、部下には正しく伝わらないでしょう。
部下に対する一定の理解や意図や前提説明があった上で、効果的なマネジメントが成り立つ関係であるということは識学以前の前提として押さえてください。そうすれば、最初は冷たく見えても、成長した暁には「上司のお陰」という信頼関係につながっていきます。
部下を迷わせないためには?
まず、全体像を明確にすることが必要です。
(1)最終的に求められている結果は何か?
(2)そのために守るべきルール(自分で采配可能な範囲と、会社で決まっている範囲など)は何か?
(3)上司の役割と部下の役割はそれぞれどうなっているか?
まずはこれらを明確にすることで、メンバーが一定の同一環境の中にて、同一基準で日々行動していくことが出来ます。他者との比較から学ぶことも出来ます。ゲームルールをシンプルにすることでメンバー同士競い合う競争環境をつくることもできます。
また上記(1)(2)については、前述のように部下の尺度(知識や経験)で力点を置く箇所が変わります。 ルールに関しても部下が迷わず行動出来るように、上司は試行錯誤して精度を高めていくことが重要です。
組織として「本当に優しい上司」を機能させるには?
最後に、上司個人の取り組みだけでなく組織全体で取り組むことにも言及します。
上司に対して「部下の成長にコミットしろ」というのは簡単ですが、そのままでは組織として上司に丸投げしていると同義になってしまいます。「本当に優しい上司」を会社の中で機能させるには、組織としてどうすればよいでしょうか? 以下の三つの観点を押さえることが大切です。
評価との連動
上司が自分の仕事だけに集中した時の方が、結果的に評価が上がるという環境であれば、上司も自分のことに意識が向いてしまうのは明らかです。上司も人間です。
部下を成長させることが自分にも必要であるという状況をつくるためには、評価指標の一つとして部下の成長を組み込むことです。例えば、通常の業績評価に加え、部下が何人以上退職すると何かしらのペナルティが発生するなどです。当然、上司には、部下の成長をマネジメントする必要性が発生します。
経営や人事から上司へのサポート体制
「部下の成長は上司責任なのであとはよろしく」という押し付け型組織では上司が疲弊するのは明らかです。例えば、部下の現在のデータ等を確認するために、すべてのことを上司が管理しろというのはただの丸投げです。
経営(人事)が上司のマネジメントに役に立つ根拠となるようなデータを蓄積するなど、上司に武器・材料を与えることが出来る環境を経営層や人事が環境整備すると、より再現性の向上に繋がります。
部下側への成長プロセスの提示
また、部下側にも一定の理解をさせることが効果的です。今後どのように成長してもらいたいか? という成長の道筋や、部下自身のキャリアステップの選択肢などが明確に描ける材料があるほど、「未来にこうなりたいから、今の業務に集中する」という部下側の理解を生みやすくなります。
まとめ
識学の観点から「本当に優しい上司」として機能させるポイントは三つです。
(1)「本当に優しい上司」=部下の未来の成長にコミットする上司。
(2)前提として、部下個人を見極めた上での課題やルールの設定、部下との継続的なキャリアステップを確認し擦り合わせていく関わりが重要。
(3)「部下の未来の成長」という観点では、会社は上司だけに丸投げするのではなく、組織共通のゴールとして捉え、組織・上司・部下の三位一体で継続していく運用体制を構築することが再現性を生み出す。
「本当に優しい上司」とは、上司のマインドや表層の言動だけの話ではなく、「部下の未来の成長にコミットする」役割と責任を担う人物になります。また、上司だけでなく会社としての取り組みが継続性、再現性を生み出します。表現を変えれば、「本当に優しい会社」が最強という結論になります。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/