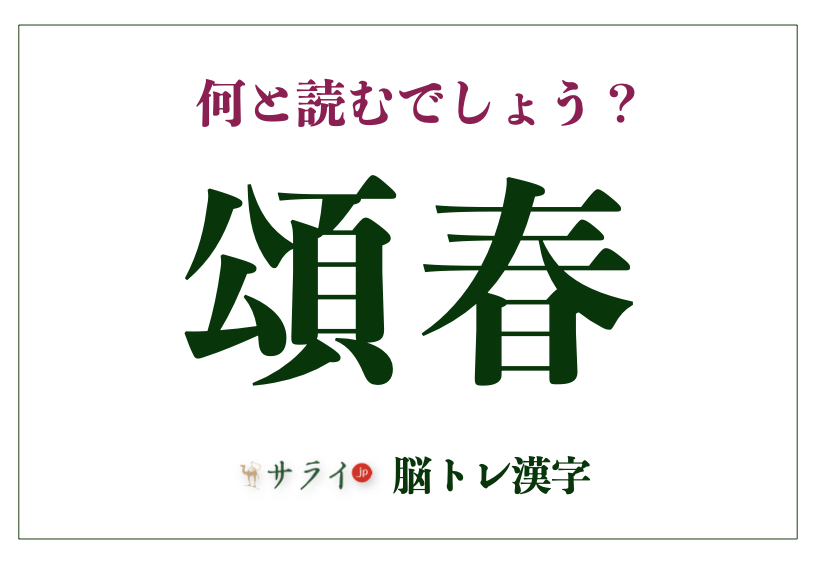今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「墓場に近き、老いらくの 恋は怖るる何ものもなし」
--川田順
前回は、柳原白蓮の恋愛事件にまつわる話を紹介したが、いま改めて歌壇の人物史を見渡してみると、道ならぬ恋に激しい情熱を燃やした歌人は、白蓮だけでなく、案外と多いのに驚く。己の内面や情念と向き合いながら、思うところ、感じるところを三十一文字に結晶させていくという歌づくりの仕事が、そこに何らかの影響を及ぼしているのかもしれなかった。
今日は、そんな歌人の中から、川田順のことを取り上げてみたい。
川田順は明治15年(1882)東京生まれ。第一高等学校を経て、東京帝国大学の文科に入学したが、まもなく法科に転じる。大学卒業後は、大阪の住友総本店に入社。実業人として活躍し、常務まで務めた。一方で、10代半ばから勤しんだ歌づくりは、一貫してつづけていた。
そんな川田順は、60代半ばで、ふた回り以上も年下の人妻(京大教授・中川与之助夫人)の俊子と恋に落ちた。川田は中川与之助と旧知の仲で、その妻の俊子を歌の弟子として指導したのがふたりの出会い。10年ほど前に妻を亡くして孤独な日々を送っていた川田順の心に、いつか俊子の影が深くしのび入ったのである。俊子もまた、夫との関係は冷えきっていた。
掲出のことばは、その頃に川田が俊子におくった恋歌『恋の重荷』の序章の一節。序章の全文を掲げると、以下のようになる。
「若き日の恋は、はにかみて
おもてを赤らめ、壮士時の
四十歳の恋は、世の中に
かれこれ心配(くば)れども
墓場に近き、老いらくの
恋は怖るる何ものもなし」
そんな情熱を受けて、俊子もこんな歌を返している。
「命こめて作らむものを歌に寄せし この吾心君によりゆく」
互いの覚悟はできていても、なお激しい葛藤はつきまとう。俊子には3人の子もあった。ことが表沙汰になると、世間はこれを「老いらくの恋」と呼んだ。
心配し、応援してくれる者もいた。古くからの友人の山本義路は、川田をこんなふうに励ました。
「君はなぜそんなに苦しむのか。真実に相愛する者が一緒になるのになんの悪いことがあるものか。君の場合は相手の境遇上けっして美事善行ではない。けれども同時に非事悪行でもない。あえていえば、旧来の日本人の結婚と家庭とが間違っているのだ。君は恋愛をもって、それへあえて抗議をしたのだ。真実に生きて貫くことだ」
友情に感謝しつつも、川田は黙って聞いていた。川田の中には、旧道徳に抗議するなどという観念も意図もなかった。ただ恋愛に陥っただけだった。
川田の苦しみはつづき、亡妻の墓に頭を打ちつけて自殺を図るという事件まで引き起こした。
やがて、俊子は夫と協議離婚した。川田と俊子は住みなれた京都を離れ、湘南の辻堂で新しい暮らしをはじめた。風に潮の香る、松林の緑に囲まれた場所に家を持ち、「沙上亭」と名づけた。ほどなく俊子のふたりの子どもも手元に引き取り、彼らは静かな余生を過ごしたという。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。