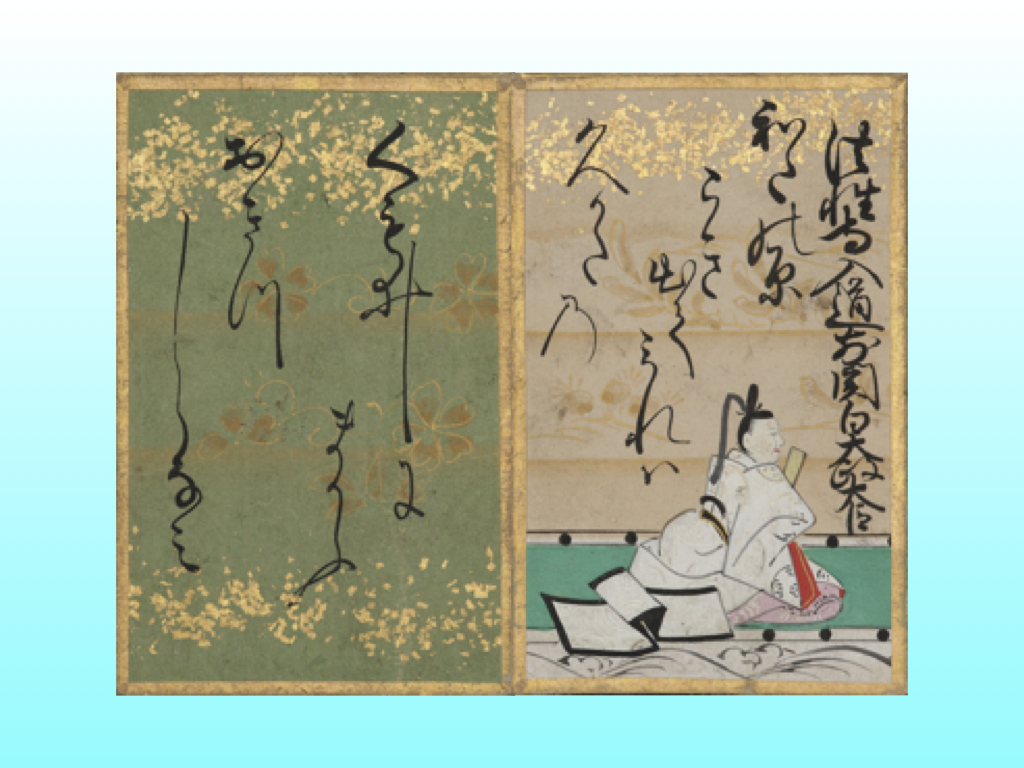今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。
【今日のことば】
「私たちは、折に触れ、ものに触れ、何かを言いたいのです。美しいものを見つけたら、ことばに出して讃嘆し、人にも告げたくなります。季節にしたがう日常の暮らしの中で、心に響くものを柔らかく、つつましやかな気持で十七文字に表すのが俳句です」
--中村汀女
俳人の中村汀女の本名は破魔子。明治33年(1900)4月、熊本の江津湖畔で生まれ育った。県立高等女学校を卒えてまもない18歳の師走、いつもと同じように自宅の拭き掃除をしていて、ふと頭の中に浮かぶ文句があった。
「我に返り見直す隅に寒菊赤し」
これが、ほどなく九州日日新聞の俳句欄選者・三浦十八公から絶賛されることになる、中村汀女の処女作だった。
ここから作句をはじめた汀女は、その後『ホトトギス』同人として活躍。やがて、星野立子、橋本多佳子、三橋鷹女と並ぶ俳壇女傑「四T」と賞賛される存在となった。
昭和22年(1947)からは俳誌『風花』を主宰し、後進の指導にも意を注いだ。
主婦兼母親の日常から多くの作句をなし、一部からは揶揄をこめて「台所俳句」と評されたこともあったが、汀女は「それでよし」と胸を張って毅然と受け止めた。『中村汀女 俳句入門』に記された掲出のことばにも、汀女のその心組みがあらわれている。
同書の中に、汀女はこうも綴っている。
「俳句というものは、むつかしい学問や格式を必要とせず、万人が楽しめる文学として生まれ、そして今日まで発展してきたものですから、だれでも、気軽に、自分たちの周囲から、美しい詩を見つけて、十七文字にすることです」
「悲しいことも、辛いことも、十七文字に詠むことによって、不思議に自分から離れてしまいます。思いを文字につづるということは、ほんとうに不思議な強い力を持っています。そして十七文字に表現するために自分を見つめる、つつましい自分がそこに生まれるのを覚えます」
やさしい言い回しの底に、揺るぎないものを感じる。
以前、熊本近代文学館で中村汀女の愛用品の数々にふれる機会があった。硯や筆などをおさめた文箱の中に、文鎮代わりに使用したとおぼしき刀の鍔があった。それがいかにもこの人らしいと感じた。穏やかな良妻賢母の顔の向こうに、火の国の女の勁(つよ)さを秘めていた中村汀女なのである。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。