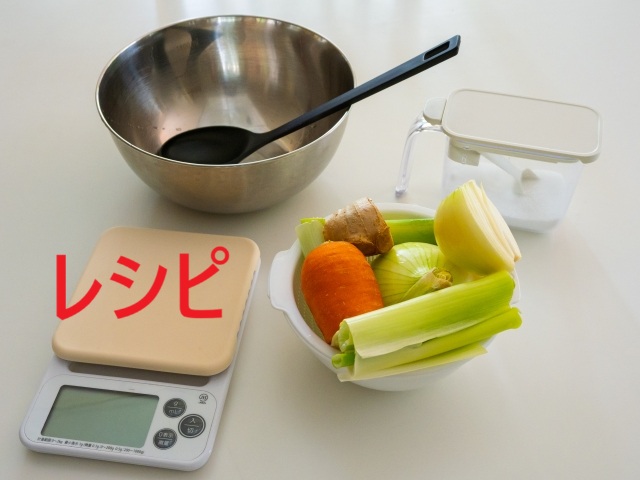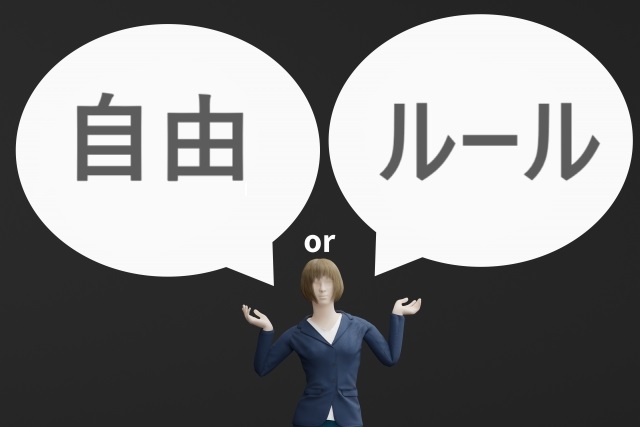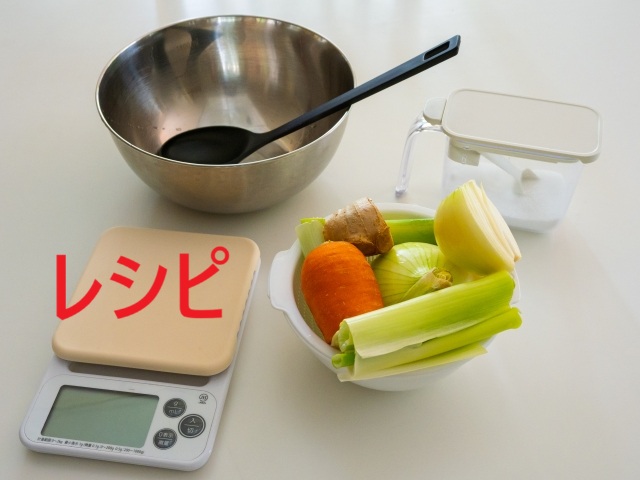
マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、型・手順・ルールの重要性について、識学理論の視点から解説します。
はじめに
「自分は料理が苦手だけど、レシピ通りにやったら意外と美味しくできた」──。このような経験を持つ人は多いのではないでしょうか。特に、調理経験の浅い人ほど、「正確な手順」に従うことで驚くほどの成果を出すことができます。
この構造は、実はビジネスの世界にもそのまま当てはめることができます。すなわち、業務においても「才能」や「経験」に頼らず、「明確なレシピ=型・手順・ルール」に基づいて行動することで、高い成果を再現性高く出すことが可能になるのです。
この記事では、識学理論の視点から「なぜビジネスにおいてもレシピ(型)が重要なのか」「再現性のある仕組みがいかに組織の生産性と安定性を高めるか」について、料理の例えを用いながら考察していきます。
感覚や才能に頼る組織は再現性が低い
まず前提として、「できる人」のやり方をそのまま他人が真似しても、同じような成果が出るとは限りません。なぜなら、その人の中には膨大な経験、独自の判断基準、微妙な感覚値が蓄積されており、それらは暗黙知として他人には伝わりにくいからです。
たとえば、ベテランの料理人が「適量で」と言っている調味料の分量は、初心者には到底分かりません。結果、「しょっぱすぎた」「味がぼやけた」といったブレが生まれます。これはビジネスにおいても同様で、感覚に頼るやり方は属人性が強く、成果の再現性が著しく低いのです。
識学では「組織は再現性によって強くなる」と定義します。つまり、「誰がやっても一定の成果が出る」状態を目指すことが、組織力を高める最大の近道であると位置付けます。
レシピ=型がもたらす5つの効果
ビジネスにおける「レシピ」は、業務マニュアル、ルール、手順書、フロー図といった形式で整備されます。こうした「型」を用意することで、以下のような明確な効果が生まれます。
(1)業務の属人化を防ぐ
(2)成果のばらつきを抑える
(3)新人育成が高速化する
(4)業務改善が可能になる
(5)評価と管理がしやすくなる
このように、型があるだけで組織全体のパフォーマンスは飛躍的に向上します。実際、識学では多くの企業に対して、こうした「業務の型化」と「再現性の確保」をテーマとした組織改革を通して、劇的な成果向上が見られています。
創造性も「型」から始まる
「型にはまったやり方は面白くない」「創造的な仕事にはマニュアルなどいらない」──こうした声もあります。確かに、芸術や商品開発、マーケティングなど、創造性が求められる場面では、自由な発想が重要です。
しかし、重要なのは「自由」と「無秩序」は違うということです。料理人の世界でも、基礎的なレシピや手法を習得していない者が独自の創作をしようとしても、それは単なる自己満足に終わるケースが多いものです。
創造とは、あくまで「型の上に乗った逸脱」であるべきです。つまり、基本を正しく理解しているからこそ、その上で工夫やアレンジが可能になるのです。これを識学では「逸脱の許可」とは呼ばず、「逸脱が意味を持つのは、守るべき型が確立されている場合に限る」と解釈します。
型を守らせるマネジメントが鍵
ここで重要なのは、ただ「型を作る」だけではなく、それを「守らせる」仕組みを同時に構築することです。
よくある失敗パターンは、「立派なマニュアルを作ったが、現場では誰も見ていない・使っていない」という状態です。これは、型を守る文化が組織に根付いていない証拠です。
識学では、組織内においては「ルールを破った場合のペナルティ」を明確にすることを推奨しています。ルールがあるのに破っても何の指摘もされない状況では、やがてルール自体が形骸化してしまいます。つまり、「ルールを守らせること」こそが、マネジメントを行う上での土台となります。
さらに、「なぜこの型が必要なのか」という意図や背景を明確に伝えることも、現場の理解と協力を得る上で非常に重要です。人は理由がわからないと動きません。単に「守れ」ではなく、「守る目的」を示すことが、型の定着には欠かせないステップです。
KPIと型を連動させる
実際のビジネスでは、型(マニュアルや手順)とKPIをセットで運用することが効果的です。KPIとは、成果を数値で可視化し、進捗や課題を管理するための指標ですが、これは「型が機能しているかどうか」を測定する物差しとも言えます。
たとえば、営業部門において「月間訪問件数」「成約率」「初回アポからのリードタイム」などをKPIとして設定し、それらに対する具体的な行動手順(トークスクリプトやヒアリングフロー)を型として明示します。このように、KPIと型が結びつくことで、数字をもとに業務の見直しができ、属人的な指導や曖昧な指摘を排除できます。
まとめ:レシピがあるから、誰でも美味しく作れる
料理が苦手な人でも、レシピ通りに作れば美味しい料理ができる。この構造は、ビジネスにおいても完全に一致します。
才能や経験に頼るのではなく、「誰がやっても一定の成果が出る型=レシピ」を整備し、それを現場に徹底することが、強い組織づくりの第一歩です。そのための「定義」「ルール」「再現性の確保」「逸脱の管理」という視点で業務を捉えてみることが大切です。型は作るだけでは意味がありません。型が守られ、その土台を元に発展や創意工夫があることに価値があるのです。
まずは、今あなたの組織に「レシピがあるのか」「そのレシピは守られているのか」を見直してみてください。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/