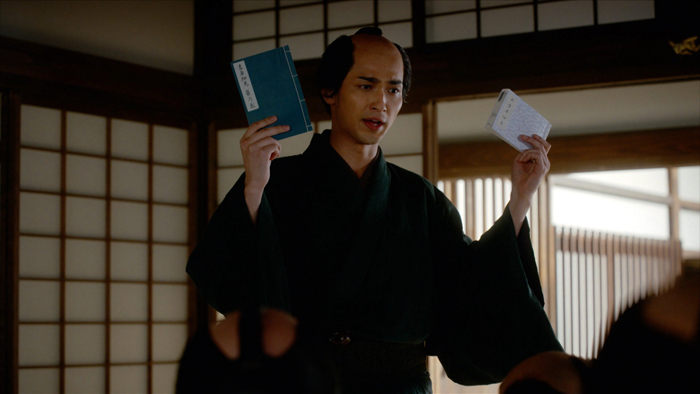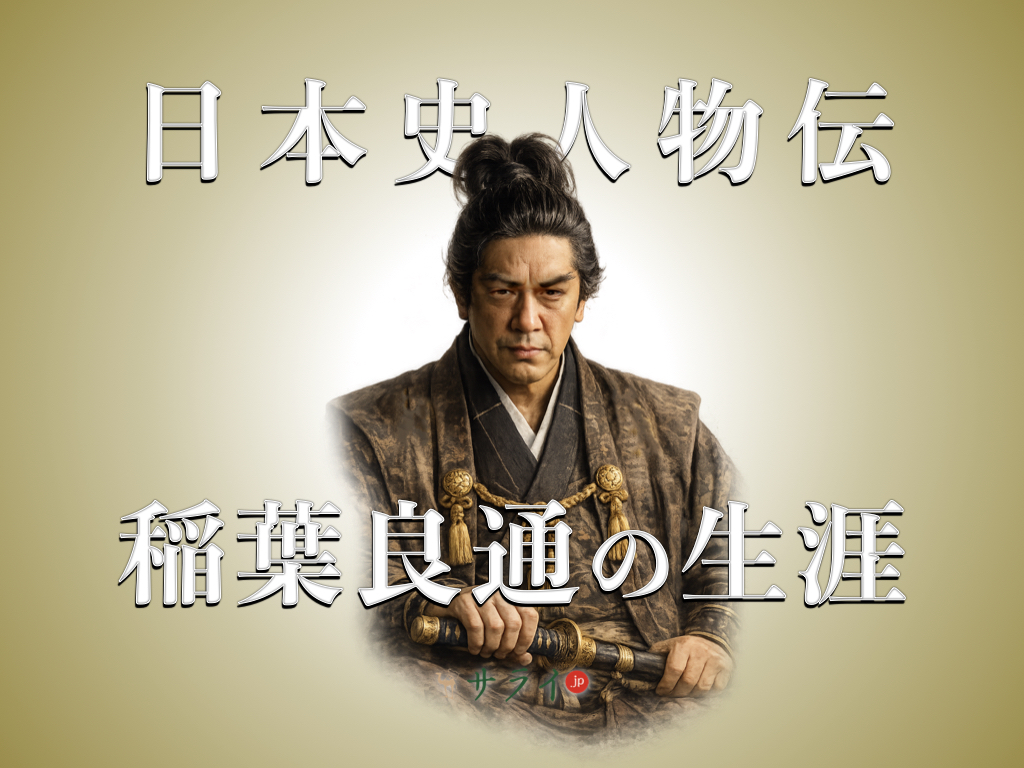ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第19回では、将軍世子家基(演・奥智哉)の生母である知保の方(演・高梨臨)が将来を悲観して毒をあおるという展開になりました。さらに、将軍家治(演・眞島秀和)が周囲から求められた子作りもうまくいかないようです。目をかけていた嫡男家基の不可解な急死という事態を受けて、周囲から新たに後継者をもうけるべく勧められていたのですが、どうもうまくいきません。
編集者A(以下A):いわゆる大奥と称される江戸城の深奥部については、映画やドラマの題材になっていますが、将軍世子の生母の立場からの「転落」というのは精神的にかなり辛い状態だったと思われます。家治にしても「子づくり」に消極的だったというエピソードもあったりしますから、後継ぎの家基が亡くなって、なにもかも面倒くさかったのではないでしょうか。
I:でもこのころの家治はまだ40代ですからね。
A:初代将軍の家康が、御三家の九男義直(尾張)、十男頼宣(紀州)、十一男頼房(水戸)をもうけたのは50代後半以降。家治も年齢的にはまだまだこれからという感じですが、それだけ家基急死のショックが大きかったのでしょう。直前まで元気いっぱいで鷹狩に出かけたと思ったら、急死ですから、やはり「暗殺」「毒殺」を疑ったのかもしれません。
I:将軍世子の暗殺となると大事件ですよね。世子が亡くなったから、もう一度「子作りを」といわれても萎えてしまったのかもしれません。
A:8代将軍吉宗は、息子の家重に将軍の座を譲り、大御所になった後は、孫である家治の養育に力を注いで「帝王学」を授けたそうです。現代でいう小学校中学年から中学生時代に直接祖父吉宗の薫陶を受けた家治は、吉宗がほれこむほど優秀だったといわれています。趣味は『べらぼう』劇中でも描写があったように将棋。詰将棋の著書もあるくらいのめりこんでいたようですし、絵画にも秀でていたようです。田沼意次(演・渡辺謙)を重用したのは、父家重の遺言を忠実に履行した結果です。きっと優秀で律儀な、真面目な人物だったのでしょう。
I:家治は、「秀忠、家光、家綱」と並んで、初代家康の幼名「竹千代」を名乗った将軍。このうち秀忠の初名は「長丸」ですから、「生まれながらの将軍」という正統的な将軍なんですよね。
A:そういう観点でいえば、家基も幼名竹千代ですからね。
I:家治の偏諱を受けた大名で有名なのは米沢藩の上杉治憲でしょうか。号名の鷹山の方で知られた人物ですが、藩政改革を行ない、地場産物の紅花の栽培を奨励するなど、「家治―田沼意次」体制の影響を受けて「名君」と称された代表的な大名のひとりです。
【蔦重「耕書堂」のゆくえ。次ページに続きます】