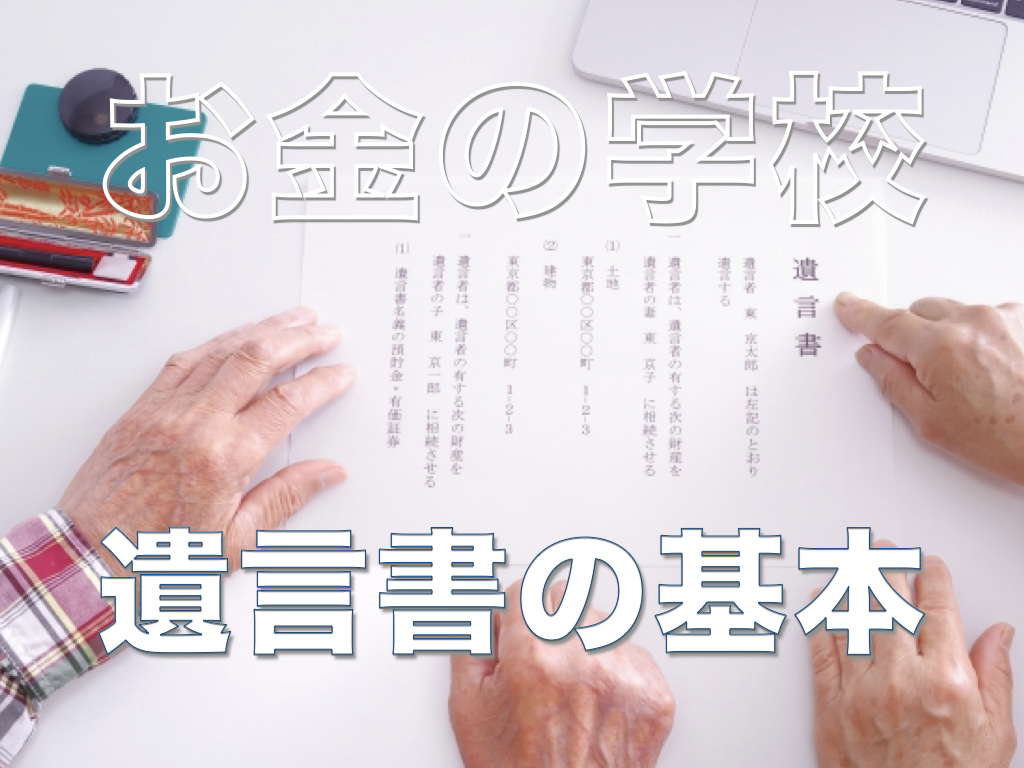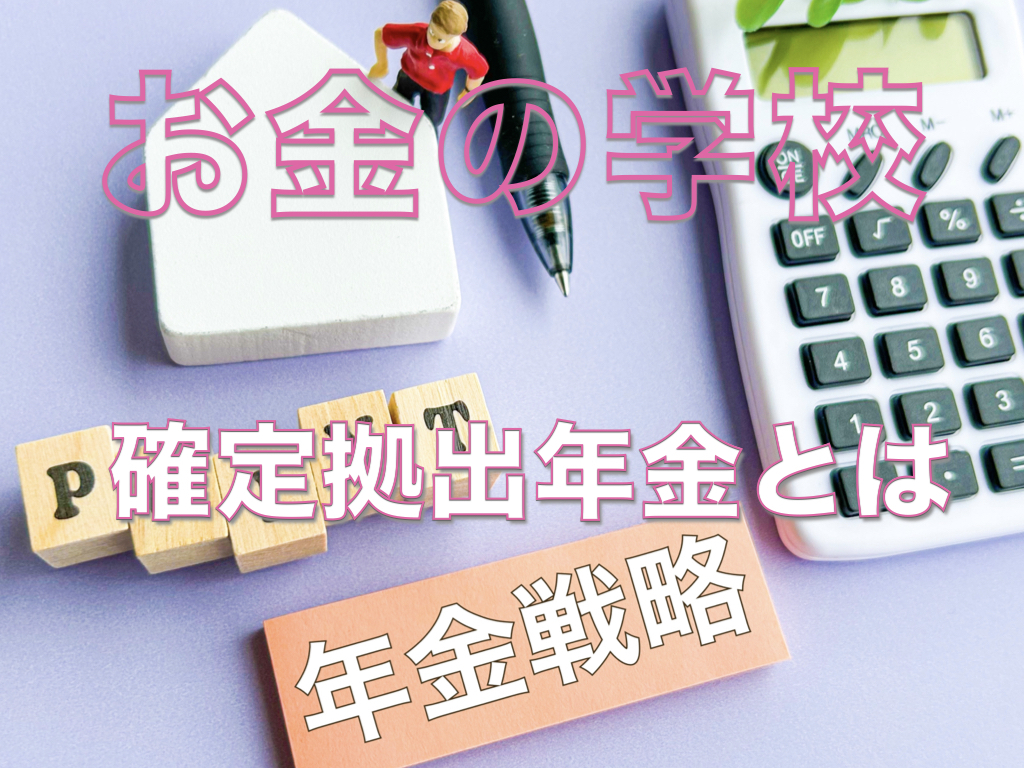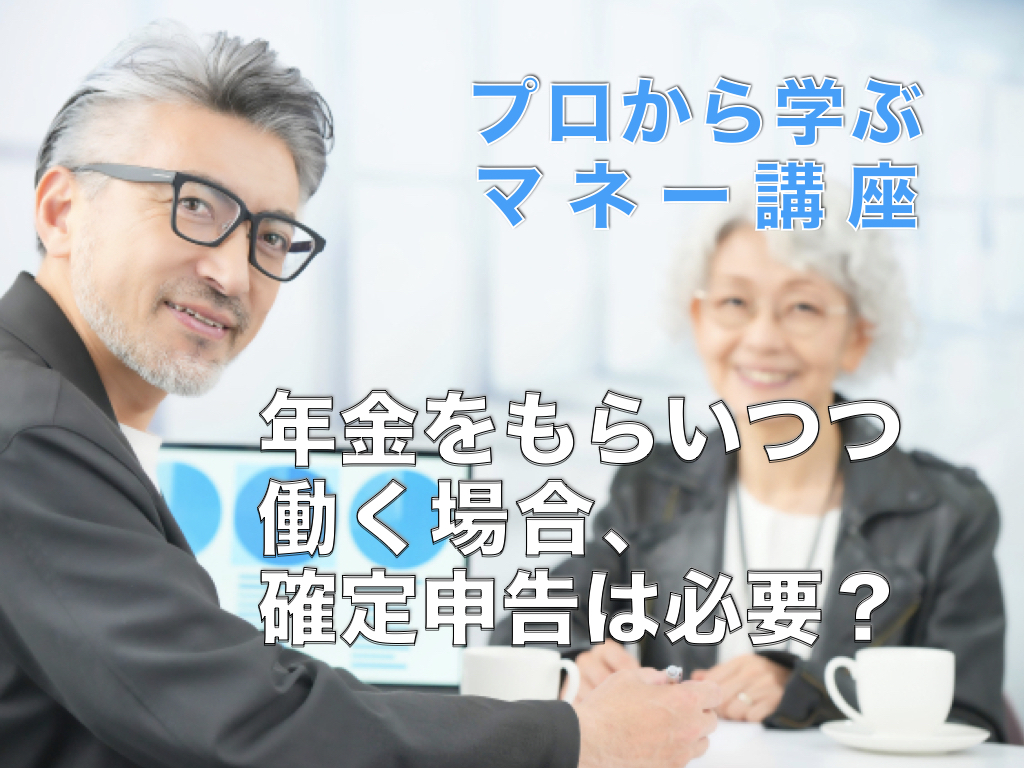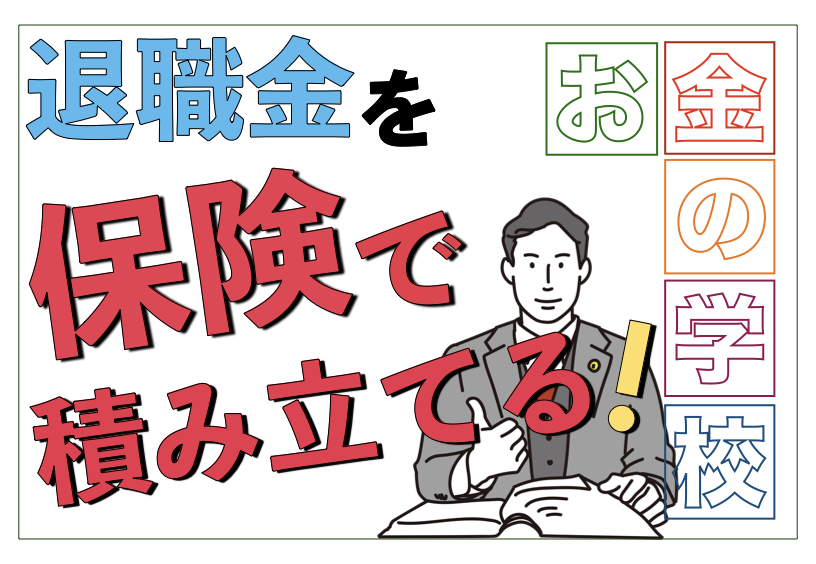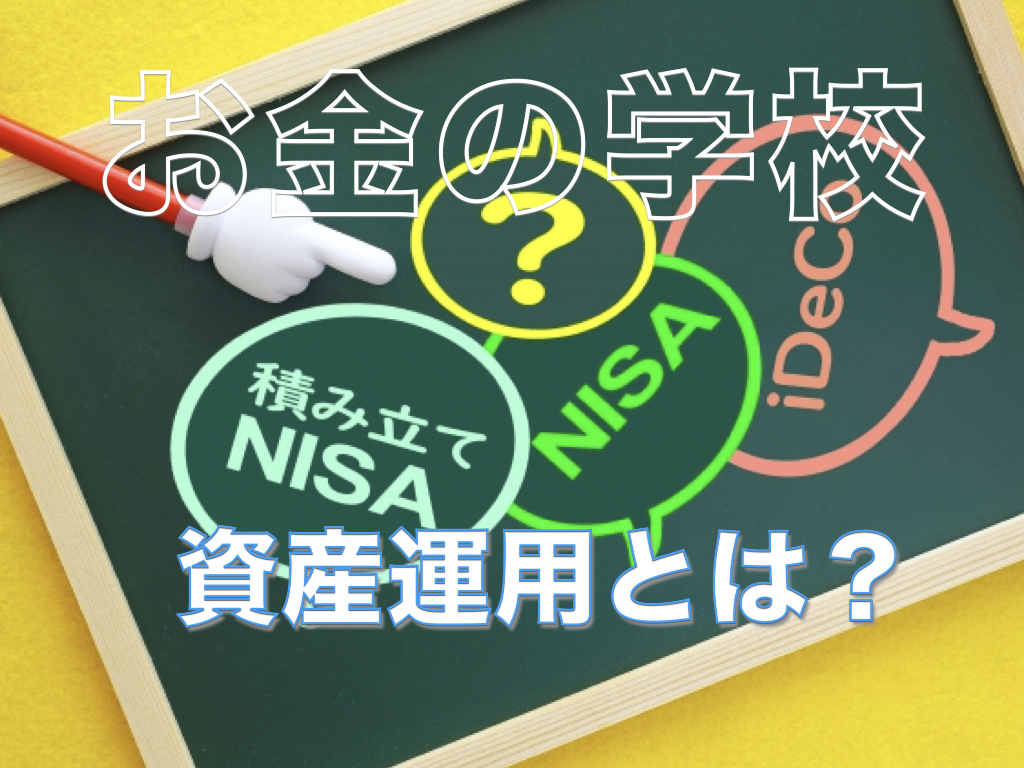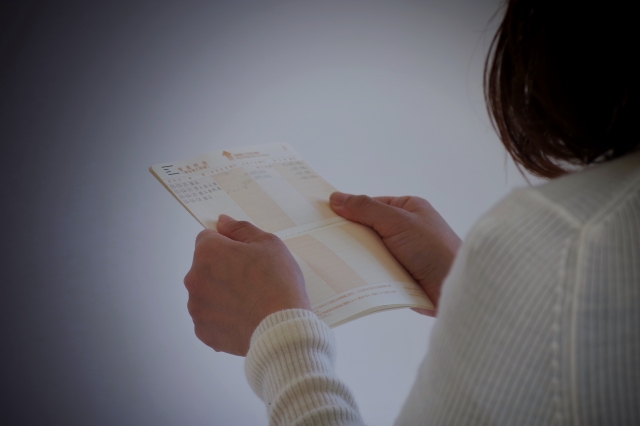「遺言書を見つけたけれど、家庭裁判所で検認を受けないと効力がない」といったケースがあります。「検認」を正しく理解しておかないと、相続手続きが滞ることや、他の相続人とのトラブルにつながりかねません。
今回は「検認とは何か」「しないとどうなるのか」「必要書類や流れ」など、遺言書の検認に関する基礎知識について見ていきましょう。100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、LIFEBOOK(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。
そもそも「検認」とは何か? しないとどうなる?
遺言書の検認とは、家庭裁判所が相続人全員の立ち会いのもと、遺言書の存在や内容を確認・記録する手続きのことを言います。検認の目的は「遺言書が偽造・改ざんされていないか」をチェックすることで、遺言の有効性そのものを判断するものではありません。
遺言書の検認が必要な理由と法的な意味
自筆で書かれた遺言書や、秘密証書遺言を見つけた時は、そのまま使うことはできず、家庭裁判所に持っていって「検認」という手続きを受ける必要があります。これは、あとで「勝手に書き換えられたのでは?」と相続人同士で争いにならないように、証拠として残しておくための仕組みです。
つまり検認は、遺言の内容が正しいかどうかを決めるものではなく「遺言書が確かに存在していて、こういう形で残っていた」という事実を確認するための手続きなのです。
検認をしないと無効になる? 違法になる?
検認を受けなかったからといって、遺言書が「無効」になるわけではありません。ただし、検認を受けずに相続手続きを進めると、金融機関や法務局で受け付けてもらえず、結果的に使えない状態になります。
また、家庭裁判所に提出しないと5万円以下の過料に処される可能性もあります。これは、検認を通さずに遺言書を勝手に使ってしまうと、他の相続人が内容を知らないまま手続きが進んでしまい、不公平やトラブルにつながるおそれがあるためです。

検認が不要なケース(公正証書遺言など)
すべての遺言書が検認を必要とするわけではありません。公正証書遺言は、公証人と証人の立ち会いのもとで作成されることで、偽造・変造の恐れがないため、検認は不要です。
また、法務局で保管される「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合も検認は不要となります。この場合、遺言書が公的機関である法務局にそのままの形で保管され、改ざんなどの心配がないためです。
検認に必要な書類と手続きの流れ
検認を受ける時に、必要な書類や手続きの流れについて見ていきましょう。
検認申立書の書き方
検認申立書は、裁判所の公式サイトからダウンロードすることができます。主な記載事項は以下の通りです。
・被相続人(亡くなった方)の氏名・本籍・死亡日
・遺言書の種類(自筆証書・秘密証書など)
・相続人全員の氏名・住所・続柄
・申立人の情報
記入が難しい場合は、裁判所の窓口や司法書士などの専門家に相談するのも方法の一つです。
申立時に必要な戸籍謄本や住民票
提出が必要な主な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(相続人を確定するため)
・相続人全員の戸籍謄本
・申立人の住民票
・遺言書の原本
これらの書類は役所で取得する必要があり、一般的に、書類を揃えるために数日~1週間程度かかります。

申立人とは? 相続人の中の誰が出す?
検認の申立ては「遺言書を発見した人」が行なうのが原則です。多くの場合は相続人が申立人になりますが、相続人以外の人が遺言書を保管していた場合、相続人以外の人でも申立ては可能です。重要なのは「検認は相続人全員に通知され、立ち会う機会が与えられる」という点です。
検認の期限・期間・所要時間の目安
「検認はいつまでにしなければならないのか?」という点もよく聞かれます。
検認は「いつまでに」「どのくらいかかるのか」
検認の期限は、法律で明確には定められていません。しかしながら、検認を経なければ遺言を使って相続登記や預金解約ができないため、できるだけ早めに申立てを行なう必要があります。手続き自体は、申立てから1〜2か月程度で検認期日が指定されるのが一般的です。
期日が来たら何が起きる?
検認期日には、家庭裁判所で遺言書が開封され、その内容が確認・記録されます。相続人が立ち会って遺言書の存在を確認するため、後日「そんな遺言は知らなかった」という争いを防ぐことができます。検認が終了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が交付されます。
検認後にやるべきこと(相続手続きなど)
検認が終わったら、相続人は検認済証明書を使って、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを進めます。検認はあくまで形式的な手続きなので、その後は遺言の内容に沿った遺言執行の手続きが重要になります。
欠席・コピー対応など、よくある例外ケースの対処法
検認に関しては「当日出席できない」「原本が手元にない」など、実務上よくある例外ケースがあります。
検認に欠席したらどうなる? 不利になる?
検認期日に欠席しても不利になることはありません。立ち会いは義務ではなく、あくまで参加する機会が与えられているだけです。ただし、欠席した人は、後日「検認調書(家庭裁判所での検認手続きの内容を記録した公的な書類)」を確認して内容を把握しておくことが大切です。
検認にコピー提出は可能? 正式な扱いとは
検認には遺言書の「原本」が必要です。コピーでは検認を受けることができません。ただし、検認後には裁判所で原本の写真撮影や写しの交付を受けることができます。
郵送での申立てや遠方在住者の手続き
申立書や必要書類は郵送で提出することが可能です。期日に出席できない場合も、必ずしも出席する必要はありません。遠くに住んでいる場合でも、書面だけで手続きを進めることができます。
まとめ
遺言書の検認は、「遺言を有効にするため」ではなく、「遺言書の内容をしっかり記録して、あとで相続人同士のもめごとを防ぐため」の制度です。自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合は、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行ないましょう。
「検認しないと無効になるのでは?」と不安に思う方も多いですが、正しくは「無効になるわけではなく、手続きが進まない」という解釈です。検認は、後々の争いや混乱を防ぐために欠かせないステップといえます。
資産運用や投資のアドバイスは、今や銀行などの金融機関の窓口でもさかんに行われています。同時に、インターネット上でもYouTubeやSNSを通じて色々な人がそれぞれの立場から投資術などを発信しています。しかし、それらのアドバイスは本当にあなた自身に適したものなのでしょうか?
さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考える時には、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。
●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)
●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)