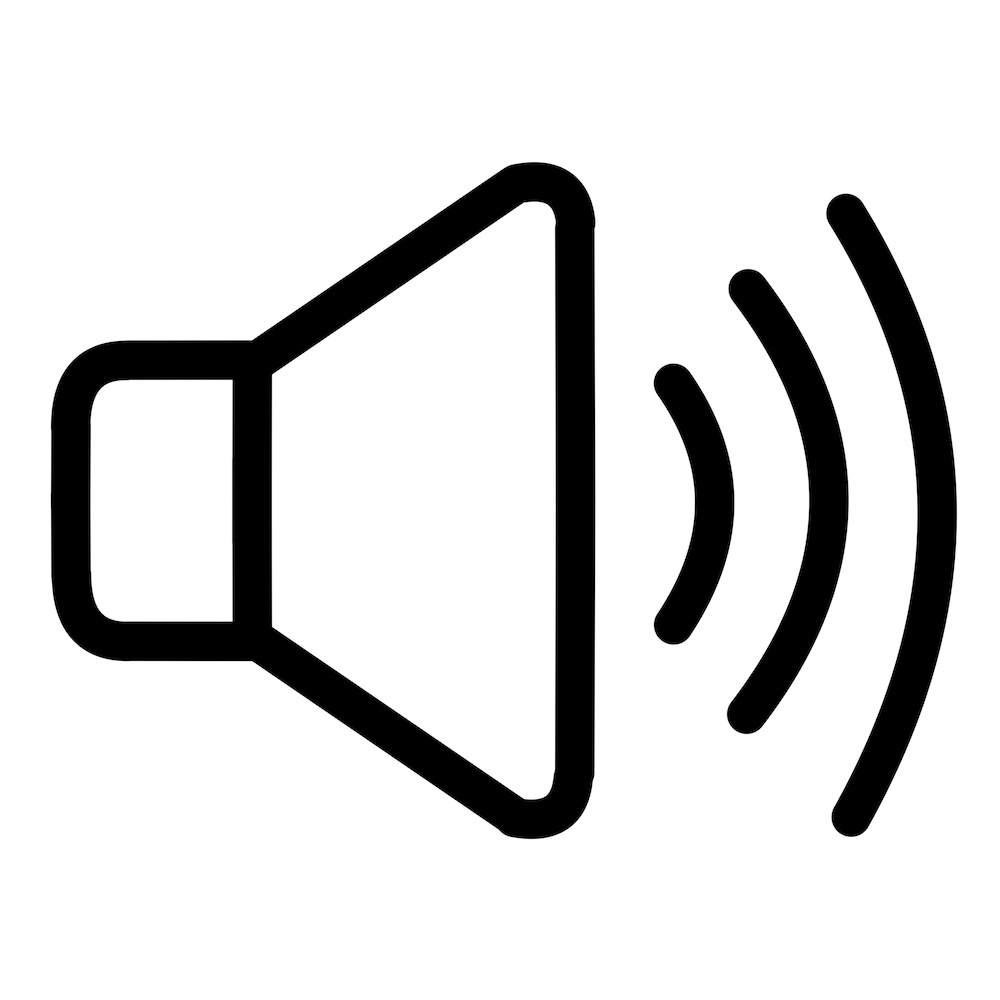■3年間の「空白」を、早く埋めたい……との焦燥感
正式に姉妹の家庭復帰が決まってから、姉妹の言動には変化が現れた。
特に小さな次女は、いくら注意しても言うことを聞かず、ときに部屋の中でおもらしをしてまで、激しく泣きわめき、拒否しようとしたという。
その変化に動揺した母は、我慢できなくなり、実力行使で黙らせようとしてしまった。
「3年間の空白を、少しでも早く埋めようとして、ついやってはいけないことをしてしまった。焦っていたのかもしれません」と、母親は涙ながらに反省の弁を述べた。
さらに、母親の弁護人は、母親の手をいったん離れて、児童養護施設などに断続的に預けられていた子どもたちは、はたして母親が自分を受け入れてくれるかどうか、ずっと不安にさいなまれていたと指摘した。
そして、次女が部屋でおもらしをしたり、タンスの上に登って抵抗したりしたのは、母親が自分を見放さずに守ってくれるかどうかを見極める「試し行動」だったと主張したのである。
試し行動が繰り広げられている段階では、母親だけで対応するのは無理があり、児童相談所など専門家のフォローが必要だったとし、情状酌量を求めた。
対して、検察官は母親による虐待が日常的に行われていて、娘たちは生傷が絶えないだけでなく、将来にわたって影響をおよぼしかねない精神的な傷も負っていると非難した。加えて、母親が娘たちに行った「しつけ」の一環を詳細かつ具体的に指摘し、その残虐性を法廷でアピールした上で、懲役5年の実刑を求刑した。
■限りなく実刑に近い執行猶予
そして後日、判決を言いわたす公判が開かれた。
担当の裁判官は、「たしかに虐待は悪質だが、もともとは2人の娘に対して深い愛情があり、関係を取り戻そうと焦るあまり、行きすぎてしまったことが認められる。孤立した状態で、虐待の歯止めが効かずにエスカレートしてしまった。今は深い反省も感じられる」として、懲役3年の刑を言いわたした。
ただし、その懲役刑には5年間の執行猶予が付けられた。その上で、保護司というボランティアとの面会を定期的に義務づける保護観察も命じられた。
確かに執行猶予判決ではあるが、法律上、執行猶予が許される刑は懲役3年が上限で、執行猶予期間の上限は5年間と定められている。つまり、限りなく実刑に近い執行猶予判決だった。
この判決に対しては、「子どもを虐待する親を、実刑にできない裁判所は甘い」「愛情なんか、あるはずない」などと、インターネットを中心に激しい批判が浴びせられた。
ただ、この事件に至るまでの、数年間にわたる背景事情や、裁判官が抱えた決断の苦悩を垣間見れば、少しは執行猶予判決に対する印象が変わるのではないだろうか。
娘ふたりを家に再び迎え入れるまで、約3年間、関係の再構築を続けてきた被告人の努力を、裁判官は無視できず、残虐な「毒親」だと決めつけるのは忍びなかったのだろう。
今後なお虐待を繰り返すなら、いよいよ刑務所にぶちこむなり、親権を剥奪するなり、煮るなり焼くなり最後通告を突きつけることもできる。
■「家庭の中で、罪を償ってください」
母親に一度だけチャンスを与えた裁判官は、最後にこのように説諭した。
「私にも、あなたと同じぐらいの年齢の子どもがいまして、今朝も叱ってきました。『幼稚園に行きたくない!』と、ぐずるものですからね。嫌なことがあっても、気まずいことがあっても、行かなければならない場所があります。でも、叱るとしても絶対に手をあげてはいけません。いくら小さくても、ひとりの人格を持った人間です。決して見捨てず、笑顔で迎えてください。そして、家庭の中で罪を償ってください」
家庭内の問題は、誰かを刑務所にぶち込めば解決するわけではない。その近すぎるがあまりにこじれてしまった親子の関係性と、引き続き向き合い続けるよう義務づける。そうした執行猶予判決のほうが、当事者にとってむしろ厳しい場合もありうるのではないだろうか。
※本記事の裁判の情報は、著者自身の裁判傍聴記録のほか、新聞などによる取材記事を参照させて頂いております。また事件の事実関係において、裁判の証拠などで断片的にしか判明していない部分につき、説明を円滑に進める便宜上、その間隙の一部を脚色によって埋めて均している箇所もあります。ご了承ください。
取材・文/長嶺超輝(ながみね・まさき)
フリーランスライター、出版コンサルタント。1975年、長崎生まれ。九州大学法学部卒。大学時代の恩師に勧められて弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫し、断念して上京。30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)の刊行をきっかけに、記事連載や原稿の法律監修など、ライターとしての活動を本格的に行うようになる。裁判の傍聴取材は過去に3000件以上。一方で、全国で本を出したいと望む方々を、出版社の編集者と繋げる出版支援活動を精力的に続けている。

『裁判長の沁みる説諭』(長嶺超輝著、河出書房新社)