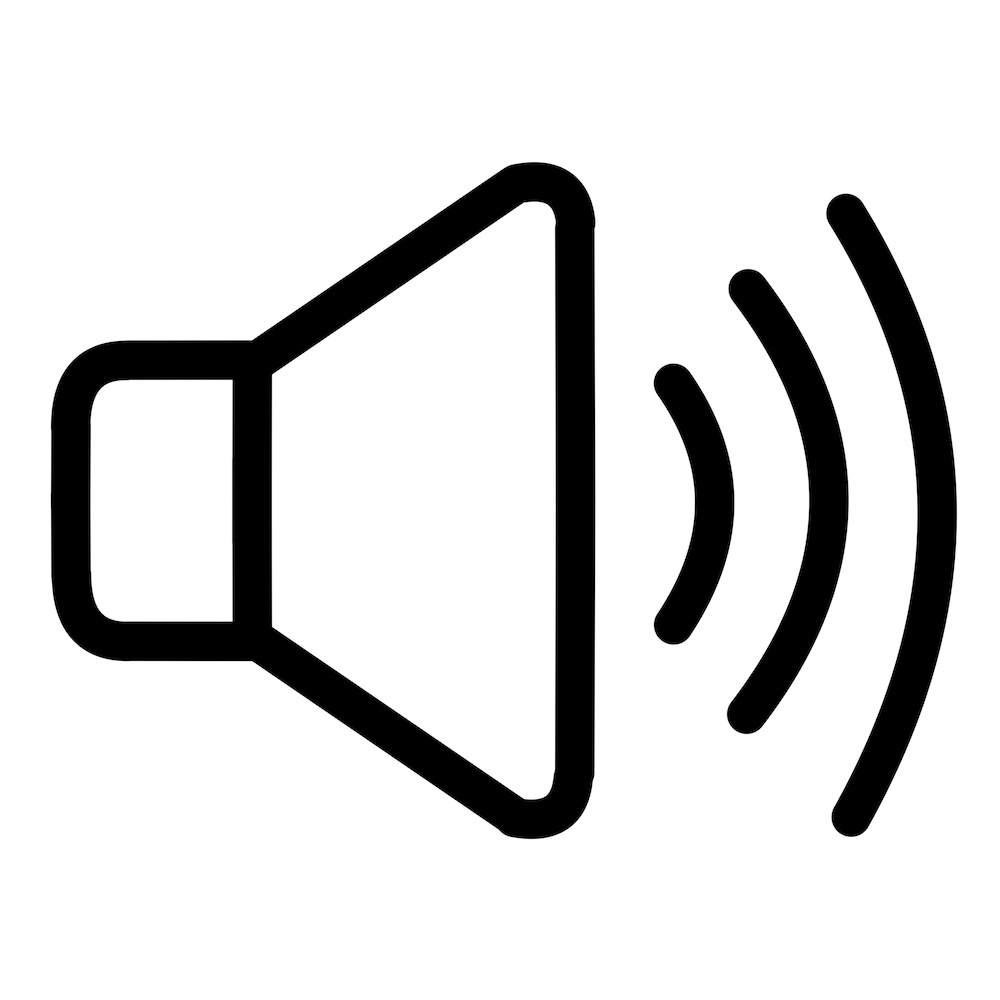取材・文/長嶺超輝

自宅に火を放ち、自らの命を絶とうとした男。
年老いて持病に倒れ、妻の介護を受け続ける自分自身の立場に我慢がならず、妻を介護生活から解放してあげたいとの思いからの「犯行」だった。
病院のベッドで意識を取り戻し、死ねなかったことを泣いて悔やんだ男の、痩せ細りしわくちゃになった手を、妻は優しく握った。
男は、現住建造物等放火の罪で、裁判所に起訴された。
その事件の背景事情を、法廷でじっくりと聞き取った裁判長は、恩情を掛ける判決を言いわたした上で、男の顔をジッと見つめて、説諭した……。
【前編はこちら】
* * *
■どんな罪が「裁判員裁判」で裁かれるか?
この男を裁く法廷は、裁判官だけでなく一般国民も参加する「裁判員裁判」となった。
毎年11月頃に、次の年の「裁判員候補」が、国民の中から無作為に選ばれ、通知される。そして、次の年に実際に、その裁判員候補が住む地元で「裁判員裁判対象事件」が発生し、裁判にかけられれば、実際に裁判所へ招集がかかるのである。
「裁判員裁判対象事件」は、次のいずれかに当てはまる犯罪である。
(1)わざとやった犯行で、人が亡くなっている犯罪(殺人・傷害致死・強盗致死など)
(2)最高刑が死刑または無期懲役と定められている犯罪(覚醒剤密輸・通貨偽造・身代金目的誘拐など)
住居として実際に使われている建物に火を放つことを、日本の刑法では「現住建造物等放火罪」(第108条)と呼ぶ。このたびの放火によって幸い、誰も亡くなってはいない。
だが、現住建造物等放火罪は、最高刑が死刑と定められている重罪である。たとえ、火を放ったのが自身の所有する持ち家だとしても、そこから延焼して近隣の地域にまで危害を加えるおそれが高い犯行だといえるためだ。
そこで、この男の「罪」を裁くため、裁判員裁判が開かれることとなった。
■行ってらっしゃいの代わりに「さよなら」と告げた
刑事裁判の法廷には、1人の被告人の身柄を確保し、逃亡や反抗などを防止するため、2人の看守が付いている。看守が歩行の補助しようとするのを断り、男は自分の力で証言台の椅子に座った。どこまでも、他人の助けはできるだけ借りたくないという態度を貫こうとしている。
法廷の壇上には、3名の裁判官だけでなく、地元の街から抽選などで選ばれた6名の裁判員、そして裁判員が何らかの事情で欠員となった緊急時のため待機している補充裁判員2名が、放火に至るまでの経緯を説明する男の話に耳を傾けている。
その日の朝、緊急の用事で出かける妻に対して、男は「さよなら」と別れを告げていた。そして、妻はその「さよなら」の意味に漠然と気づいていたという。
過去にも同じように出かけるとき、まるで「永久の別れ」を意図するかのような言葉をかけられることが何度かあった。ただ、それは決して自暴自棄の感情から出たのではなく、毎日の介護に時間や労力を割かなければならず、そのせいで迷惑を掛け続けて「申し訳ない」との思いからの発露であることにも気づいていた。
しかし、帰宅すれば変わらずに畳の上で横になっている夫の姿を見て、妻は安心していた。
■裁判長ら9名がかけた、温情の判決
ただ、夫は不甲斐ない思いにも苛まれていた。いくら介護され続けても、状況は何も改善されない。むしろ、自分が衰えていく一方である。
ならば、そのような介護は妻の人生を縛りつけるだけではないか。それはあまりにも心苦しい。自分との関係を断ち切ったほうが、妻は残りの人生を自由に生きられると信じた。
そして、寝たきりの鈍った身体を懸命に動かして、自分の仕事人生の象徴でもあった持ち家に火を放ち、炎と灼熱の中に留まっていたのである。
3名の裁判官と6名の裁判員が評議をした結果、判決公判で裁判長は懲役3年の刑を言いわたした上で、その刑の執行を猶予する宣言を行った。
【裁判長は、男の将来に思いを馳せて、穏やかな口調で説諭を始めた。次ページに続きます】