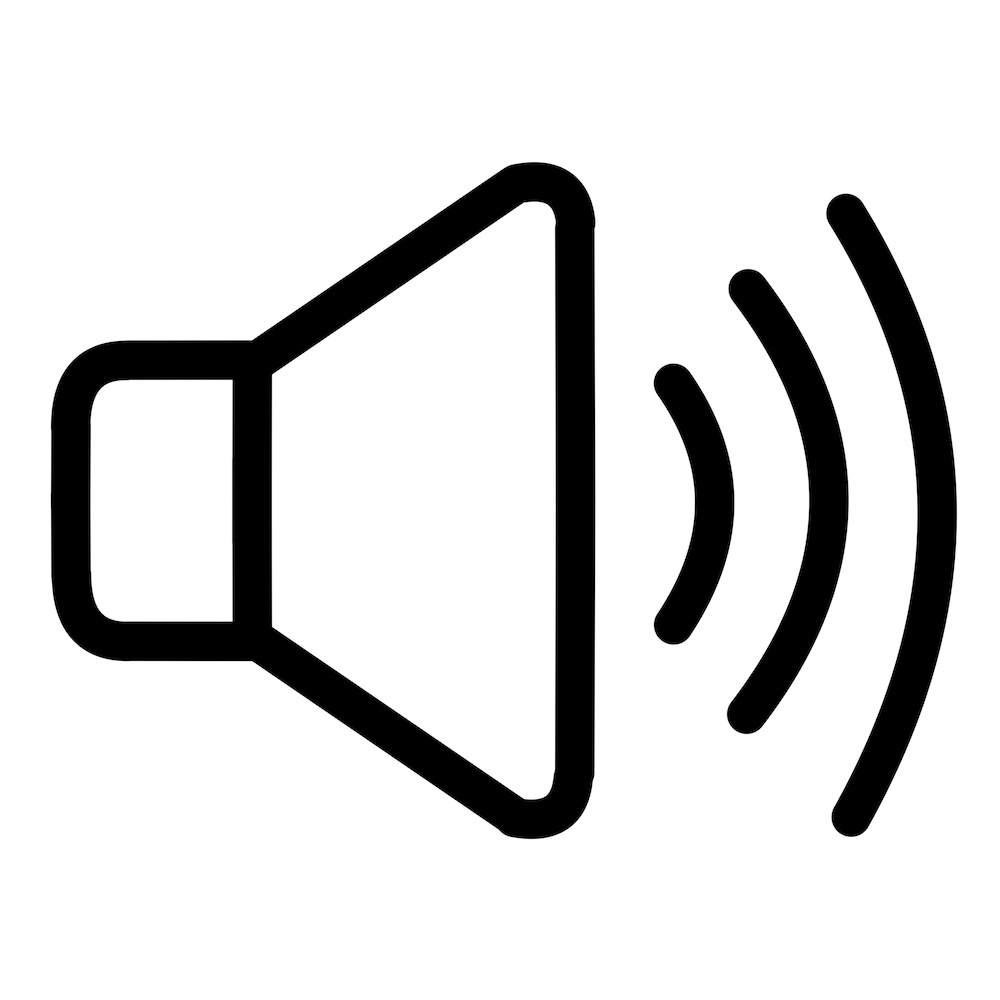■待っていたのは温情ある判決
しかし、担当した裁判官は、女性に対して特別に「2回目の執行猶予」を付けた。
執行猶予の期間中に行われてしまった再犯で、さらに執行猶予を付けるのは異例である。法律上、「再度の執行猶予」を付けるには、次の3つの条件を満たす必要がある。
(1)1年以下の懲役刑(または禁固刑)を言い渡すこと
(2)前の執行猶予に保護観察(保護司による日常生活の監督)が付いていないこと
(3)情状に特に酌量すべきものがあること
裁判官は、女性に対して懲役1年の刑を言い渡し、(1)(2)の条件を満たした上で、「子供にひもじい思いをさせたくないと考えて、やむをえず犯行に及んでいる。もし実刑を科せば、学校に通う2人の子供の生活が行き詰まってしまう」として、(3)の特別情状酌量を認めたのである。
再び、母として子どもの元へ帰ることが許された女にとっては、意外な判断だったろう。
2度目なのだから、厳しく罰するべきだという批判が出てくるのは無理もないし、実際、この場合は刑務所行きを命じる裁判官がほとんどのはずだ。しかし、それも承知の上で、この裁判官は温情のある判決で応えたのである。
しかし、裁判官の温かい裁きは、それだけでは終わらなかった。
■体感で伝わる説諭
閉廷した後、裁判官は書記官にお願いして、法廷を出ようとする女を呼び寄せた。そして、裁判官席から身を乗り出し、ひとこと告げながら、握手を求めたのである。
「もう、やったらあかんで。がんばりや」
女は、感激のあまり、その場で泣き崩れ、涙声で「ありがとうございます」と何度も繰り返した。関西弁の「がんばりや」に、裁判官の思いが詰まっている。
法律の論理で温情をかけ、握手を求めるスキンシップで感覚にも訴えかける。民間人の私たちにとっては、特別に何ということのない励ましかもしれない。しかし、日本の裁判所で、ここまでできる裁判官が稀であることは間違いない。
被告人と法廷で出会うことも、ひとつの「縁」だと捉え、これ以上の犯罪を抑止するために何かできないかと、自分事として受け止められる裁判官だけが実行できる。握手という「体感で伝わる説諭」も、その心構えがあったからこその着想なのかもしれない。
※本記事の裁判の情報は、著者自身の裁判傍聴記録のほか、新聞などによる取材記事を参照させて頂いております。また事件の事実関係において、裁判の証拠などで断片的にしか判明していない部分につき、説明を円滑に進める便宜上、その間隙の一部を脚色によって埋めて均している箇所もあります。ご了承ください。
取材・文/長嶺超輝(ながみね・まさき)
フリーランスライター、出版コンサルタント。1975年、長崎生まれ。九州大学法学部卒。大学時代の恩師に勧められて弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫し、断念して上京。30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)の刊行をきっかけに、記事連載や原稿の法律監修など、ライターとしての活動を本格的に行うようになる。裁判の傍聴取材は過去に3000件以上。一方で、全国で本を出したいと望む方々を、出版社の編集者と繋げる出版支援活動を精力的に続けている。

『裁判長の沁みる説諭』(長嶺超輝著、河出書房新社)