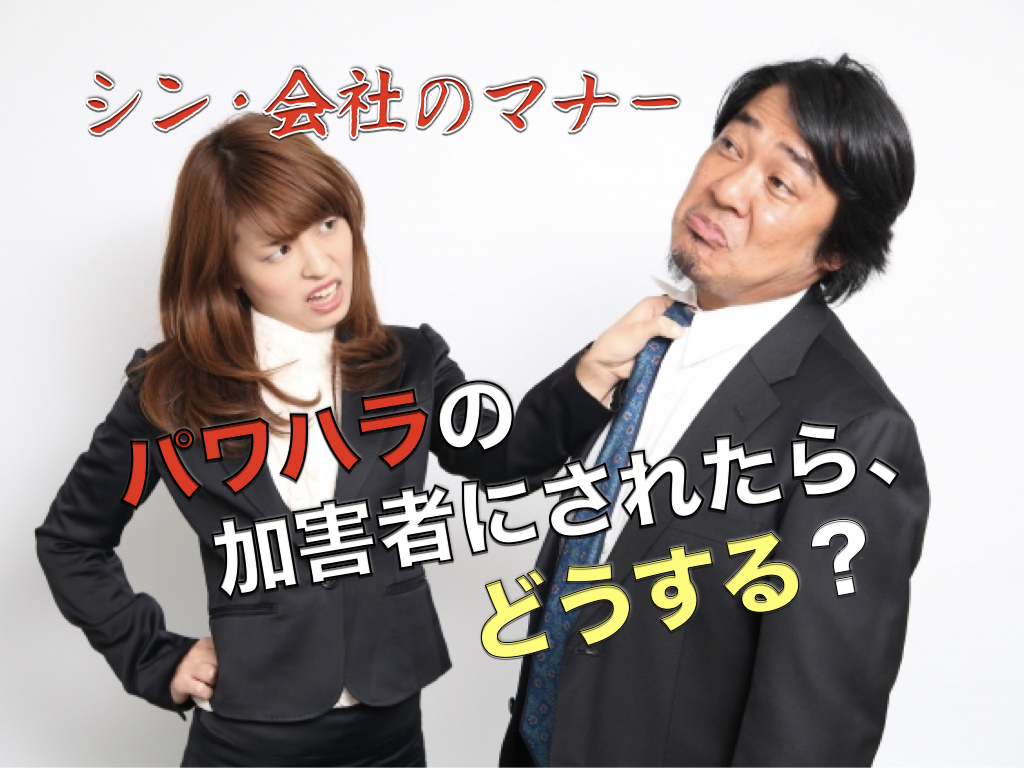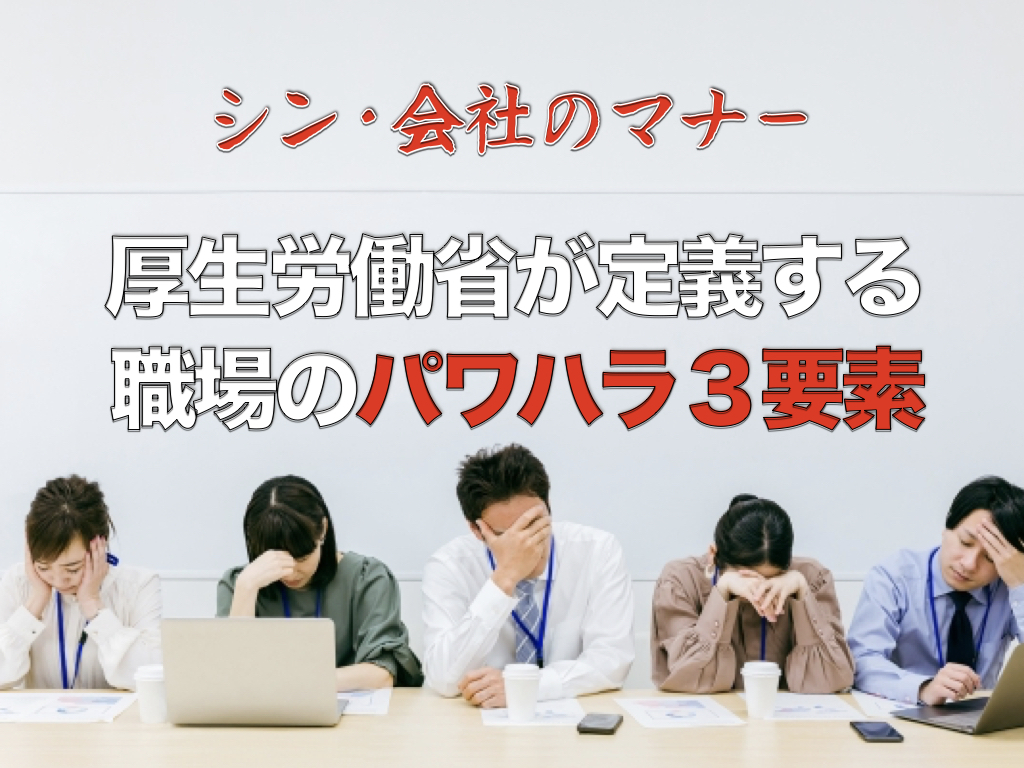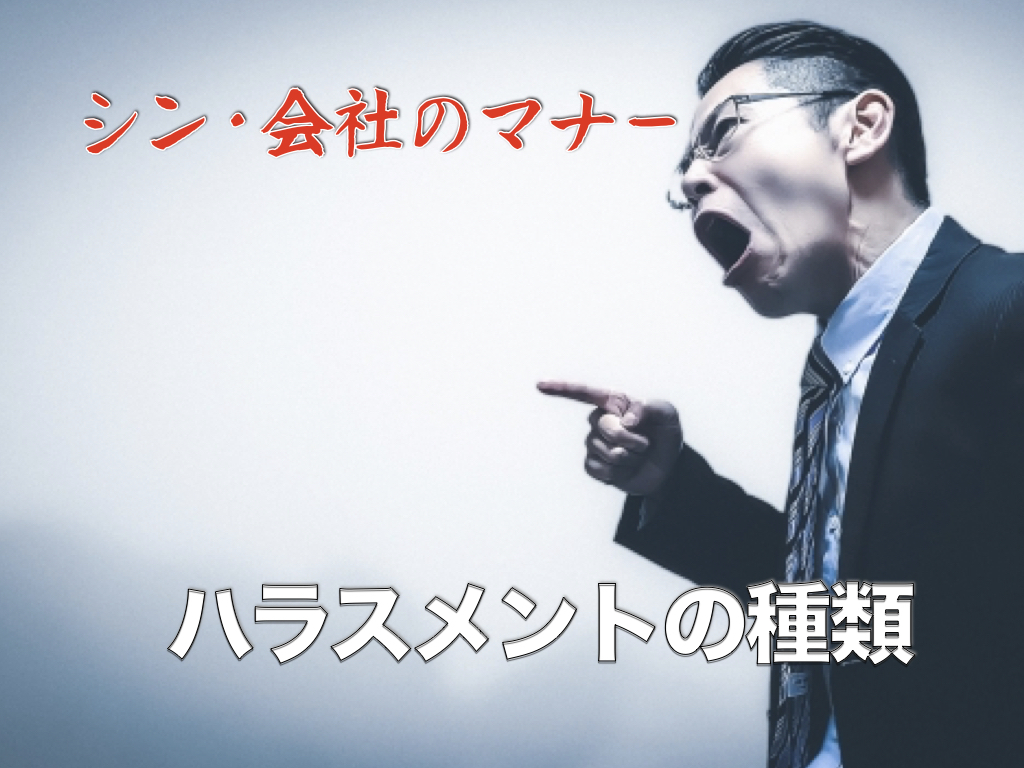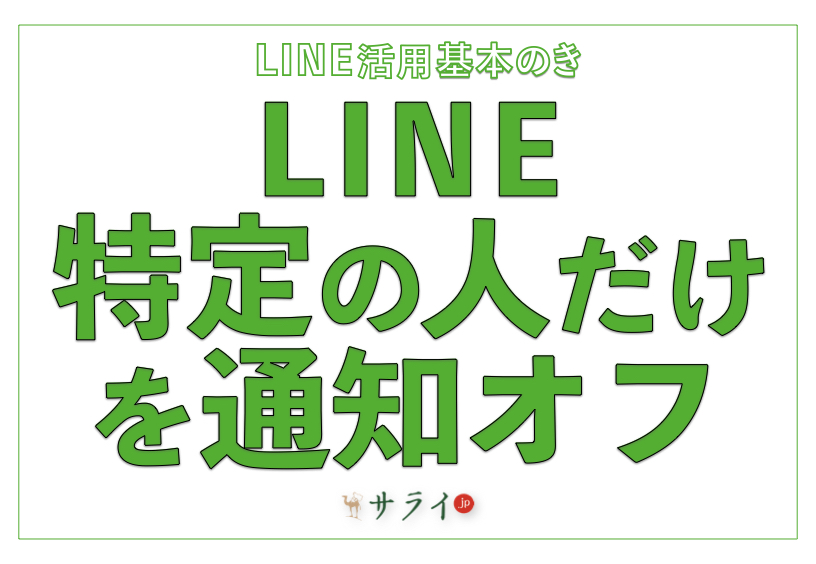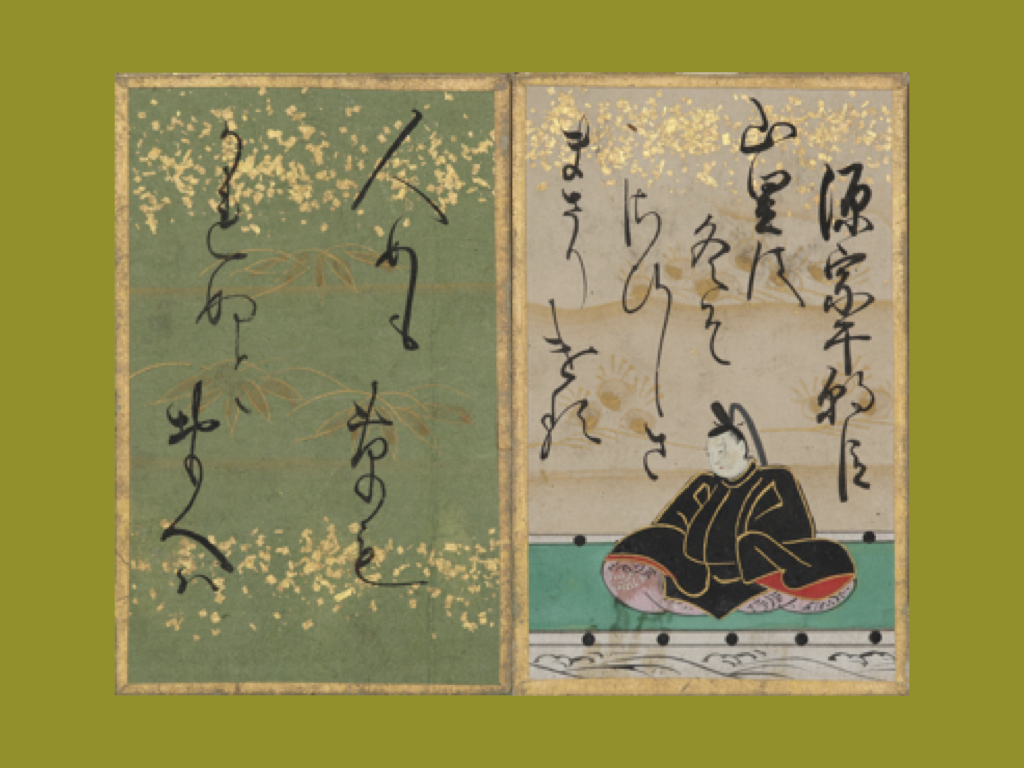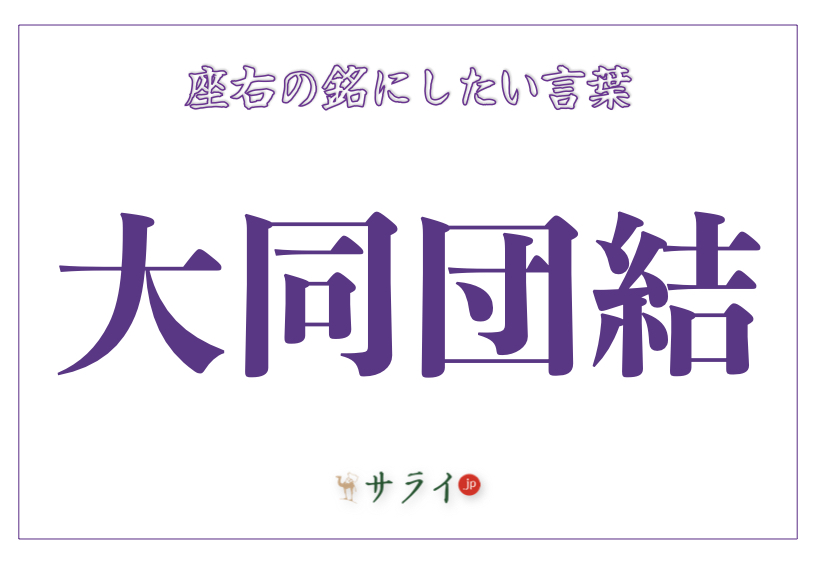多くの会社では就業規則が整備されていると思いますが、それとは別に会社規定が存在する会社もあります。会社規定に違反すると、就業規則違反と同様に処分されるのでしょうか?
今回は、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が、会社規定の基本と法的効力について解説していきます。
目次
会社規定とは? 基礎知識と整備するメリットを解説
規定違反が発生した場合の対応策と法的効力
まとめ
会社規定とは? 基礎知識と整備するメリットを解説
会社規定には、どのようなことが定められているのでしょうか? 最初に会社規定の基本と、整備するメリットについて確認しましょう。
会社規定とは何か? 就業規則との違いを明確に
「会社規定って就業規則とどう違うの?」。そういった疑問を抱く人は数多くいると思います。会社に雇用されて働いている人からすれば、会社の規定も就業規則も大差なく感じるかもしれません。
けれども、この両者には明確な違いがあります。就業規則は、常時10人以上の労働者が働く事業場では、労働基準監督署に届け出ることが労働基準法で義務付けられています。
労働時間・休憩・休日・賃金など、必ず記載しなければならない事項も規定されており、 届け出るときは、労働者の代表の意見を聞かなければなりません。
一方、会社規定は社内のルールであり、会社の裁量で内容を決めることができます。 労使間の合意も特に必要ありません。
会社規定を整備することで得られるメリット
就業規則に必ず記載しなければならない事項は、基本的には労働基準法に準拠して作成することになります。服務規律などの社内で遵守すべき事項も盛り込むことができますが、内容のほとんどが就業に関するルールに限られています。
これに対して会社規定は、会社全般の幅広い内容を任意に定めることが可能です。社内の手続きや業務遂行のルールなどを詳細に決められるので、会社の業務を円滑にし、トラブルを防ぐ面で役に立ちます。
また、会社規定で経営者の方針や企業理念なども示すことにより、社内秩序の維持やコンプライアンス強化などの効果も見込めるでしょう。

最低限整備すべき代表的な規定一覧
広い意味では就業規則は会社規定の中の一部といえます。就業規則は法的な性格がありますが、社内規定は会社独自に定めることができます。一般に重要度の高い規定としては次のようなものがあります。
1.会社組織・役員・経営理念
2.人事考課・社員教育・昇進・賞与
3.社員教育
4.会社の内部情報および個人情報の管理
5.服務規律・出張旅費などの社内規程
6.ハラスメント防止
7.ソーシャルメディア利用規定
8.育児・介護休業などの社内規定
これらの規定のうち、経営理念などは一般に就業規則などには記載されないものですので、会社規定の中で整備しておくことが重要です。
個人情報管理やハラスメント防止などは、今はほとんどの会社で就業規則への記載があると思います。しかし、職場での具体策という点では不十分というケースが多いでしょう。詳細なルールを示すことで、公平で一貫した対応が確保されます。
また、育児・介護休業などは法律で規定されていますが、会社の裁量によってより手厚い対応を定めることも可能です。
規定違反が発生した場合の対応策と法的効力
会社規定に違反した場合、会社はどのような処分をすべきなのでしょうか? 違反の具体例を挙げて、対応策を見ていきましょう。
会社規定違反とは? よくある事例と注意点
会社規定違反でよくあるケースは服務規律、情報の取り扱い、ソーシャルメディアのトラブルなどです。具体的な例としては、服装の乱れや荒い言動などの就業態度の悪さ、内部情報の不適切な管理、SNSで会社や上司の悪口を書くなど。
これらの事例は、法的に罰せられる性質のものではないため、会社は慎重な対応が必要になります。多くの場合、口頭や書面による注意や始末書の提出、人事考課への影響などの対応が見られます。
解雇や減給などの制裁のルールは法律で定められているため、会社規定に違反したからという理由だけでは安易な処分はできません。
規定に法的効力はあるのか? 労働基準法との関係を解説
会社規定は、基本的に法的な効力はありません。一方、就業規則は、労働基準法で届出が必要な条件が規定されています。必ず記載しなければいけない事項も決まっており、労働者の代表の意見聴取も義務付けられています。
法的にも、就業規則は法令、労働協約に次ぐ効力があるとされています。一方で、会社規定は、会社の裁量で決めた独自のルールです。会社の適正な運営のために必要なものであっても、労働基準法などで作成が義務付けられているものではありません。
そのため、就業規則ほどの効力は認められないので、会社規定違反で処分を行なうことは、合理性に欠くと判断されることもあります。

会社がとるべきリスク回避対策
会社規定は社内の様々な取り決めや手続きを明確にし、企業理念から社員教育、労務管理、会計や業務のプロセスなどなど幅広い内容を定めることができます。
会社規定を整備しておくことは、会社の秩序の維持だけでなく、社員が働きやすい環境を作るためにも大変有効です。ただし、基本的に法的拘束力がないという問題点もあります。単なる社内ルールというだけでは、違反があっても十分な対応ができません。
この点をカバーするためには、就業規則と連携していくことが重要になります。例えば、社員の労働条件に関係する内容については、就業規則の記載事項をベースとして詳細な規定を作っていく方法があります。
違反に対する処分などは、就業規則の懲戒規定を基本として決定しましょう。法の下での有効性を備えることによって、会社はリスクを回避することができます。
会社規定と社員教育の重要性
社員教育もまた会社規定の中で重要視されることが多い事項です。会社規定が有効に機能し、社員の満足度につなげるためには社員教育は欠かせません。
社員教育は業務遂行の円滑化や個人のスキルアップだけでなく、社員に企業理念や会社の価値観を伝えるものです。社員教育によって法令順守意識や職場環境の向上を目指す意識が高まり、会社規定違反などを未然に防ぐことができます。
まとめ
会社にとって就業規則は法律上重要なものですが、同時に会社規定を整備しておくことは大きなメリットがあります。会社規定は企業の運営に役立つだけでなく、そこで働く人の労働環境を守るものでもあるのです。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com