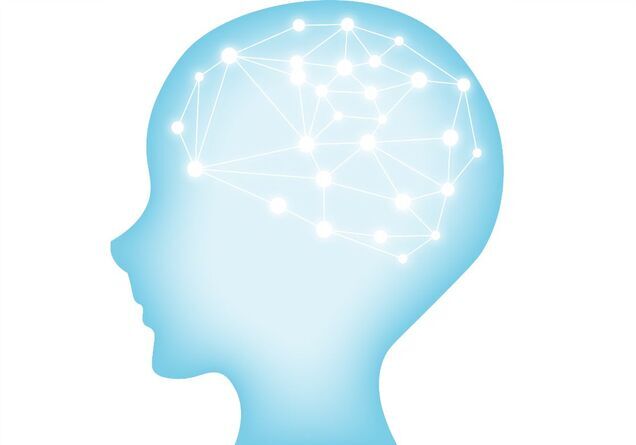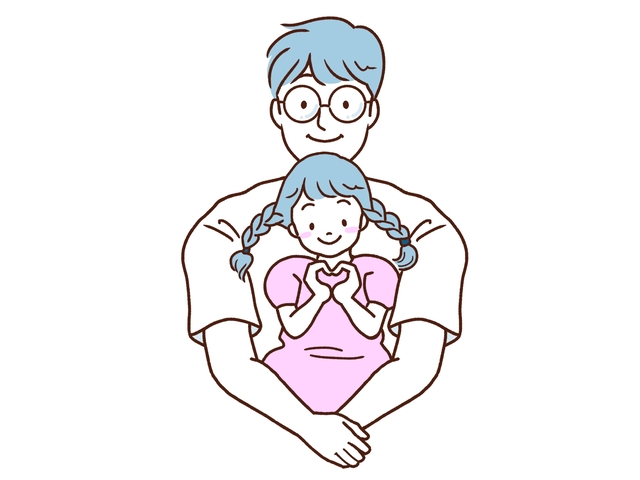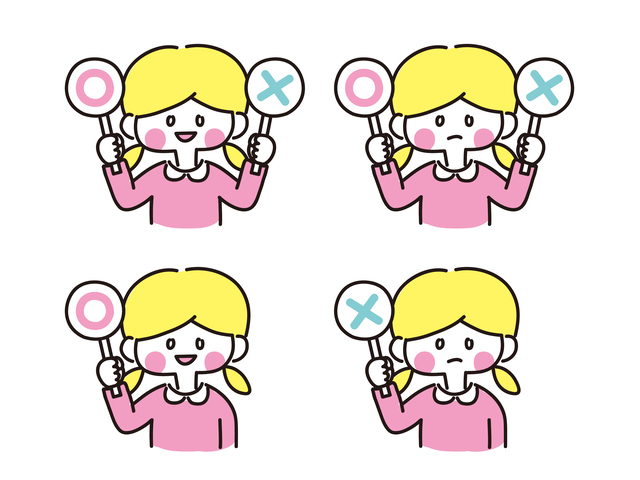13歳〜15歳は「子ども脳」から「大人脳」への移行期であると言われている。そのため、この時期の脳は不安定になりやすく、大人が理解しようとしても難しいことがあると話すのは、脳の仕組みをベースにしたコミュニケーション方法を説く、人工知能研究者・黒川伊保子さん。そんな黒田さんの著書『思春期のトリセツ』から、思春期の脳の傾向を理解した上でのコミュニケーションのコツをご紹介します。
文・黒川伊保子
日本語は「主語なしNO」を言いやすい
思春期の脳の構造について解説する前に、大事なことをひとつ、お伝えしておきたい。思春期のお子さんをお持ちの方に、一分でも早く、このことを知ってほしいから。
それは、「主語なしNO」のこと。大切な人に「主語なしNO」を言ってはいけない。特に、思春期の子どもには、禁忌である。ついでに言えば、部下と倦怠期のパートナーにも言ってはいけない。
「無理」「ダメに決まってるでしょ」「何言ってんの」「バカなこと言ってないで、宿題しなさい」――そんなセリフに覚えがないだろうか。主語をつけない全否定である。
よく子どもに言っている、あるいは、自分が親から言われたことがある。そんな日本人は多いと思う。
日本語は、日常会話の大半に、主語をつけない。英語の「I think(私は思う)」や「I wonder(私は案ずる)」に当たる部分がたいていは省略される。相手を否定するときも、いきなり「無理」「ダメ」を突きつける人は多い。特に、親が子に、上司が部下に。
主語がないから、相手の脳の中では、暗黙の主語がつく。「世間」あるいは「ふつう」である。相手には、「ふつう、無理でしょ」「ふつう、ダメだよね」というふうに聞こえる。つまり、世間を笠に着て、上から目線で、全否定してくるように聞こえるのである。このセリフを言った人が、一秒もこっちの気持ちになって親身に考えてくれてなんかいないのもわかってしまう。
また、いきなりの「ダメ」には、別の主語が付されることがある。「おまえは」である。そう、「おまえはダメなやつだな」と聞こえるわけ。
言ったほうは、「これ(この度のやりかた)」がダメだと言っただけかもしれないが、相手の脳が「おまえは」を補完してしまうのである。これは、生命の与奪権を握られている脳に、自然に起こる補完だ。ひねくれているわけじゃない、生存本能に基づく反射的な反応である。
「主語なしNO」は未来を奪う
だから、上司は部下に、「主語なしNO」を言ってはいけないのである。上司にこれを言われたら、部下の脳は、発想力を失う。自己肯定感が低くなってしまうからだ。このため、このセリフを言う上司のもとでは、けっして豊かな発想は生まれない。20世紀までの企業は、それでよかったのかもしれない。企業が「夢を見る」のはマストじゃなかったから。
20世紀メーカーの使命は、一般消費者が見る夢を実現することだった。冷蔵庫、掃除機、洗濯機、電子レンジ、クーラー、そして自動車は、1970年代の日本の家庭には行きわたっていなかった。市井の人々が、それらがある暮らしを夢見る。その夢を、メーカーは追いかければよかったのである。
2022年の日本には、「一般消費者が想像できるもの」がたいてい存在している。メーカーの存在意義は、「市場の見る夢を、はるかに超える夢を見ること」に集約してきている。アメリカの巨大企業は、それをし続けているように見える。アップルしかり、アマゾンしかり。――それって、もしかすると、「主語なしNO」を言わない文化だからなのでは?
ビジネス英会話の例文を見ていると、相手の意向を否定する際の、言いぶりの丁寧さに気づかされる。言語特性上、必ず主語をつけるし、よく「いいね」受けもする。「斬新なアイデアね。けれど、私には実現可能性が低いように思えるの」「論理的でいいと思う。でも、少しクールすぎないかしら」のように。It’sもつかない、いきなりの「無理」なんて、訳しようもない。
相手の人格を尊重したまま、ことの是非だけを論じる。それが、主語を省略できない英会話の基本スタンスである。こと否定に関しては、英語表現のほうがずっと繊細で、だからこそ言いやすくもある。「主語なしNO」を、日本の企業から、消さなければならない。若い人たちの発想力を削がないために。
いわんや、家庭の中においてをや、である。上司が部下のそれを削ぐ罪より、親が子どものそれを削ぐ罪のほうが大きい気がする。何より、親子関係が快適でなくなるのが残念である。
「目の上のたんこぶ」と「人生の師」、どちらになる?
頭ごなしの否定と、共感受けからの主語つき否定。どちらも、娘のしようとすることに反対しているにもかかわらず、親子関係は180度違ってしまうことに、お気づきだろうか。
娘の選択を、「そりゃ、ダメだろう。無理に決まってる」と阻止する親は、娘にとって目の上のたんこぶになってしまう。思春期に何度かそれをしてしまったら、「人生の選択に、いちいち口を出してくる、厄介な敵」として位置づけられる。大人になって、はるか年月が経ったのちにも、何かあった時には、親の顔を思い浮かべては、「あ〜あ。父さん(母さん)になんて言われるだろう。やだなぁ」と思うことになる。困難にぶち当たっても、親には相談できない。せっかく、自分を愛してくれる、人生の先輩なのにもかかわらず。
一方、娘の選択を、「気持ちはわかる」と受け止めたうえで、「もっと別のアイデアもある」と言ってくれる親は、人生の師(メンター)になる。娘自身の人生をより良いものにするために、共に心を痛め、最善策を考えてくれる支援者に位置づけられる。やがて親を失ったのちも、何かあれば、親の愛を思い出せる。
あなたは、どちらになりたいですか? 疎まれる「目の上のたんこぶ」か、愛される「人生の師」か。
あなたは、子どもにどちらを残したいですか? 苦々しい気持ちか、愛か。
誰もがこう尋ねられたら、何の迷いもなく、後者を選ぶに違いない。
では、こう尋ねられたら、どうだろうか。――あなたは、親にどちらを感じ、どちらを残してもらったのだろう。
きっと、多くの人が、親に一抹の苦々しさを感じ、「目の上のたんこぶ」感を拭えないのではないだろうか。
そう、親である人たちは、子の支援者になり、子に愛を残したいのに、実際には、その逆になっている。あなたの親の世代だって(私はその世代である)、同じように願っているのに。その矛盾を、繰り返してはいけない。
* * *

『思春期のトリセツ』(黒川伊保子 著)
小学館
黒川伊保子(くろかわ・いほこ)
1959年、長野県生まれ。人工知能研究者、脳科学コメンテイター、感性アナリスト、随筆家。奈良女子大学理学部物理学料卒業。コンピュータメーカーでAI(人工知能)開発に携わり、脳とことばの研究を始める。1991年に全国の原子力発電所で稼働した、“世界初”と言われた日本語対話型コンピュータを開発。また、AI分析の手法を用いて、世界初の語感分析法である「サブリミナル・インプレッション導出法」を開発し、マーケティングの世界に新境地を開拓した感性分析の第一人者。著書に『妻のトリセツ』『夫のトリセツ』(講談社)、『娘のトリセツ』(小学館)、『息子のトリセツ』(扶桑社)など多数。