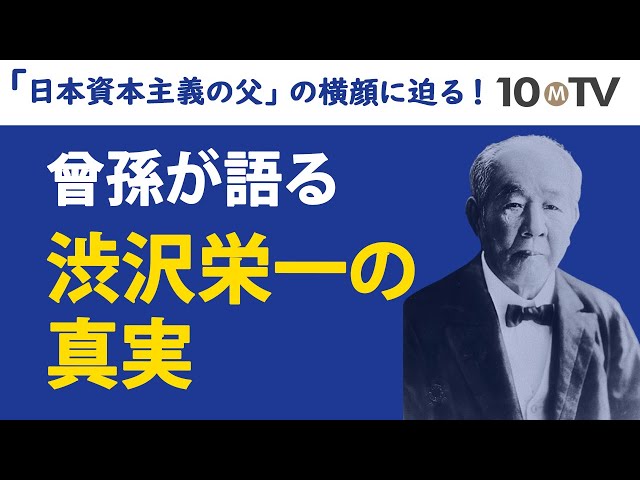クラシック音楽を知れば、生き生きとした「世界史の裏側」もわかる――。
教養動画メディア「テンミニッツTV(https://10mtv.jp/lp/serai/)」の片山杜秀氏の「クラシックで学ぶ世界史」講座では、全13話で、グレゴリオ聖歌からバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンから、ワーグナー、国民楽派、マーラー、20世紀の音楽までを総覧していますが、今回は、ベートーヴェンの時代をピックアップします(その後編です)。
「分かりやすい、うるさい、新しい」、ベートーヴェンの前と後で、音楽は違うものになったといわれています。その理由は、彼が受け取り手である市民の状況と流行に細心な目配りをし、「今、時代が求めるもの」を真摯に追求していったからだといいます。では、ベートーヴェンの「第九(交響曲第9番)」や「フィデリオ」などの作品は、フランス革命後の時代状況をいかに映し出し、いかなるモデルを提示したのでしょうか。
以下、教養動画メディア「テンミニッツTV(https://10mtv.jp/lp/serai/)」の提供で、片山杜秀氏の講義をお届けします。
※動画は、オンラインの教養講座「テンミニッツTV」(https://10mtv.jp/lp/serai/)からの提供です。
講師:片山杜秀(慶應義塾大学法学部教授/音楽評論家)
インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)

フランス革命以後の時代のニーズに応えたベートーヴェン
片山 話が少し遡りますが、ベートーヴェンがそういう人間の感情の発露を意識したのは、やはり1790年代だと思います。ベートーヴェンのピアノソナタに『悲愴』と呼ばれている曲があります。原題はフランス語で“Pathetique”と、自分でつけています。
「悲愴」という訳し方は、悲しみのなかでも凄みのある悲しさということで、その点は当たっていますが、もともとはギリシャ・ラテン語の「パトス」からきているわけで、これは「激しく心が動く」ということです。そういう標題を付けたということは、単に悲しいというのではなく、激しく心を動かす方法に意味があるということです。ハイドンやモーツァルトまでの時代と、フランス革命以後のボンからウィーンに出てきたベートーヴェンが知っている新しい時代では、もはや音楽の表現法が違うということですね。
今までのような幅でやっていても、誰も心が動かなくなってしまった。もっと音楽のボリュームやメロディラインの激しさなどを変えていかないといけない。そういう方法を考えることを、ピアノソナタの『悲愴』あたりから、ベートーヴェンは自覚していたと思うんです。
だから、ベートーヴェンは確かに自身が天才的だったんだけれども、その天才性は、彼がゼロから思いついた独創的なものではありません。自分の世界の中で勝手にやって、「みんな、ついてこい!」と言ったのではなくて、フランス革命以後の時代のニーズに応えたのでした。また、音楽家がフリーランスで生きていくためにはどういう表現を考えたらいいのかということについて一番敏感だったのもベートーヴェンでした。ボンから出てきてウィーンで生き残ろうとした、ある意味では田舎者の彼にとっては、生き残り戦略として最も切実に考えたことだったのでしょう。
しかも、この頃から彼はだんだん耳が悪くなっていきます。使っているオーケストラに「このくらい鳴らせ」と指示するのですが、彼自身がよく聞こえなくなっているので、「これで聞こえているかな」と不安を覚えたりしたのではないか。これは私のやや推測になりますが、そんなことから「強く。もっと強く鳴らしましょう」という感じで、必要以上に激しくなってしまったと思うんです。
これが、かえって良かったんです。その時代の常識の一つ先を行くんだけれども、ちょっと経てばみんながついてくるような過激さがあったわけです。これによって、ベートーヴェンという人は、フランス革命や市民革命期という動乱期を生きることで大勢の市民が新しく身に付けた感性に合致することができた。市民たちはもう貴族や国王の真似をする必要はなく、彼ら自身の聞きたい音楽をベートーヴェンが探求した。そういうかたちで、ベートーヴェンの音楽は説明できると思うんです。
戦争や革命のなかで人々が体験した「殺到」の感覚
――それぞれの時代の求めるところということでは、先ほどの交響曲五番『運命』にまつわる伝説的かもしれない話がありました。あれは、ベートーヴェンお得意の苦しみから歓喜へ向かう曲で、冒頭が「ジャジャジャジャーン」で始まり、最終楽章になると「ドミソファミレドレド」と、「ワァーッ勝ったぞー」みたいな感じで終わっていきます。それがパリで初演されたときに、聞いていた元兵士が「これは皇帝だ。ナポレオン万歳」と叫んだという、伝説みたいな話を聞きました。
片山 『皇帝交響曲』といわれていたという。
――そういう話もありますね。だから、やはり時代的な雰囲気に合っているわけですし、ベートーヴェンは本当に「うるさい」トランペットやティンパニーの使い方も天才的な部分がありますし。
片山 そうですね。
――息継ぎができないというか、休みがなくて、永遠に「ウワァーッ」とテンションが続いていく曲。もちろん静かな部分もありますけど、「うるさい」ところになると、すごい書き込みようです。もう「ウゥーッ」と凝縮して書かれた曲というのが非常に特徴的だと思うんですけど、それは今、先生がおっしゃったような時代性なのですね。
片山 そうですね。やっぱり社会のなかで、あるいは戦争や革命のなかで、特にヨーロッパの中央部の人間が実際に経験した、また、その渦中にいなくても感覚的には理解せざるを得なくなったのが「殺到」ということでしょう。
大勢の人間が殺到したバスティーユ監獄襲撃がフランス革命の象徴的事件ですが、ナポレオンの国民軍もそういうものがヨーロッパ中に攻めてくる感じとして捉えられました。とにかく何か秩序からはみ出すような余剰というか、騒音的・雑音的なものを含めたものが殺到してくるということです。
大砲の爆撃に負けない「うるささ」を演奏会で実現
片山 そういうテンションを演奏会用の音楽で表現しようと思った場合には、前回の話題にしたように、フランス革命によって発達した野外の軍楽隊に始まる吹奏楽が一つの方法でした。フランス国民軍は、そういう軍楽隊を連れ歩いて、ヨーロッパ中にやってきた。それはまさにオスマン帝国が軍楽隊を引き連れ、トルコ行進曲と一緒に世界のあちこちを侵略して回ったのと同じような現象です。強圧的な軍楽隊の響きとともにフランス軍がやってくるという経験の大きさですね。
ハイドンは亡くなる間際、フランス軍がウィーンを包囲して大砲を撃った時にびっくりしたあまり寿命が縮んだといわれています。ハイドンもロンドン時代はいろいろな工夫をしましたが、それでも彼が常識としてわきまえ、許容した範囲にはなかった音が、大砲の「ボカン、ボカン」にはあったわけですね。
大砲も、ちょうど発達している時代です。フランスを先駆けとして、争うように大砲の規格が向上し、大量生産されていきます。性能も射程距離もどんどん向上していくため、撃つときの音の大きさも、みんながビックリしてしまうぐらいに増してくる。そういう感覚に合わせながら、それを野外で経験しているのに負けないぐらい、演奏会として、ホールの中で成立させる必要があったのです。
当時、普通のホールはそれほど大きくなかった。そんな場所で、大群衆が殺到したり、大きな軍隊が戦っているような音響を実際に体験している聴衆を非日常に誘い込むには、別に戦争の模倣じゃなくてもいいのですが、どういうタイプの音楽にせよ、よほど刺激を与えないといけません。
そういう工夫をベートーヴェンはして、金管楽器の数も増やしていったし、野外の音楽じゃないと使わなかったような楽器を交響曲の楽器編成に入れてくる。例えばトロンボーンなどは、それまで演奏会にはあまり入れないように思われていた楽器でした。
つまり、貴族や王族などが楽しんでいた室内オーケストラの響きと、フランス革命以後、とくにヨーロッパ中で経験されてくる野外の吹奏楽的な響きを大きな演奏会場の中に融合させようという試みが、ベートーヴェンの交響曲などの編成やオーケストレーション、押しの強さとか、単純にいうと「うるささ」となりますね。
師のハイドンが発見した「合唱」による高揚
片山 あと、もう一ついえば合唱です。合唱は、ヘンデルやバッハのバロック時代、つまり18世紀前半のロンドンにおいてすでに非常に好まれ、大合唱が愛好されました。合唱クラブに入っていることがブルジョワのステータス・シンボルになっていたのです。
ハイドンは、ロンドンに行った時にこの習慣に出会って驚きます。「ハプスブルク帝国では、こんなに大勢がみんなで歌うような合唱はないんだけど、ロンドンでは盛んなんだ」、と。当時はハプスブルク帝国も、商業的・経済的にまだまだ発達していく時代なわけですから、ウィーンの市民を動員して大きな合唱を行うのはアリだと気づきます。
今まで教会音楽でやっていたようなものを、もう少しそうではないかたちにし、テキストも少し俗っぽくして、大勢の合唱とオーケストラで、みんなで歌いましょう、と呼びかける。そのためにハイドンは、聖書ネタの『天地創造』や、ドイツ・オーストリアの農民の一年を織り込んだ、世俗的な『四季』と題するオラトリオを作曲します。
このような大合唱とオーケストラを使った音楽というものは、師のハイドンがロンドンから学んできたものだったのです。ですから、戦争や革命と結びつけなくても、市民社会が発達すれば合唱は発達します。
これがフランスにおいては、革命の名残で『ラ・マルセイエーズ』などが皆で好んで合唱するところになった。これによりナショナリズムが高まる。大合唱による高揚というものが、ロンドン発では「市民の連帯」になったのが、パリ発では「国民の連帯」になったわけです。いずれにしても大合唱というものは、重要なファクターとして働きました。
この大合唱をどのようにクラシック音楽の演奏会の世界に取り込んでくるかということが、ベートーヴェンにとっての大きな仕事になります。
「群衆を主人公」に流行を追求したベートーヴェン
片山 ベートーヴェンは、オペラとしては『フィデリオ』という作品を残しています。もちろんオペラなので登場人物がいて、主役級の人たちもいるんだけれども、これは実際に聴けばすぐに分かります。要所要所で、独唱以上に合唱が目立ち、ほとんど「合唱団のオペラ」なんじゃないかというような作品です。合唱ばかりが主役の歌手を食って、最後の華も持って行ってしまうようなもので、つまりは「群衆が主人公」という考えですね。個人というんじゃなく、国民や市民が主人公で、大きな人数が主役になる時代になったということです。
これが演奏会用の曲として結実すると、『ミサ・ソレムニス』という宗教曲と、世俗的な音楽としての交響曲第九番になる。これで、もう「みんなで歌おう」ということになるわけです。これが市民の歓喜の連帯の大合唱であり、しかも世俗的なものだということで、ナショナリズムを超えた世界平和のメッセージにもなる。だから今でもEUの歌は、あの「歓喜の歌」です。
だからベートーヴェンは、まさに市民社会、市民革命、それに伴う戦争などのある意味暴力的な経験、それから産業革命になって、機械や大砲で音がうるさくなっていく時代などの全てに対応する最適モデルを編み出しました。それが、大音量、楽器編成の変更、大人数、そしてテンションが高い、というものです。こういうかたちの理想形にまで、一代にして到達してしまったのです。これを考えると、やはりものすごい人です。
だからベートーヴェンの後の作曲家は、やることに困ってしまうといわれるわけですね。
――(ベートーヴェンは)一つの到達を一人でやってしまったということですね。
片山 そうですね。やっぱりベートーヴェンという人は驚くべき人なんだけど、でも、それはベートーヴェン個人がすごかったんじゃなくて、冒頭に言ったように、ベートーヴェンがいかに時代のニーズによく応えようとしたかということです。まさにこの人は「広告代理店なのか」というぐらい、真面目に流行を追ったことがベートーヴェンのすごさだったと思うんです。
1話10分の動画で学べる「大人の教養講座」テンミニッツTVの詳しい情報はこちら
協力・動画提供/テンミニッツTV
https://10mtv.jp/lp/serai/