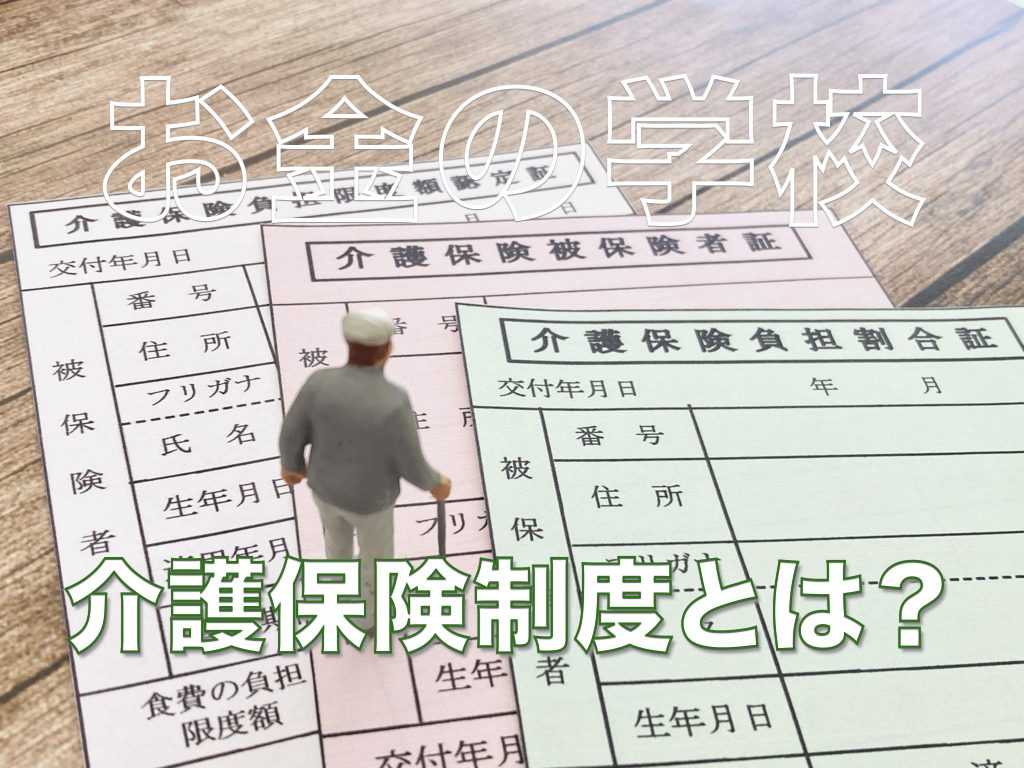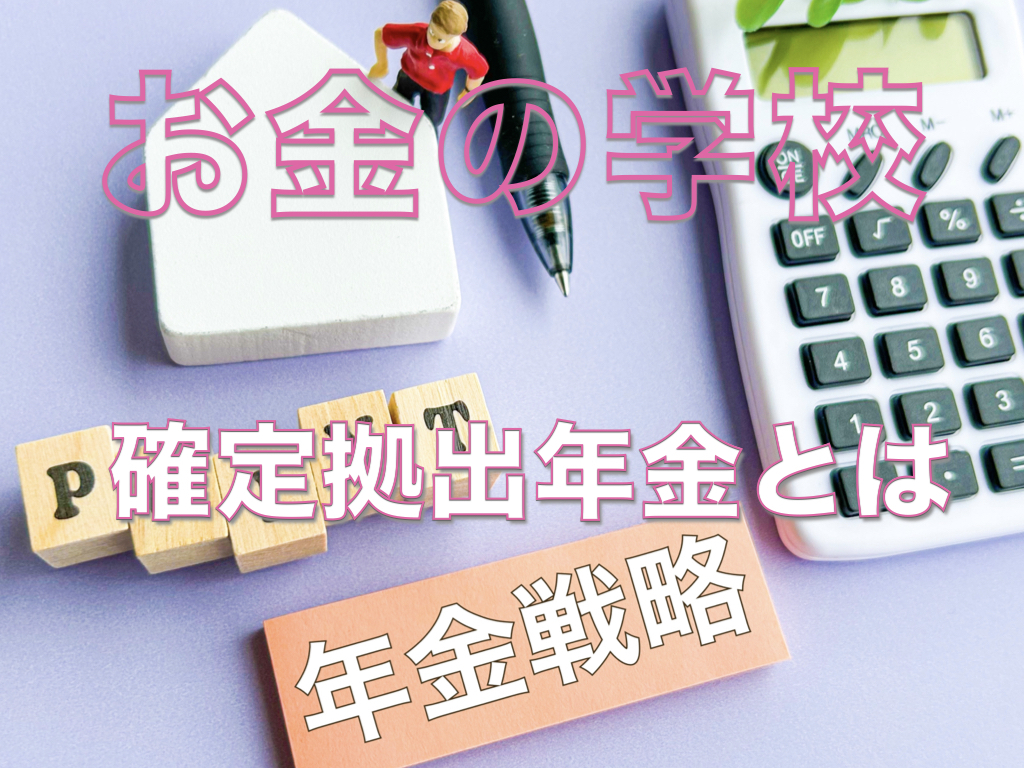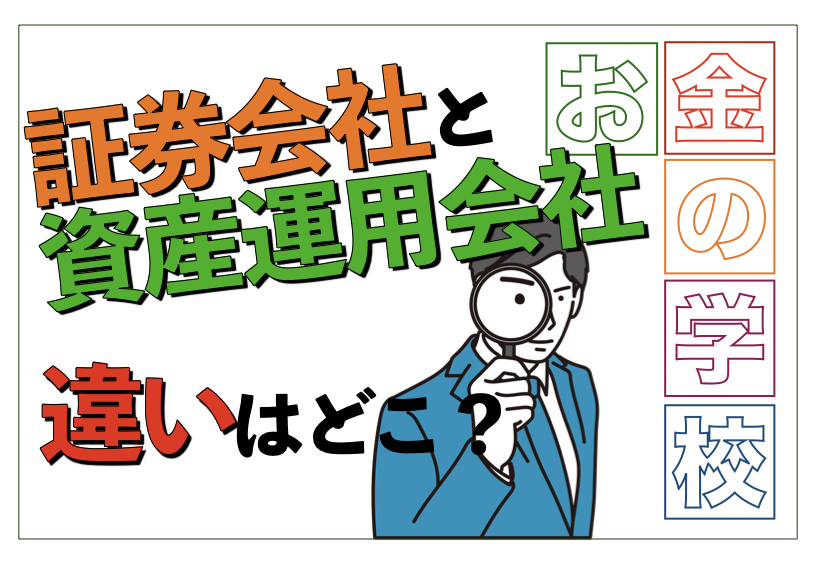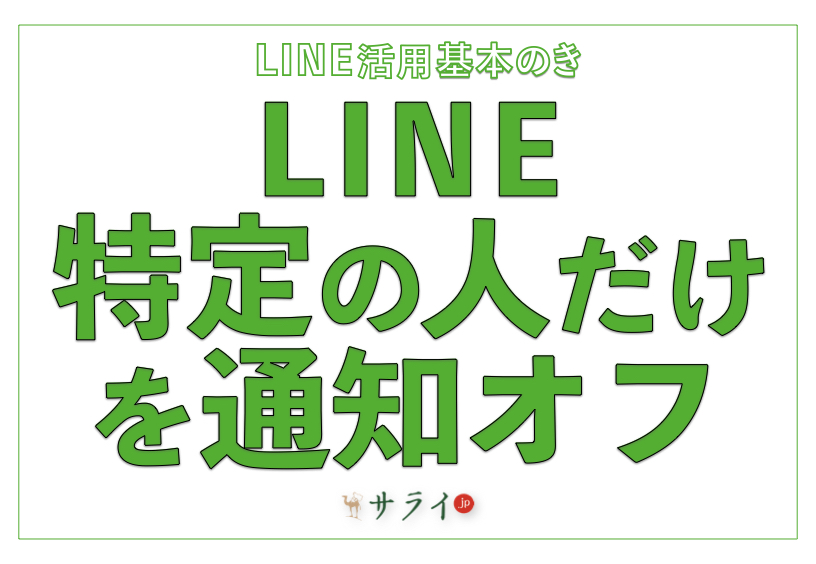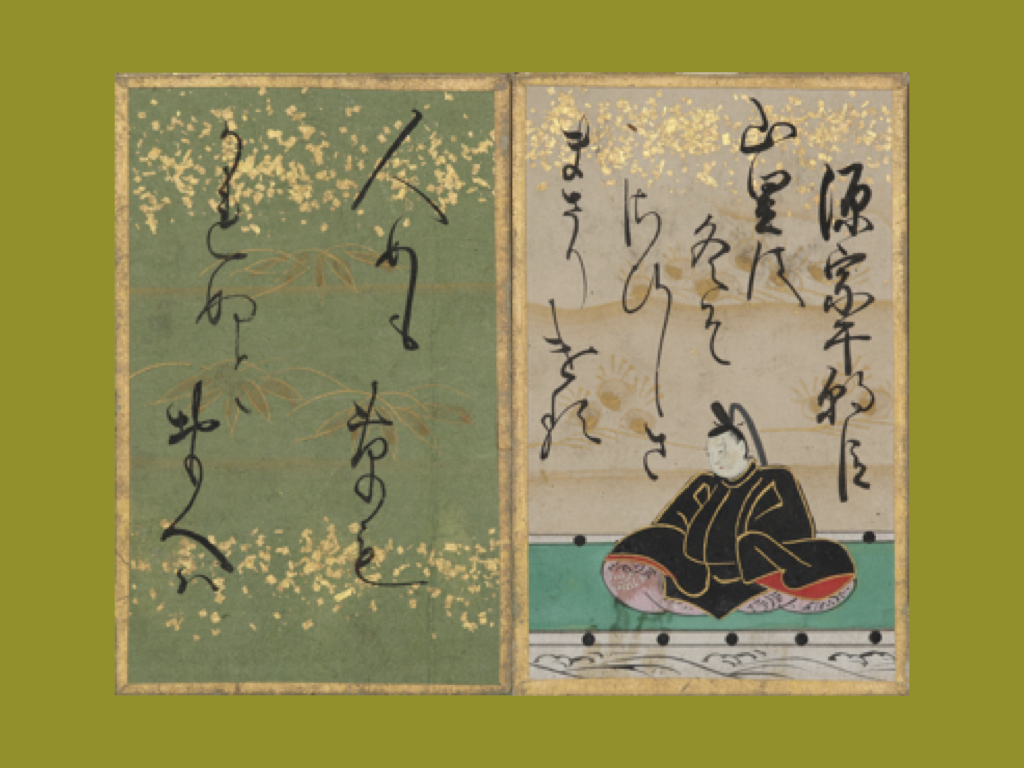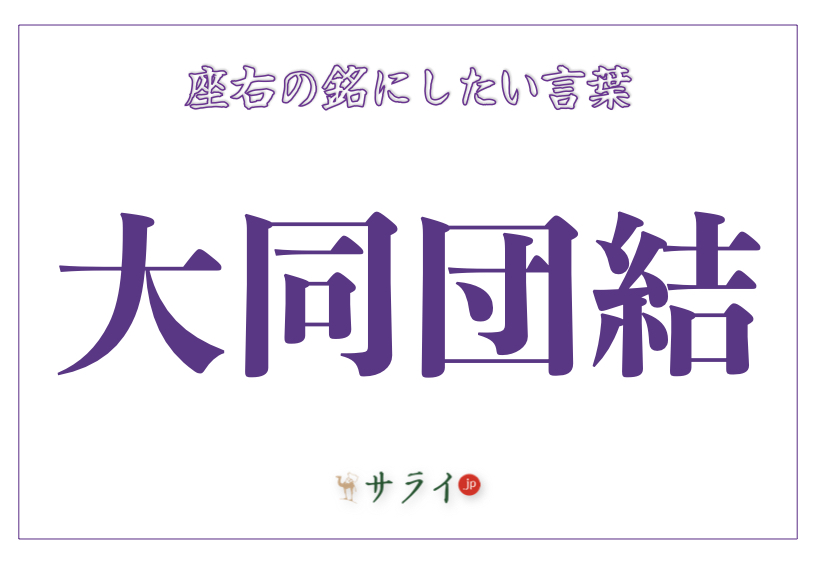介護というと、健康な人にとっては「まだ先のこと」と感じる方も多いかもしれません。しかし、超高齢社会となった現在では、介護は誰にとっても身近な問題となっています。
一般的に、介護が必要になると、介護を「する側」も「される側」も大きな負担を抱えることになります。そうした負担を少しでも軽減するために設けられているのが「介護保険制度」です。今回は、その「介護保険制度」の基本的な仕組みや利用方法について、分かりやすく解説していきます。
100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。
目次
介護保険制度とは? わかりやすく基本を押さえよう
2024年の介護保険制度改正|何が変わった? 押さえておきたいポイント
介護保険制度の目的と課題|知っておきたい現実
まとめ
介護保険制度とは? わかりやすく基本を押さえよう
介護保険制度とは、高齢者や一部の介護を必要とする人が、要介護・要支援状態になったときに、必要な介護サービスを受けられる公的な社会保険制度です。はじめに、介護保険制度の基本について見ていきましょう。
介護保険制度はいつから始まった? 背景と歴史
介護保険制度は、少子高齢化が進む中で高齢者の介護を社会全体で支える仕組みを作るために創設され、2000年4月に施行されました。それ以前の日本では、家族が高齢者の介護を担うのが一般的で「介護=家庭内の問題」とされてきました。
特に女性(嫁や娘)が主な介護者となるケースが多く、肉体的・精神的・経済的な負担が大きな社会問題となっていました。また、要介護状態の高齢者は長期間にわたって医療機関に入院するケースが多く、「本来は医療より介護が必要な状態で、病院に入院し続けること」が医療費の増加や病床のひっ迫を引き起こしていました。
こうした背景の中で「高齢者の介護は家族ではなく社会全体で支えるべきである」という考え方が広がり、1997年に「介護保険法」が成立し、準備期間を経て2000年4月から本格的に制度がスタートしました。この制度によって、高齢者やその家族の負担が軽減されただけでなく、介護サービスの質や選択肢の向上、介護業界の整備といった社会全体の変化ももたらされています。

介護保険制度の仕組みと役割
介護保険制度は、原則として40歳以上の人が、介護が必要になったときに、安心して介護サービスを受けられるようにする公的な制度です。ここではその仕組みと役割について解説します。
介護保険制度の仕組み
・対象者(加入者)
介護保険には、年齢によって以下の2つの被保険者区分があります。
1.第1号被保険者(65歳以上)
第1号被保険者は、原則として65歳以上のすべての人が対象です。要介護・要支援の状態になれば、原因を問わずサービスを受けることができます。
2.第2号被保険者(40歳〜64歳)
第2号被保険者は40歳〜64歳の人が対象です。加齢に伴う16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り介護サービスを利用できます。
・保険料の支払い
介護保険の財源は、加入者からの保険料と公費(国・都道府県・市区町村の税金)でまかなわれています。保険料は40歳から支払いが開始となります。
・運営主体(保険者)
介護保険は市区町村が運営主体となっており、介護サービスを必要とする人は、市区町村が設置する窓口に申請します。
・サービス利用の条件
介護サービスを利用するには、市区町村に「要介護(または要支援)認定」の申請をし、認定を受ける必要があります。この認定には「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階があり、認定された区分によって利用できるサービスの内容や量が異なります。
・ケアプランの作成
認定を受けた後、ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人の状態や希望に応じた介護サービスの計画(ケアプラン)を作成します。
・自己負担
介護保険のサービス利用者は、サービス利用料の原則1割(所得により2割または3割)を自己負担します。残りは介護保険から給付されるため、費用の負担が軽減されます。
介護保険の役割
介護保険の役割は、高齢者やその家族の経済的・精神的な負担を軽減し、必要な人が必要なときに、適切な介護サービスを受けられるようにすることです。高齢化が進む現代社会において、介護を家族だけの問題とせず、社会全体で支える仕組みとして、介護保険制度は設けられました。
これにより、介護を「家庭内の責任」から「地域・社会全体の課題」へと転換することで、持続可能な介護福祉の実現を目指しています。
民間の介護保険との違い
民間の保険会社でも「介護保険」などで介護に関する保障を提供していますが、公的な介護保険制度とは目的や内容が異なります。公的な介護保険制度は、「介護サービスの提供」が中心で、必要なサービスを受ける仕組みです。
一方、民間の介護保険は「介護にかかる費用」を保障するもので、介護状態になった際に一時金や年金形式で保険金が支払われるのが一般的です。公的制度ではサービス利用時に自己負担が発生しますが、民間の介護保険を組み合わせることで、金銭的な負担の軽減が期待できます。将来に備えて、併用を検討してみるのもいいでしょう。

2024年の介護保険制度改正|何が変わった? 押さえておきたいポイント
2024年は、介護保険制度が大きく見直される年となりました。少子高齢化の進行、財政負担の増加、地域での介護ニーズの多様化などを受けて、制度の持続可能性を高めるための改正が行なわれています。
2024年の改正では、福祉用具の給付や居宅介護支援の見直しなど、利用者と事業者の双方に影響のある変更が含まれており、しっかりと内容を把握しておくことが重要です。
2024年改正の主な変更点|福祉用具・居宅介護支援など
2024年の介護保険制度改正での注目点は、次のようなポイントがあります。
福祉用具の貸与・販売に関する見直し
軽度者(要支援・要介護1)への福祉用具利用について、給付の対象が見直されました。利用の実態や必要性を踏まえて「真に必要なもの」への支給に限定する方針が明確になっています。
居宅介護支援(ケアマネジメント)の費用負担
これまで全額保険でまかなわれていたケアマネジャーによるケアプラン作成費に、自己負担を導入することが検討され、段階的に実施される方向となりました。利用者にとっては、サービス選択に関わる費用意識が必要になります。
その他の見直し
上記の見直しの他に、「訪問介護の基本報酬の調整」や「地域包括ケアシステムの推進に伴う体制強化支援」など、サービスの質と効率性の向上、財源の適正配分を目的とした見直しも行なわれています。
なぜ改正される? 制度見直しの背景
介護保険制度は2000年のスタート以来、少子高齢化の進行に伴って利用者数・給付費ともに年々増加しています。特に2025年には、いわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上となるため、介護ニーズの急増と、それに伴う財源確保の課題がより深刻化することが見込まれています。
また、ケアプランの乱立や福祉用具の過剰給付など、制度の不適切な利用や運用のゆがみを是正する必要性も高まっています。そのため、2024年の改正では、「真に必要な支援」へと資源を集中させ、制度の持続可能性を確保することが重視されています。さらに、限られた人材・財源の中で、地域社会における高齢者の自立支援や効率的なサービス提供体制を整えるには、制度の定期的な見直しが不可欠とされています。

介護保険制度の目的と課題|知っておきたい現実
2000年に始まった介護保険制度は、「高齢者の介護を社会全体で支える」という理念のもと設けられました。制度の導入により、介護は「家族だけの責任」から「地域や社会全体の支援」へと転換され、多くの高齢者が安心して暮らせる環境が整いつつあります。
しかし、制度開始から20年以上経過した現在、急速な高齢化や人手不足、財政負担の増加など、さまざまな課題が浮き彫りになっています。ここでは、介護保険制度の本来の目的を振り返るとともに、直面している現実と今後の見通しについて解説します。
介護保険制度の目的とは? 「自立支援」と「負担の公平」
介護保険制度には、主に2つの目的があります。
自立支援の促進
介護保険は、介護を受ける人ができる限り自分らしく暮らせるようにサポートすることを重視しています。訪問介護やデイサービスなどで、生活機能を維持・改善し、要介護状態の悪化を防ぐことを目指しています。
負担の公平性の確保
介護は家族だけが負担するのではなく、保険料や税金を使って、社会全体で支える仕組みです。これにより、誰でも公平に介護サービスを受けられるようになり、介護する側・される側双方の負担軽減につながっています。このように、「自立支援」と「負担の公平」は、制度を支える2本柱として位置づけられているのです。
今後の課題と見通し|財政負担・サービス不足への懸念
介護保険制度は、高齢者にとって欠かせない社会保障制度となりましたが、今後に向けて大きな課題も抱えています。
財政負担の増大
高齢者の増加とともに介護費用も増え続けており、保険料や税金の負担も重くなっています。制度の持続性を保つには、見直しや効率化が必要です。
介護人材・サービスの不足
地方を中心に、介護職員の人手不足や、必要なサービスが受けられない「介護難民」の増加も深刻な問題です。介護の質を確保しつつ、安定的にサービスを提供する体制づくりが急務となっています。
今後の見通し
国は地域で支える「地域包括ケアシステム」や、ICT(見守りセンサーやオンライン面談など)・介護ロボットの活用を進めています。とはいえ、「人」と「お金」の確保は引き続き大きな課題です。今後も制度の動きに注目し、備えることが大切です。
まとめ
介護保険制度の内容は、介護が身近でない人にとってはあまり知られていないのが現状です。しかし、自分や家族などが将来介護を必要とする可能性を考えると、あらかじめ制度を理解しておくことが大切です。介護が必要になる前に、介護保険制度の仕組みや利用方法を知っておくことで、安心して備えることができます。
資産運用や投資のアドバイスは、今や銀行などの金融機関の窓口でもさかんに行なわれています。しかし、それらのアドバイスは本当にあなた自身に適したものなのでしょうか?
さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。
●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)
●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)