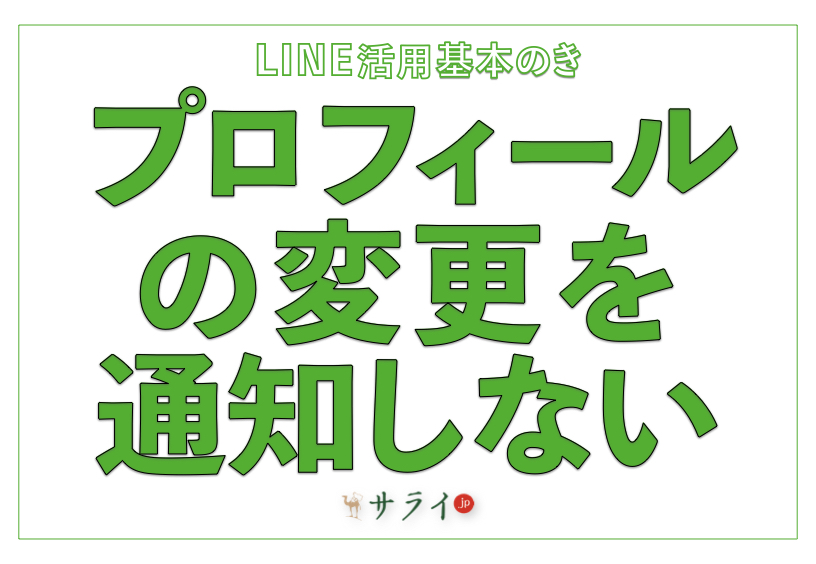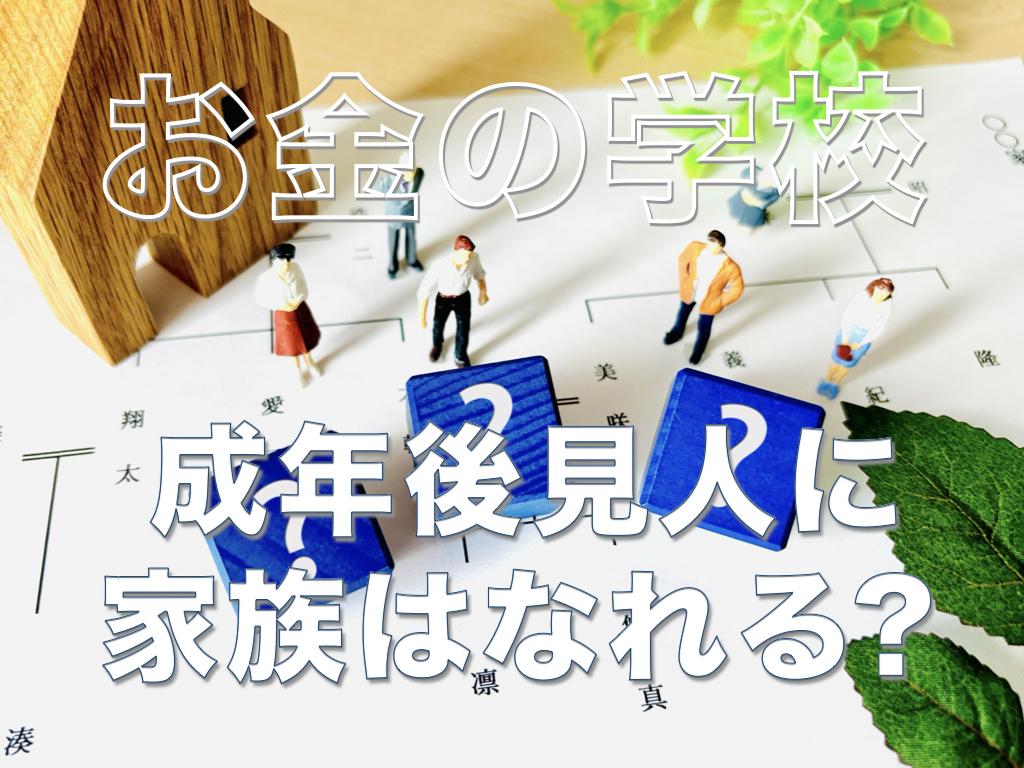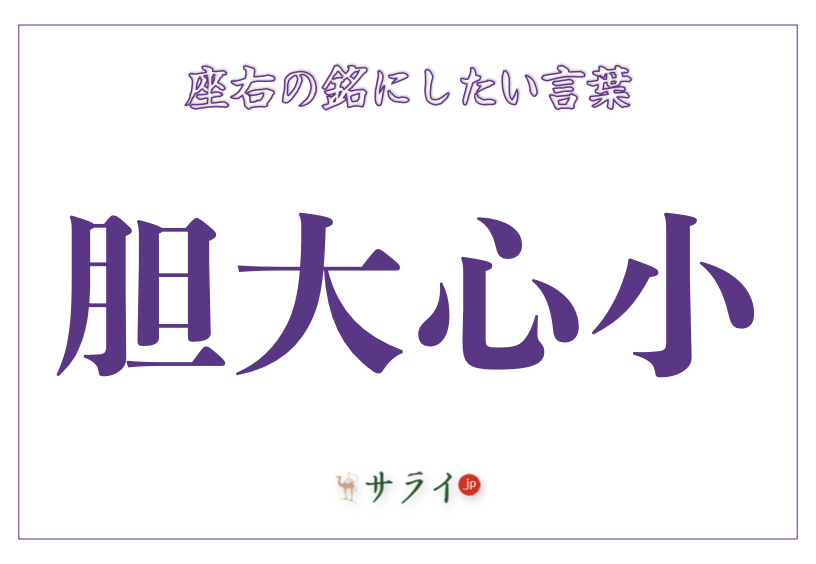黄表紙の再発掘
I:さて、蔦重ですが、おもしろいけれど古いから摺っていない黄表紙の板木を安く売ってもらって仕立てなおして売るという作戦にでました。これがけっこう受けるわけですから、凄いですよね。意外と現代でも通用するかもしれない作戦ですよね。
A:そうかもしれません。目利きがいれば、再発掘もありですね。
I:それにしても、須原屋(演・里見浩太朗)が嘆いていましたが、お上の力って凄いですよね。黄表紙、狂歌、錦絵もすっかり力を失っていきます。
A:市井の人々がお上の施策について、嘆いているなかで、松平定信は、側近の水野為長(為永/演・園田祥太)の「新作の点数はグッと減りましてございます。中身も黄表紙は教訓的に、狂歌は格調高いものが多くなりましたかな。錦絵は相撲絵、武者絵などが流行り。殿の望み通りの流れになってきておりますな」という報告を受けています。
I:なんだか、そういう報告を受けていますけれども、定信、本心では、辛いような雰囲気じゃないですか?
A:この水野為長という男ですが、松平定信の少年期から側に仕えています。前週紹介した『宇下人言』の定信14歳のときのエピソードで、怒りっぽい定信を諫めていたという側近のひとりが水野為長です。
栃木の豪商と歌麿
I:江戸から下野の豪商のもとに転じた喜多川歌麿(演・染谷将太)は、釜屋伊兵衛(演・益子卓郎)の口利きでどんどん肉筆画の仕事が入ってきていました。歌麿が描いた襖絵の前に金持ちたちが集まって、綺麗どころも呼ばれ、歌麿の絵を鑑賞している場面が描かれました。歌麿も綺麗な身なりで、先生然としている様子が印象的でした。
A:地方の豪商を「谷町」にできるのは才覚でしょう。実際に釜屋さんはかなり力のある商人だったようですから。この栃木の豪商は栃木出身のお笑いコンビ「U字工事」の益子卓郎さん(釜屋伊兵役)と福田薫さん(喜兵衛役)が演じているわけです。私はせっかく栃木弁のネイティブスピーカーをキャスティングしているわけですから、もっとコテコテのそれこそ、津軽弁に字幕がつくような栃木弁を展開してほしかったですね。
I:当時の方言は、なかなか聞き取りできないほどだったといいますものね。さて、歌麿と生臭坊主のやり取りがおもしろいけど、ちょっと切なかったです。生臭坊主が「先生、次はぜひ、ウチの寺に艶めかしい弁財天でも」というと、先生と呼ばれた歌麿が「いいんですか? 私はなかなか罰当たりですけど」と応えました。
A:現代もそうですが、地方の「豪商」ってすごいですよね。生臭坊主もお笑いコンビ「どぶろっく」の江口直人さんが演じています。

吉原で遊ぶ金がないからといって……
I:さて、劇中では、市井の美人に人気が集まる様子が描かれました。不景気で吉原で遊ぶ金がないっていうのが理由のようです。
A:お上がいろいろ締め付けてきたら、庶民は、どんどん新たな知恵をだしてくるんですね。
I:市井の美人人気に加えて、いわゆる「人相」の流行。このふたつに蔦重が目ざとく食いつき、新たな本を作ってしまいます。
A:これを機に歌麿が江戸にもどってきますが、人の性格を判じる人相本を出した蔦重が、話して歌麿の気持ちを読み切ることはできるのでしょうか。
I:栃木で先生、先生ともてはやされた歌麿、江戸にもどってきて今度こそ幸せになれるのでしょうか。うたまろーって、切なくなってしまいます。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり