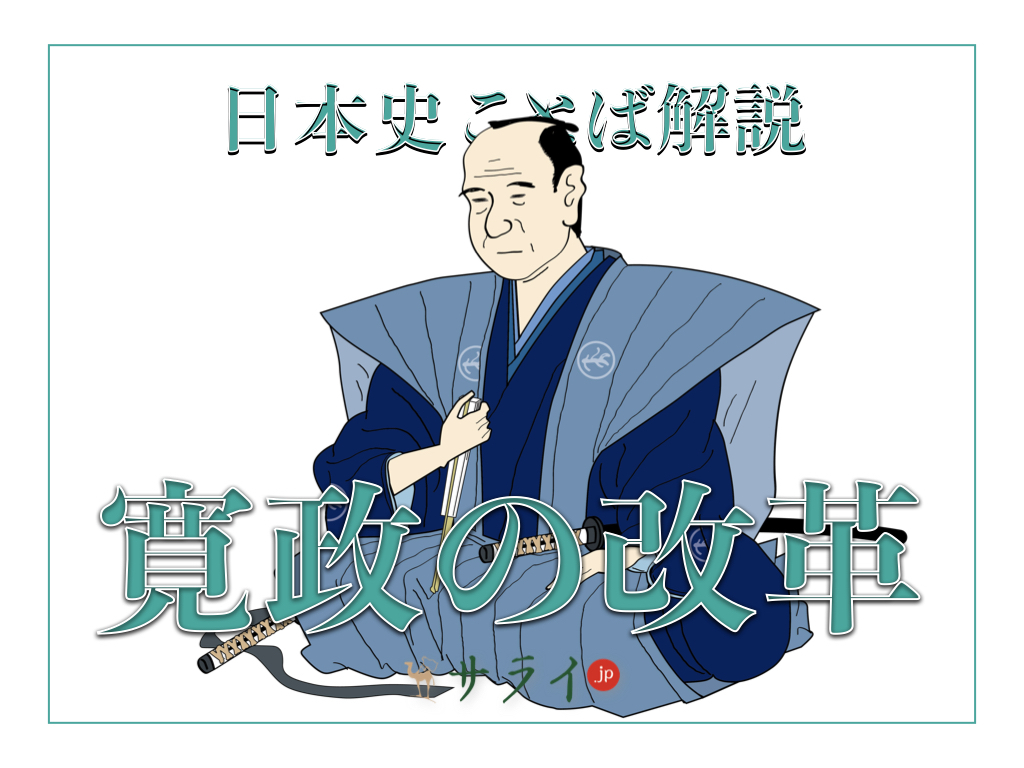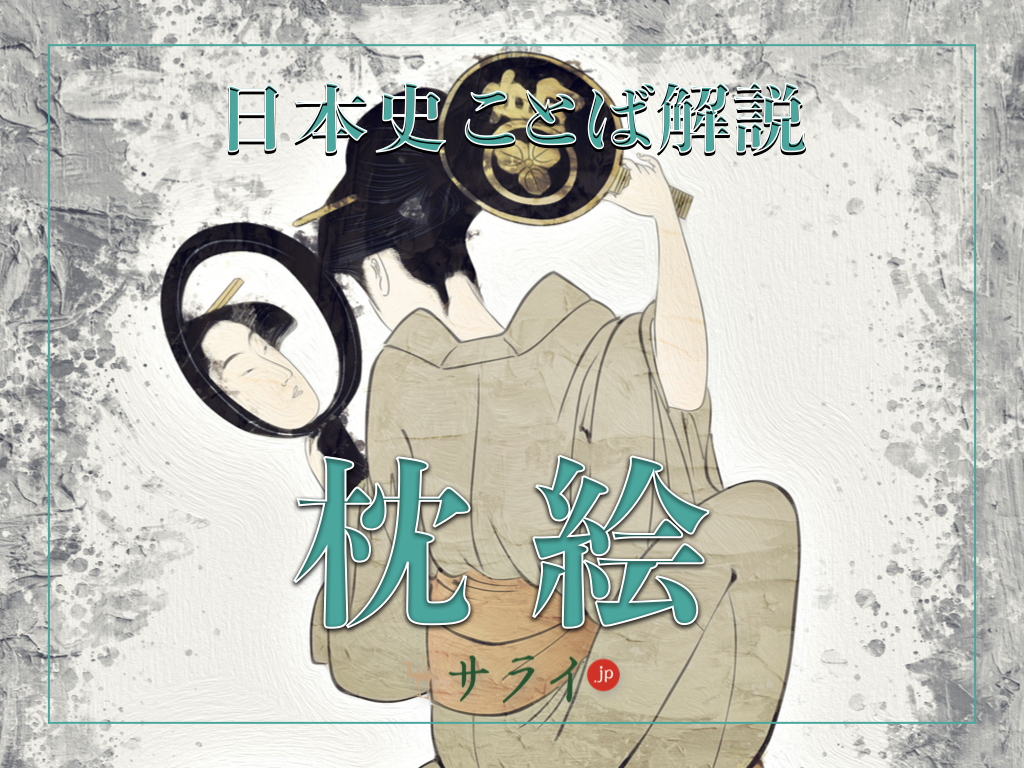大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。
しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?
【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、“大河ドラマ”や“時代劇”に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。
さて、今回は「寛政の改革」という言葉をご紹介します。この記事では、この大改革の内容と、江戸の人々にどのような影響を与えたのかを解説します。

「寛政の改革」とは?
「寛政の改革」とは、天明7年(1787)から寛政5年(1793)の6年にわたり老中・松平定信が主導した、江戸幕府の政治・経済・社会制度の大改革のことです。享保の改革、天保の改革と並び、「三大改革」のひとつに数えられます。
前任の老中・田沼意次による重商主義政策は、一時的な財源拡大をもたらしたものの、賄賂と癒着、農政の放置により幕府財政は逼迫。さらに天明の大飢饉や都市打ちこわしの多発が追い打ちをかけ、社会は混乱を極めていました。
松平定信は、8代将軍・徳川吉宗の孫にあたる人物。その血統と将軍家斉の後見人である一橋治済の推薦を受けて老中に就任し、財政再建・農村振興・風紀粛正・社会秩序の回復を柱に改革を断行しました。
「寛政の改革」の社会的・経済的な意味
寛政の改革の本質は、「社会の根本から立て直すこと」にありました。
特に重視されたのが、農業と農村の再生です。農民の出稼ぎを制限し、農村に戻らせる「旧里帰農奨励令」や、種籾・農具代の貸付制度、飢饉に備えた籾蔵の設置などを通じて、本百姓層の維持・復興が図られました。
また、都市政策では、窮民対策として「七分積金令」による町会所資金の積立、石川島人足寄場の設置など、下層社会の安定化を目指しました。さらに、物価高騰を抑えるための流通統制、米価の操作なども実施されました。

写真は、石川島灯台。
金融政策では、旗本・御家人の借金帳消しを行う「札差棄捐令」を発令し、同時に猿屋町貸金会所を設けて札差に融資を行い、市場の混乱を防ぎました。
一方、思想・出版面では「異学の禁」を出し、朱子学以外の学問や風俗を乱す出版物を取り締まるなど(出版統制令)、情報・教育の統制を強化。これらは、幕府に忠実な官僚層の育成と統治秩序の強化を意図していました。
「寛政の改革」を行った結果
寛政の改革は、財政面では幕府の赤字を黒字に転じさせ、備金も生じる成果を上げました。また、町会所や石川島人足寄場といった制度は、幕末まで継続されるなど、長期的に見ても一定の功績を残しました。
しかし、生活に直接関わる倹約令や物価統制、思想弾圧などは、庶民や武士階級からの反発を招くことにもなります。
その象徴が、有名な落首「白河の 清きに魚も 住みかねて 元の濁りの 田沼恋しき」。
改革の清廉さがかえって息苦しさを生み、定信は寛政5年(1793)に老中を退任。とはいえ、その後も定信とともに寛政の改革を推進した松平信明をはじめとした「寛政の遺老」と呼ばれる幕閣たちにより、改革の理念や制度は文化期(19世紀初頭)まで引き継がれました。
まとめ
「寛政の改革」は、ただの倹約や規制の強化ではありませんでした。農村の再生、都市の安定、金融の整備、思想の統制──江戸という大都市と日本社会を立て直すための包括的なプロジェクトだったのです。
大河ドラマ『べらぼう』に描かれる江戸の賑わいの裏には、こうした改革の影響と成果が色濃く息づいています。政治の混乱と社会の不安に立ち向かう若き老中の姿は、現代の視点から見てもなお学ぶべき多くの示唆を与えてくれます。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『国史大辞典』(吉川弘文館)