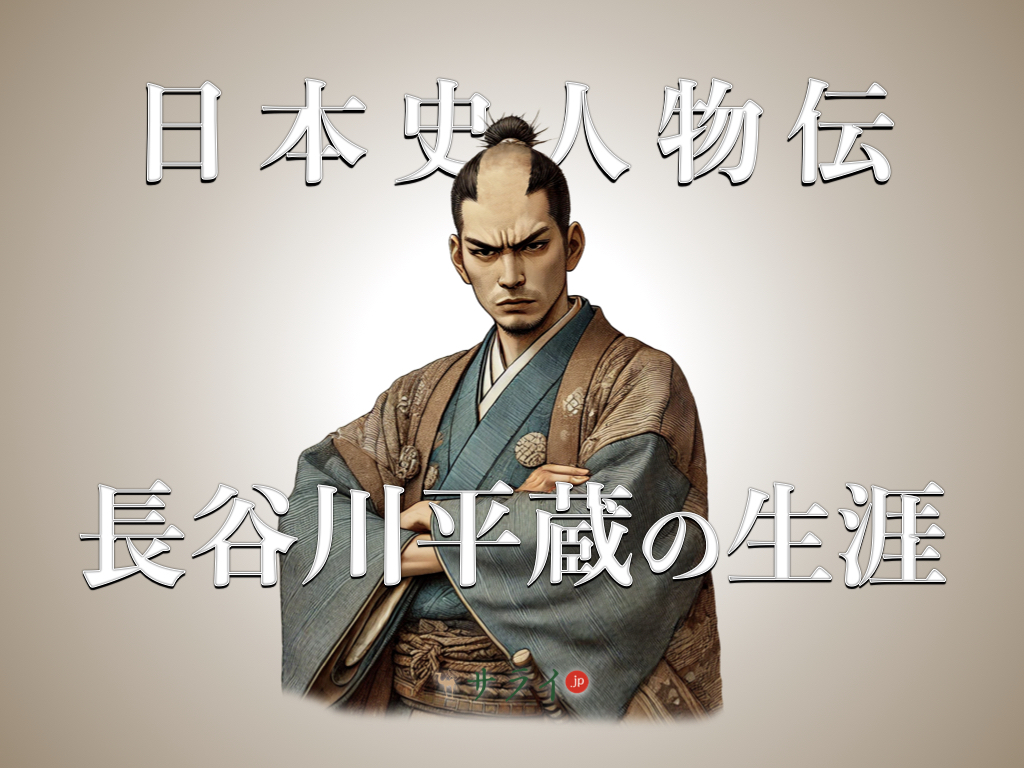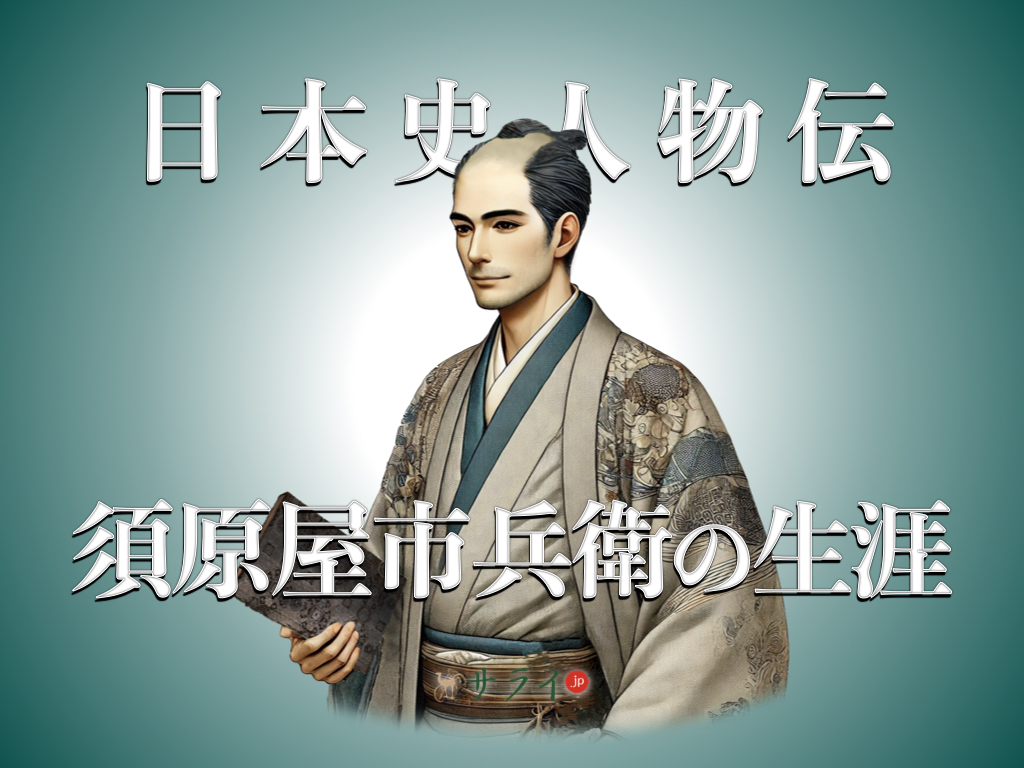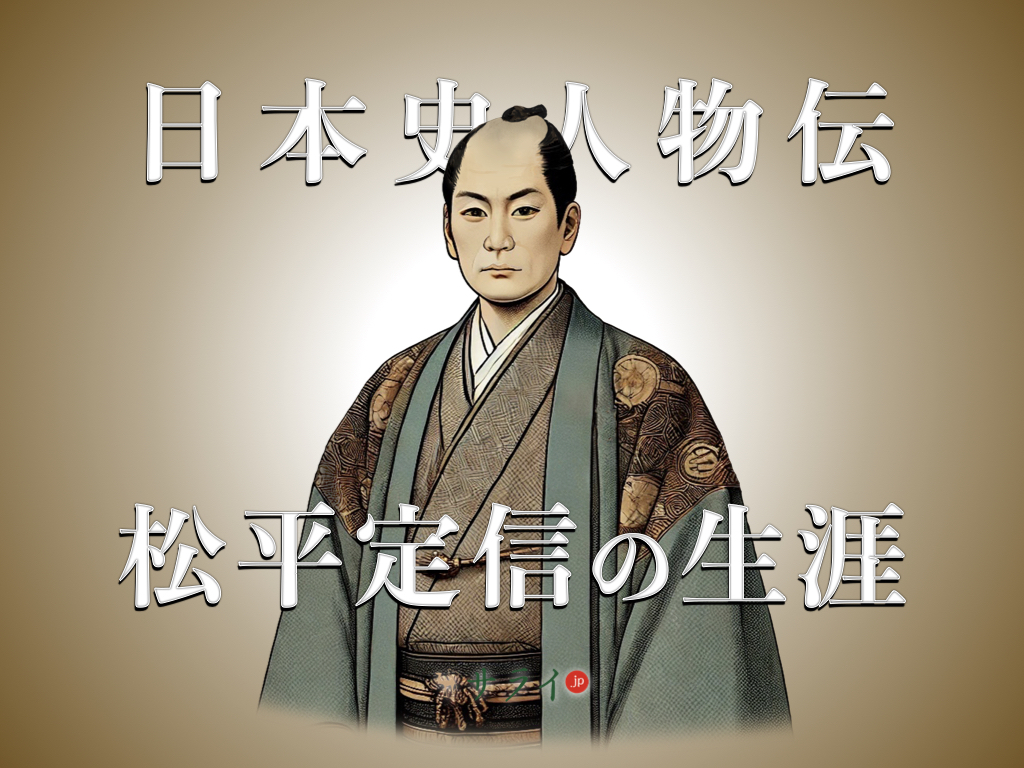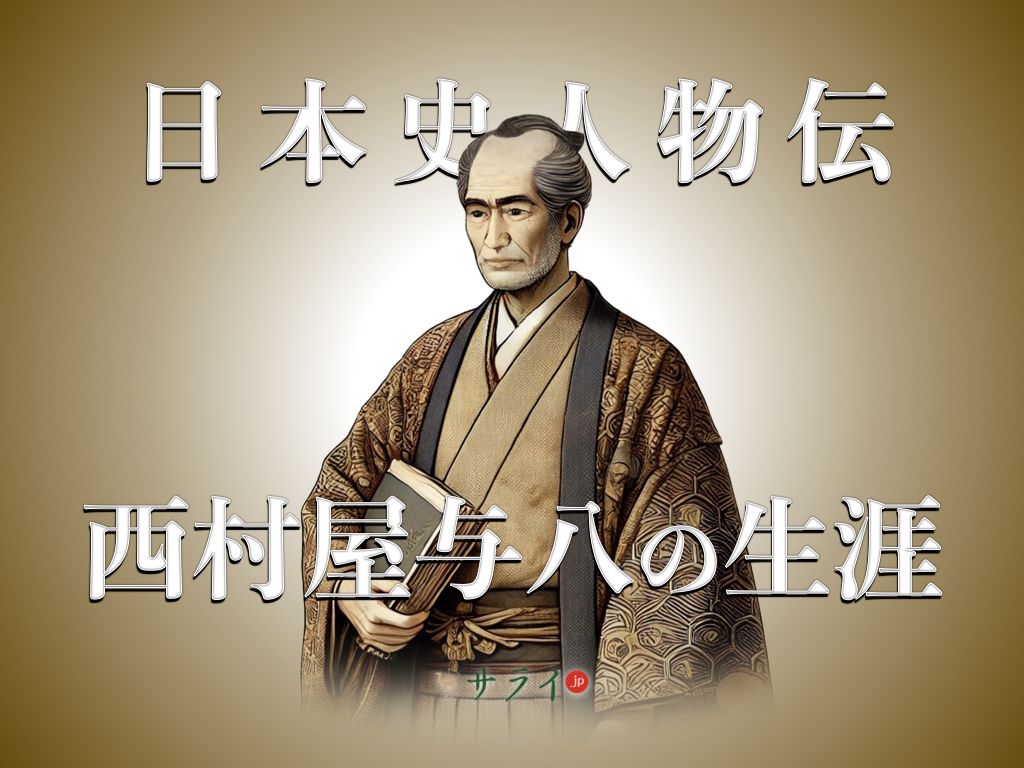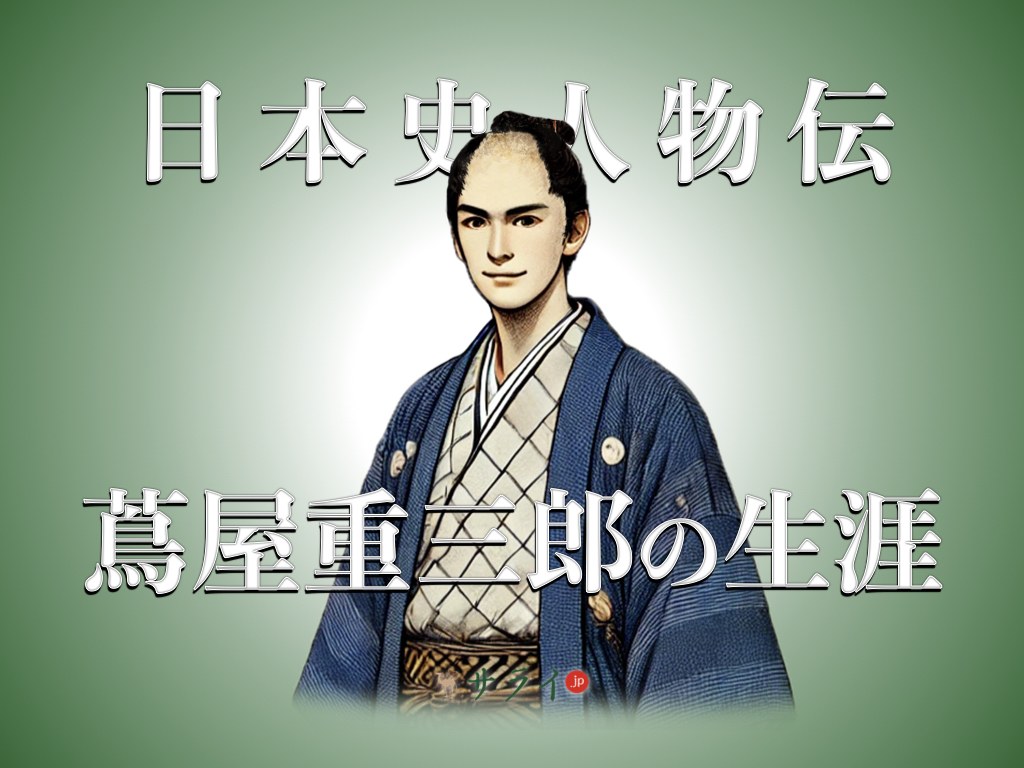火付盗賊改役としての活躍
火付盗賊改役は、放火犯や盗賊を取り締まる江戸時代のいわば特別警察で、全国規模の捜査権限を持つ重要な職務でした。平蔵はこの役職で数々の犯罪者を追跡し、逮捕に成功したようです。
人足寄場の設立と社会改革
天明2年(1782)から天明7年(1787)にかけて「天明の飢饉(てんめいのききん)」が起こり、江戸に無宿(むしゅく)の浮浪人が激増し、社会問題化しました。
そこで、平蔵は幕府に意見をし、その意見を老中・松平定信(さだのぶ)が受け入れ、寛政2年(1790)、江戸市中にあふれる無宿人を収容し、更生させる施設「人足寄場(にんそくよせば)」を設立したのです。

写真は、石川島灯台。
平蔵は、わずか3か月という短期間で石川島(現在の東京都中央区)に寄場を建設し、運営を軌道に乗せました。予算が限られた中で効率的かつ寛厳(かんげん)を使い分けた対応は、平蔵の手腕の象徴にもなっています。
平蔵は、無宿人や軽い犯罪者たちに仕事を与え、油絞りなどの手業を習わせ、自活を促しました。さらには、心学の道話も聞かせたとのこと。成績がよかった人は、資金を与えて出所させたそうです。
しかし、定信とは意見の相違があり、わずか2年半で人足寄場取扱の任を解かれました。
晩年と死去
人足寄場の任を解かれた後、平蔵は火付盗賊改役としての職務に専念しました。
平蔵の晩年は、賞罰の公正さにより、江戸市民から「今大岡(いまおおおか)」(名奉行大岡越前守の再来)と呼ばれ、尊敬されたそうです。
寛政7年(1795)、51歳で死去。法名は「海雲院殿光遠日耀居士」として戒行寺(かいぎょうじ、現在の東京都新宿区四谷)に葬られましたが、墓石は現存していません。
『鬼平犯科帳』のモデルとしての平蔵
平蔵といえば、『鬼平犯科帳』のイメージが強いでしょう。池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』では、平蔵は「鬼平(鬼の平蔵)」の異名を持つ火盗改役長官として描かれています。
平蔵のもとには、与力や同心、かつての無頼仲間や元盗賊など個性豊かな人々が集まり、悪党を裁くさまが生き生きと描かれています。この物語は、時代小説ファンのみならず多くの人々に愛され続けています。
なお、『鬼平犯科帳』で描かれる平蔵の業績の中には、父・宣雄のものも混ざっているようです。
まとめ
長谷川平蔵は、江戸時代の治安維持と社会改革に尽力した人物でした。現在では「鬼平」として平蔵の活躍は、語り継がれています。平蔵の存在は、江戸文化の一翼を担う重要な人物として、今もなお日本史の中で輝き続けています。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
肖像画/もぱ(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『日本人名大辞典』(講談社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)
『新版 日本架空伝承人名辞典』(平凡社)