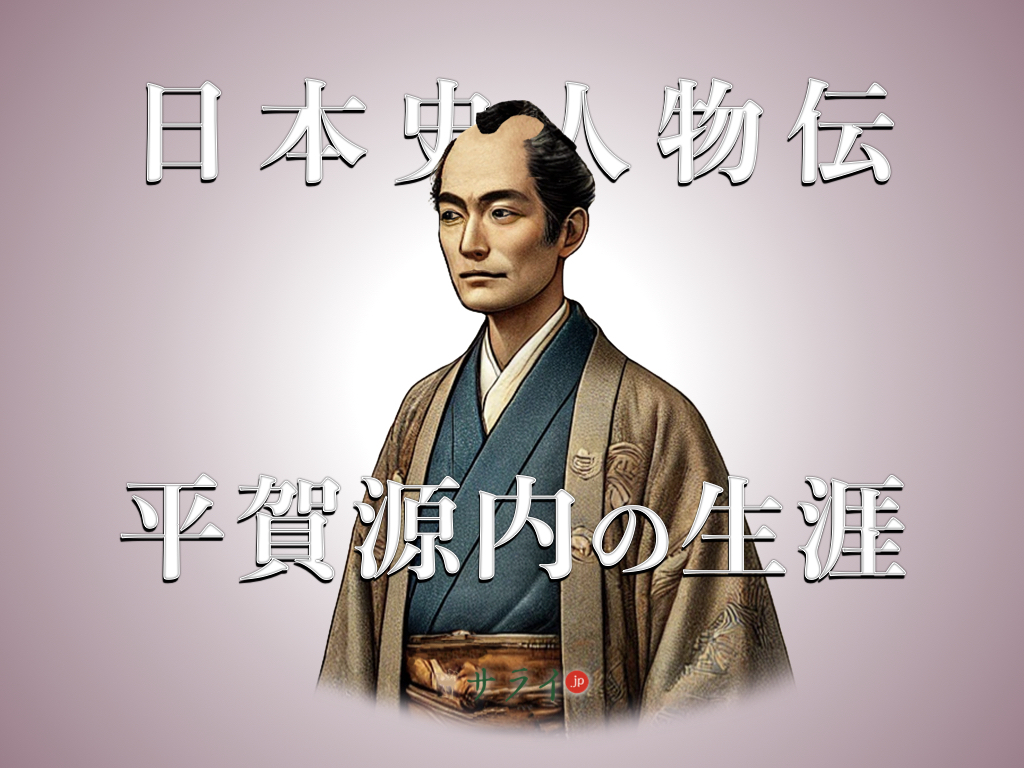平賀源内と田沼意次の関係
平賀源内は、老中・田沼意次との交流を通じて、その才覚を一層発揮する機会を得ました。田沼政権下では、殖産興業が推進されており、源内のような発明家や学者の知識と技術が重宝されたのです。
田沼の庇護を受け、源内は二度目の長崎遊学を行い、そこで得た知識を基に多くの発明や事業計画を実行します。例えば、火浣布(不燃布)の開発や秩父の鉱山採掘、さらには陶器や毛織物の製造など、田沼の経済政策に沿った実用的な事業を手がけました。
一方で、源内の革新性が田沼の政策と完全に一致したわけではなく、彼の大胆な挑戦がしばしば失敗に終わることもありました。それでも、田沼意次の進取の気風と源内の奇抜な才能が交わることで、江戸中期の学問や産業に新たな息吹をもたらしたことは間違いありません。
二人の関係は、当時の日本が抱えていた新技術への期待とその限界を象徴するものといえるでしょう。

技術者としての活動
源内は新しい技術の導入にも熱心でした。明和元年(1764)、秩父で採取した石綿から火浣布(耐火織物)を製作し、『火浣布略説(かかんぷりゃくせつ)』(1765)を出版。
さらに長崎で入手したエレキテル(摩擦起電器)の修理に成功し、その仕組みを応用して医療用具としても活用を試みました。源内はこのエレキテルを用いて電気ショックを発生させる実演を行い、人々を驚かせたそうです。
当時の知識人や富裕層を相手にした実験は人気を博し、源内の名声を高めました。その一方で、「奇術師」的なイメージも伴うことになったようで、後援者も得られず生活は荒みました。
また、磁針器や寒暖計などの理化学的な機器を製作し、その奇抜な発想は注目を集めました。加えて、陶器や毛織物の製作にも取り組み、輸出用の製品開発を目指しましたが、残念ながら、これらの事業は大きな成功を収めるには至らなかったようです。

源内は、現在の東京都江東区にあった自宅でエレキテルの構造を解明し、数々の実験を行っている。
文学者としての活躍
源内は文学の分野でも才能を発揮しました。文人としては『根南志具佐』や『風流志道軒伝(ふうりゅうしどうけんでん)』などで、滑稽本の端緒をなし活躍。また、浄瑠璃作家として『神霊矢口渡』を執筆し、劇場での上演も成功を収めました。
さらに、狂文『放屁論(ほうひろん)』では「エレキテルを発明した浪人貧家銭内」の口を通じて当時の社会を鋭く批判しています。
晩年と獄死
源内は晩年、事業の失敗や生活苦から失意のうちに過ごしました。安永8年(1779)、秘密にしていた設計図の盗難を疑ったからか(※理由は不詳)、激昂して人を殺傷。その結果入牢し、同年12月18日、小伝馬町の獄中で病死しました。享年52歳。台東区の橋場総泉寺跡に墓が残されています。
【「土用の丑の日」の発案。次ページに続きます】