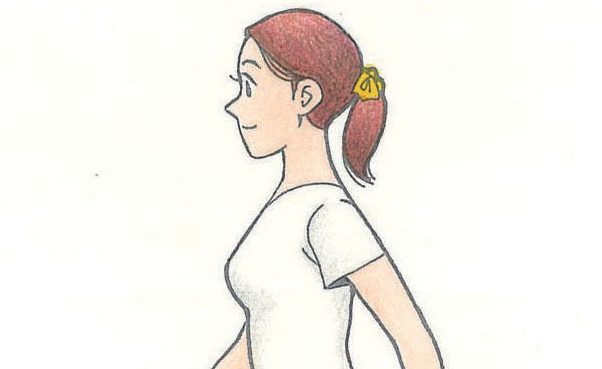池波志乃さん(女優)
─夫婦の“終活”も話題の名門落語家一家の長女─
「サインには気の利いた画でも添える。そんな父の教えを大切にしています」

── 金原亭馬生のCDブックが新たに出ます。
「はい。この3月に、父・十代目金原亭馬生が遺した東横落語会の口演がまとまって世に出ることになりました。これまで父の落語の音源はあまり出ていません。“落語の芸というのは、そのときだけで消えてゆく、一回限りのものだから、録って残さないほうがいい”という考え方の人でしたから。
そんな父がいちばん力を入れて臨んでいたのが東横。昭和43年からレギュラーに定着して、亡くなる前月の昭和57年8月まで高座に上がり続けました。今回は噺家として最も脂が乗っていた時期の音源から、初出し46席を含む50席を厳選したと、うかがっています」
──東横はホール落語の一番の名門でした。
「私が小学5年生くらいの頃から、うちでは“トウヨコ”というのは特別な呪文のようでした。子供心に、トウヨコと聞くと、意味もわからないまま〈きょうは大変な日なんだ〉という、ひそかな興奮があって。出かける父の背に、母がいつも以上に精魂込めて切り火をきって送り出す。そんなふたりの様子に〈トウヨコはすごい!!〉っていう、不思議な高揚感を覚えていたものなんですよ。
晩年の父は食道癌の影響もあり、喉の調子がよくなかった。なのに、世の中には父の体調が悪くなってからの音源がわりと出てしまっている。それが私には残念というか、気持ちとしてすごく嫌だったんです。だから、東横のいい時代の口演を何とか世に出したかった。みなさんにいちばん聴いてもらいたかった。それが実現して本当に嬉しく思います」
──父の高座を直にお聴きになったことは。
「私は行ったことがないんです。“家族が(職場を)うろうろするな”というのが、うちのカタチでしたので。ただ、女優になってから、小さん師匠(五代目柳家小さん)と父の二人会か何かのとき、東横劇場で踊った記憶があります。あとは父が亡くなった年の暮れの追善興行の際、志ん朝叔父ちゃん(三代目古今亭志ん朝)と舞台に上がって、ご挨拶をさせていただいた。今回のCDブックで、父が最も力を入れていた“トウヨコ”をじっくり聴けるので、私も愉しみに待っています」
──きょうの帯の柄は“馬”ですね。
「これは父の手描きの帯なんです。父は日本画の大家・鴨下晁湖先生に教えを受けています。先生は、父の画才を子供の頃から見抜いて“絵描きにしたい”と言っていたそうです。花鳥風月でも何でも得意で、頼まれればいろんな画を描いていましたが、やっぱり名にちなんで“馬”を描くことが多かった。これも帯に直に描いたとは思えない迫力があり、私はこれ1枚しか持っていません。父は私が中尾(彬)さんと結婚して4年目、54歳の若さで亡くなりました。そんなに早くいなくなるとは思ってもいなかったので、もっと描いてもらえばよかったと、今は思います。
女優になったとき、父にこう言われました。“色紙にサインを求められたときは、気の利いた画のひとつでも添えられるようにしなさい。1年12か月の風趣を描くとか、せめて春夏秋冬の四季4枚の画は描けるようにしておきなさい”ってね」
──なぜ女優の道に進まれたのですか。
「小学生の頃は、栄養士とか家庭科の先生に憧れ、中高一貫の私立戸板学園(現・三田国際学園)へ進学しました。ところが、専門学校の附属なのに中学は義務教育だから家庭科の授業が多いわけでもなくて、熱が冷めてしまったのです。その代わり、部活の放送部で、DJみたいなことをやっていました。“お昼のひととき、みなさま、どうお過ごしですか”とか言っちゃってね(笑)。そこから音楽や演劇に興味がわいて、女優になりたい、芝居がしたいと思ったんです。父に相談してみたら、“甘い世界じゃないよ。本気なら、学校はやめて、演劇の養成所に入るとかして修業をしなさい”と。さっそく次の日、学校へ退学届を持って行きました」(笑)
──中尾彬さんとの出会いは。
「単純にいえば、職場結婚(笑)。出演したドラマの相手役でした。その頃は、今よりずっとのんびりしていたというか、テレビ時代劇を1本撮るのに1週間とか10日とかかけていました。だから、ロケバスのなかで何時間待ちとか結構あって。お昼も時代劇の格好をしたまま撮影所の近くへ一緒に食べに行く。出演者たちの距離がべったり近かったので、濃厚につき合おうと思えばそれができたんです。最近はドラマをやっても、みなさん淡々とやっているというか、昔とは雰囲気が違う。今の時代に若くて同じ状況で中尾さんと知り合っていたとしても、たぶん恋愛にはいたらないんじゃないかな(笑)。のんびりした時代に知り合ってよかったなと思います」

「もう一度“新婚”のやり直しを。終活でそんな気持ちになりました」
──ご夫婦の“終活”が話題になりました。
「私と中尾さんには子供がいませんから“誰にも迷惑をかけずにいなくなる”というのを旗印に“要らないモノを手放す旅”を始めたんです。それを世の中では“終活”と呼ぶというのは、後で知ったんですけどね(笑)。
公証役場で遺言状をつくり、住まいに近い谷中(東京都台東区)に墓も建てた。角のない自然石が3段に横たわっている斬新なお墓で、小さく“無”の一字が彫ってあります。“どの墓石も立ってるから、横にしてやろう”と言って、中尾さんがデザインしました。次に中尾さんがアトリエにしていた築30年の千葉の実家と、訪れる機会が次第に減っていた沖縄のセカンドハウスを売却処分しました。それから細々した物の整理を始めたんです」
──何かきっかけがあったのですか。
「私が50歳になる頃から、思いがけないことが重なって起きました。2006年9月に、私が沖縄の住まいで倒れ、筋肉に命令がうまく伝わらず、目や口など身体の末梢神経が痺れてしまう“フィッシャー症候群”という難病にかかってしまいました。その時期、私の母も癌治療のため闘病中。中尾さんは仕事の合間をぬって、沖縄の私と木更津(千葉県)の病院にいる母を見舞ってくれていました。
ところが11月に母が亡くなり、翌年3月に中尾さんが仕事先の大阪で倒れて病院に運ばれてしまった。急性肺炎から多臓器不全を併発しかねない状態で、私が駆け付けたときには生存率20%とまで言われました」
──半年に3つもの大災難が重なった。
「怒涛のように。でも、そういう災難を乗り越えると“人生何があってもおかしくない”という覚悟が決まります。終活を意識し始めたのは、それから。自分たちの生活を縮小していく時期がきたと思って、実行に移し始めたのは2013年です。食器や台所用品、本も大量に処分した。私の好きな推理小説だけでもトラック2台。舞台衣装や鬘(かつら)も手放したし、写真も1万枚くらい破棄したんです。人間関係と仕事の断捨離もしました」(笑)
──捨てる決断が難しかったでしょうね。
「写真でいえば、捨てた1万枚は私たちが大人になってからの分です。昔の写真は、母が持っていた段ボールを妹に引き継いでもらいました。妹には子供(「落語協会」二ツ目・金原亭小駒)がいるので、まだ必要かもしれないと。写真を始末する基準は“これを見て懐かしいと思う人がいるか”ということ。だから、私たち夫婦ふたりだけの写真はほとんど捨てました。でも、そこに一緒に写ってい る人がいたら、その人に渡してみて、あとの判断は任せる。そういう整理の仕方です」
──終活で身軽になってからのテーマは。
「中尾さんと話し合って決めたのが、労り合って楽しく、もう一度“新婚”のやり直しをしようねということです。その核になるのが、これまで仕事で行ったところなどへ、あらためて行ってみようという夫婦の旅。仕事で行っても、じつは何も見られない。空港と駅と宿と会場しか知らない。旅番組はロケ車(移動に使う車)が迎えにきて“こういう流れです”って、ほぼ予定どおりに動くので、自分たちの興味では全然行動できない。だから、お仕着せではなく、昔懐かしいところを、ちゃんと訪ねてみようよと。一昨年までは、ふたりで好き勝手に先々の予定を決めたり、現地で興味の向くままに赴いたりという旅を愉しんでいたんですけど、このコロナ騒ぎで行けなくなってしまって、去年は旅の予約をキャンセルしては謝ってばかりでした」


「コロナで『居酒屋しの』がフル回転。自宅でのんびり過ごす時間も幸せ」
──今はどんな日々をお過ごしですか。
「コロナ騒ぎで、仕事がないので完全に主婦化しています。もともと、夫婦で家に居る日の夕食は、私の手料理のフルコースで、お酒を飲みながら、ゆっくり2時間はかけておしゃべりを愉しむというのが夫婦の習い。それが中尾さんのいうところの『居酒屋しの』(笑)。以前は、お互いに仕事もあって、ひんぱんに開店していたわけじゃないんですけど、今は外へ食べに行くことがなかなかできなくなり、おかげで、常連1名の『居酒屋しの』は時短・休業なしのフル回転なんですよ。
でも終活の際、調理器具も大方処分してしまったんです。10年後は重くて絶対に持てなくなる鉄製のフライパンやテリーヌをつくる器具、麺棒も要らないねって感じで。食べたくなったら外食すればいいよねって、もの凄い勢いで処分しました。でも、毎日『居酒屋しの』を開くとなると、また料理のパターンを増やさないといけない。そのためには調理器具もまた必要になってきちゃって。ネット通販であらためて軽くて使い勝手のいいものを買い直したのですが、だんだん台所が手狭になってきてしまいました」(笑)
──ご自分の時間は何をされますか。
「私はひとりでも退屈しないんです。本が大好きで一日中読んでいても平気。中尾さんも同じです。お互い月に30冊くらい読んでは、感想を話し合ったりしています。コロナ前は、中尾さんと“ご飯を食べに行こうか”と言って、待ち合わせをするのは必ず本屋さんでした。レストランに入るときは、ふたりとも手に本を持っている。今も外へ出る理由は、読みたい本を買うか、食材の買い出しか、そのいずれかなので、店に食べに行けないのは残念ですけど、あまり不自由は感じていません。
中尾さんは一見怖い顔をしてますけど、意外に“お茶目”で、愉しい人なんですよ。顔真似なんかすごく上手」
──誰の顔真似をするのですか。
「最近だと日産自動車のカルロス・ゴーン元会長。表情や眉毛の動かし方が本当にそっくりで、思わず笑ってしまいます。あとは、動物のカピバラの顔真似もうまい、絶品ですよ。そう言われると何となく似ている気がするでしょう(笑)。
中尾さんは顔のパーツがよく動くので表情がとても豊か。高いトーンの声も出るので、声や音の真似もうまい。私も負けじと物真似をするのですが、コマーシャルを一緒に真似して、お互いに“ノルなぁ!”って笑い合ったりしています。今はそんなのんびりと過ごす時間がとても幸せです」
──やり直しの新婚生活は充実してますね。
「そうでしょう。私、中尾さんがいなくなったら、今みたいにお料理をちゃんとつくるかといったら、つくらなくなると思うんです。料理は食べてくれる人がいて、ちゃんと反応がないと面白くない、張り合いがない。同じ料理を食べて“この食材はフランスへ行ったときにさ”とかって話が広がってゆくのがいい。ひとりだと、そういう愉しみがまったくない。私は自分だけのために料理はつくらないと思うから、『居酒屋しの』は閉店。ひとり好きな本を読みながら餓死しちゃうか、お酒が大好きだから“酒樽のなかで溺れる”か。これは父の台詞ですけどね」(笑)

池波志乃(いけなみ・しの) 昭和30年、東京生まれ。十代目金原亭馬生の長女。祖父は五代目古今亭志ん生。三代目古今亭志ん朝は叔父。俳優小劇場養成所を経て新国劇に入り、昭和48年テレビドラマ『女ねずみ小僧』でデビュー。翌49年NHK連続テレビ小説『鳩子の海』で注目を集め、以降『悪魔の手毬唄』『鬼平犯科帳』などテレビ、映画、舞台で活躍。随筆家としても健筆をふるう。著書に『食物のある風景』等。夫との共著『終活夫婦』が話題に。
※この記事は『サライ』本誌2021年4月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/ 佐藤俊一 撮影/宮地 工 )