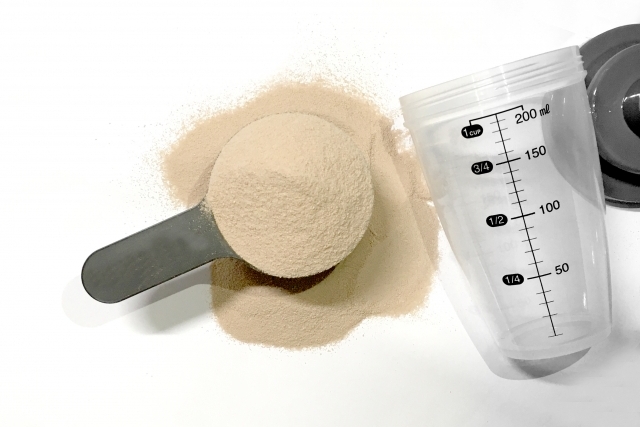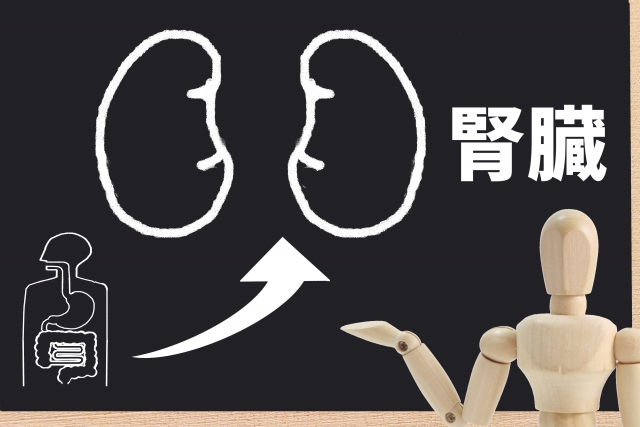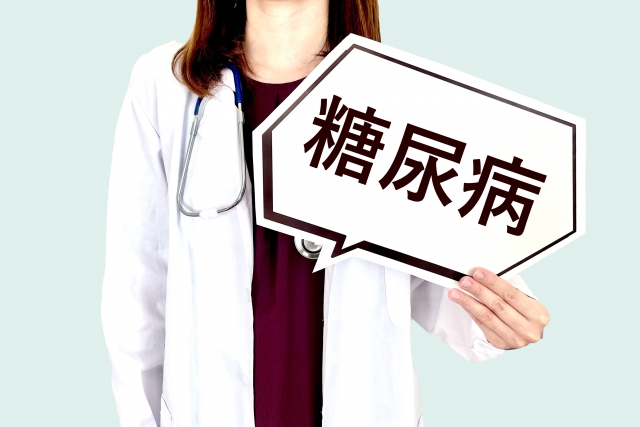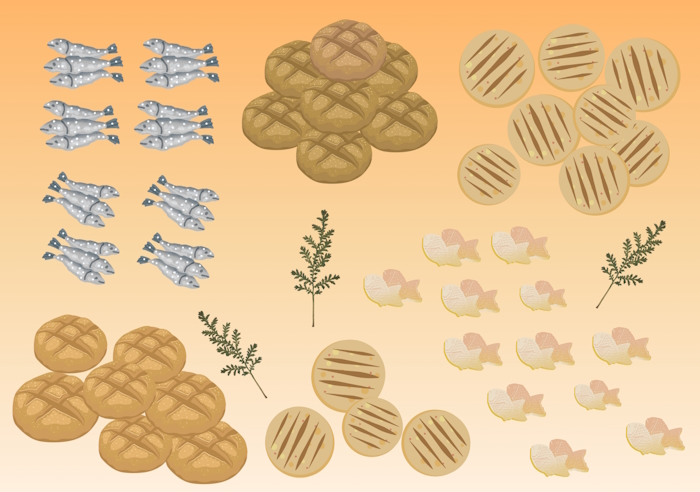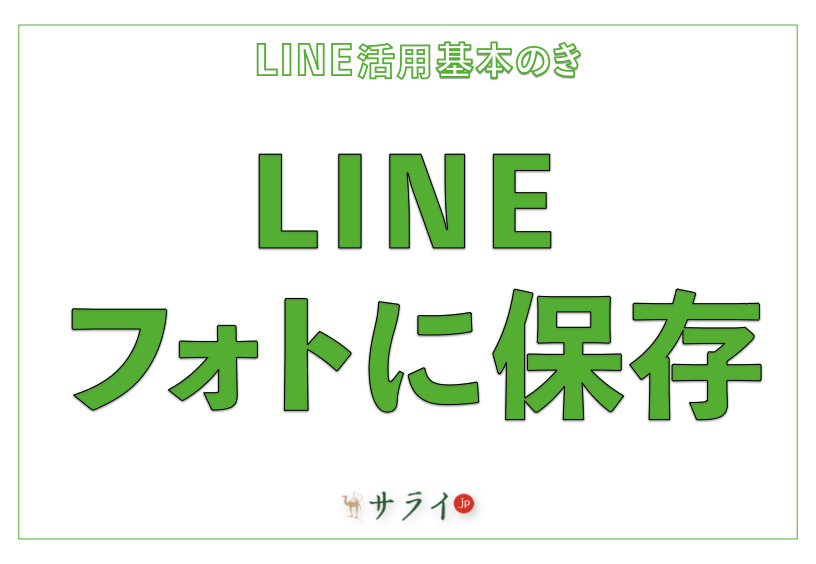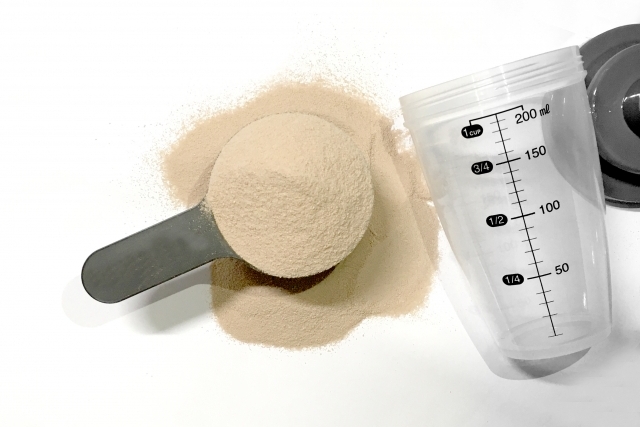
日本人の約8割が「疲れている」と回答するなど、疲労は現代的な“国民病”と言われます。仕事や人間関係のストレス、運動や睡眠の不足、スマートフォンへの依存など、様々な原因が指摘されますが、医学的に間違った「食事のあり方」を問題視するのが牧田善二医師です。新著『疲れない体をつくるための最高の食事術』が話題の牧田医師が解説します。
解説 牧田善二(まきたぜんじ)さん(糖尿病・アンチエイジング専門医)

「タンパク質」はプロテインで補わない
私たちが肉や豆腐を食べると、そのタンパク質は分解されてアミノ酸となり、体内で再びタンパク質がつくられます。
そのことから、多くの人が「たくさんタンパク質を摂れば、アミノ酸が増えて筋肉の原料となるし、不足したら内臓など全身のタンパク質が足りなくなる」と考えるようです。でも、それは本当なのでしょうか。
結論から言うと、その考えは捨てるべきです。タンパク質摂取に関しては、「今のままで大丈夫」です。
「ステーキなら300グラム食べる」という人であっても、「タンパク質は豆腐や納豆が中心」という人であっても、そのままで大丈夫。
つまり、みなさんが普段の食事から摂るタンパク質(一日約60グラム)で充分だということです。
それ以上に摂ろうとしたり、ましてや粉末や液体のプロテインで補ったりする必要は皆無です。むしろ、それをやってはいけません。なぜなら、私たちの体には、「アミノ酸プール」という優れたシステムがあるからです。
アミノ酸プールは、その名の通り、アミノ酸をプール(ストック)しておけるシステムです。そのアミノ酸は再利用できるため、そもそも不足することはありません。
こうして、もともとアミノ酸プールが整っている上に、食事からもタンパク質を摂っているのだから、アミノ酸は余ってしまうぐらいの状況にあります。
腎臓病の原因になると指摘
そこにプロテインを摂れば、大量のアミノ酸が生成され、行き場がなくなります。行き場がなくなった大量のアミノ酸は、ほとんどが尿から排泄されます。
その役割を担っているのが腎臓です。
腎臓は、老廃物や毒素を処理することで手一杯なのに、そこにわざわざ余計な仕事を増やしてしまうのが、プロテインの摂取なのです。
毎日の食事で肉や魚、大豆食品などタンパク質を摂るのはいいことです。炭水化物と違って、タンパク質は血糖値を上げないので、むしろ大いに食べてOKです。
ただし、プロテイン製品のような高濃度のタンパク質を摂ると、腎臓を悪くして腎臓病の原因になることが、約50年前から医学の研究では指摘されています。
みなさんの中にも、プロテインは健康に良いと教えられた人がいることでしょう。そして、「運動して筋肉を使ったり、疲れたりしたら飲んだほうがいい」と考え、実践している人もいるでしょう。
でも、もうやめましょう。
もちろん、プロテインをすすめる人たちに、まったく悪気はないはずです。医者ですら、健康のためにプロテインをせっせと摂取している人もいるくらいです。
しかし、そうした医者は腎臓について専門外で、素人と同じくらいの知識しか持っていません。
みなさんは、医者よりも賢くなって、自分の体を守ってください。
***
世界最新の医学的データと20年の臨床経験から考案『疲れない体をつくる最高の食事術』
現代人の疲れは過労やストレスではなく、「食」にこそ大きな原因がある。誤った知識に基づく食事は慢性疲労ばかりか、肥満や老化、病気をも呼び込む。健康長寿にも繋がる「ミラクルフード」の数々を、最新医学データや臨床経験を交えながら、具体的かつ平易に解説している。
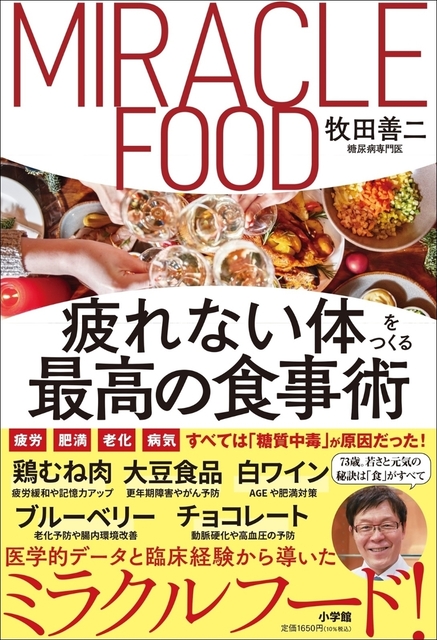
牧田善二/著 四六判208ページ 小学館刊 1650円(税込)