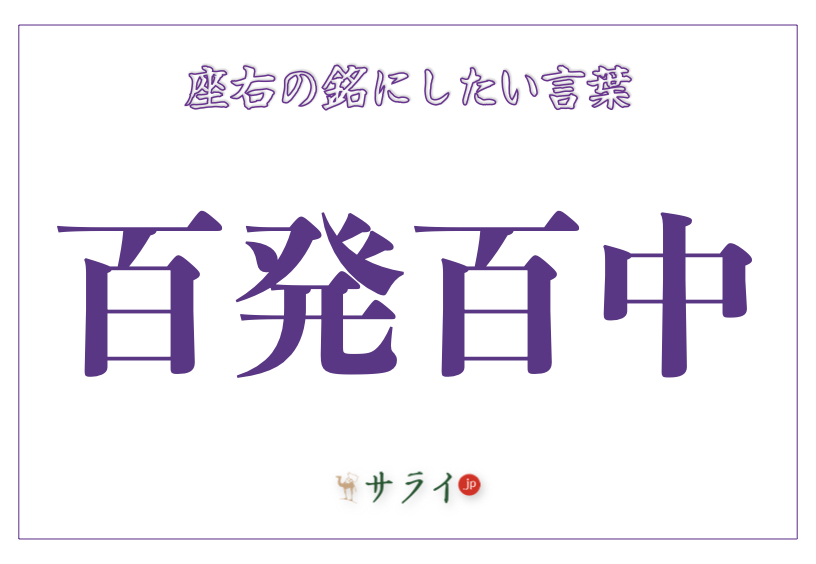近年、“スパークリング日本酒”という新たなジャンルが注目を集めています。シャンパーニュのように泡立つ日本酒は、これまでの日本酒のイメージを一新し、20代から30代の若い世代、そして米国、欧州やアジア圏などの海外の方々にも親しまれています。今回は、そんなスパークリング日本酒の魅力について詳しく解説します。
文/山内祐治
目次
スパークリング日本酒とは?
スパークリング日本酒「澪」。コンビニで購入できる人気製品
スパークリング日本酒のフルーティーな魅力
スパークリング日本酒の人気銘柄を紹介
スパークリング日本酒の作り方。伝統と革新の融合
スパークリング日本酒に合うつまみ。新しいペアリングの提案
まとめ
スパークリング日本酒とは?
スパークリング日本酒とは、発泡性のある日本酒のことを指します。泡の量や質には様々な種類があり、シャンパーニュのようにきめ細かく弾ける泡から、微かにチリチリとした感覚を残す微発泡まで多様です。また、見た目も透明なものから薄く濁っているものまであり、甘さやガスの強さも製品によって異なります。
日本酒自体は長い歴史を持つ伝統的なお酒ですが、醸造技術や設備の進化により、これまでにない楽しみ方が近年になって切り開かれました。特にスパークリング日本酒は、日本酒の新たな可能性を導くジャンルとして注目されています。乾杯のシーンにも相応しく、ワイングラスで楽しむことで、より洗練された時間を演出することが可能です。
スパークリング日本酒「澪」。コンビニで購入できる人気製品
誰もが知るスパークリング日本酒と言えば「澪(みお)」でしょう。宝酒造が製造・販売するこの商品は、いまや国内外で広く親しまれています。
「澪」の特徴は、まずその飲みやすさにあります。アルコール度数が5%と、一般的な日本酒より低く設定されており、日本酒に馴染みのない方でも気軽に楽しめます。製法としては“炭酸ガス充填法”を採用しており、完成した日本酒に後から炭酸ガスを注入しています。
また、この「澪」は、海外でも展開され、2021年度には42の国と地域で販売されています。つまり日本酒の国際化に一役買っており、主に欧米、アジア圏でかつて見られた日本酒=熱燗という旧態依然としたイメージを覆す存在となっています。スッキリとした味わいと適度な甘さで食前酒としても良く、またデザートとの相性も抜群なのです。
「澪」を入り口に、様々なスパークリング日本酒を試してみるのも良いでしょう。それぞれのメーカーや銘柄によって異なる個性があり、自分好みの一本を見つける楽しさがあります。
スパークリング日本酒のフルーティーな魅力
フルーティーさを求めるなら、特に純米大吟醸や大吟醸をベースにしたスパークリング日本酒がおすすめです。高度に磨かれた酒米を使用し、低温でじっくりと発酵させることで、より繊細で華やかな香りを引き出しています。
これらのフルーティーなスパークリング日本酒は、リンゴや洋梨といった果物を思わせるフレッシュでフルーティーな香りを持っています。これは吟醸香という清酒酵母が生み出す香気成分によるもので、適切な温度管理と発酵技術によって引き出されます。特に微発泡タイプの日本酒は、醸造過程で生まれた天然の泡をそのまま活かしているものが多く、発泡によってフルーティーさがより際立つ傾向にあります。
近年では醸造技術や設備の革新により、酵母が自然に生み出すガス感を損なわない技術が発達し、微発泡の日本酒がさらに増えています。これにより、まるで炭酸飲料のようにすっきりと飲めるものから、果実の豊かな香りが広がる製品まで、バリエーション豊かなスパークリング日本酒を楽しむことができるようになりました。
スパークリング日本酒の人気銘柄を紹介
スパークリング日本酒の市場は、年々拡大しています。その中でも特に注目すべきは、「AWA SAKE(あわさけ)」として認定されている製品群です。awa酒協会は2016年に設立され、東京オリンピックに向けて日本酒の新たな価値を発信することを目指して活動を始めました。AWA SAKEの基準は厳格で、「酵母が作り出した天然の泡であること」や「ガス圧が5気圧以上あること」などの諸条件を満たす必要があります。
AWA SAKEの認定を受けている人気銘柄としては、「水芭蕉」(群馬県)、「七賢」(山梨県)、「出羽桜」(山形県)、「南部美人」(岩手県)などが挙げられます。AWA SAKEは祝いの席を彩るにふさわしい、高品質なスパークリング日本酒です。

一方で、微発泡タイプとして人気を集めているのが、奈良県の「風の森」です。このお酒は爽やかな炭酸感と清々しい香りが特徴で、一口飲むと一瞬、炭酸飲料を思わせるような感覚があります。また同タイプで「産土(うぶすな)」(熊本県)も見逃せません。透明感のある美しい泡立ちと洗練された味わいで、多くの愛好家を魅了しています。
スパークリング日本酒の造り方。伝統と革新の融合
スパークリング日本酒の製法は大きく分けて4つあります。それぞれの特徴を理解することで、より深く楽しむことができるでしょう。
- 炭酸ガス充填法:最もカジュアルな方法で、完成した日本酒に後から二酸化炭素を注入する方法です。「澪」など大量生産されている商品に多く用いられています。比較的手軽に製造できますが、その一方で泡が少々粗く感じられることもあります。
- 瓶内一次発酵法:発酵途中または発酵後の日本酒を瓶詰めし、アルコール発酵の際に生まれたガス(二酸化炭素)をそのまま瓶内に封じ込める方法です。自然な泡立ちとフレッシュな風味が特徴です。
- 瓶内二次発酵法:シャンパーニュ製法に近い高度な技術を用いた方法です。一度発酵を終えた日本酒を瓶詰めし、瓶内で再び発酵させることでガス圧を高めていくと説明されています。色々な方法がありますが、awa酒協会が認める高級スパークリング日本酒は、この方法で製造されるお酒が主流です。
- 活性清酒:濁り酒など、濾す際に酵母を残して、濁ったまま発酵を続けているお酒のことです。
さらに高級な瓶内二次発酵製品では、シャンパーニュと同様に「デゴルジュマン」という工程を経て、発酵後に生じた酵母などの沈殿物(オリ)を除去します。これら手間のかかる工程を経ることで、透明感があり繊細な泡立ちを持つ高品質なスパークリング日本酒が生み出されるのです。
スパークリング日本酒に合うつまみ。新しいペアリングの提案
スパークリング日本酒の特徴であるフレッシュ感とフルーティーな風味を活かすなら、従来とは異なるアプローチがおすすめです。
特に相性が良いのが、フレッシュなフルーツ。シャインマスカットやいちご、桃などの果物は、スパークリング日本酒の甘みや香りを引き立てます。さらに、フレッシュチーズを組み合わせると、より洗練された味わいを楽しむことができます。例えば、フレッシュなモッツァレラチーズやフロマージュブランのような、爽やかなチーズがおすすめです。
フィンガーフードのように小さく切ったフルーツとチーズを一緒に楽しむと、これまでの日本酒とは一線を画したスタイリッシュなペアリング体験ができるでしょう。また、シーフードの中でも特に甲殻類(エビやカニ)や白身魚のカルパッチョなども、スパークリング日本酒の爽快感を引き立てる良いパートナーになります。
このような新しいペアリングの提案は、日本酒の可能性をさらに広げ、食文化の多様性を楽しむきっかけになるはずです。
まとめ
スパークリング日本酒は、伝統的な日本酒文化に新たな息吹を吹き込む存在です。醸造技術の革新により、これまでにない多様な味わいと楽しみ方を提供してくれます。
特に注目すべきは、スパークリング日本酒が日本酒の国際化に貢献している点です。シャンパーニュやスパークリングワインに代わる選択肢として、海外の方々の乾杯のシーンにスパークリング日本酒を提案できることは、日本文化の発信においても大きな意味を持ちます。
また、このお酒をワイングラスで楽しむことで、より香りを感じられ、見た目にも華やかな印象を与えるため、特別な席や祝いの場にもぴったりです。これまで日本酒に馴染みのなかった方々にとっても、入りやすいジャンルとなっています。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。
構成/土田貴史