文/鈴木拓也

歴史上、日本にチーズが伝わったのは、飛鳥時代のこととされている。これは、蘇(そ)と呼ばれ、牛乳を煮詰めて固めた食べ物だったようだ。
意外にも、人類がチーズをつくり始めたのは、それよりも遥かに古い。文明が芽生えた頃の土器には、チーズづくりの形跡が残っているし、シュメール人の残した石板には、チーズについての言及がある。
そうした悠久の歴史を持つチーズだが、これを新書『チーズの世界史』(河出書房新社 https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309504568/)にまとめたのが、木榑(こぐれ)博さんだ。
NPO法人チーズプロフェッショナル協会で活躍する木榑さんだが、深い知見に裏付けされた本書は、チーズ好き、歴史好きなら必読の1冊。
今回は、その内容の一部を紹介しよう。
ローマの版図拡大でチーズが広まる
古代社会は争いの絶えない時代であったが、チーズは、戦士の栄養食として重宝された。
例えば、トロイア戦争を描いた『イリアス』には、青銅のおろし金ですった硬いチーズの入った飲み物が、戦士を回復させたとある。
古代ローマにおいても、「ペコリーノ・ロマーノ」というチーズが、兵士に毎日27グラム支給されたという。ポエニ戦争に勝利し、穀倉地帯たるシチリア島を手に入れると、大規模な農場が増え、チーズの大量生産が可能となっていたのが背景にある。
ローマの支配圏が広まるにつれ、チーズも各地で生産されるようになり、地域の特産品となる。アントニヌス・ピウス帝が病で没したのも、「アルプス山チーズの食べ過ぎが原因」であったと当代の作家が語っているが、権力者から市井の人々まで様々なチーズを賞味できたようだ。
しかし、ローマ帝国が滅んだとき、新たな支配者となったゲルマン人は、チーズにさほど価値を認めず、チーズ文化も消滅の危機を迎える。
チーズの誘惑に耐えられなかったルイ16世
その危機を救ったのが、キリスト教の司教や修道院であった。自給自足や収入の糧として農場を持っており、チーズもつくられていたからである。特に西ヨーロッパ各地に教勢を広げていったベネディクト派修道院は、チーズづくりに積極的であった。ゲルマン人の統治者も、チーズの真価を認めるようになり、チーズ文化は中世に向かって花開いていく。
中世になると、自国産チーズはお国自慢であり、外交の道具として使われさえした。木榑さんは、一例を挙げる。
たとえば、ローマ教皇ユリウス2世は、イングランド国王ヘンリ8世に「パルミジャーノ・レッジャーノ」を100個も贈っている。「パルミジャーノ・レッジャーノ」の重量は1個15~20キログラム以上だから、約2トンものチーズをプレゼントした計算になる。(本書124pより)
ユリウス2世のねらいは、イタリアからフランスの勢力を駆逐することであった。贈答されたチーズが功を奏したようで、ヘンリ8世は一時、ユリウス2世の味方についた。
18世紀になると、フランスがヨーロッパ随一の国力を誇るようになった。当時、かの国を代表するチーズは、白カビタイプの「ブリ」。なかでも最高峰とされたのが「ブリ・ド・モー」であった。
このチーズに魅せられたのが、国王のルイ16世である。産地のモー村から宮殿まで、毎週このチーズが馬車で運ばれた。しかし、1791年にフランス革命が勃発。身の危険を感じたルイ16世一家は、オーストリアへ亡命をはかる。
ところが、オーストリアに向かう途上で「ブリ・ド・モー」が食べたくなり、立ち寄った先でこのチーズを堪能したことで遅れが生じた。結局、国王らは追っ手に捕まり、絞首台の露と消えたのである。
歴史は浅いが「世界トップレベルの地位」を築いた日本のチーズ
本書は、日本のチーズ史についても1章割いている。
飛鳥~平安時代にかけて、宮廷内のごく限られた世界にチーズ文化があったが、武士の時代が到来するとそれも断絶する。例外的に、長崎出島にいたオランダ人が、徳川綱吉将軍にチーズを献上したという記録が残っているぐらいである。
明治維新を迎えると状況は一変する。国を挙げて欧米の食文化を採り入れようとする取り組みが始まった。その一環としてチーズづくりがあり、1875年に函館の官業試験所で製造が始まっている。ただ、優先されたのは牛乳の安定生産であり、チーズの普及は緩慢な歩みとなる。
戦後、それが一変する。復興を急ぐ政府による農畜産業の振興で、牛乳が飛躍的に増産され、消費も伸びていったのである。あわせてチーズも生産量が拡大したが、ヨーロッパと違いプロセスチーズが主力であった。給食にもプロセスチーズが登場し、子供たちはチーズに親しんだ。チーズの味を覚えた彼らが大人になった1980年代以降、ハンバーガー店やイタリア料理店で、チーズを使った料理がおなじみとなった。
今では、スーパーやデパ地下の食品売り場には、国内外のチーズが当たり前のように並ぶ。大手の食品メーカーのみならず、小規模事業者もチーズづくりに参入し、「世界規模のコンテストで高い評価を受けているチーズが続々と誕生している」ほどだ。木榑さんは、日本のチーズは「すでに世界トップレベルの地位」にあるという。
となると今後は、ヨーロッパのように各地域の風土に根ざした個性的なチーズが、どんどん生まれてきそうである。本書を読んで、そんな嬉しい予感をおぼえた。
【今日の教養を高める1冊】
『チーズの世界史』
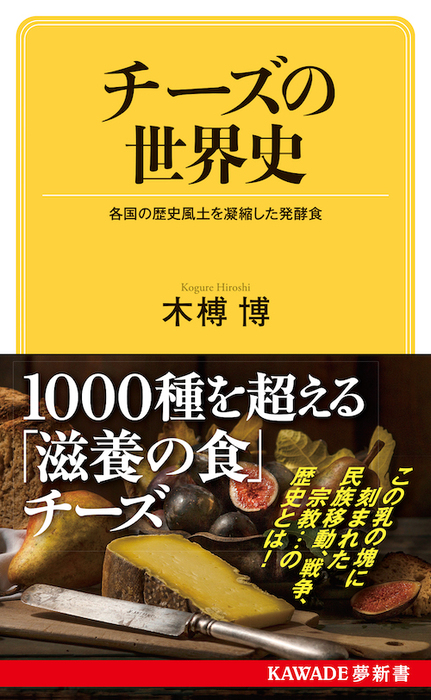
定価1100円
河出書房新社
文/鈴木拓也
老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。




































