文/鈴木拓也

「日本美」とは、なんであろうか?
古今、日本の文化に潜む美しさという、難しいテーマに挑んだ人は少なくない。
その1人が、三笠宮家の彬子(あきこ)女王殿下だ。
現在、京都の大学で教鞭を執る殿下だが、日本美を追究し始めたのは、オックスフォード大学大学院の博士課程を修了し、帰国してからのこと。その遍歴をエッセイに綴り1冊に収めたのが、2015年に刊行された『日本美のこころ』(小学館)である。さらに後年、伝統技術の職人たちを描いた「最後の職人ものがたり: 日本美のこころ」(小学館)も出された。
このたび、この2冊を合本して1冊の文庫に収録。『日本美のこころ』(小学館 https://www.shogakukan.co.jp/books/09407413)として刊行された。
日本美を愛する外国人の多さに「心温かくなる」
本書を味読して最初に感じたのは、日本の文化には実に多くの側面があること。
例えば、「外国人が残してくれた浮世絵」という一編。
筆者(鈴木)は、江戸時代の浮世絵は、日本から輸出された陶磁器の包み紙として使われ、海外に流出していったという認識をもっていた。包み紙云々というのは、根拠の薄い俗説らしいが、膨大な数の浮世絵が海外にあるのは事実。その事実の一翼を担う者として、建築家のフランク・ロイド・ライトが関わっているというのは驚きであった。
著者は、ライトについて調べているうちに見つけた写真から、自邸に仏画が飾られていたのを知り、そこからライトと浮世絵との接点が探られていく。
1893年のシカゴ万博で浮世絵に出会ったライトは、非常に複雑な技法を用いて生み出される表現の簡潔さにすっかり魅了され、それ以来「自然を全く異なった視点で見るようになった」そうだ。彼の自叙伝によると、彼の建築に見られる日本の影響は、日本建築からではなく、浮世絵に由来するものであるらしい。(本書75pより)
ライトは、自身が浮世絵の熱心な蒐集家であっただけでなく、資産家のスポルディング兄弟の依頼を受けて、日本各地で浮世絵探しも代行した。今はボストン美術館が、兄弟のコレクションを所蔵する。浮世絵に限らず、海外に出て行った日本の美は多いが、著者はそれを遺憾だとは思わない。むしろ、「日本美術を愛した人が海外にこれだけいたのかと思うと、とても心温かくなる」と記している。
また、他のエッセイでも、海外で愛好された日本の美に言及がある。日本を基点にしただけでは、見えてこないものは多い。
もてなしの心が息づく喫茶店の文化
著者は、昔ながらのレトロな感じの喫茶店が好きだという。そして、喫茶店は「日本が世界に誇るべき文化」であるとも。
意外にも、そうした雰囲気を持つ喫茶店は、海外では見かけないそうだ。実際に深堀りして調べた結果、これは「日本独特」なものであるという結論を得るに至る。
そもそも、日本の庶民が珈琲を飲むようになったのは、明治時代に入ってしばらくしてからのこと。日本初の喫茶店は「可否茶館(かひさかん)」という屋号で、明治21年の開業。ビリヤード台やシャワー室まで備えた、一種の複合レジャー施設だったそうだ。
現代の我々が、レトロ喫茶などと呼ぶスタイルができあがったのは、1950年代だという。日本人と珈琲の関係について、次のように論が展開される。
効率化を追求し、大量生産・大量消費があたりまえの戦後の世の中にあっても、ドリップやサイフォンで一杯ずつ珈琲を淹れるスタイルが残り続けた。これはお客様一人ひとりのために時間をかけ、心を込めてお茶を点てる・淹れるという、茶の湯や煎茶の持つもてなしの精神と結び付くものがあるに違いない。(本書195pより)
この精神は、外国の人たちにある種の感銘を与えたようだ。アメリカやドイツでは、日本スタイルの喫茶店が最近増えているそうで、珈琲文化を学びに訪日する熱心な人もいるくらい。かつての日本人は、シルクロード経由で海外の文化を採り入れ、一部は正倉院の宝物として今に残る。著者は、珈琲文化をして「今度は正倉院の宝物が逆のルートを辿る」と表現している。
技術が継承される「あたたかなひととき」
伝統技術の後継者不足が叫ばれて久しい。
後を継ぐ者が欠けたまま、そうした仕事を続けている人を、著者は「最後の職人」と呼ぶ。
その1人として本書が取り上げるのは、富山市の四津谷敬一さん。烏帽子を作り続けて約半世紀のベテランだ。
烏帽子の主な素材は和紙。100~150年前の和紙が軽くて丈夫ということで、四津谷さんは、古本屋や骨董市で集めた古紙を大量にストックしている。
著者は、四津谷さんの工房を訪れ、烏帽子作りの様子を描写する。
糊とこてを使って接着し、錐(きり)を使って上手にしわを寄せていくと、見る見るうちに見慣れた烏帽子の形になっていく。普段は穏やかな表情の四津谷さんも、作業をされているときは鋭い職人の顔になる。何の変哲もない、本来は捨てられていたかもしれない1枚の和紙が、一人の職人の手によって姿を変え、命が吹き込まれていく。(本書224~225pより)
著者の「最後の職人」を見るまなざしが優しい。それは研究者というよりも、ものが創られるかけがえのない時を共有する詩人のようでもある。
この出会いから数年後、老職人は「風のように旅立たれた」。今は、ただ一人の弟子であった若い男性が烏帽子作りを継承している。このようにして伝統が残される瞬間は、「あたたかなひととき」なのだという。さらには、ある神職者の言葉を引き合いに、残るべきものであるなら「神様が微笑んでくださる」とも記す。このようにして、新しい時代が紡ぎ出されていくのだろう。
* * *
瑞々しい感性に裏打ちされた54篇のエッセイが収録されている本書は、筆者の浅薄な知識を上書きし、あらたな視点をもたらす玉手箱のような存在であった。日本の文化と美に関心をもつ、全ての方に読んでほしいと素直に思う1冊である。
【今日の教養を高める1冊】
『日本美のこころ』
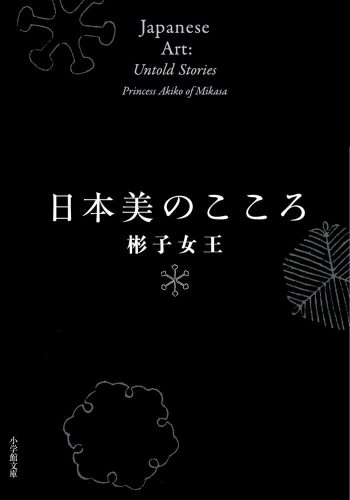
定価1210円
小学館
文/鈴木拓也
老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。























