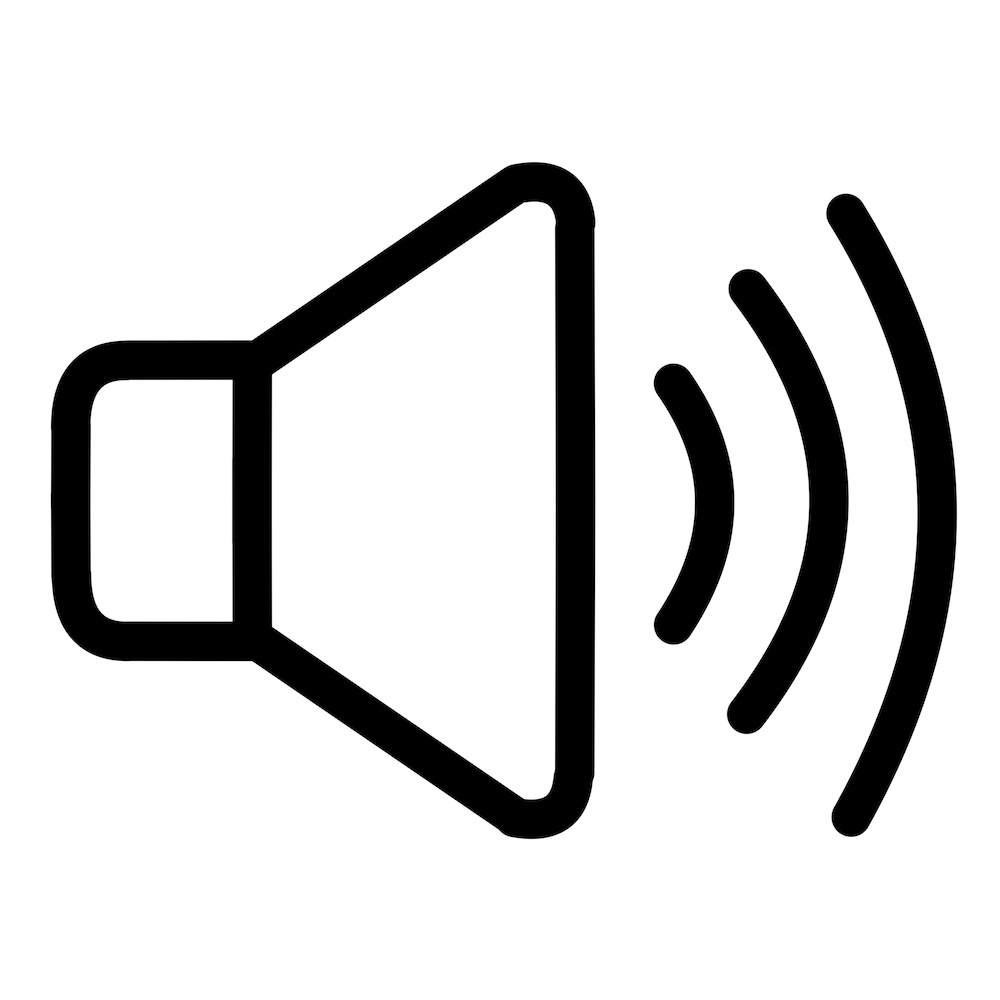取材・文/長嶺超輝

アパートの住人は、その部屋から聞こえてくる母親の怒鳴り声と、泣きわめく娘たちの絶叫を、毎晩のように聞いていた。しつけだとしても「やりすぎ」だと心配する住人も少なくなかったが、児童相談所への通報には至らなかった。
ある夜、下の娘がタンスに登って遊んでいたところ、床に転落して気を失う事故が起き、娘が救急車で病院へ運ばれた。しかし、それは事故ではなかった。
タンスで遊んでいた娘を叱りつけるあまり、感情が高ぶった母親が、無理矢理に両手で床へ引きずり下ろした結果だったことが明らかとなったのである。
それをきっかけに、母親は日常的に虐待を繰り返していた事実も発覚した。その夫も、虐待に加担していたという。
母親にとって、長女は前夫との間に生まれ、次女は離婚後に交際していた男性との間に授かった。ただし、現在の夫は、2人の娘のいずれとも籍を入れていない。
【前編はこちら】
* * *
■若くして離婚し、シングルマザーに
裁判では、被告人となった母親の半生が、検察官の冒頭陳述によって明らかにされた。加えて、被告人質問の手続きで、母親自身の口からも語られていった。
高校を卒業した後、歓楽街でホステスとして働いていた被告人は、前の夫となった男性と出会って結婚したのを機に、すぐにホステスの仕事を辞めて専業主婦となった。
まもなく長女が産まれるも、前の夫は仕事が多忙でほとんど帰宅せず、孤独感と子育てのストレスが募っていった。
ふたりの生活費は、またホステスとして働いて得ればいいと覚悟した被告人は、元夫に離婚届を突きつけ、長女を連れて家を出ていった。
しばらくは実家で静養し、実母にも育児を手伝ってもらうことで、精神的にも余裕を取り戻していったのである。
■交際相手との子を身ごもるが……
娘が寝静まった後、母は再び夜の街で働くことにした。ただ、自慢話ばかりの男性客の相手をするのに嫌気が差していた。別れた夫が、いつも偉そうに振る舞っていた姿と重なったからかもしれない。
そんなとき、客として知り合った若いサラリーマンの男性客の言動に、被告人は癒やされることになる。自分の話を黙って聞いて、頷いてくれるその人柄に惹かれていった。
昼間にも会うようになり、やがてプライベートでの交際に発展した。しかし、まもなくして妊娠したことを告げると、その男は静かに離れていった。
そのときに身ごもった次女が、のちに本件虐待の被害者となったのである。
■娘ふたりを、いったん手放す決断
シングルマザーのまま、次女を妊娠したことを気まずいと感じた被告人は、実家にも帰れなくなっていた。ホステスとの仕事も辞めなければならない。
次女を出産してからも、しばらくは貯蓄でしのいでいたが、乳児と幼児をひとりで抱えこんで育てることにも、限界が訪れようとしていた。
誰にも頼らず、ふたりの娘を育てることの限界を自覚したのは、何度注意しても言うことを聞かない長女に対して手をあげたときだった。
「あんたたちさえ、いなければ……」との逆恨みの感情が、一瞬でも脳裏をよぎった自分を責めた。
意を決して、児童相談所に駆け込み、長女を児童養護施設に、次女を乳児院に預けることにした。
ふたりにとって、自分がいるのといないのと、どちらが幸せなのだろう。
最悪の場合、ふたりに今後一生、会えなくなることも、母は覚悟したという。
■3年努力し、ふたりの娘を再び自宅へ迎え入れる
しばらく、児童養護施設や乳児院に通い詰めるうち、職員から、娘たちとの接触や一時帰宅を許してもらえるようになった。
静かだった部屋に、笑顔や賑わいが戻ってきたことに、被告人はワクワクと胸を躍らせていた。
そして、少しずつ親子の関係を取り戻し、児童相談所への最初の相談から約3年経って、母はふたりの娘を再び、取り戻すことができたのである。
悲劇は、それからわずか、3か月後に起きた。
【3年間の空白を、早く埋めたいという焦燥感で、やってはいけないことを…次ページに続きます】